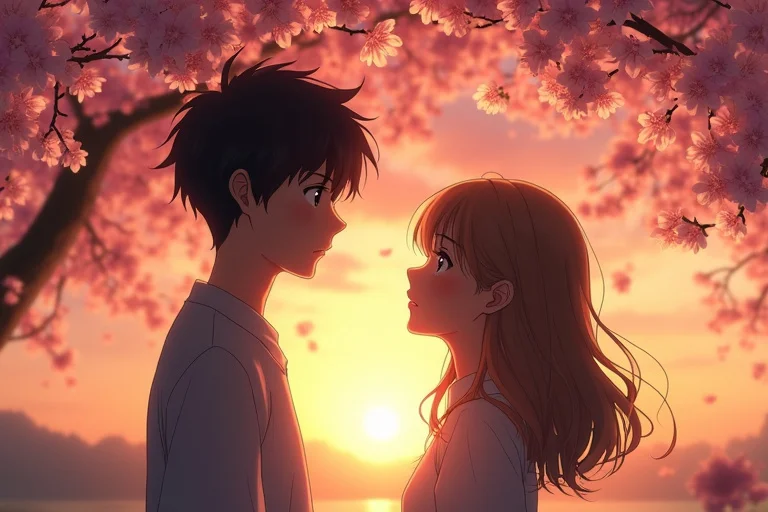第一章 蜜の味、硝子の日常
朝、目が覚めると、世界は黄金色の蜜に浸されていた。
窓から差し込む陽光は完璧な角度でレースのカーテンを透過し、淹れたてのコーヒーは、まるで天上の飲み物のように芳醇な香りを放っている。私は一口含み、幸福に震える。満たされている。これ以上ないほどに。
私はベッドサイドにある古びた手帳を手に取った。革の表紙は手垢で黒ずんでいるが、私の宝物だ。ページを捲る。
『七歳の夏。父さんと行った海。青い絵具を溶かしたような空』
文字を目で追うだけで、潮風の匂いと、父の大きな手の温もりが胸の奥から湧き上がってくる。ああ、なんて幸せな記憶だろう。
しかし、ふと指が止まる。
「父さん」の名前は何だったか。
記憶の中の父は、太陽を背にして笑っている。その笑顔は眩しくて、温かくて……けれど、顔のパーツが陽光に溶けて判然としない。
まるで、ピントの合わない写真を見せられているようだ。
「……まあ、いいか」
私は思考を止める。深く考えようとすると、幸福な陶酔に冷や水が浴びせられるような気がしたからだ。微かな違和感は、甘美な日常のノイズに過ぎない。私は手帳を閉じ、今日もまた、光に満ちた世界へと踏み出した。
第二章 漂着する色彩
街は、誰かの落とした「幸せ」で溢れていた。
交差点ですれ違った女子高生の笑い声が、シャボンの泡のように弾け、私の肌に吸い込まれる。その瞬間、胸の奥に甘酸っぱい切なさが広がった。
――放課後の教室。夕焼け。手渡された手紙。
私の記憶ではないはずの情景が、鮮烈なリアリティを持って脳裏に焼き付く。気がつけば、私は手帳を開き、無心でペンを走らせていた。
『初めての恋文。心臓が痛いほど鳴っていた』
書き終えた文字を見て、首を傾げる。
先ほどのページの筆跡と、微妙に癖が違う。右上がりの「恋」の字。以前の私は、もっと丸文字だったはずだ。
いや、それ以前に、私は男子校出身ではなかったか?
「……違う」
唐突に、心の底から冷たい風が吹き抜けた。
この満たされた幸福感は、本当に私のものなのか?
幼少期の家族旅行、初恋の思い出、受験合格の歓喜。手帳に記された無数の「幸せ」は、あまりにも色彩が豊かすぎる。それなのに、なぜか彩度がバラバラで、継ぎ接ぎだらけのパッチワークを見ているようだ。
私は胸のあたりを鷲掴みにした。そこにあるはずの核が、空っぽだ。
私の心は、他人の幸福を貪り食うだけの、美しい空洞なのではないか。
その時、手帳のページの間から、一枚の栞が滑り落ちた。それは、私が一度も開こうとしなかった、手帳の「最後のページ」に挟まっていたものだった。
第三章 黒く塗り潰された真実
震える指で、私は最後のページを開いた。
そこには、黄金色の記憶など一つもなかった。
美しい筆記体でも、躍るような文字でもない。紙を突き破るほどの筆圧で、黒いインクが殴り書きされていた。
『痛い。熱い。助けて』
『全部燃えてしまった』
『僕だけが生き残ってしまった』
呼吸が止まる。
脳髄を、灼熱の業火が駆け巡った。
思い出した。
海になど行っていない。恋文など貰っていない。
あの日、私の家は火に包まれた。愛する家族も、撮りためたアルバムも、幸福な未来も、すべてが炎の中で灰になった。
私は一人、黒焦げの廃墟の前に立ち尽くし、絶望という名の毒を飲み干したのだ。
あまりの苦しみに耐えきれず、私は自らの心を殺した。
自分の「本当の記憶」を心の最深部に封印し、その空白を埋めるために、世界に漂う「誰かが忘れた幸福」を無意識に啜り続けていたのだ。
私が感じていた違和感。手帳の空白。顔のない父。
それらはすべて、私が泥棒である証拠だった。
「う、あぁ……ああああッ!」
喉の奥から、獣のような咆哮が漏れた。
偽物の幸せが、胃液と共に込み上げてくる。甘ったるい蜜の味が、今は腐った肉のように吐き気を催させる。
私は、他人の幸せの残骸で自分を飾り立てた、醜い怪物理(バケモノ)だったのだ。
第四章 灰色の夜明け
涙と鼻水でぐしゃぐしゃになりながら、私は手帳を抱きしめていた。
窓の外では、いつの間にか夜が明けようとしている。
昨にまでの私なら、この朝焼けを「希望の光」だと感じ、手帳に詩的な一文を加えていただろう。
だが、今の私に見えるのは、ただの薄暗い、寒々しい灰色の空だ。
幸福感は消え失せた。代わりに胸に残ったのは、焼けつくような喪失感と、一生背負わなければならない孤独な十字架だ。
手帳のページを捲る。
『七歳の夏。父さんと行った海』
その文字が、滲んで読めなくなっていく。他人の記憶が、本来の持ち主の元へ帰ろうとしているのか、それとも私が拒絶したからか。
美しい偽りの記憶たちが、砂のように崩れ去っていく。
残されたのは、最後のページの、黒い殴り書きだけ。
私はペンを執った。震える手で、黒い文字の下に、新たな一文を刻むために。
もう、借り物の光はいらない。この身を裂くような痛みこそが、私が私である唯一の証明なのだから。
インクが紙に染み込む。
『私は生きている。この地獄のような世界で、一人で』
手帳を閉じる音だけが、静寂な部屋に響いた。
私の頬を伝う涙は、初めて、鉄の味がした。