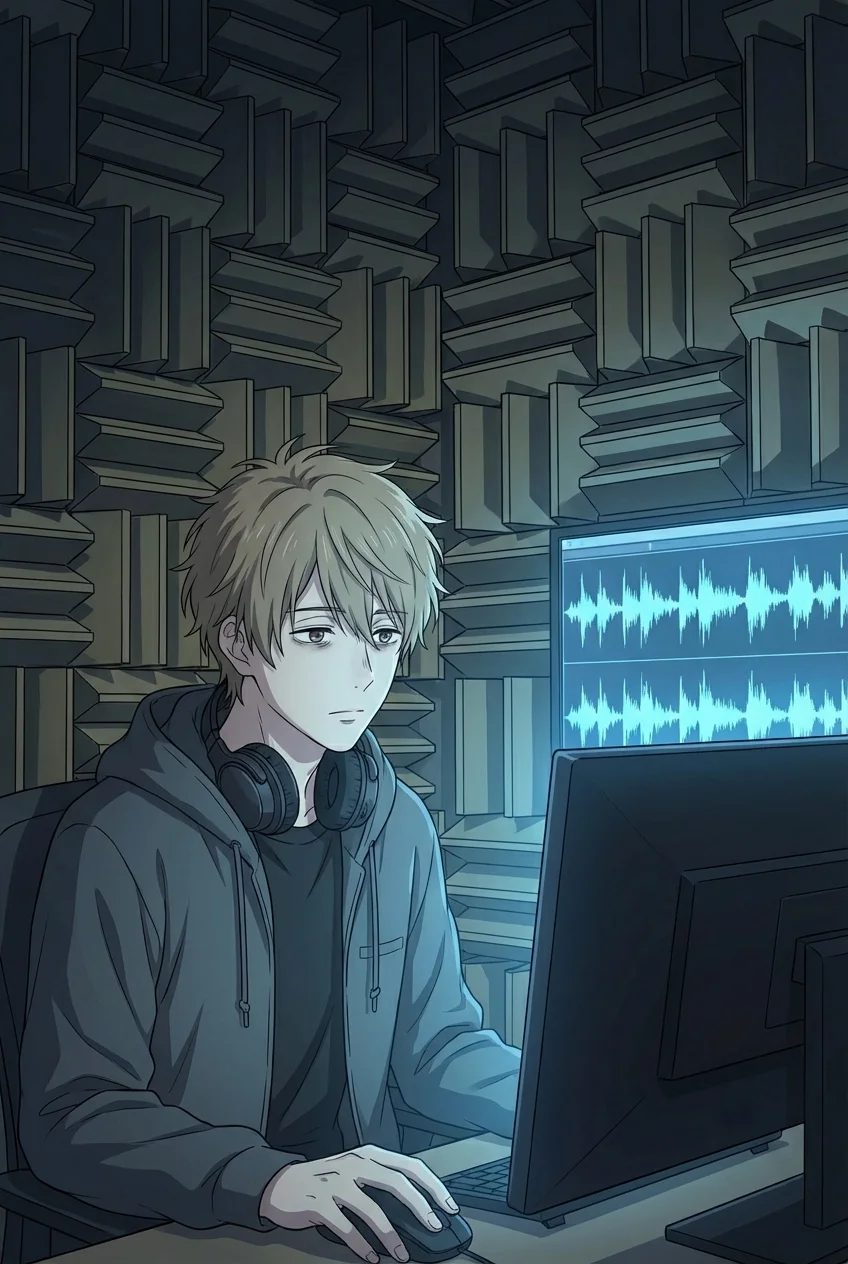第一章 忘れ物の感情
僕、柏木湊(かしわぎ みなと)の営む古道具屋『時の澱(おり)』は、街の忘れ物たちが集まる終着駅のような場所だ。錆びたブリキの玩具、インクの染みが残る万年筆、持ち主を失った懐中時計。僕はそれらに触れるたび、微かな感情の記憶を読み取ってしまう。それは、熱病の時に見る夢の断片のように、曖昧で、それでいて確かな手触りがあった。
「……また、増えたな」
店の窓から見える空には、半透明の泡がいくつも浮かんでいた。人々が「日常」と呼ぶ行動を放棄した時に生まれるという『余剰な時間』の塊。世間では『空の涙』などと詩的な名前で呼ばれ、観光名物にすらなりかけていたが、僕にはそれらがただの美しい現象とは思えなかった。
ひとつ、ふたつと、シャボン玉のように頼りなく漂う泡は、朝焼けの光を浴びて虹色にきらめいている。しかし、その輝きはどこか虚ろだ。僕は知っている。あの泡は、放置されると次第に色褪せ、やがて消滅する。そして、その度にこの世界から、何かの『音』がひとつ、永遠に失われるのだ。
先日、近所の公園に浮かんでいた泡にそっと指先で触れてみた。途端に流れ込んできたのは、ひどく冷たい諦観だった。それは、これまで僕が触れてきた無数のモノたちが纏う、喜びや悲しみ、退屈といった雑多な感情の記憶とは全く異質だった。たった一つの源泉から湧き出たような、純粋で、深く、そしてあまりにも孤独な『喪失感』。
街に浮かぶ全ての泡から、僕は同じ感情を読み取っていた。まるで、この世界そのものが、誰か一人の巨大な悲しみに覆われているかのように。
第二章 メトロノームの微かな刻音
店の奥、祖母の遺品が収められた桐箪笥の上に、古びた木製のメトロノームがひとつ置かれている。ゼンマイはとうの昔に切れ、振り子は沈黙したまま。しかし、このメトロノームは、僕が特に強い感情の記憶に触れた時だけ、ごく稀に、独りでに音を立てるのだ。
カチリ。
それは、背後で微かに鳴った。僕が、客の持ち込んだ古い銀のロケットペンダントに触れていた時のことだ。中にはもう写真はなく、空白だけが残されていた。そこから流れ込んできたのは、やはりあの『喪失感』だった。泡と同じ、冷たい諦めの感情。
振り向くと、メトロノームの振り子が小さく揺れていた。規則的なリズムではない。まるで何かに躊躇うかのように、不規則に、そして途切れ途切れに。
「……おばあちゃん、これは一体……」
祖母も僕と同じ力を持っていたのだろうか。だとしたら、このメトロノームは何のために?
その夜、僕は店の屋根裏に上がり、窓から夜空に浮かぶ泡を眺めていた。月光を吸って青白く光る泡のひとつが、ふ、と張力を失い、音もなく弾けて消えた。
瞬間。
僕の耳の奥で、キーンと鋭い音が鳴った。世界が一瞬だけ、真空になったような錯覚。そして、気づく。いつもならこの時間に聞こえてくるはずの、遠くの踏切が鳴らす警報音の、あの独特の甲高い響きが、わずかに欠けていることに。音が、ひとつ、また失われたのだ。
その時だった。階下から、澄んだ音が聞こえた。
カチン。
メトロノームが、たった一度だけ、これまで聞いたことのない、鈴が鳴るような清らかな音を立てた。まるで、消えゆく音に哀悼を捧げるかのように。
第三章 失われたメロディの断片
翌日から、僕は街を彷徨った。人々が日常を捨てた場所に、『余剰な時間』は生まれる。閉鎖されたパン屋の朝。もう誰も通らない通勤の近道。子供の声が聞こえなくなった公園の昼下がり。そこには必ず、あの泡が浮かんでいた。
僕は、泡が消える瞬間に立ち会うことに意識を集中させた。泡が消え、世界から音が欠落する。その直後に、必ずメロノームが共鳴するように音を立てる。僕はその音を五線譜に書き留め始めた。
ド、ソ、ファ……ミ♭……。
それは不協和音のようでありながら、どこか懐かしい響きを持っていた。失われた音の残響。忘れ去られたメロディの亡霊。
「この感情の記憶……このメロディは、一体誰のものなんだ?」
泡に触れるたびに流れ込む、寄る辺ない喪失感。それは、何かを創り出し、そしてそれを愛していた者が、その全てが自分の手からこぼれ落ちていくのを、ただ無力に見つめているかのような感情だった。諦めているのに、心のどこかでまだ悲鳴を上げているような、痛々しい静寂。
世界から音が失われるにつれて、人々の表情から少しずつ感情の機微が失われていくことに、僕以外の誰も気づいていないようだった。笑い声は乾き、涙は表面的になった。街全体が、ゆっくりと色褪せていく画布のようだった。
第四章 創造主の孤独
その日、街の中心部、かつて最も賑わっていた広場の上空に、巨大な『余剰な時間』が出現した。それは、この街全体の『朝の挨拶』という巨大な日常が放棄された結果だった。ビルほどもある巨大な泡は、不気味なほど静かに、空を覆っていた。人々は感情の薄れた瞳で、ただそれを見上げている。
このままでは、まずい。直感が警鐘を鳴らす。これが消滅すれば、世界は決定的に何かを失ってしまう。
僕は広場の中央へ走り、錆びた噴水の縁に足をかけた。そして、天に浮かぶ巨大な泡に向かって、手を伸ばす。
指先が泡の表面に触れた瞬間、僕の意識は激しい奔流に飲み込まれた。
―――ビジョンが見えた。
何もない、無垢な虚空。そこに、ただ一人の存在がいた。姿形ははっきりしないが、その存在が途方もない孤独の中にいることだけは分かった。
存在は、音を紡ぎ始めた。
一つの音が次の音を呼び、和音が生まれ、やがて壮大なメロディが虚空を満たしていく。そのメロディが世界に秩序を与えた。朝と夜を分け、喜びと悲しみを定義し、人々が互いを愛し、憎むための『日常』という名の舞台を創造したのだ。
メロディこそが、この世界の感情の設計図だった。
しかし、人々はいつしか日常を疎み、放棄し始めた。それは、創造主が編み上げたメロディを、一音、また一音と引き裂いていく行為に他ならなかった。
自分の創造した世界が、愛したはずの人間たちが、自らの手で感情の源泉を破壊していく。その絶望が、止めどない諦念が、そして深い喪失感が、僕の全身を貫いた。
泡から感じていた感情は、この世界の『日常』をデザインした、名もなき創造主の悲しみそのものだったのだ。―――
「……ああ……」
ビジョンから解放された時、僕は噴水の縁に崩れ落ちていた。目の前の巨大な泡は、急速にその輝きを失い、死んだような灰色に濁り始めていた。消滅が、近い。
第五章 究極の選択
メロディが壊れる。感情が、消える。
このままでは、人々は心を失った人形になるだろう。愛も、悲しみも、怒りさえも知らない、ただ生命活動を繰り返すだけの存在に。
それは、ある意味で穏やかな世界なのかもしれない。もう誰も傷つかず、喪失に涙することもない。創造主が味わったような、深い絶望もない世界。
それを受け入れるか?
それとも、抗うか?
僕に何ができる?僕はただの古道具屋だ。忘れ物の声を聞くことしかできない。
その時、懐に入れていた祖母のメトロノームが、強く脈打った。
カチ、カチン、カチ、カチ……。
これまで僕が書き留めてきた、失われたメロディの断片を、まるで道を示すかのように、力強く奏で始めた。不完全で、途切れ途切れのメロディ。だが、その音は確かに、創造主の悲しみだけでなく、世界が生まれた瞬間の、あの歓喜に満ちた響きをも宿していた。
そうだ。創造主は『日常』からメロディを紡いだ。ならば。
失われたメロディを、もう一度。
僕は立ち上がり、決意を固めた。メトロノームを強く握りしめる。新しい音を、最初の音を生み出すんだ。僕自身の、『日常』から。
第六章 心臓の鼓動
僕の日常とは何だろう。古道具に触れること?コーヒーを淹れる朝?それらはすべて、創造主が与えてくれた舞台装置の上にある。もっと根源的な、僕だけの音。
僕は目を閉じ、全ての意識を自分の内側へと沈めていった。
街の喧騒が遠ざかる。風の音が消える。
そして、聞こえた。
ドクン、ドクン、ドクン――。
僕自身の、心臓の鼓動。生まれてからこの方、一度も休むことなく僕という存在を支え続けてきた、最も個人的で、最も確かな日常のリズム。それは喜びの時に速まり、悲しみの時に深く沈む、僕の感情の原風景。
僕はそっと、メトロノームを自分の胸に当てた。
「頼む……響いてくれ」
僕の鼓動が、古い木製の箱に伝わる。メトロノームの振り子が、そのリズムに呼応するように、ゆっくりと、しかし力強く揺れ始めた。
カチッ……カチッ……カチッ……。
それは、僕の生命そのものが奏でる音だった。
その規則正しいリズムは、空に浮かぶ巨大な灰色の泡へと、見えない波紋のように広がっていく。
すると、奇跡が起きた。
死の色をしていた泡が、その中心から、微かな、本当に微かな温かい光を灯し始めたのだ。消滅は、止まった。そして、僕の心臓の鼓動という『新しい最初の音』を吸収し、ゆっくりと、しかし確かに、生命の色を取り戻し始めた。
第七章 新しいメロディの始まり
巨大な泡は、消えなかった。ただ、以前よりもずっと小さくなり、僕の鼓動のリズムを宿したまま、夜明け前の空に静かに浮かんでいる。それはもう『余剰な時間』ではなく、新しいメロディの始まりを告げる、希望の種子のように見えた。
世界から感情が完全に戻ったわけではない。失われた音はあまりに多く、創造主の悲しみは今もこの世界のどこかに漂っているだろう。
でも、終わりではなかった。
僕は胸に当てたメトロノームを空にかざす。それはもう、僕の心臓と同じリズムで、静かに時を刻み続けていた。
これから僕の旅が始まる。忘れ去られたモノたちの声に耳を澄まし、失われたメロディの断片を拾い集め、そして僕自身の日常の音で、この世界をもう一度、感情の響きで満たしていく旅が。
空が白み始め、朝の光が街を照らし出す。その光には、昨日までとは違う、ほんの少しの温もりが含まれているような気がした。僕は、静かに微笑んだ。