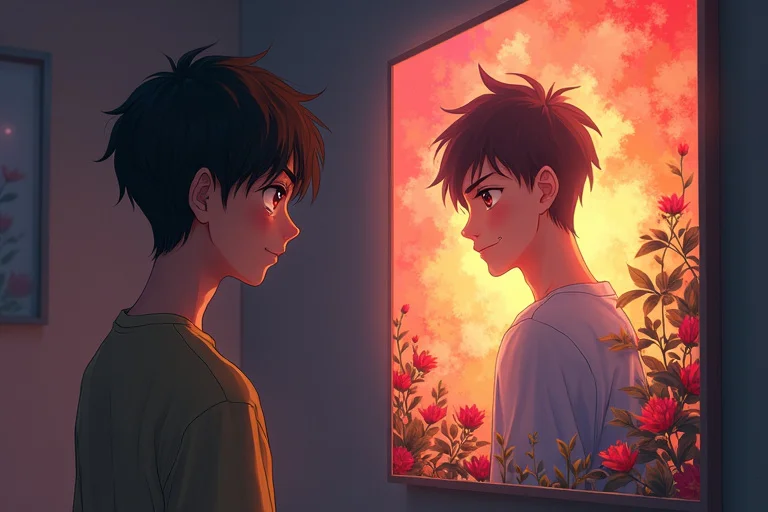第一章 奇妙な贈り物
高槻湊(たかつき みなと)の世界は、いつもファインダー越しに切り取られた、静かで整然としたものだった。人付き合いが苦手で、言葉を尽くす代わりにシャッターを切る。それが彼のコミュニケーションの全てだった。そんな湊にとって、天野陽介(あまの ようすけ)という存在は、まるで太陽光そのもののような、理解しがたい闖入者だった。正反対の性格でありながら、陽介は大学のキャンパスで孤立していた湊に、何のてらいもなく声をかけ、それ以来、二人はいつも一緒にいた。
ある雨上がりの午後、湊のアパートのドアがけたたましくノックされた。息を切らして立っていたのは、案の定、陽介だった。その腕には、古びた革のケースに収まった、見慣れないカメラが抱えられていた。
「湊! これ、見ろよ!」
陽介は宝物を見せびらかす子供のように笑い、重厚な金属の塊をテーブルに置いた。それは、湊が愛用するデジタル一眼レフとは全く違う、クラシックなフィルムカメラだった。黒いボディは所々塗装が剥げ、使い込まれた風合いが刻まれている。レンズの縁には、ギリシャ文字のようなものが小さく刻印されていた。
「骨董市で見つけたんだ。お前にぴったりだろ?」
「…なんで、俺に?」
「だってお前、いつも四角い世界ばっか見てるからさ。たまには、こういう面倒で、何が写るか分からないヤツも面白いかと思って」
陽介の理屈はいつも突飛だが、不思議な説得力があった。湊は礼を言い、そのずっしりとした感触を確かめるようにカメラを手に取った。冷たい金属の質感が、妙に手に馴染む。ファインダーを覗くと、いつもの部屋が少しだけ色褪せて、ノスタルジックな風景に見えた。
その週末、二人はテスト撮影と称して、近所の公園に出かけた。陽介が買ってきたフィルムを装填し、湊はまだ蕾の固い桜並木にレンズを向けた。カシャン、という硬質で心地よいシャッター音が響く。
数日後、現像から上がってきた写真を見て、湊は息を呑んだ。
そこに写っていたのは、満開の桜の下で、こちらに手を振る陽介の姿だった。
「…嘘だろ」
呟きは誰にも届かない。まだ固い蕾だったはずの桜が、写真の中では春を謳歌するように咲き誇っている。他の写真も同様だった。まだ更地だった駅前の土地には、完成したばかりの真新しい商業ビルが建っていた。まだ出会ってもいない、隣の部屋に越してくるはずの住人が、荷物を運び込んでいる姿まで写っていた。
このカメラは、未来を写すのだ。
湊の背筋を、今まで感じたことのない興奮と、正体不明の怖気が同時に駆け抜けた。日常が、音を立てて歪み始めた瞬間だった。
第二章 未来の断片
「すげえ! 最高じゃんか、このカメラ!」
未来が写るという突拍子もない事実を、陽介はあっさりと受け入れ、腹を抱えて笑った。恐怖よりも好奇心が勝るのが、いかにも彼らしかった。それからというもの、二人の間では「未来の写真」が共通の秘密になった。
「次の小テスト、ヤマが張れるかもな」
「馬鹿言え。そんなことに使ってたまるか」
軽口を叩き合いながらも、湊の心は少しずつ変化していた。臆病で、常に一歩引いていた彼が、未来の断片を手にすることで、ささやかな自信を持つようになったのだ。写真に写っていた通り、出がけに折り畳み傘を持っていけば、予期せぬ夕立をしのげた。写真に写っていたセール情報を頼りに店へ行けば、欲しかった画集が手に入った。
未来が少しだけ見える。その事実は、不確かな世界を歩くための、小さな杖になった。湊は以前よりもよく笑うようになり、陽介以外の人間とも、ぎこちないながら言葉を交わせるようになった。
その変化を、陽介は誰よりも喜んでくれた。
「最近のお前、いい顔してるぜ」
夕暮れの河川敷で、陽介はそう言って湊の肩を叩いた。湊は、陽介が差し出した缶コーヒーを受け取りながら、照れ臭そうに視線を逸らす。沈みゆく太陽が、川面を黄金色に染め上げていた。その光景のあまりの美しさに、湊は無意識に例のカメラを構えていた。
「なあ湊、俺たちの未来って、どうなるんだろうな」
陽介がぽつりと言った。
「卒業しても、こうやって馬鹿なこと言って笑ってんのかな」
「…さあな」
言葉を濁しながら、湊はシャッターを切った。ファインダー越しに見える陽介の横顔は、いつもの快活さの奥に、ふとした寂しさを滲ませていた。このカメラなら、その答えを教えてくれるかもしれない。そんな淡い期待が胸をよぎった。このかけがえのない時間が、未来でも続いているという証が欲しかった。
この友情が、永遠だという証明が。
その時の湊は、知る由もなかった。パンドラの箱を開けるということは、希望と共に、必ず絶望をも解き放つということを。
第三章 消失の予兆
現像された写真を見た瞬間、湊の全身から血の気が引いた。
そこに写っていたのは、夕暮れの河川敷の、美しい風景だけだった。黄金色の川面、長く伸びる土手の影、そして、陽介が座っていたはずのベンチ。そこには誰もいなかった。まるで、最初から陽介など存在しなかったかのように、彼の姿だけが綺麗に消え去っていた。
「何かの間違いだ…」
湊は震える手で、他のコマを確認する。だが、どの写真にも陽介の姿はなかった。慌てて、以前撮った写真を見返す。満開の桜の下で笑う陽介、商店街を歩く陽介。そこには、確かに彼がいた。なぜ、今回は写らない?
悪い予感が、心臓を氷の指で鷲掴みにするようだった。
翌日、湊は平静を装って、再び陽介を撮影した。大学の食堂で、講義室で、帰り道で。しかし、結果は同じだった。賑やかな群衆の中に、ぽっかりと空いた不自然な空白。陽介がいるはずの場所だけが、歪んだ空間のように切り取られている。未来の写真から、天野陽介という存在が、完全に消失してしまったのだ。
湊はパニックに陥った。これは、予兆ではないのか。陽介の身に、何か取り返しのつかないことが起こるという、カメラからの警告ではないのか。
その日から、湊の行動は常軌を逸し始めた。
「陽介、今日のバイト、休めないか? なんだか胸騒ぎがするんだ」
「そこの交差点は危ないから、遠回りして帰ろう」
「一人で出歩くな。どこへ行くにも俺が付き添う」
あまりに過保護で、神経質な湊の言動に、陽介は最初こそ笑っていたが、次第にその表情から笑顔が消えていった。
「おい、湊。どうかしちまったのかよ。俺はガキじゃねえぞ」
「でも…!」
「でも、じゃねえよ! お前、最近ずっとおかしいぞ。何か隠してるだろ」
鋭い指摘に、湊は口を噤む。真実を話すことなど、できるはずがなかった。親友に「お前はもうすぐいなくなるかもしれない」などと、どうして告げられようか。
湊はカメラの正体を必死に調べ始めた。レンズに刻まれたギリシャ文字を手掛かりに、古い文献や海外のオークションサイトを漁った。そして、ある海外の怪奇譚を集めたサイトで、ついに同じ特徴を持つカメラについての記述を見つけたのだ。
そのカメラは「クロノスの忘れ形見」と呼ばれていた。前の所有者は、最愛の親友を事故で亡くした写真家だったという。彼は、親友が事故に遭う未来を写真で見てしまい、それを防ごうと奔走したが、運命を変えることはできず、絶望のあまりカメラを手放した、と。
記事を読んだ湊の指先は、氷のように冷たくなっていた。やはり、これは死の予告なのだ。陽介を守らなければ。何としても。
焦燥感に駆られた湊の行動は、さらにエスカレートしていく。それはもはや友情ではなく、狂気じみた執着だった。二人の間にできた溝は、もはや修復不可能なほど、深く、暗いものになっていた。
第四章 ファインダー越しの真実
決定的な亀裂は、雨の日に訪れた。
「いい加減にしろ、高槻!」
陽介の怒声が、狭いアパートに響き渡った。湊が、アルバイトへ向かおうとする陽介の腕を掴んで離さなかったのだ。「今日だけは行くな、頼むから」と懇願する湊の目は、恐怖に染まっていた。
「お前は俺を信じられないのか! 未来がどうとか、そんな得体の知れないもののために、俺たちの今を壊すな!」
陽介は湊の手を振り払い、ドアを激しく閉めて出て行った。残された湊は、その場に崩れ落ちた。守りたかった。ただ、それだけだったのに。友情も、陽介の信頼も、全てを自分の手で壊してしまった。
呆然と床に座り込んだまま、湊はテーブルの上のカメラを睨みつけた。こいつのせいだ。こんなものがなければ。憎しみに任せてカメラを壁に叩きつけようとした、その瞬間。ふと、あの怪奇譚サイトの別の記述が頭をよぎった。
『そのカメラが写すのは、確定した未来ではない。それは、撮影者が心の底で望む、あるいは恐れる未来の可能性の具現である』
可能性…。湊はハッとした。だとすれば、陽介が写らないのは、彼が死ぬ未来が確定しているからではないのかもしれない。単に、自分が「陽介を失うこと」を、この世の何よりも恐れているからではないのか。その恐怖心が、陽介の存在しない未来を幻視させているだけだとしたら…?
希望とも絶望ともつかない仮説が、脳内で渦を巻く。どちらにせよ、確かめなければならない。湊は震える足で立ち上がった。信じるべきは、不確かな未来の写真か、それとも、今まで共に過ごしてきた友との時間か。答えは、とうに出ていた。
湊はアパートを飛び出し、雨の中を走った。陽介のアパートへ。彼が事故に遭うかもしれないという恐怖は消えない。だが、それ以上に、彼に会って謝りたかった。全てを話したかった。
陽介のアパートのドアを開けると、彼は事故に遭うどころか、ずぶ濡れで心配そうな顔をして立っていた。
「…湊」
「陽介…!」
湊は、堰を切ったように全てを話した。未来が写るカメラのこと。陽介が写真から消えてしまったこと。彼を失うのが、どれほど怖かったか。言葉にならない想いが、嗚咽となって溢れ出す。
陽介は、黙って湊の話を聞いていた。そして、泣きじゃくる湊の肩を、そっと、しかし力強く抱きしめた。
「馬鹿だな、お前は…」
その声は、驚くほど優しかった。
「俺がいなくなるわけないだろ。たとえ未来がどうなろうと、俺はここにいる。お前との今が、俺にとって一番大事なんだ」
その言葉が、湊の心の呪いを解かしていった。
しばらくして、落ち着きを取り戻した湊は、カバンから例のカメラを取り出し、陽介に手渡した。
「陽介。これで、最後の一枚を撮ってほしい。俺を」
「…いいのか?」
「ああ。もう、怖くないから」
陽介は戸惑いながらも、カメラを構えた。湊は、レンズの向こうの親友を、まっすぐに見つめる。カシャン、と最後のシャッター音が、静かな部屋に響いた。
数日後、現像された最後の一枚を、二人は並んで覗き込んでいた。
そこに写っていたのは、奇跡のような光景だった。
不安そうに、しかしどこか吹っ切れたような顔で立つ湊。そして、その隣には、まるで陽炎のように半透明の陽介が、いつものように屈託なく笑っていた。それは未来の光景ではなかった。失われることへの恐怖と、それでも揺るがない友情そのものが、一枚の写真に焼き付けられたようだった。
「…なんだか、心霊写真みたいだな」
陽介が笑うと、湊もつられて笑った。
未来は分からない。この先、何が起こるか誰にも分かりはしない。けれど、ファインダー越しではない、自分のこの目で見る親友の笑顔がここにある。不確かな明日を、共に歩いてくれる友が隣にいる。
湊は、もう未来を写す必要はなかった。彼が手に入れたのは予知能力ではなく、不確かな未来を友と笑って乗り越えていく、ささやかで、しかし何よりも強い勇気だったのだから。