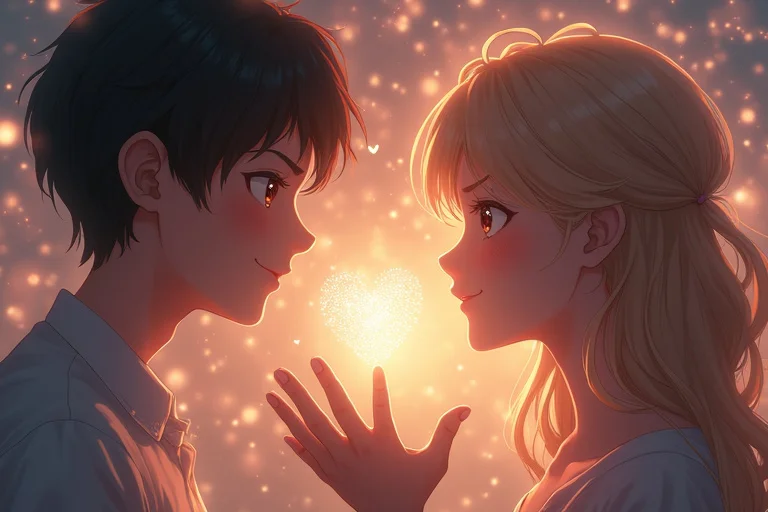第一章 幻の共鳴
左手の小指の先に、ちりちりと焼けるような微かな痛み。慌てて見下ろしても、白く細い指には傷ひとつない。大学の講義中、僕、水無月涼(みなづき りょう)を襲うこの奇妙な感覚は、もう半年以上も続いていた。時としてそれは、覚えのない甘い菓子の味覚だったり、ふいに鼻腔をくすぐる潮の香りだったりした。精神科の扉を叩くべきか、と本気で悩んでいた矢先のことだ。彼、日向陽(ひなた はる)と出会ったのは。
陽は、その名の通り太陽みたいな男だった。くしゃっとした明るい髪、人を惹きつける大きな瞳。初対面の僕に、まるで十年らいの友人のように「なあ、この課題、さっぱり分かんなくない?」と話しかけてきた。人との間に見えない壁を築き、その内側で安寧を貪っていた僕にとって、彼の存在は眩しすぎた。だが、なぜか拒絶できなかった。
彼と話していると、不思議なことが起きた。陽がペットボトルの緑茶を一口飲むと、僕の舌の上に、あの独特の渋みと爽やかな香りがふわりと広がったのだ。そして彼が、うっかり机の角に膝をぶつけて顔をしかめた瞬間、僕の右膝にも、鈍く疼くような痛みが走った。まさか、と思った。僕を悩ませてきた幻の感覚は、すべて彼のものだったのか?
その日から、僕は陽を観察するようになった。僕が感じたコーヒーの苦みは、彼がカフェで注文したものだった。僕が嗅いだ甘い花の香りは、彼が帰り道に通りかかった花屋のものだった。まるで、彼の五感が僕の神経に漏れ出しているかのようだった。
この現象は、陽に近づくほど鮮明になった。彼の隣を歩くだけで、彼の見ている世界の色彩が、僕の世界に流れ込んでくるような錯覚さえ覚えた。他人との関わりを極力避けてきた僕が、陽という人間を、その感覚を通して、強制的に追体験させられている。それは恐怖であると同時に、抗いがたい魅力を持っていた。僕は、日向陽という名の太陽に引かれる、名もなき惑星のように、彼の周りを回り始めていた。
第二章 繋がる感覚、深まる絆
「それ、『共鳴』って言うらしいぜ」
ある日の放課後、僕の奇妙な体験を恐る恐る打ち明けると、陽はスマホの画面を見せながら、あっけらかんと言った。そこには、ごく稀に、極めて親しい間柄の人間同士で感覚が共有される現象についての記事があった。科学的な根拠は未解明。オカルトや都市伝説として扱われることが多い、と。
「俺たち、そんなに親しいってことか。なんか、すげえな!」
僕が抱いていた不安や恐怖を、陽は一瞬で吹き飛ばした。彼の屈託のない笑顔は、僕が築き上げてきた壁を、いともたやすく溶かしていく。自分の内側に他人が侵入してくるような不快感は、いつしか「彼と繋がっている」という特別な感覚へと変わっていった。
僕たちは、急速に距離を縮めた。いや、もとより僕たちの間には、距離などなかったのかもしれない。陽がバイト先で食べた賄いの生姜焼きの味を、僕は自室で味わった。陽が徹夜で課題に取り組む眠気を、僕はベッドの中で感じて共に夜を明かした。僕が読書中に感じた静謐な空気は、きっと陽にも届いていただろう。
孤独だった僕の世界は、陽というフィルターを通して、無限に色を増していった。僕一人では決して見ることのなかった景色。味わうことのなかった感情。陽が感じる喜びは僕の喜びとなり、彼の小さな悲しみは僕の胸をちくりと刺した。感覚の共有は、僕たちの友情を、他の誰にも理解できないほど深く、濃密なものへと育て上げていった。
「なあ、涼。俺たち、どっちかが死んだらどうなるんだろうな」
ある夏の夜、二人でコンビニのアイスを食べながら、陽がぽつりと言った。
「縁起でもないこと言うなよ」
「だって、気になるだろ。俺の感覚、お前の中に残ったりするのかな。そしたら、俺、死んでも寂しくないかもな」
夜風に揺れる彼の髪を見ながら、僕は想像した。この繋がりが永遠に続く未来を。それは、僕にとって何より心強いお守りのようだった。陽がいる限り、僕は一人ではない。この温かい共鳴が、僕の人生から孤独という言葉を消し去ってくれた。僕は、生まれて初めて、他者を失うことを心から恐れている自分に気がついた。
第三章 割れた鏡、砕ける心
その日は、突然やってきた。
講義を終え、アパートへの道を歩いていると、全身を貫くような、凄まじい衝撃と熱に襲われた。骨が軋み、肉が裂けるような感覚。鉄の匂いと、噎せ返るような血の生臭さ。視界がぐにゃりと歪み、アスファルトに膝をついた。これは僕の感覚じゃない。陽のものだ。
震える手でスマホを取り出し、陽に電話をかけるが、呼び出し音が虚しく響くだけ。胸騒ぎが頂点に達したとき、知らない番号から着信があった。警察からだった。陽が、交差点でトラックにはねられ、病院に救急搬送された、と。
病院に駆けつけると、集中治療室のガラスの向こうに、陽が横たわっていた。たくさんのチューブに繋がれ、痛々しい包帯が巻かれた彼の姿は、僕の知っている太陽のような彼とは似ても似つかなかった。医師は、厳しい表情で「峠は今夜でしょう」とだけ告げた。
その瞬間から、地獄が始まった。僕たちの友情の証だった「共鳴」は、牙を剥き、僕を苛む呪いへと姿を変えた。
ベッドに横たわる陽から、絶え間なく流れ込んでくる感覚。それは、もはや単なる痛みではなかった。全身が氷水に浸されたように冷えていく感覚。肺に空気が入ってこない息苦しさ。意識が闇の底へ、どこまでも沈んでいくような、途方もない恐怖。それは、陽が体験している「死」そのものだった。
僕は、親友がゆっくりと死んでいく過程を、一秒一秒、己の肉体で追体験させられていた。悲しいとか、辛いとか、そんな言葉では表現できない。ただ、純粋な苦痛と恐怖だけが、僕の精神を蝕んでいく。何度も吐き、過呼吸になり、その場にうずくまった。
「いっそ、もう……」
声にならない声が喉から漏れた。いっそ、早く楽にしてやってくれ。いや、違う。僕を、この苦しみから解放してくれ。そう願ってしまった自分に気づき、絶望した。あれほど大切だった繋がりを、僕は今、心の底から断ち切りたいと願っている。陽の死を、僕自身の安楽のために望んでいる。なんて醜いんだ。僕たちの友情は、この程度のものだったのか。
繋がっていることの温もりを知った僕は、今、繋がっていることの地獄を味わっていた。陽の命の灯火が弱まるのと比例して、僕の心もまた、粉々に砕けていった。
第四章 残響のぬくもり
何時間経っただろうか。僕は、まるで亡霊のように陽の眠るベッドの傍らに座り続けていた。陽から流れ込む感覚は、もはや嵐のようだった。荒れ狂う苦痛の奔流の中で、僕は溺れかけていた。だが、そのときだった。ほんの僅かに、流れが変わった。
苦痛の隙間に、ふと、微かな「温かさ」を感じたのだ。それは、僕が握りしめている陽の左手に、僕自身の体温が伝わっている感覚だった。ハッとして、僕は陽の顔を見た。彼の意識はないはずだ。だが、僕の温もりは、確かに彼に届いている。僕がここにいることが、彼に伝わっている。
その瞬間、僕の中で何かが弾けた。そうだ。共鳴は、一方通行じゃない。僕が陽の苦しみを受け取るだけじゃない。僕の感覚も、陽に送ることができるんだ。
「陽、聞こえるか」
僕は、チューブの隙間から見える彼の耳元に顔を寄せ、必死に語りかけた。
「覚えてるか。初めて二人で見た、あの海のことを。しょっぱい潮風の匂い。足の裏に感じた、熱い砂の感触。打ち寄せる波の音。綺麗だったよな。本当に……」
楽しかった思い出を、一つ一つ、言葉にして紡いだ。あの時食べたラーメンの濃厚なスープの味。真夏の日差しの暖かさ。二人で笑い転げたときの、腹の底からこみ上げてくるような幸福感。僕は、僕が生きているこの世界の感覚のすべてを、陽に届けようとした。君が愛した世界は、まだこんなにも美しくて、温かいんだと。
僕が語り続けるうち、陽から流れ込んでくる感覚が、少しずつ変化していくのに気づいた。荒れ狂っていた奔流は、次第に穏やかな流れになり、死への恐怖は、静かな諦観へと変わっていった。そして、明け方の光が病室に差し込み始めた頃、彼の心臓の鼓動を知らせるモニターの線が、一本の直線になった。
繋がりが、ぷつりと途絶えた。
激しい喪失感が僕を襲った。けれど、不思議と、陽の最後の感覚は苦痛ではなかった。それは、僕の手に包まれた自らの手の温かさと、そして言葉にできないほどの、穏やかな感謝の念だった。彼は、僕を感じながら、旅立っていったのだ。
陽を失ってから、季節が一つ巡った。僕はあの日以来、一人になった。だが、もう孤独ではなかった。
今でも時々、ふとした瞬間に「共鳴」の残滓がよみがえることがある。街角で、陽が好きだったコーヒーの香りが鼻をかすめる。晴れた日の昼下がり、まるで陽だまりに包まれたような温かさを背中に感じる。それはもう、僕を苛む幻覚ではない。陽が僕の中に残してくれた、確かな温もりの欠片だ。
友情とは、共に生きることだけではないのかもしれない。相手の痛みも、喜びも、その存在のすべてを自らの中に受け入れ、その残響と共に、未来へ歩いていくこと。僕は、左手の小指の先に、もう決して感じることのないはずの、ちりちりとした愛おしい痛みを感じながら、陽が愛した世界を、これからも生きていく。