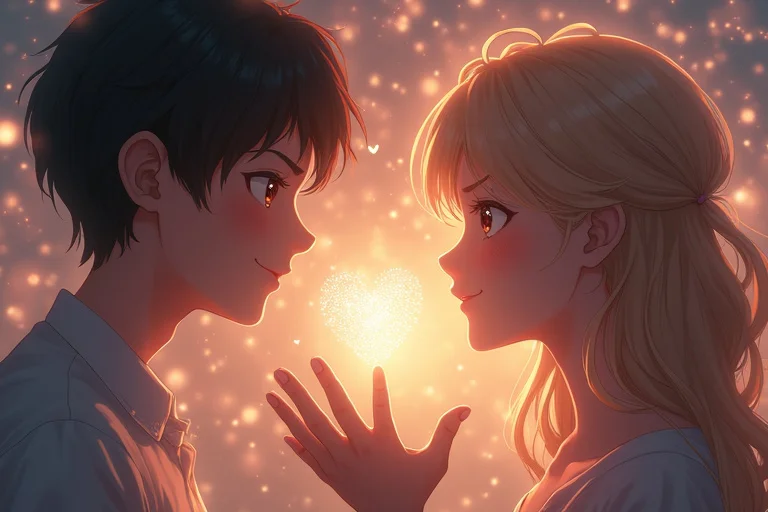第一章 硝子の蝶と錆びた羅針
カイの手の中で、古びた真鍮の羅針盤が静かに震えた。彼の「存在の羅針」。その針は、今しがたカフェの席に着いた親友、サラの方向を指して、微かに揺れている。カイの存在の重みが、ほんの少しだけ彼女の方へ流れ込んでいる証拠だ。
「また、それ見てるの?」
サラがコーヒーカップを置き、悪戯っぽく笑う。その笑顔にカイの心が温かく共鳴した瞬間、不思議な現象が起きた。カフェの窓辺に差し込む午後の光が、ふわりと屈折し、色とりどりの硝子でできた蝶が生まれたのだ。羽ばたくたびに、カラン、コロンと涼やかな音を立てる。サラの思考の断片――今日の午後の、ささやかで美しい幸福感そのものだった。
「綺麗……」サラがうっとりと呟く。彼女はカイのこの奇妙な能力を知る、数少ない友人の一人だ。
「君の心が穏やかだからだよ」カイは微笑み返し、羅針盤をポケットに仕舞った。
しかし、カイの胸には拭えない不安が澱のように溜まっていた。羅針盤の縁が、ここ数週間で急速に錆びつき始めているのだ。それは、強い憎悪や執着を伴う誰かが、彼の存在の重みを一方的に狙っていることを示唆していた。針はサラとは正反対の方向、街の最も古い廃工場地区を指して、不吉に震え続けている。友情が深まるほどに、この共鳴の力は強くなる。ならば、これほどの執着を向けてくる相手は、一体誰なのか。カイの指先が、冷たい汗で湿っていた。
第二章 影の襲撃
夜の帳が下りた路地裏。湿ったアスファルトが、ネオンの滲んだ光を鈍く反射していた。カイを追い詰めたのは、フードを目深に被った一人の男だった。その男が顔を上げた瞬間、カイは息を呑んだ。
「リオ……」
かつて、誰よりも深く心を分かち合った親友。彼の目は、底なしの昏い井戸のように、光を一切映していなかった。その手には、カイのものと同じ「存在の羅針」が握られている。だが、それは赤黒い錆に覆われ、まるで血に濡れているかのようだった。
「お前の重みを、寄越せ」
リオの声は、ひび割れたガラスのようだった。彼がカイに一歩近づくと、カイの身体から力が抜け、まるで風に溶けていくような虚脱感に襲われる。存在の重みが、強制的に引き抜かれていく感覚。同時に、カイの周囲にリオの思考の断片が具現化した。それは、錆びついた無数の歯車。互いに噛み合い、軋み、火花を散らしながら、空間を歪めていく。ギリ、ギリ、と耳障りな音が響き渡り、焦げ付いた鉄の匂いが鼻をついた。
「どうして……どうしてこんなことを!」
カイの叫びに、リオは答えなかった。ただ、その虚ろな瞳が、カイを射抜く。
「お前を、『思い出』にしてやる」
その言葉には、憎しみとも、悲しみともつかない、歪んだ響きがあった。リオの影が伸び、カイの存在そのものを飲み込もうと迫っていた。
第三章 移譲される温もり
リオの襲撃から逃れたカイは、心身ともに消耗しきっていた。自分の羅針盤を見ると、針が示す重みの数値が、明らかに減っている。このままでは、本当に自分が消えてしまう。恐怖に震えるカイの肩を、そっとサラの手が包んだ。
「大丈夫。私にできることがあるなら、何でもする」
サラはカイの手を取り、自分の羅針盤を重ね合わせた。温かい光が二つの羅針盤から放たれる。サラの存在の重みが、ゆっくりと、しかし確かにカイへと流れ込んでくるのが分かった。それは、温かい鉛が心の空洞を満たしていくような、深く満ち足りた安堵感だった。
「サラ、やめてくれ。君の重みが減ってしまう」
「いいの。友達でしょ? 重みなんて、分け合うためにあるんだから」
彼女の澄んだ瞳を見つめていると、カイの胸に一つの疑問が浮かんだ。リオは本当に、自分の存在を憎んでいるのだろうか。「強奪」とは、こんなにも冷たく、一方的なものだっただろうか。サラから伝わるこの温もりを知っているはずのリオが、なぜ。あの錆びた歯車の軋む音は、まるで助けを求める悲鳴のようにも聞こえた。彼の真の目的は、本当に自分の消滅なのだろうか。カイは、錆びついた記憶の扉に、そっと手をかけた。
第四章 追憶の残滓
カイとリオは、かつて双子のように寄り添って生きていた。互いの羅針盤はいつも同じ方向を指し、その文字盤は二人の存在の色が溶け合った美しいマーブル模様を描いていた。リオはカイよりも繊細で、彼の思考が具現化する断片は、いつも壊れそうなほど美しい音を奏でる氷の彫刻だった。
転機が訪れたのは、数年前の冬。リオが心から慕っていた姉を、突然の事故で失ったのだ。
その日を境に、リオは変わった。彼は姉の「存在の羅針」を握りしめ、何日も部屋に閉じこもった。姉の重みはゼロになり、彼女は「思い出」の存在となった。触れることも、話すこともできない。ただ、皆の記憶の中にだけ生き続ける、永遠の存在に。
「カイ、永遠って、何だと思う?」
ある日、リオはぽつりと呟いた。
「それは、忘れられないってことだよ」
「違う」リオは首を横に振った。「永遠は、孤独だ。そして、あまりにも、残酷だ」
彼の羅針盤が錆びつき始めたのは、その頃からだった。カイは、リオが姉の死を受け入れられず、この世界の法則そのものを憎んでいるのだと思っていた。だが、今になって思う。彼は憎んでいたのではない。絶望の果てに、何かを見つけてしまったのではないだろうか。あの軋む歯車は、彼の止まってしまった時間そのものだったのかもしれない。
第五章 最後の天秤
廃工場の最上階。月明かりが、錆びた鉄骨の影を床に長く伸ばしていた。カイは、待ち受けるリオと対峙した。
「終わりにしよう、リオ」
「ああ、終わりにしてやる」
リオが羅針盤を掲げると、再びあの錆びた歯車が空間を埋め尽くす。だが、カイはもう怯まなかった。彼は自らの羅針盤を強く握りしめ、リオの心に呼びかける。憎しみではなく、かつて分かち合った友情の記憶、その温もりだけを込めて。
二人の感情が、激しく共鳴した。
その瞬間、世界が変わった。軋んでいた歯車が、音を立てて砕け散る。その破片は眩い光の粒子へと変わり、宙を舞い始めた。そして、その光が集まり、一つの形を成していく。それは、優しく微笑む、リオの亡き姉の姿だった。彼の思考の深層に眠っていた、最も美しく、最も切ない記憶の断片。
カイは愕然とした。自分の身体が軽くなるどころか、逆に、凄まじい質量が流れ込んでくる。温かく、そして悲しいほどの重みが、彼の魂を満たしていく。リオの羅針盤の針が、急速にゼロへと向かっていた。
「強奪じゃ、なかったのか……?」
「……言っただろ」リオの身体が、足元から透き通り始めていた。その表情は、長い苦しみから解放されたかのように、穏やかだった。「お前を、『思い出』にしてやるって」
彼の目的は、奪うことではなかった。自らの存在の全てをカイに「移譲」し、カイを時間という牢獄から解き放つこと。それが、彼が見つけ出した、友情の究極の献身だったのだ。
第六章 透明な永遠
「俺は、姉さんを失った。時間と共に薄れていく記憶が、耐えられなかった。でも、思い出になった者は、永遠に忘れられることがない」
リオの声は、風に溶ける囁きのようだった。彼の身体はほとんど光の粒子となり、カイの周りを漂っている。
「君には、そんな悲しみを味わってほしくなかった。カイ、君が俺の全てを記憶してくれれば、俺は君の中で永遠に生きられる。君は、俺や、サラや、これから出会う全ての友の想いを抱いて、無限の時を生きるんだ」
それが、君への、俺からの最高の贈り物だ。
そう言い残し、リオの姿は完全に消えた。彼の錆びた羅針盤は、カシャンと音を立てて砕け散り、砂のように崩れていく。それと同時に、カイの手にあった羅針盤が、まばゆい光を放った。その真鍮の枠の中で、文字盤は一点の曇りもない完全な透明へと変わっていく。カイの存在の重みが、ゼロになった証だった。
カイの身体もまた、光に包まれ、その輪郭を失っていく。物理的な世界から彼の姿が消え、意識だけがどこまでも上昇していくのを感じた。もはや、重さという概念はない。彼は、街を見下ろし、世界を見渡し、過去と未来を同時に見ていた。サラがカフェで微笑む姿も、リオが姉の手を握っていた遠い日の記憶も、全てが等しく、彼の内に在った。
触れることはできない。語りかけることもできない。だが、彼は全てと共にあった。孤独でありながら、決して一人ではない。
透明に輝く羅針盤を胸に、カイは、ゼログラムの永遠を静かに生き始めた。