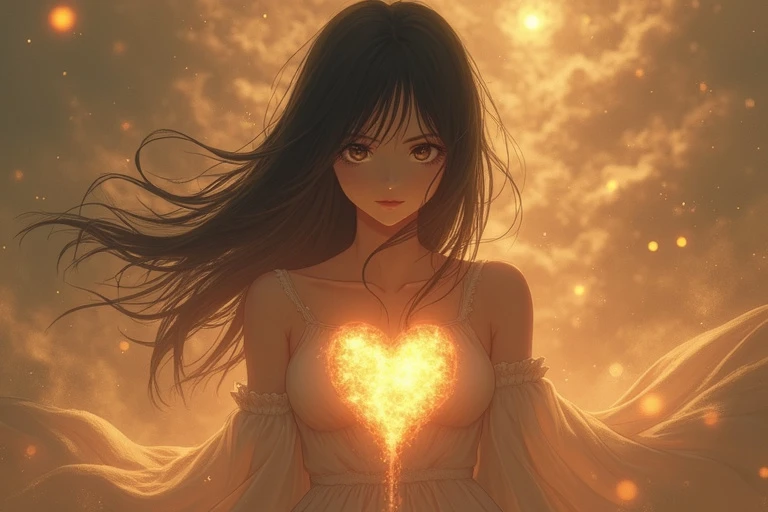タイトル**: 砂の檻、君と紡ぐ明日
第一章 瑠璃色の破片
口腔いっぱいに広がったのは、噛み砕いたアルミホイルのような味だった。
視覚よりも先に、不快な電気信号のような痺れが舌先を走り、私の世界を灰色に塗り潰していく。
建設中のビルから落下した鉄骨がアスファルトを砕く重低音。その残響が、耳の奥でいつまでも不協和音を奏でている。
舞い上がる粉塵は、夕焼けの光を吸い込んでドロリとした粘膜のように視界を覆っていた。その濁った膜の向こう側に、レンがいた。
かつて白かったシャツが、べっとりと濡れた黒に近い赤に侵食されている。
「あ……」
喉から漏れたのは、言葉ですらない空気の摩擦音だった。
駆け寄ろうとする足がもつれる。靴底でガラス片が悲鳴を上げ、その感触が背筋を冷たく駆け上がった。
レンの体は、不自然に折れ曲がっていた。まるで糸の切れたマリオネットのように、重力に無防備に晒されている。
彼の手首を掴む。
脈がない。
昨夜、あんなに熱く私の手を握りしめ、「ずっとそばにいる」と誓ってくれたその指先が、今は濡れた石ころのように冷たい。急速に、暴力的なまでの速度で、彼という生命が物体へと変質していく。
レンの瞳が開いていた。焦点はどこにも結ばれず、硝子玉のように虚ろに天を仰いでいる。その瞳の奥底に焼き付いているのは、恐怖か、それとも痛みか。それを読み取ることさえ、もう許されない。
四度目だ。
四度、私は彼が肉塊に変わる瞬間を見ている。
胸のポケットで、硬質な金属が肋骨をノックした。
震える指先が、無意識のうちにそれを探り当てていた。銀色の懐中時計。装飾の一切ない、冷ややかな感触。
蓋を弾くと、そこには時間を刻む針の代わりに、青白い燐光を放つ砂が封じ込められたガラス管が鎮座している。
「時の砂時計(クロノス・サンドグラス)」。
(戻らなきゃ)
思考よりも先に、脊髄が反射した。
このままではいけない。彼が死ぬという事実は、私の世界において許容できないエラーだ。修正しなければならない。
底にあるネジを巻く。カリ、カリ、という乾いた音が、頭蓋骨の内側を直接ひっかくように響く。
重力を嘲笑うように、青い砂が下から上へと昇り始めた。
その瞬間、内臓を素手で鷲掴みにされたような悪寒が走る。
代償の徴収だ。
昨晩の記憶が脳裏を過る。古い映画のエンドロール、二人で分け合った冷めたピザの味、レンが私に向けた照れくさそうな視線。
その映像が、強酸に浸されたフィルムのように溶け出す。
「楽しかった」という情報のタグだけを残して、その瞬間に私の胸を焦がした高揚感や、彼を愛おしいと感じた温度だけが、砂時計の砂となって吸い上げられていく。
「やめて……」
恐怖で歯の根が合わない。
レンの死に顔を見ても、悲しみよりも先に「またやり直し作業が発生した」という事務的な徒労感が首をもたげた自分に、戦慄する。
涙が出ない。喉が詰まるような慟哭がない。
ただ、システムログを確認するように、「レンが死んだ」という事実だけが冷徹に処理されていく。
愛する人を失ったというのに、私の心は凪いだ水面のように静まり返ろうとしている。その静寂こそが、何よりも恐ろしかった。
それでも、私はネジを巻き続けることを止められない。
私の心が凍りつき、彼への愛が単なるデータの羅列に成り下がったとしても、彼という個体が消滅するよりはマシだ。
そう自分に言い聞かせ、私は奥歯が砕けるほど強く噛み締めた。
世界が青白い光に溶け、血の赤も、灰色の粉塵も、すべてが逆回転する渦の中へと飲み込まれていく。
私の魂の一部を燃料にくべて、時間は再び、あの朝へと遡る。
第二章 歪む世界、欠落する心
小鳥のさえずりが、耳障りなノイズのように鼓膜を叩く。
瞼を開けると、見慣れた天井があった。差し込む朝陽は白々しく、部屋の輪郭を鋭利に切り取っている。
枕元の時計は午前七時。
体が鉛のように重い。繰り返される時間遡行が、肉体ではなく精神の摩耗として蓄積しているのだ。
「……おはよう、アリス」
階下に降りると、レンがトーストを焼いていた。
香ばしい小麦の匂いが漂うキッチン。彼は振り返り、屈託のない笑顔を私に向ける。その目尻の皺、少し癖のある前髪。かつてはそれを見るだけで、胸の奥が甘く疼いたはずだった。
私は自分の胸に手を当てる。
動かない。
心臓はただ血液を送り出すポンプとして機能しているだけで、そこには何の情感も宿っていない。
目の前にいる彼が「生きていてよかった」という安堵はある。だがそれは、高価な花瓶が割れずに済んだときに感じる安堵と、何ら変わりがなかった。
彼への熱情が、愛着が、まるで古い塗装のように剥がれ落ちている。
「……おはよう」
表情筋を引きつらせて作った笑顔は、きっと酷く歪んでいたに違いない。けれどレンは気づかない。
「今日は駅前には行かないで」
食卓につき、私は事務的に告げた。コーヒーの湯気が立ち上る向こうで、レンが不思議そうに首を傾げる。
「え? 新作のケーキ、楽しみにしてたじゃないか」
「気分が変わったの。今日は家で……映画でも観ましょう」
私の声は、ひどく平坦だった。説得というよりは、指示に近い。
レンは一瞬、戸惑いの色を見せたが、すぐに「わかったよ」と苦笑した。「アリスの気まぐれには慣れてるからね」
午後、リビングで二人きりの時間を過ごした。
レンはソファに寝転がり、古いコメディ映画を見て声を上げて笑っている。
私は窓際に立ち、外の景色を監視していた。
世界は、確実に狂い始めていた。
最初は小さな違和感だった。庭の紫陽花の色が、毒々しい蛍光ピンクに変色している程度のこと。
だが今は違う。
向かいの家の屋根が、ありえない角度で捻じれている。まるで濡れた雑巾を絞ったかのように、瓦が歪曲し、空に向かって鋭く突き出しているのだ。
通りを歩く人々の顔が一瞬、のっぺらぼうに見える。目も鼻も口もない肌色の塊が、何食わぬ顔で歩き、次の瞬間にはまた元の顔に戻る。
背筋に氷柱を差し込まれたような寒気がした。
世界が拒絶している。
死ぬべき定めのレン・キサラギを、無理やり生かし続けるこのループを、世界そのものが「バグ」として処理しようとしている。
修正しようとする力が、歪みとなって周囲を侵食しているのだ。
ふと、リビングの床に落ちているレンの影に目が留まった。
窓から差し込む陽光は強い。私の影はくっきりと床に伸びている。
だが、レンの足元には、影がなかった。
彼の存在だけが、光学的にも世界から切り離されている。
「……ねえ、レン」
声をかけようとした、その時だった。
ミチ、ミチミチ……という異音が、空間そのものから響いた。
天井の石膏ボードが、まるで水飴のように垂れ下がってきたのだ。物理法則を無視した粘性を持って、それは鋭利な槍の形へと変形していく。
狙いは、ソファに寝転がるレンの胸。
「レン、動いて!」
私が叫ぶと同時に、天井から白い槍が射出された。
「え?」
レンが反応するよりも早く、私はテーブルを蹴って彼に体当たりをした。
ドォォォン!!
凄まじい衝撃音と共に、レンがいたはずのソファが粉砕される。綿とバネが飛び散り、床板ごと貫通した石膏の槍が、深々と地面に突き刺さっていた。
土煙の中、レンが腰を抜かして震えている。
「な、なんだよこれ……。地震? いや、天井が……」
彼の顔色は蝋のように白い。
私は理解した。これは事故ではない。
明確な殺意だ。
世界が、牙を剥いている。物理法則を書き換えてでも、レンという異物を排除しようとする強制力。
回数を重ねるごとに、その殺意はより直接的で、より回避困難なものになっている。
ポケットの中の砂時計が、焼けた鉄のように熱を帯びていた。
これ以上使えば、次は家ごと潰されるかもしれない。
いや、その前に、私の心が完全に壊れる。
レンを助けてと願うたびに、彼を愛した理由が消えていく。
彼を守ろうとすればするほど、彼が私にとって「どうでもいい他人」に近づいていくパラドックス。
その恐怖さえも、今は薄膜越しの出来事のように遠い。
「逃げるよ、レン」
私は彼の手を引いた。その手の温かさが、もはや不快な熱さにしか感じられない自分に気づかないふりをして。
第三章 ゼロへの回帰
逃げ込んだのは、町外れの廃工場だった。
夕闇が迫る空は、紫色と緑色が混じり合った不吉なマーブル模様を描いている。遠くに見える街並みは、蜃気楼のように揺らぎ、時折ブロックノイズのような欠損を見せていた。
二人で錆びついた鉄骨の陰に座り込む。
レンは荒い息を吐きながら、自身の足元を見つめていた。そこにはやはり、影がない。
「……アリス、僕だけおかしいんだね」
震える声が静寂に落ちた。
「影もない。鏡を見ても、自分が映らないんだ。世界中が、僕をいないものとして扱おうとしてる」
彼は賢い。この異常事態が、自分を中心に起きていることを悟ってしまった。
私はポケットから砂時計を取り出した。ガラス管の中の砂は、もはや青白くはない。どす黒い赤色に変色し、不規則に脈動している。
「これのせいだね」
レンが砂時計を見つめる。責めるような響きはなかった。ただ、悲しいほどの納得だけがあった。
「君が何度も時間を戻してくれた。僕を助けるために。……その代償に、君は何を失ったの?」
心臓が跳ねた。
彼は気づいていたのだ。私の目が、かつてのように彼を見ていないことに。
熱のない視線。義務感だけの接触。
私の魂から彼への愛が削げ落ちていく様を、彼は一番近くで感じ取っていたのだ。
「私は……」
言葉に詰まる。
嘘をつこうとしたが、言葉が出ない。感情の枯渇は、嘘をつくための情熱さえも奪っていた。
「もういいよ、アリス」
レンが私の手を取り、砂時計を包み込んだ。
「これ以上、君を空っぽにしてまで生きたくない。僕が死ねば、世界は元に戻る。君も、君に戻れる」
「だめ……!」
「アリス、君は今、僕のために泣いてない」
その言葉は、鋭利な刃物のように私の胸を抉った。
ハッとして自分の頬に触れる。
乾いている。
目の前で彼が死を受け入れようとしているのに、世界が崩壊しかけているのに、私の涙腺は一滴の雫も生み出さない。
悲しいという概念はある。けれど、心が震えない。
まるで他人の悲劇をスクリーンの外から眺めている観客のように、冷え切っている。
このまま砂時計を使い続ければ、私は完全に感情を失うだろう。レンを生かすためだけの、心を持たない観測装置になる。
逆に、砂時計を使うのをやめれば、レンは数分以内に世界の修正力によって殺される。私は彼を愛した記憶を持ったまま、彼に別れを告げることができる。
(それでいいの?)
心の中の残滓が囁く。
愛する人の死を悼む心を守るために、彼を見殺しにするのか?
美しい悲劇のヒロインで終わるために、彼を犠牲にするのか?
否。
たとえ私が私でなくなっても。
彼への想いが完全に消滅し、二度と思い出せなくなったとしても。
彼が生きて、明日を迎えること。それだけが、私がこの狂った時間を繰り返した唯一の「願い」だったはずだ。
愛が消えるなら、消えればいい。
その感情があったという事実ごと、この砂時計に食わせてやる。
ゴゴゴゴ……と、工場の屋根が唸りを上げた。
頭上の鉄骨が、飴細工のようにねじ切れ、落下してくる。
時間切れだ。
「レン、ごめんね」
私は砂時計を握りしめた。
「君を愛していた記憶なんて、くれてやる」
「アリス、何を──」
「生きて、レン。私が君を忘れても、君が私を他人のように扱っても、それでも生きて!」
私は砂時計のネジを巻くのではない。
石畳に、そのガラス管を叩きつけた。
パァン!!
硬質な破砕音が響き渡る。
赤黒い砂が空中に弾け飛んだ。それは煙のように舞い上がり、落下してくる鉄骨を、崩れ落ちる屋根を、歪んだ空の色を、すべて光の彼方へと押し流していく。
因果の鎖が千切れる音がした。
私の胸の奥にあった、レンへの最後の執着が、愛しさが、光の粒となって剥がれ落ちていく。
ああ、これが彼を好きだった気持ちか。こんなにも温かくて、苦しくて、綺麗なものだったのか。
それが指の隙間からこぼれ落ち、虚無へと吸い込まれていくのを、私はただ呆然と見送った。
視界が真っ白に染まり、意識が溶けていく。
さようなら、私の愛。
最終章 名前のない関係
ふと、金木犀の甘い香りが鼻をかすめた。
気がつくと、私は駅前のベンチに座っていた。
手の中には、砕けた金属の欠片が握られている。それはもう何の力も持たない、ただのガラクタだった。
深く息を吸い込む。
肺に満ちる空気は、秋の冷涼さを孕んで澄み切っていた。
胸に手を当てる。
そこには、ぽっかりと大きな空洞があった。
何かが決定的に欠落している。とても大切な、私の半身とも呼べるような何かを失った喪失感。けれど、それが何だったのか、どうしても思い出せない。
悲しくはない。ただ、ひどく風通しがいい。
「……あれ? アリス?」
不意に名前を呼ばれ、顔を上げる。
改札口から出てきたのは、学生服を着た少年だった。
レン・キサラギ。近所に住む幼馴染。
彼を見て、私は瞬きをした。
怪我ひとつない。元気そうだ。
その事実を確認して、「ああ、よかった」と思った。
それだけだった。
胸の高鳴りも、駆け寄りたいという衝動も、一切湧き上がってこない。
まるで、クラスメイトの一人に偶然会ったときのような、平坦な感情。
「……ああ、レンくん。奇遇だね」
自分の口から出た「レンくん」という響きが、妙に他人行儀で、けれど今の私にはしっくりときた。
以前はどう呼んでいただろうか。思い出せない。今の私たちには、この距離感が適切なのだと感じる。
レンは少し驚いたように目を丸くし、それから複雑そうな、どこか寂しげな笑みを浮かべた。
「『レンくん』か……。なんだか、久しぶりに会ったみたいだ」
彼もまた、何かを感じ取っているのかもしれない。
私たちを結びつけていた太い絆が消失し、ただの細い糸になってしまったことを。
しかし、彼は生きていた。
影もちゃんと足元にある。世界は彼を受け入れ、当たり前の日常が動いている。
それこそが、私が代償を払って手に入れた結果なのだと、理屈ではなく直感で理解した。
失ったものは戻らない。
あの熱烈な感情も、魂を共有するような一体感も、もう二度と手に入らないかもしれない。
私は彼の「親友」でも「特別な人」でもなくなり、ただの「顔見知り」になった。
けれど。
「ねえ、アリス。もし時間あるならさ」
レンが少し頬を赤らめて、鞄の持ち手をぎゅっと握りしめた。
「駅前に新しいカフェができたんだ。一人じゃ入りづらくて……付き合ってくれない?」
その不器用な誘い文句を聞いたとき、胸の空洞の底で、小さな、本当に小さな灯火が揺れた気がした。
それは過去の残骸ではない。
まったく新しい、未知の感情の種火。
私は空っぽになった心で、その温もりを確かめるように、ゆっくりと口角を上げた。
かつてのようには笑えないかもしれない。
でも、新しい笑顔なら、作れるかもしれない。
「いいよ。行こうか、レン」
ベンチから立ち上がり、彼と並ぶ。
肩と肩の間には、以前よりもずっと広い隙間がある。
ぎこちなく、よそよそしい二人の距離。
秋の高い空の下、私たちは歩き出した。
ゼロになった関係。白紙になったページ。
そこからまた、どんな物語を描けるのかはわからないけれど。
私たちは生きて、明日へと続く道を、確かに踏みしめている。