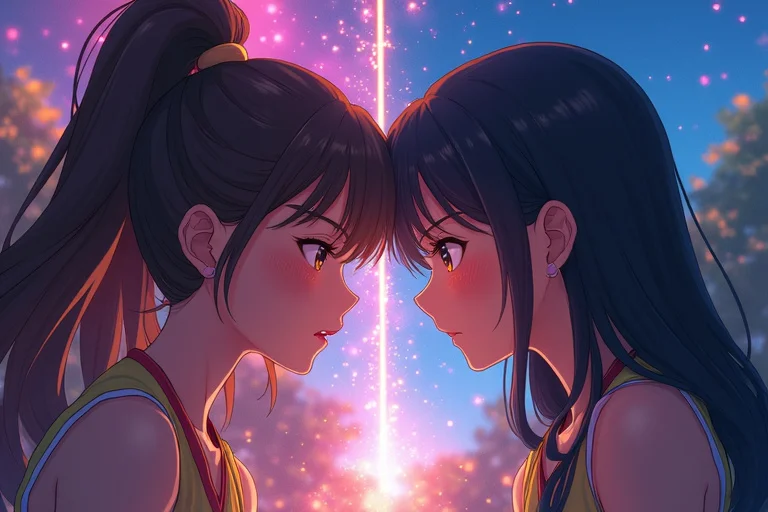第一章 灰色の遺言
葬儀の間、空はずっと泣いていた。
あるいは、そう見えただけかもしれない。
俺の視覚野には、降り注ぐ雨がただのノイズ信号として処理されていたからだ。
「カイト君、これ」
差し出されたのは、小指の先ほどのチップだった。
濡れた喪服の袖口から覗く、レンの母親の手が震えている。
「あの子の部屋から見つかったの。『カイトにだけは渡してくれ』って、メモ書きがあって……」
俺は無言でそれを受け取った。
指先に触れた瞬間、ひやりとした冷気が走る。
旧世代のメモリードライブ。
今のクラウド全盛の時代に、わざわざ物理メディアに残すなんて、アナログ好きのあいつらしい。
「……ありがとうございます」
喉から絞り出した声は、ひどく掠れていた。
悲しいわけじゃない。
ただ、喉が渇いているだけだ。
俺は感情というバグを排除して生きる、フリーランスの記憶技師(メモリー・エンジニア)。
他人の脳内にあるトラウマを除去するのが仕事だ。
自分の感情すら整理できない人間に、他人の心が救えるわけがない。
そう嘯(うそぶ)いて、俺は十年前に「感情」という回路を意図的に閉じた。
だから、親友だったレンが死んでも、涙は出ない。
心拍数すら一定だ。
ただ、受け取ったチップを握る右手が、微かに熱を持っている気がした。
帰宅後、俺は遮光カーテンを閉め切った作業部屋に籠もった。
機材のファンが唸りを上げている。
デスクには飲みかけの冷めたコーヒーと、無造作に置かれたドライブ。
「さて……何を残したんだ、お前は」
ヘッドギアを装着し、ジャックを首筋のポートに接続する。
視界が暗転し、網膜に緑色のコードが走り始めた。
俺にとって、記憶のデータは「音」と「色」で見える。
通常、整理された記憶は美しいハーモニーを奏でる。
だが、レンのドライブから流れてきたのは、耳をつんざくような不協和音だった。
ガリガリ、ザザッ。
砂嵐のようなノイズ。
『アクセス権限がロックされています』
無機質なシステム音声。
俺は眉をひそめた。
ただの遺言ムービーなら、こんなプロテクトはかけない。
これは、深層領域(ディープ・レイヤー)だ。
人間の人格形成に関わる、最も深い場所の記憶。
「……上等だ」
俺はコンソールを叩いた。
キーボードを打つ指が加速する。
俺に見せてみろ。
いつも馬鹿みたいに笑っていたお前の、その裏側にあったものを。
第二章 陽だまりの亡霊
ファイアウォールを一枚破るたびに、ノイズが形を変えていく。
最初は不快な金属音だったものが、次第に懐かしい旋律を帯び始めた。
放課後のチャイム。
自転車のチェーンが回る音。
炭酸が弾ける音。
視界に広がるのは、セピア色の景色だ。
『よお、カイト。相変わらず辛気臭い顔してんな』
不意に、目の前にレンが現れた。
高校時代の制服姿。
首から一眼レフをぶら下げ、悪戯っぽい笑みを浮かべている。
これはAIによって再現されたアバターだ。
本人の思考パターンを模倣しているに過ぎない。
「死人が軽口を叩くな。これは何だ?」
俺は周囲の空間を指した。
そこは、俺たちがよくサボっていた学校の屋上だった。
『何って、俺の最高傑作だよ。お前に見せるためのな』
レンのアバターがフェンスに寄りかかる。
風が吹くと、彼の方になびく髪の毛一本一本までがリアルに計算されていた。
「俺は忙しい。要件を言え」
「相変わらずだなあ。まあいい、そこにある『キャンバス』を見てみろよ」
レンが顎でしゃくった先。
何もない空中に、一枚の絵画が浮いていた。
それは、俺の肖像画だった。
だが、異様だった。
顔の部分が黒く塗りつぶされ、そこから極彩色の花が溢れ出している。
「なんだこれ……趣味が悪い」
「そうか? お前の内側はいつだってこんな感じだろ」
レンが笑う。
「お前は天才だよ、カイト。人の記憶を解析して、悪い部分を切り取る。まるで外科医だ。でもさ、切り取った『痛み』はどこに行くと思う?」
「消去されるだけだ」
「違うな。データは消えない。どこかに移動するだけだ」
レンの表情から笑みが消えた。
「お前が十年前、自分の『悲しみ』を消去した日。あの日のバックアップ、どこにあるか覚えてるか?」
心臓が、ドクリと跳ねた。
十年前。
俺が記憶技師になると決めた日。
そして、ある事故で両親を失った日だ。
あの時の記憶は曖昧だ。
あまりのショックに、俺は自分の記憶の一部を自分で処置(ハッキング)した。
悲しすぎて壊れそうだったから、感情回路を焼き切ったのだ。
そう思っていた。
「覚えてないよな。お前は『消した』と思ってる」
レンが一歩近づく。
「でも、俺が『預かった』んだよ」
第三章 共鳴する傷跡
「……は?」
思考が停止した。
預かった?
記憶の移植は違法だ。それに、そんな技術は未完成のはずだ。
「嘘だ」
「嘘じゃない。証拠を見せてやる」
レンが指を鳴らす。
瞬間、屋上の景色が崩壊した。
青空がガラスのように砕け散り、どす黒い闇が溢れ出す。
耳鳴りがする。
子供の泣き声。
サイレンの音。
炎が爆ぜる音。
『熱い、熱いよカイト!』
俺じゃない。
これは、レンの声だ。
視界に浮かぶログデータ。
[Timestamp: 2035.08.15]
[Target: Kaito_S]
[Action: Memory Transfer -> Ren_A]
[Status: Complete]
あの日、火事の現場で。
泣き叫ぶ俺の横で、レンが俺の頭にケーブルを繋いでいる。
『カイト、このままだとお前の心が壊れる』
『俺が半分もらう。いや、全部もらう』
「やめろ……!」
現実の俺は、椅子の上で頭を抱えていた。
激痛が走る。
封印されていた回路が、無理やりこじ開けられていく。
俺が「感情を捨てた」んじゃない。
レンが、俺の「絶望」をすべて引き受けてくれたんだ。
その代償に、あいつはずっと。
この十年間、俺の両親が焼け死ぬ悪夢を、俺の代わりに見続けていたのか?
「ふざけるな……!」
俺は叫んだ。
「なんで言わなかった! なんで平気な顔をして笑ってたんだ!」
闇の中で、レンのアバターが困ったように笑っている。
その体はノイズ混じりで、今にも消えそうだ。
『言ったら、お前は自分を責めるだろ? それじゃ意味がない』
『お前には、綺麗な目のままで世界を見ていてほしかった』
レンの体が透けていく。
『でも、もう限界だったんだ。俺の脳(ハードウェア)が、お前の悲しみ(データ)に耐えられなくなった』
レンの死因は不明とされていた。
だが、これで分かった。
脳への過負荷(オーバーロード)。
俺の記憶を守り続けたことによる、精神の崩壊だ。
「俺が……お前を殺したのか」
震えが止まらない。
涙が、止めどなく溢れてくる。
十年分の涙が、決壊したダムのように。
『違う。俺が選んだんだ。これが俺の友情だ』
レンの手が、俺の頬に触れる。
冷たいはずのデータなのに、温かい。
『このドライブには、俺が預かっていたお前の感情と、俺自身の楽しい記憶を混ぜてある』
『これをインストールすれば、お前は元に戻れる。……ただし、痛みも戻ってくるけどな』
第四章 雨上がりのノイズ
目の前に、二つの選択肢(コマンド)が浮かんでいる。
[DELETE] : すべてを消去し、感情のない平穏な日々に戻る。
[MERGE] : レンが遺したデータを取り込み、痛みと共に生きる。
迷いはなかった。
「……返せよ、馬鹿野郎」
俺は[MERGE]を叩いた。
光が溢れた。
濁流のような感情が流れ込んでくる。
悲しみ、後悔、絶望。
けれど、その中には確かな光があった。
放課後の屋上で飲んだサイダーの味。
くだらない冗談で笑い転げた日々の体温。
「お前はすごいよ」と、俺を認め続けてくれた親友の声。
それらすべてが、レンというフィルターを通して、鮮やかな色彩(カラー)となって俺の中に溶けていく。
「ぐっ、ううぅ……あぁぁあああ!」
俺は吠えた。
部屋の中で、一人。
獣のように泣き喚いた。
痛い。
苦しい。
寂しい。
でも、この痛みこそが、あいつが生きていた証だ。
あいつが守ってくれた、俺の命だ。
第五章 世界は色で満ちている
ヘッドギアを外すと、朝が来ていた。
カーテンの隙間から、朝日が差し込んでいる。
埃がキラキラと舞っているのが見えた。
窓を開ける。
雨上がりの匂いがした。
濡れたアスファルトの匂い。
街路樹の緑の匂い。
どこかの家で朝食を作る匂い。
「……眩しいな」
呟いた声は震えていたが、もう掠れてはいなかった。
世界は、こんなにもうるさくて、煩わしくて。
そして、どうしようもなく鮮やかだ。
俺はデスクに残されたチップを手に取った。
データはもう空っぽだ。
でも、その琥珀色のチップは、朝日を透かして美しく輝いていた。
「行くか」
俺はジャケットを羽織る。
今日は、あいつの好きだった丘へ行こう。
そこでなら、あいつのノイズがまだ聞こえる気がする。
俺の中で生き続ける、お節介で、馬鹿で、最高の親友のノイズが。
俺はドアを開けた。
騒がしい世界が、俺を待っていた。