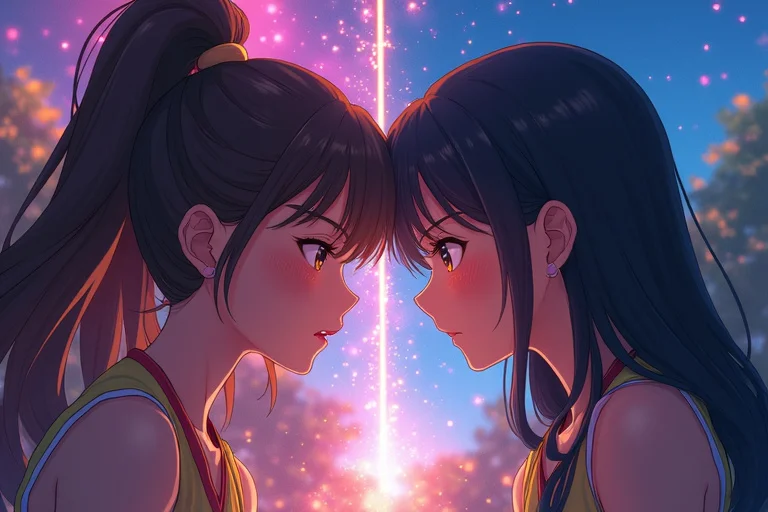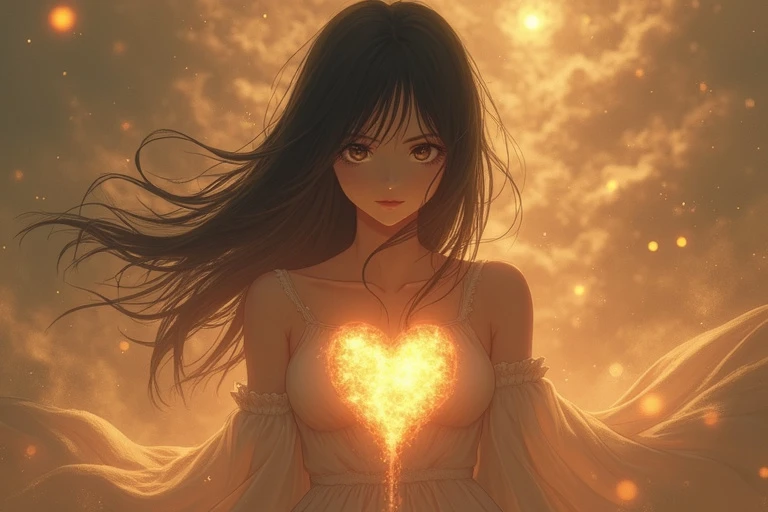「なあアキラ、もっと高く飛べないのか?」
ヘッドセットから響くユウキの快活な声に、俺、斉藤アキラは溜め息で応じた。目の前には、現実と寸分違わぬ、しかし物理法則が通用しない摩天楼が広がっている。俺たちは今、重力の軛を解かれた鳥のように、ネオンきらめく夜のビル群を縫って飛んでいた。
ここは、俺が偶然発見した秘密の遊び場。都市インフラを統括する超高度AI『マザー』のシステム深層に存在する、開発者用の仮想空間――通称『サンドボックス』だ。現実世界では運動音痴で引きこもりがちな俺も、ここでは創造主になれる。
「無茶言うな。これ以上パラメータをいじると、マザーに異常を検知される」
「ちぇっ、つまんないの。現実のお前みたいに慎重だな」
軽口を叩きながら、ユウキはきりもみ回転して俺を追い抜いていく。ユウキは俺の幼馴染で、正反対の男だ。快活で、誰にでも好かれ、パルクールで鍛えた身体能力は人間離れしている。そんな彼が、デジタルの世界では俺の指示に従うのが、少しだけ誇らしかった。この秘密を共有できるのは、世界でユウキただ一人だ。
その日、俺たちの楽園に、不協和音が響いた。
サンドボックスの風景が、一瞬、砂嵐のように乱れたのだ。
「なんだ今の?」
「ノイズ……?いや、違う。外部からの不正アクセスだ」
俺はすぐさまコンソールを開き、ログを走査する。そこには、見たこともない凶悪なコードが、まるでウイルスのように自己増殖しながら、サンドボックスの壁を侵食している記録が残っていた。
「まずいぞユウキ、誰かがここを嗅ぎつけた。しかも、マザーのコアシステムにアクセスするための踏み台にしようとしてる!」
もしマザーが乗っ取られれば、交通、電力、通信……この街の全てが機能不全に陥る。
「どうするんだよ、アキラ!」
ユウキの焦った声が、俺の覚悟を固めさせた。
「決まってる。俺たちの遊び場は、俺たちが守る」
ハッカーの正体は、すぐに割れた。都市伝説的に語られていたハッカー集団『グレイ・ノイズ』。彼らの目的は、マザーを支配し、都市を混乱に陥れることだった。
俺は自室のPCに向かい、猛烈な勢いでキーボードを叩き始めた。ユウキは俺の背後で、固唾を飲んで見守っている。
「奴らの侵入経路を特定した。防火壁を三重に張る!」
「よし、やっちまえ!」
しかし、敵は想像以上に手強かった。俺が壁を築くと、彼らは即座にそれを破壊する。イタチごっこが続く中、部屋の窓の外で、不審な飛行音が聞こえた。
「アキラ、上だ!」
ユウキが叫ぶ。窓の外には、カマキリのようなアームを付けた小型ドローンが十数機、ホバリングしていた。そのうちの一機が、アームの先端から赤いレーザーを照射し、俺たちの部屋の窓ガラスを焼き切り始める。
「リアルでも来たか!奴ら、俺の個人情報を特定しやがった!」
デジタルとリアルの同時攻撃。完全に俺たちのキャパシティを超えていた。
「アキラはコーディングに集中しろ!こっちは俺がなんとかする!」
ユウキはそう言うと、クローゼットから野球の硬球を数個掴み、ベランダへ飛び出した。
「無茶だ、ユウキ!」
「無茶じゃなきゃ、お前の親友はやってらんないんだよ!」
ユウキはドローンのレーザーを紙一重で避けながら、驚異的な身体能力で壁を蹴り、隣の部屋のベランダへと飛び移る。そして、渾身の力で投げた硬球が、一機のドローンのローターを正確に砕いた。火花を散らして落下するドローン。だが、敵の数はまだ多い。
俺はモニターに集中した。ユウキが時間を稼いでくれている。負けるわけにはいかない。
グレイ・ノイズのコードは巧妙だった。だが、そこには奇妙な『癖』があった。特定の関数を執拗に繰り返す、まるで何かに固執するようなパターン。これだ。この『癖』を利用すれば、カウンターを仕掛けられる。
「ユウキ!ドローンの制御システムにハッキングする!三十秒だけ、派手に注意を引いてくれ!」
「お安い御用だ!」
ユウキは屋上へと駆け上がると、給水タンクのてっぺんに立ち、大声でドローンを挑発し始めた。すべてのドローンが、一斉にユウキへと向かう。絶体絶命の光景。
俺は指がちぎれるほどの速度でコードを打ち込む。敵の『癖』を逆手に取ったトラップ・プログラムだ。あと少し。五秒、四秒……。
「アキラ、まだか!」
ユウキの声が悲鳴に変わる。
「――今だ!」
エンターキーを叩きつけた瞬間、世界が反転した。
グレイ・ノイズの制御下にあったドローンたちが、ぴたりと動きを止める。そして次の瞬間、全ての機体がアームをくるりと回し、互いを攻撃し始めたのだ。制御権を奪い返しただけでなく、同士討ちするようにプログラムを書き換えてやった。
デジタル世界でも、俺の仕掛けたトラップが発動していた。グレイ・ノイズのシステムは連鎖的にクラッシュし、マザーの深層から完全に排除された。静寂が戻る。俺は椅子に深くもたれかかり、大きく息を吐いた。
屋上から戻ってきたユウキは、煤で汚れながらも、満面の笑みを浮かべていた。
「見たかよ、アキラ!俺たちの勝ちだ!」
「ああ……お前が時間を稼いでくれたおかげだ」
俺たちは、どちらからともなく拳を突き合わせた。デジタルとリアル。内向的なハッカーと、行動的なアスリート。一人では決して見られない景色を、二人だから見ることができた。
翌日の夕暮れ。俺たちは再びサンドボックスにダイブしていた。眼下に広がる平和な街並みは、昨日よりもずっと輝いて見えた。
「なあ、アキラ」
ユウキが隣に浮かびながら言った。
「今度は、月の裏側でも作ってみないか?」
俺は笑って答えた。
「いいぜ。最高のロケットを用意してやるよ」
俺たちの冒険は、まだ始まったばかりだ。この広いデジタルとリアルの世界で、親友が一人いれば、不可能なことなんて何もない。俺はそう、確信していた。