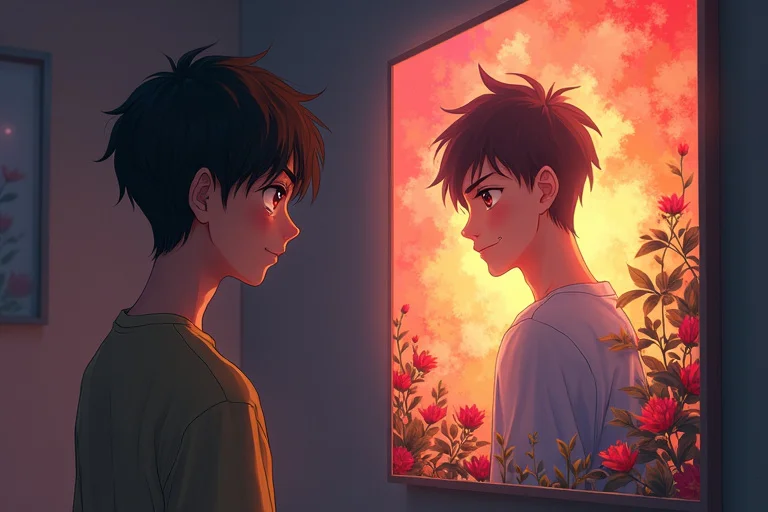第一章 才能の値段
「これで、足りるか」
重厚なマホガニーのカウンターに、俺は自分の右手を叩きつけた。
埃と古書、そして焦げた砂糖のような甘い匂いが充満する店内。アンティークランプの頼りない灯りが、店主の片眼鏡を冷ややかに照らしている。
「ほう……」
店主は細長い指で、俺の指先を宙でなぞるような仕草をした。直接触れてはいない。それなのに、皮膚の裏側を氷柱で撫でられたような寒気が走る。
「『絶対音感』に加えて、『即興演奏の才能』すべて。……よろしいのですか? レン様。貴方にとって、それは命そのものでしょう」
「能書きはいい。時間がないんだ」
喉が渇いて張り付く。心臓の早鐘が、肋骨がきしむほど激しく鳴っていた。
この店、『記憶質店(メモリー・ポーン)』では、形のないものを売買できる。
才能を売って金を得る者もいれば、悲しい記憶を消すために金を払う者もいる。
だが、俺の目的はそのどちらでもない。
「買い戻したいんだ。あいつの、ミナトの記憶を」
店主は口の端を三日月のように歪めた。
「他人の記憶を取り戻すには、等価交換以上の代償が必要です。貴方の音楽的才能すべてと引き換えに得られるのは、わずか十分間。……それでも?」
「構わない」
即答だった。迷えば、指先が惜しさを覚えて震えだすのを知っていたからだ。
店主がカウンターの下から、琥珀色の液体が入った小瓶を取り出す。
その中には、かつてミナトが売ってしまった『俺と過ごした青春』が封じ込められていた。
「契約成立です」
店主が指を鳴らす。
瞬間、俺の体から〝色〟が抜けた。
視界がモノクロームになったわけではない。ただ、世界を満たしていた音の色彩――雨粒がアスファルトを叩くB♭の響きや、空調のF#の唸り――が、ただの無機質な『雑音』へと変わったのだ。
喪失感が、胃の腑に鉛のように落ちる。
俺は震える手で小瓶を掴み、背中のギターケースを担ぎ直した。
「まいどあり」
背後で店主の低い笑い声がした気がしたが、俺は振り返らずにドアを蹴り開けた。
第二章 静寂の病室
雨が降っていた。
傘も差さずに走ったせいで、頬に張り付く髪が冷たい。だが、今の俺には雨音がただのノイズにしか聞こえない。かつてはそこにリズムを感じたのに、今はただ水が跳ねる音だ。
市立病院の三〇五号室。
消毒液と枯れかけた百合の匂いが混じる、最果ての場所。
「……ミナト」
ドアを開けると、ベッドの上の男がゆっくりと首を巡らせた。
痩せこけた頬、虚ろな瞳。そこに宿るのは、俺への親愛ではなく、見知らぬ他人に向けられる警戒心だけだ。
ミナトは若年性の認知障害を患っていた。
治療費を捻出するために、あいつは自分の記憶を少しずつ質屋に売っていたのだ。
最初は幼少期の思い出。次は好きな映画の記憶。そして最後には、俺という存在さえも。
「あなたは……誰ですか?」
掠れた声が、俺の胸を鋭利な刃物のように抉る。
俺は濡れた服も構わず、ベッドの脇に椅子を引き寄せた。
ギターケースを開ける。使い古したアコースティックギター。俺たちの夢の残骸。
「ただの通りすがりだよ。……少し、聴いてくれないか」
俺はポケットから琥珀色の小瓶を取り出し、ミナトの点滴のラインにこっそりと混ぜた。
医療行為としては狂気だ。だが、これは魂の輸血だ。
琥珀色の液体がチューブを伝って落ちていく。
俺はギターを構えた。
(指が……重い)
かつては呼吸するように動いた指先が、錆びついた蝶番のようにぎこちない。
才能を失った俺は、もう天才ギタリストじゃない。ただの、ギターが好きなだけの不器用な男だ。
それでも、弾かなきゃならない。
コードを押さえる。Gメジャー。簡単すぎるコードなのに、音が濁る。
「っ……」
情けなさで奥歯を噛み締める。
だが、ミナトの目がわずかに動いた。
俺は歌い出した。
曲名は『ブルー・アワー』。
高校の屋上で、二人で授業をサボって作った曲。
安い炭酸ジュースの味と、入道雲と、将来への根拠のない自信が詰まった曲。
音程は不安定で、リズムも走っている。
プロの耳が聞けば噴飯ものの演奏だ。
でも、今の俺にはこれしかない。
「♪錆びついたフェンスを越えて、僕らは何処へでも行けると思った」
歌声が震える。涙で視界が滲む。
その時だった。
「……コードが、違うよ、レン」
第三章 最後のセッション
心臓が止まるかと思った。
顔を上げると、ミナトが笑っていた。
あの頃と同じ、悪戯っ子のような、屈託のない笑顔で。
「そこはGじゃなくて、Gアドナインだろ。お前、相変わらず詰めが甘いな」
「……うるせえ」
声が詰まる。涙がボロボロとこぼれて、ギターのボディを濡らした。
「なんだよ、いい大人が泣くなよ。……久しぶりだな、レン。しばらく見ないうちに、随分老けたんじゃないか?」
ミナトの瞳に、確かな理性の光が戻っている。
小瓶の効果だ。だが、時間は十分しかない。
「お前こそ、サボりすぎだ。練習、付き合えよ」
「へいへい。天才様には敵わないね」
ミナトが弱々しく指を動かし、ベッドの柵をリズムよく叩き始めた。
タン、タタン、タン。
それは、俺たちがいつも合わせる時の合図。
俺は再び弦を弾く。
才能は消えた。絶対音感もない。聞こえてくるのは完璧な音楽じゃなく、泥臭い振動だけだ。
けれど、不思議なほど心地よかった。
ミナトのか細いハミングが重なる。
俺の拙いギターと、ミナトの掠れた声。
世界で一番下手くそで、世界で一番美しいセッション。
雨音がドラムのように窓を叩く。
雷光がスポットライトのように一瞬だけ部屋を照らす。
「なぁ、レン」
サビの合間、ミナトが呟いた。
「俺、いい夢を見てたんだ」
「……どんな?」
「お前がすごいミュージシャンになって、世界中のステージに立つ夢。……あれ、正夢になったか?」
俺は首を横に振った。
「いいや。俺はただの、お前の相棒だ」
「そっか……。なら、もっといいな」
ミナトが満足そうに目を細める。
九分が過ぎた。
モニターの心拍数が、静かな波を描いている。
「レン。ありがとうな。迎えに来てくれて」
「……バカ野郎。勝手に行くなよ」
「眠いんだ。……この曲が終わったら、寝てもいいか?」
俺は答えられず、ただ指を動かし続けた。
指先の皮が破れ、弦に血が滲む。痛みが、俺が生きている証だった。
最後のフレーズ。
ジャラーン、と不格好な音が病室に響き渡り、やがて静寂に吸い込まれていく。
ミナトの手が、シーツの上に力なく落ちた。
その顔は、穏やかに眠っているようだった。
「……ミナト?」
返事はない。
モニターの電子音だけが、無機質に時を刻んでいる。
俺はギターをケースにしまった。
不思議と、涙はもう出なかった。
胸の奥にあった空洞が、温かい何かで満たされているのを感じた。
俺は失った。
天才的な才能も、絶対音感も、音楽家としての未来も。
だが、俺は取り戻したのだ。
親友が最期に俺の名を呼び、笑ってくれた。
その記憶だけは、どんな高値がつこうとも、二度と売りはしない。
病室を出る。
廊下の窓から見える雨上がりの空には、薄っすらと虹がかかっていた。
「……音が、外れてやがる」
俺は自分の口笛がひどく音痴なことに気づき、一人で笑った。
その下手くそな旋律は、今まで聞いたどんな名曲よりも、美しく世界に響いていた。