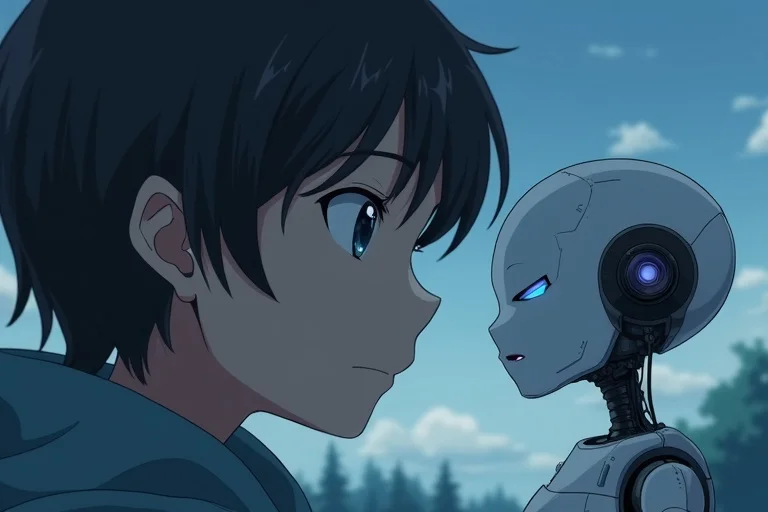第一章 閉じた瞳と、不意の来訪者
神崎湊(かんざきみなと)の世界は、常に薄い膜に覆われているようだった。大学の講義室、雑踏、アパートの自室。どこにいても、現実との間に一枚、すりガラスでもあるかのような隔たりを感じていた。人と深く関わることを無意識に避け、スケッチブックに無機質な風景を描き写すことだけが、彼の心を慰める唯一の術だった。
そんな湊には、誰にも言えない秘密があった。時折、唐突に、自分の視界ではない「誰か」の視界が脳内に流れ込んでくるのだ。それは一瞬のフラッシュバックのようで、強烈な陽光に照らされたターコイズブルーの海、黄金色に燃える水平線、猛スピードで迫ってくる波の壁といった、湊自身の生活とはかけ離れた、鮮烈な光景ばかりだった。最初は脳の異常を疑ったが、検査をしても結果はシロ。医者はストレス性の幻覚だろうと結論づけた。以来、湊はその現象をやり過ごし、孤独な日常の一部として飼い慣らしていた。
その日も、湊は巨大な講義室の後ろの席で、教授の退屈な声をBGMに、窓の外の灰色の空を眺めていた。不意に、強い陽射しの感覚と共に、視界が白く飛んだ。次の瞬間、目の前に広がったのは、白い砂浜と、どこまでも続く青のグラデーション。足元で砕ける波の音が、頭蓋の内側でリアルに響く。――またか。湊は静かに目を閉じ、幻影が過ぎ去るのを待った。
数秒後、視界が講義室に戻った時、隣の席にいつの間にか誰かが座っていることに気づいた。日に焼けた肌に、太陽の色を溶かし込んだような明るい茶髪の男。湊とは対極の存在感を放っていた。男は湊の視線に気づくと、人懐っこい笑みを浮かべた。
「わり、遅れた。ここ、空いてたよな?」
湊は小さく頷いた。男――名札には『宮内陽太(みやうちようた)』とあった――は、「サンキュ」と言うと、慌ててノートとペンを取り出した。
その時だった。
湊が何気なく陽太に視線を向けた、まさにその瞬間。彼の視界が、ぐにゃりと歪んだ。目の前の光景が、陽太の肩越しから見たノートへと、強制的に切り替わったのだ。インクの黒が滲んだ文字、『現代社会論』、教授が板書したキーワード。それは紛れもなく、陽太が見ている景色そのものだった。
「うわっ!」
湊は思わず小さな声を上げ、椅子を引いた。突然のことに、心臓が氷水で締め付けられたように冷たくなる。陽太が「ん? どうかしたか?」と不思議そうにこちらを向く。
「……いや、なんでもない」
湊は動揺を押し殺し、俯いた。全身から汗が噴き出す。今まで見てきた幻影は、いつも知らない風景だった。しかし、今のは違う。隣にいる人間の視界と、明確にリンクした。
これは一体、何なんだ?
講義の残り時間、湊は隣の男を意識しないように必死だった。だが、彼の内側で、固く閉ざされていた世界の扉が、ギシリと音を立てて軋み始めているのを、彼は確かに感じていた。それは、これから始まる嵐の前の、不気味な静けさにも似ていた。
第二章 ふたつの視界、ひとつの世界
陽太は、湊が築いてきた壁を、いとも簡単に乗り越えてくる人間だった。講義の後、「ノート見せてくれよ、ほとんど取れなかったんだ」と屈託なく笑いかけ、そのまま学食に湊を引っ張っていった。湊は戸惑いながらも、その太陽のような引力に逆らうことができなかった。
二人が親しくなるのに、時間はかからなかった。そして、あの奇妙な「視覚の共有」は、気のせいなどではなかったことを、湊はすぐに確信する。二人で話している時、感情が高ぶると、不意にお互いの視界が混線するのだ。湊がコーヒーカップを見つめていると、陽太が見ている窓の外の景色が割り込んでくる。陽太が熱っぽく何かを語っていると、その陽太を見つめる湊自身の視点が、陽太の脳内に流れ込むらしかった。「お、今見えた! 俺、そんな真剣な顔して話聞いてくれてるんだな」と陽太は面白がった。
湊が時折見ていた海の光景は、すべて陽太が見ていたものだった。サーフィンが趣味の陽太は、暇さえあれば海へ向かっていたのだ。
「お前が見てたの、絶対これだろ!」
ある週末、陽太は湊を自分の車に乗せ、半ば強引に海へ連れ出した。潮の香りが鼻腔をくすぐり、目の前に広がったのは、湊が「幻覚」の中で何度も見てきた、あのターコイズブルーの世界だった。
「……すごい」
湊は、ただ呆然と呟いた。すりガラスの向こうにあった世界が、今、目の前にある。肌を撫でる風も、寄せては返す波の音も、すべてが本物だった。
この不思議な繋がりは、二人の友情を急速に、そして強固に育てていった。湊は、陽太の目を通して、自分が決して足を踏み入れることのなかった世界を知った。サーフボードの上から見る、朝日に染まる海。仲間たちと笑い合うビーチでのバーベキュー。大会の熱気と緊張感。陽太の視界から流れ込んでくる鮮やかな光景は、湊のモノクロームだった世界に、少しずつ色を与えていった。彼は、閉ざしていた心の内側から、世界と繋がる喜びを感じ始めていた。
一方で陽太もまた、湊の視点から新しい世界を発見していた。湊がスケッチブックに向かう時の、驚くほどの集中力。一本の鉛筆が生み出す、光と影の繊細なグラデーション。図書館の窓枠に切り取られた、雨に濡れる紫陽花の静かな美しさ。陽太は、湊の目を通して、日常に潜む静謐な美しさに気づかされた。
「湊の見る世界って、なんか静かで、綺麗だよな。俺、そういうの全然気づかなかった」
そう言って陽太は、湊が描いた風景画を、宝物のように眺めるのだった。
ふたつの異なる視界は、互いを補い合い、一つの豊かな世界を形成していった。湊は生まれて初めて、他者と魂で繋がるという感覚を味わっていた。この友情は永遠に続くのだと、彼は信じて疑わなかった。この温かな光が、失われることなど想像もできなかった。
第三章 嵐の残響
その知らせは、一本の電話によって、唐突にもたらされた。季節が秋へと移り変わろうとする、ある土曜日のことだった。空は低く垂れ込めた灰色の雲に覆われ、朝から冷たい雨が降り続いていた。天気予報は、大型の台風が接近していると警告していた。
「もしもし、陽太か?」
『おう、湊! なんだよ、声暗いぞ』
電話の向こうで、陽太は不釣り合いなほど明るく笑っていた。背景には、ゴウゴウと荒れ狂う風の音が響いている。
「お前、まさか……海にいるのか? こんな日に」
『当たり前だろ! こんな最高の波、めったに来ないんだぜ。伝説作ってくるわ!』
「馬鹿なこと言うな! 危ないから今すぐ帰ってこい!」
湊の叫びは、陽太の興奮にかき消された。「大丈夫だって。じゃ、またな!」一方的に切られた通話に、湊は言いようのない胸騒ぎを覚えた。
湊はアパートの自室で、ただ窓の外の雨を睨みつけることしかできなかった。時間が経つにつれて、不安は確信に変わっていく。陽太に電話をかけ直しても、誰も出ない。落ち着かなく部屋を歩き回っていた、その時だった。
――ガツン!
頭を鈍器で殴られたような衝撃と共に、視界が強制的に奪われた。
目の前に広がったのは、絶望的なまでに荒れ狂う、鉛色の海。叩きつける雨が視界を遮り、巨大な波の壁が、空を覆い隠すように迫ってくる。恐怖。全身の血が凍りつくような、純粋な恐怖。これは、陽太の視界だ。
「やめろ……やめてくれ……!」
湊は床に蹲り、頭を抱えた。しかし、流れ込んでくる映像を止めることはできない。視界が大きく傾き、次の瞬間、世界が反転した。陽太がボードから投げ出されたのだ。灰色の空と海が、めちゃくちゃにかき混ぜられる。そして、耳を塞ぎたくなるような轟音と共に、視界は完全に水中に沈んだ。
冷たい暗闇。無数の気泡が、光を求めて上っていくのが見える。息ができない。肺が張り裂けそうだ。もがく腕が、虚しく水を掻く。湊自身の呼吸も浅くなり、過呼吸に陥っていた。陽太のパニックと苦痛が、視覚情報というフィルターを通して、ダイレクトに湊の神経を焼き付けた。遠のいていく意識の中、水面の僅かな光が、ゆっくりと消えていく。
そして、すべてが漆黒の闇に閉ざされた。
湊が意識を取り戻した時、彼は自室の床に倒れていた。窓の外は、嘘のように雨が上がっていた。しかし、湊の世界は、あの暗闇に囚われたままだった。
数日後、陽太は行方不明者として扱われた。大規模な捜索が行われたが、彼の姿も、サーフボードも見つかることはなかった。友人たちは涙を流し、彼の死を悼んだ。
だが、湊にとっての本当の地獄は、そこから始まった。
陽太は死んだはずだった。あの視界は、彼の最期の瞬間だったはずだ。それなのに、あの奇妙な「共有」は、終わらなかった。
講義を受けている時、食事をしている時、眠りにつこうとする時。何の脈絡もなく、不意に、あの視界が流れ込んでくるのだ。暗く、冷たい、水の底からの視界。ゆらゆらと揺れる海藻。時折横切る魚の影。それは、陽太がまだ、あの海の底から何かを見続けている証拠のようだった。
親友の死の瞬間を追体験し、そして今度は、彼の死後の世界を永遠に見せられ続ける。友情の証だったはずの繋がりは、湊を苛む呪いの枷へと変貌していた。湊は再び、厚く冷たい殻の中へと、深く、深く沈んでいった。
第四章 青のレクイエム
陽太の幻影は、湊の日常を静かに侵食していった。大学へ行く足は重くなり、スケッチブックを開く気力も湧かなかった。目の前に広がる現実よりも、不意に割り込んでくる海の底の光景の方が、よほど生々しく感じられた。あの暗く、閉ざされた視界は、湊自身の心の状態を映し出しているかのようだった。陽太は自分を恨んでいるのだろうか。あの日、もっと強く止めていれば。後悔と罪悪感が、鉛のように心に沈殿していた。
そんな日々が数ヶ月続いた、ある冬の日の午後だった。いつものように、湊の意識が海の底へと引きずり込まれた。またか、と目を閉じ、絶望的な暗闇が過ぎ去るのを待つ。だが、その日の光景は、いつもと少しだけ違っていた。
暗闇の中に、微かな光の柱が差し込んでいるのが見えた。まるで、天から射すスポットライトのように。その光の中を、銀色に輝く魚の群れが、壮大な渦を巻きながら通り過ぎていく。その光景は、恐ろしいというよりも、むしろ神秘的で、荘厳でさえあった。恐怖も、苦痛も、そこにはなかった。ただ、静かで、穏やかな時間が流れているだけだった。
湊は、はっと息を呑んだ。
もしかしたら、陽太は僕を苦しめようとしているわけではないのかもしれない。
彼は、自分を恨んでいるのではない。見せているのは、絶望ではない。
これは、彼が最期にたどり着いた世界。彼が愛した海の、本当の姿。そして彼は、その最後の景色を、たった一人の親友である僕に、「見せてくれている」のではないだろうか。
――湊の見る世界って、なんか静かで、綺麗だよな。
いつかの陽太の言葉が、脳裏に蘇る。陽太は、湊の見る世界を知りたがった。ならば、自分も陽太が見る世界を、最後まで見届けなければならないのではないか。それは呪いではない。途切れることのなかった、友情の続きなのだ。
その瞬間、湊の心に沈んでいた鉛が、ふっと軽くなるのを感じた。
湊は立ち上がり、埃をかぶっていたスケッチブックを手に取った。そして、震える手で鉛筆を握り、今しがた見たばかりの、海の底の光景を描き始めた。差し込む光、魚の群れの躍動、静謐な青の世界。それは、陽太への追悼であり、彼との友情を肯定する、祈りのような行為だった。
それから湊は、陽太が見せてくれる光景を描き続けた。彼の絵は、もはや無機質な風景画ではなかった。そこには、陽太の魂が宿っていた。
春になり、湊は陽太の故郷の海を訪れた。かつて陽太が連れてきてくれた、あのビーチだ。空はどこまでも青く、海は穏やかに陽光を反射していた。湊は砂浜に座り、裸足で砂の感触を確かめ、潮の香りを胸いっぱいに吸い込んだ。そして、ゆっくりと目を閉じる。
瞼の裏に、陽太の視界が流れ込んできた。
それは、湊が今見ている現実の海と重なるように、どこまでも広がる、穏やかで優しい、青い光の世界だった。
それはもはや呪いでも幻影でもない。二人の間にだけ存在する、永遠の友情の形だった。
湊は小さく微笑んだ。
「ああ、陽太。君の見る海は、やっぱり綺麗だな」
彼はこれからも、陽太と共に世界を見続けるだろう。彼の視界を通して、彼の愛した海を描き続けるだろう。
湊は静かに立ち上がると、波打ち際へと歩き出した。彼の歩みは、もう迷うことはなかった。その瞳には、陽太が見る青と、自分が生きる世界の光が、確かに重なり合っていた。