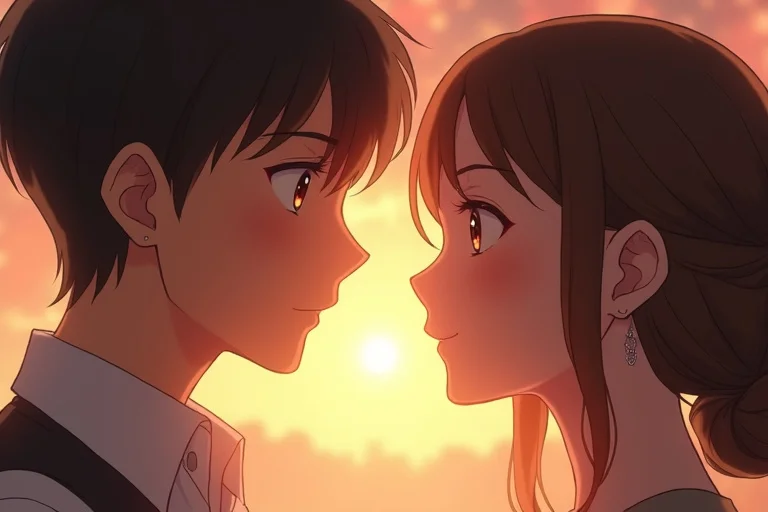第一章 触れられない日付
古書のインクと、乾いた紙の匂いが満ちる静寂。それが、水島湊(みなと)の世界のすべてだった。彼が店主を務める『時の葉書房』は、大通りから一本入った路地裏にひっそりと佇み、訪れる客もまばらだ。湊にとって、それは好ましいことだった。彼は、人と触れ合うことを極端に恐れていた。
彼の右手に宿る、呪いとも言うべき能力のせいだ。
誰かの肌に、たとえ指先が掠めただけでも、湊の脳裏には鮮やかな光の数字が浮かび上がる。それは、その人物が誰かと恋に落ちた場合、その関係が終わりを迎える「日付」だった。別れ、心変わり、あるいは死。理由は定かではないが、その日付が訪れると、恋愛という名の物語は必ず終焉を迎える。友人同士の他愛ない接触では発動しない。しかし、そこに微かでも恋愛感情の種が存在すれば、残酷なタイムリミットが宣告されるのだ。
だから湊は、誰とも深く関わらず、古書に埋もれて生きてきた。他人の幸福な恋の始まりと、その避けられない終わりを同時に見てしまう苦痛に、彼の心はとうにすり減っていた。
その日も、雨がアスファルトを叩く音だけが、店内の静寂を縁取っていた。扉のベルがちりん、と鳴り、一人の女性が入ってくる。雨粒を弾く明るい黄色のレインコートが、薄暗い店内でひときわ鮮やかだった。
「すみません、雨宿り、させてもらってもいいですか?」
快活な声。小野寺陽菜(ひな)と名乗った彼女は、タオルで髪を拭いながら、好奇心旺盛な目で店内を見回した。
「どうぞ、ごゆっくり」
湊はカウンターの奥から、できるだけ感情を殺した声で応じる。彼女が本棚の間を巡る姿を、視界の端で追う。彼女の周りだけ、空気がきらきらと輝いているように見えた。やがて、彼女は植物図鑑のコーナーで足を止め、一冊の分厚い本を手に取った。
「わあ、これ探してたんです。すみません、取っていただけますか?」
一番高い棚にある、別の図鑑を指差す彼女。湊は無言で脚立を運び、本に手を伸ばす。その時だった。バランスを崩した彼女の体が、ぐらりと傾く。咄嗟に差し出した湊の右手が、彼女の腕を支えた。
びり、と静電気が走るような衝撃。そして、脳裏を灼くように、あの数字が浮かび上がった。
―― **2024年 10月 31日** ――
今日が六月の初めだから、わずか五ヶ月もない。あまりにも短く、あまりにも残酷な期限。湊は血の気が引くのを感じた。目の前の、太陽のような笑顔を浮かべる女性との間に生まれるかもしれない恋は、秋の終わりに枯れ葉のように散る運命なのだ。
「あ、ありがとうございます」
陽菜は屈託なく笑い、湊の手から図鑑を受け取った。その指先が再び触れ合う。今度は、確信を持って見えた。間違いない。十月三十一日。湊は、始まったばかりの恋心の芽を、自らの手で踏み潰されたような絶望に襲われた。
第二章 期限付きの幸福
あの日以来、湊は陽菜を避けた。しかし、彼女はまるで引力に引かれるように、頻繁に店を訪れるようになった。新しい花が入荷したから、と小さなブーケをカウンターに飾ってくれたり、店の隅で埃をかぶっていた観葉植物を見事に蘇らせたりした。彼女が店にいる間、古書の匂いに混じって、甘い花の香りや湿った土の匂いがふわりと漂う。それは、湊がずっと忘れていた生命の香りだった。
「湊さんのこのお店、時間の流れが違うみたいで、落ち着きます」
ある日、陽菜はそう言って微笑んだ。湊は返す言葉が見つからず、ただ曖昧に頷くことしかできない。彼女の真っ直ぐな好意が嬉しい反面、胸の奥では常に冷たい数字が明滅している。
このままではいけない。終わりを知っていながら、関係を深めるのは卑怯だ。そう頭では分かっているのに、彼女のいない『時の葉書房』は、以前よりもずっと色褪せて空虚に感じられた。
七月の蒸し暑い夜、閉店作業をする湊の元に、陽菜が駆け込んできた。
「間に合った!湊さん、今夜、流星群が見えるんですって。よかったら、一緒に見に行きませんか?」
息を切らせて誘う彼女の瞳は、星のように輝いていた。断る理由を探すより先に、湊の口からは「はい」という言葉がこぼれ落ちていた。
近くの丘の上、二人で並んで夜空を見上げた。時折、光の筋が闇を切り裂くたびに、陽菜は子供のようにはしゃいだ。湊は流れ星に願う代わりに、隣にいる彼女の横顔を見つめていた。この笑顔を、あと何度見られるだろう。この声が、あと何回聞けるだろう。
「終わりが来るその日まで、全力で彼女の時間を彩ろう」
その夜、湊は覚悟を決めた。呪われた能力に抗うのではなく、受け入れる。期限付きの幸福だとしても、この手で陽菜を幸せにしたい。たとえそれが、未来のない恋だとしても。
夏が過ぎ、秋が訪れた。二人は水族館へ行き、青い光の中で揺蕩うクラゲを眺めた。プラネタリウムで満天の星に包まれ、海辺で裸足になって砂の感触を確かめ合った。一つ一つの思い出が、宝石のように輝いて湊の心に積もっていく。しかし、その輝きが増せば増すほど、十月三十一日という日付の影は、より濃く、より深く、彼の心に落ちていった。
彼は、陽菜に能力のことは決して話さなかった。これは自分一人が背負うべき十字架だと信じていたからだ。彼女の笑顔を見るたびに、胸が締め付けられるような切なさと、どうしようもない愛しさが込み上げてくる。残された時間は、もう一月を切っていた。
第三章 十月三十一日の真実
十月に入ると、湊は静かに心の準備を始めた。陽菜との別れを、どう受け入れようか。どんな言葉をかければ、彼女を傷つけずに済むだろうか。まるで遺言を考えるように、彼は来るべき日に思いを巡らせた。
しかし、陽菜の様子が少しずつ変わってきたことに、湊は気づいていた。時折、ふっと会話が途切れ、遠くを見つめるようになった。笑顔の裏に、隠しきれない疲労の色が滲むこともあった。湊は、彼女もまた、この関係の終わりに気づき始めているのかもしれない、と悲しい予感を抱いた。
十月三十日。ハロウィンの飾り付けで賑わう街を歩きながら、陽菜が不意に足を止めた。
「湊君。明日、話したいことがあるの。いつもの公園で、待っててくれる?」
その声は、いつもより少しだけ低く、真剣だった。ついに、この時が来たのだ。湊は心臓を氷の鷲に掴まれたような心地で、静かに頷いた。
そして、運命の十月三十一日。
落ち葉が舞う公園のベンチに座り、湊は陽菜を待っていた。空は高く澄み渡り、あまりにも美しい秋晴れだった。やがて、彼女がゆっくりと歩いてくるのが見えた。その表情は、なぜか決意に満ちているように見えた。
「ごめんね、待たせて」
隣に座った陽菜は、別れの言葉を切り出す代わりに、一枚のパンフレットを湊に差し出した。それは、スイスの著名な植物園が主催する、若手アーティスト向けの長期研修プログラムの案内だった。出発日は、明日――十一月一日。
湊が言葉を失っていると、陽菜は静かに、しかしはっきりとした声で続けた。
「私ね、生まれつき心臓に病気があるの。ずっと経過観察だったんだけど、最近になって、大きな手術が必要だって言われて。でも、怖くて……ずっと、手術から逃げてた。失敗したらって思うと、何も手につかなくて」
彼女は一度言葉を切り、湊の目を真っ直ぐに見つめた。
「でも、湊君と出会って、一緒に時間を過ごして……初めて、未来を生きたいって、強く思うようになったの。この研修プログラムも、手術が成功したら挑戦したいってずっと思ってた、私の夢なの。だから、決めたんだ。手術、受けることにした」
湊の頭の中で、何かが砕ける音がした。数字。日付。十月三十一日。
それは、二人の恋愛の終わりではなかった。
もし、彼女が手術を受ける決意をしなければ、今日が彼女の「命」のタイムリミットになる可能性があったのだ。
湊が見ていたのは「終わり」の宣告ではない。「運命の分岐点」を知らせる警告灯だった。彼との恋が、陽菜に生きるための勇気を与え、未来を選ぶための力を与えた。呪いだと思っていた能力は、愛する人の命を救うための、奇跡の道標だったのかもしれない。
「……そう、だったのか」
湊の目から、熱い雫がとめどなく溢れ落ちた。それは、絶望の涙ではなく、安堵と、悔恨と、そして何よりも深い愛から生まれた涙だった。
第四章 色のない未来図
「湊君は、私が死んじゃうかもしれないって思いながら、ずっと……ずっと、一緒にいてくれたんだね」
公園のベンチで、湊はすべてを打ち明けた。自分の右手に宿る能力のこと。初めて会った日に見た日付のこと。そして、終わりを知りながら彼女を愛してしまった、自分の愚かさと切なさのこと。陽菜は驚きながらも、静かに彼の告白を聞いていた。やがて、彼女の瞳からも大粒の涙がこぼれ落ち、湊の頬を伝う涙と混じり合った。
数日後、陽菜は手術を受けた。病院の長い廊下の隅で、湊はただひたすらに祈り続けた。手術中のランプが消え、医師が穏やかな表情で出てきた時、彼はその場に崩れ落ちそうになるのを必死でこらえた。手術は、成功した。
季節は巡り、冬の冷たい空気が春の柔らかな光に変わる頃。
すっかり回復した陽菜と湊は、久しぶりにあの海辺を歩いていた。まだ少し肌寒い潮風が、二人の髪を優しく揺らす。
「ねえ、湊君」
陽菜が不意に立ち止まり、湊の右手を取った。湊は息を呑む。彼女の肌に触れる。しかし――何も見えなかった。かつてあれほど鮮明に見えた光の数字は、跡形もなく消え去っていた。
それは、彼の役目が終わったということなのか。それとも、二人の愛が、定められた運命さえも書き換えてしまったということなのか。答えは、風の中だった。
湊は、もう未来の日付を恐れない。不確かな明日を憂うよりも、確かな今日の温もりを大切にすること。終わりがいつ来るかではなく、この一瞬一瞬を、どう愛し、どう生きるかこそが重要だと、彼は陽菜から教わったのだ。
彼は、陽菜の細い指を強く、優しく握り返した。目の前には、日付の記されていない、無限の未来という名の真っ白な水平線がどこまでも広がっている。二人の物語は、今、本当の意味で始まったばかりだった。