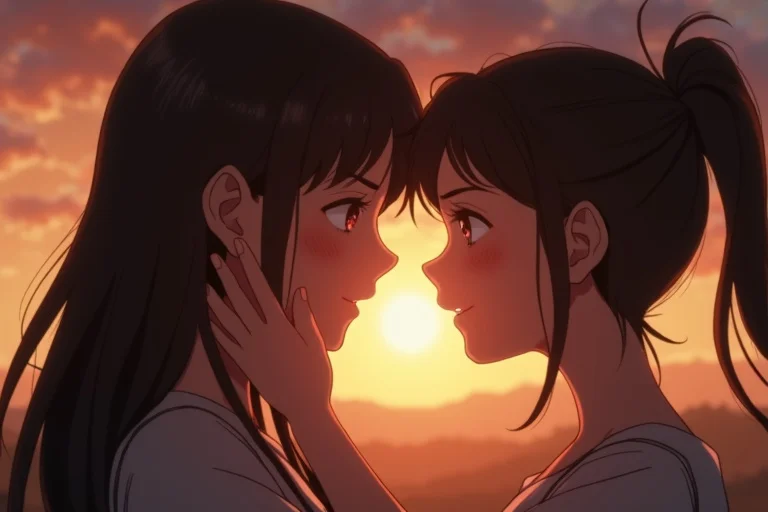第一章 記憶を溶かす病
午前八時。窓から差し込む春の陽光が、白いレースカーテンを透過し、寝室に柔らかな光の筋を描いていた。隣で眠る拓哉の規則的な寝息が心地よく、葉月はゆっくりと瞼を開けた。彼の髪にそっと指を通すと、くすぐったそうに身じろぎ、薄く目を開ける。
「おはよう、葉月」
掠れた声が、葉月の心を満たす。こんな穏やかな朝を迎えるのは、いつぶりだろう。いや、いつも彼といると、世界は光に満ちている気がする。
拓哉は葉月にとって、完璧な恋人だった。優しくて、賢くて、そしてなにより、葉月の漠然とした不安を包み込んでくれるような温かさがあった。二人が出会って三ヶ月。瞬く間に深まった関係に、葉月は驚きと同時に、一抹の寂しさを感じていた。
昨夜、拓哉と観た映画のタイトルが思い出せない。いや、タイトルだけではない。主演俳優の名前も、ストーリーの細部も、ぼんやりとした輪郭しか残っていなかった。しかし、拓哉と手をつないでいたその温もりだけは、手のひらにまだ残っているかのように鮮やかだ。
葉月は、自身が抱える秘密の病を知っていた。それは、新しい恋に落ちるたびに、過去の恋愛の記憶が、まるで古いファイルのデータが新しいデータに上書きされるように、次第に消滅していくという奇妙な病だった。診断されたのは数年前のこと。最初はただの物忘れかと思った。しかし、昔の恋人とのアルバムを見ても、その顔に見覚えはあるのに、具体的なエピソードや感情が一切思い出せない。まるで、他人の日記を読んでいるかのような感覚。過去の自分が確かに経験したはずの「愛」が、跡形もなく消え失せていくのだ。
その病は、葉月から過去の恋の傷を奪う代わりに、学びの機会も奪った。いつも新鮮な気持ちで恋に落ちる。それはある意味で祝福であり、また呪いでもあった。
拓哉と出会ってからの三ヶ月は、まさに幸福の絶頂だった。彼の声、彼の笑顔、彼の温かい指先。それらすべてが、葉月の世界を塗り替えていく。しかし、その輝きが増すほどに、葉月は感じていた。脳の奥で、何かが少しずつ溶け出しているような感覚を。過去の記憶の輪郭が、また一つ、また一つと曖昧になっていくのを。
「葉月?どうしたの?」
拓哉の声に、葉月はハッと我に返った。拓哉は心配そうに眉を下げている。
「ううん、なんでもない。ちょっと考え事をしてただけ」
そう言って微笑んだが、内心は深い闇が広がっていた。この幸福も、いつか記憶の彼方に消えてしまうのだろうか? 拓哉との出会いを、彼との愛を、私はどれだけ覚えていられるのだろう?
初めて拓哉に会ったのは、職場のカフェだった。たった一度のアイコンタクトで、言葉もなく惹かれ合った、運命的な出会い。そう信じて疑わない。だが、もしかしたら、この「初めて」も、私にとっての「初めて」なだけで、本当は違うのかもしれない。そんな疑念が、葉月の心の奥底で、常にさざ波を立てていた。
彼女の記憶は、砂でできた城のように脆く、新しい波が来るたびに、その形を変えていく。そして、いつか、すべてを失ってしまうのではないかという恐怖が、いつも葉月の胸を締め付けていた。
第二章 消えゆく日々の影
拓哉との日々は、まるで蜜のように甘く、そして同時に、儚く過ぎ去っていった。葉月は、少しでも多くの記憶を留めようと、日々日記を書き綴った。拓哉と観た映画、一緒に作った夕食、交わした言葉、感じたこと。ありとあらゆる出来事を、詳細に、鮮やかに。しかし、一週間前のページをめくると、それはもう自分のものではない、誰かの物語を読んでいるような奇妙な感覚に襲われた。感情が伴わない、ただの文字の羅列。
「葉月、今日、あれ食べに行かない?この前言ってた、新しいパンケーキ屋さん」
ある週末、拓哉が笑顔で尋ねた。葉月は首を傾げる。
「パンケーキ屋さん?私が言ってた?」
拓哉は少し戸惑った表情を見せたが、すぐに笑顔に戻った。
「ああ、先週の火曜日に、雑誌を見ながら『ここ行ってみたいね』って言ってたんだよ。忘れちゃった?」
葉月の脳裏には、その会話の記憶が一切なかった。それでも、拓哉の言葉を疑うわけにはいかない。
「ああ、そうだったね!ごめん、ちょっと忘れちゃってた。行こう、行こう!」
葉月は明るく振る舞ったが、心の中ではひそかに鉛のような重みが広がっていた。こうして、拓哉との記憶ですら、少しずつ、少しずつ、その輝きを失っていくのだろうか。まるで霧の中に沈んでいくように。
ある日、拓哉の部屋で、葉月は彼の机の上に見慣れない木彫りの鳥のオブジェを見つけた。掌に収まるほどの小さな鳥は、なめらかな曲線で削り出され、磨き上げられた木肌が、ほのかに光を反射していた。
「可愛いね、これ」
葉月がそう言うと、拓哉は少し驚いたような顔をして、オブジェを手に取った。
「ああ、これかい?これは、俺にとってすごく大切なものなんだ」
拓哉の指先が、その鳥の頭を優しく撫でる。
「誰かからの贈り物?」
「うん、そうだよ。昔、大切な人にもらったんだ」
拓哉の瞳の奥に、遠い記憶を辿るような光が宿るのを、葉月は感じた。それは、どこか物悲しく、しかし温かい光だった。葉月は、その鳥に言いようのない既視感を覚えた。どこかで見たことがある。いや、それ以上に、この手のひらに馴染む感触を、どこかで知っている気がした。だが、それがいつ、どこで、誰と、という具体的な記憶は、やはり欠落していた。
その夜、拓哉が眠りについた後、葉月は自分の日記帳を広げた。最近の出来事は、まだ鮮明に綴られている。拓哉の誕生日、二人の記念日、初めての旅行。しかし、それ以前のページは、もはや他人事のように感じられた。そこに書かれた過去の恋人たちの名前は、もう彼女の心に何の感情も呼び起こさなかった。
葉月は、自分は拓哉を愛している、そう確信している。だが、この愛も、いつか、他の記憶と同じように、ただの文字の羅列になってしまうのだろうか? 彼女は深い絶望に包まれ、静かに涙を流した。記憶という、人間を人間たらしめる最も重要な要素が、彼女から日々、剥がれ落ちていく。そして、その喪失感だけが、なぜか記憶の中に残り続けるのだった。
第三章 繰り返される奇跡
その電話は、突然鳴った。会社の休憩中、葉月が拓哉に送ろうとしていたメッセージを打ち込んでいる最中だった。
「拓哉さんが事故に遭いました。すぐに病院へ来てください」
耳に飛び込んできた言葉は、あまりにも唐突で、現実感がなかった。葉月の全身から血の気が引いていく。心臓が凍りついたかのように脈打つのを止め、やがて激しく打ち鳴らし始めた。
病院に駆けつけると、拓哉はまだ意識不明の状態だった。医師の説明を聞きながらも、葉月の頭の中は真っ白だった。彼を失うかもしれない。その恐怖が、葉月の心を締め付けた。
拓哉の手を握りしめたとき、葉月の心の中で、何かが弾けた。
彼の温かい手のひら。柔らかな指先。そのすべてが、記憶の奥底に封印されていた感情の扉を、こじ開けるかのように思えた。
「拓哉……」
葉月の目から、とめどなく涙があふれ出した。それは、ただ拓哉を心配する涙だけではなかった。
その瞬間、葉月の脳裏に、まるで高速で巻き戻されるフィルムのように、無数の映像が蘇った。
最初は、ぼんやりとした光景だった。
公園のベンチで、誰かと笑い合っている自分。
雨宿りをした喫茶店で、向かい合って話している自分。
夜景の見える場所で、抱きしめられている自分。
そして、それらの「誰か」の顔が、全て拓哉に重なっていく。
「嘘……」
葉月は震える声で呟いた。
記憶の上書き。それは、過去の恋人の顔やエピソードを消し去るものだった。しかし、今、葉月の脳裏に鮮明に蘇るのは、彼らの顔の向こう側に、確かに存在した拓哉の姿だった。彼は、あの時も、あの時も、そして、あの時も、私の隣にいた。
葉月は、拓哉に初めて木彫りの鳥を贈った日のことを思い出した。それは、彼らの最初の一周年記念日だった。公園の桜の木の下で、はにかむ拓哉の手に、葉月は自作の木彫りの鳥を乗せた。
「拓哉の旅の安全を願って。私に似てるでしょ?」
拓哉は笑って、大切そうにその鳥を胸に抱いた。それは、今の彼がいつも持っている、あの木彫りの鳥だった。
「あなた、だったの……」
葉月は拓哉の無意識の顔を見つめた。記憶は、確かに彼以外のあらゆる恋人を消し去った。だが、拓哉との記憶だけは、消滅するどころか、より深く、より本質的な感情の層へと刻み込まれていたのだ。表層的なエピソードは消えても、彼への「愛」や「魂の繋がり」そのものは、決して上書きされず、むしろ純粋な形で残り続けていた。
拓哉は、葉月の記憶がリセットされるたびに、彼女の前に姿を変え、新たな出会いを演出してきたのだ。葉月が初めて彼に出会った時、運命を感じたのは、それが本当に「初めて」ではなかったからだ。彼女の魂が、彼を「知っていた」からなのだ。
葉哉は、この病気のことを知っていたのだろうか? そして、知っていたとして、どうして何度も、記憶を失った自分に、再び恋をしてくれたのだろう? 葉月は、これまでの自分がいかに愚かで、そしていかに拓哉の途方もない愛に守られていたかを悟り、嗚咽した。
それは、恐怖と混乱、そして途方もない感動が入り混じった、感情の濁流だった。
第四章 忘却の彼方の愛
拓哉は数日後、奇跡的に意識を取り戻した。目を覚ました彼に、葉月は自分の病のこと、そして、すべてを思い出した(あるいは、初めて知覚した)真実を、震える声で打ち明けた。
拓哉は、葉月の話を聞きながら、静かに涙を流していた。
「ごめんね、葉月。本当は、もっと早く話すべきだった。でも、君が僕を忘れてしまうたびに、僕は新しい君に、また恋に落ちた。その度に、今度こそは、僕のことを覚えていてほしいと願った。だけど、君が幸せなら、それでよかったんだ」
拓哉の言葉は、葉月の心を深く震わせた。彼は、彼女が記憶を失うたびに、何度となく同じ苦しみを味わい、それでもなお、彼女の傍らにいることを選び続けてきたのだ。
「なぜ? なぜそこまで……」
「わからない。でも、君に出会うたびに、僕の魂が叫ぶんだ。この人だ、と。君が僕を忘れても、僕は君を忘れない。何度だって、君に恋をするよ」
拓哉の瞳は、悲しみに濡れていながらも、確固たる愛の光を宿していた。彼の途方もない愛に触れ、葉月の心は大きく揺さぶられた。
彼女はこれまで、記憶が失われることを、自分の一部が奪われる悲劇だと捉えていた。しかし、拓哉の言葉を聞き、彼女は考え方を改めた。記憶が失われても、魂の奥底で繋がっているという感覚。それこそが、彼らが幾度となく再会し、恋に落ちてきた理由なのだろう。
「拓哉……私、もう怖くない」
葉月は拓哉の手を握りしめた。
「たとえ私がまた、あなたとの記憶を失ったとしても、私の魂はきっと、あなたを見つける。そして、何度でも、あなたに恋をする。だから、これからも、私の隣にいてくれる?」
拓哉は、信じられないものを見るように葉月を見つめ、そして、深く頷いた。彼の目から、大粒の涙がこぼれ落ちた。
「もちろんだよ。何度だって、君を見つけ出す。そして、何度だって、恋に落ちよう」
彼らの愛は、記憶の不確かさの上で咲く、奇妙で美しい花だった。過去の積み重ねの上に築かれるのではなく、常に「今」という一瞬の輝きの中で、しかし、魂の深い場所で、何度でも繋ぎ直される。それは、永遠に新鮮であり続ける、終わりのない物語なのだ。
退院の日、病院の門を出たところで、拓哉は葉月の手を握り、ふと立ち止まった。
「あのさ、葉月。僕と結婚してくれないか?」
葉月は、その言葉に、胸の奥が熱くなるのを感じた。そして、彼女は、これまでで最も、そして最も新鮮な笑顔で答えた。
「はい! ぜひ、私と、初めての結婚をしてください!」
二人の笑い声が、春の優しい陽光の中に溶けていく。葉月の記憶が、いつか、この日のプロポーズすら曖昧にしてしまうかもしれない。しかし、その時、拓哉はきっと、新しいプロポーズの言葉を用意してくれるだろう。そして、葉月は、その言葉に、また初めてのように心ときめかせ、そして、また深く、彼に恋をするのだ。彼らの愛は、忘却の螺旋を巡りながらも、決して色褪せることのない、真実の輝きを放ち続けるだろう。