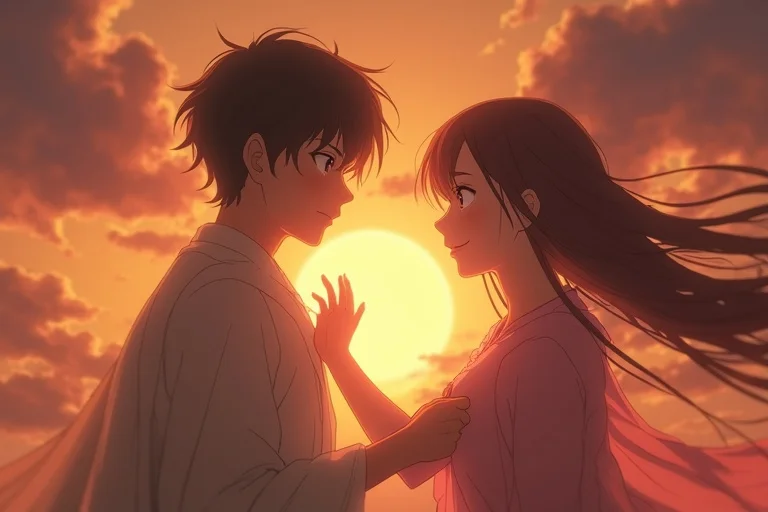第一章 透明な男
古書店『時紡ぎ堂』の古い木の匂いが、私、響(ひびき)の心をいつも静めてくれる。誰かを深く愛すると、その人の記憶の断片――最も幸せな瞬間と、最も深い悲しみを、香りや肌触りとして感じてしまう私の体質にとって、多くの物語が眠るこの場所は聖域のようだった。
彼、零(れい)と出会ったのもこの場所だ。雨の匂いが染み込んだ古い革表紙の詩集を、彼はまるで壊れ物に触れるかのようにそっと撫でていた。その指先の白さと、静けさを湛えた瞳に、私は一瞬で心を奪われた。
恋に落ちるのは、いつも突然だ。胸の奥で小さな鈴が鳴り、相手の記憶が流れ込んでくる。かつての恋人を愛した時は、卒業証書を握りしめたざらついた紙の感触と、夏の終わりの潮の香りがした。だが、零からは何も感じなかった。私が彼の手を取っても、抱きしめても、流れ込んでくるのは洗い立てのシーツのようにどこまでも無垢な匂いと、冷たい清水を掬った時のような、味も素っ気もない空虚な感触だけ。
この世界では、愛の深さは目に見える。深く愛し合う者たちの周りには、共有された過去が透明な光の映像となって浮かび上がるのだ。カフェで談笑する老夫婦の周りには若い頃のダンスシーンが、公園のベンチに座る恋人たちの足元には初デートの緊張した面持ちが、キラキラと舞っている。
けれど、零の周りには何もない。彼と手を繋いで街を歩いても、私たちの周りだけが、まるで時間が存在しないかのように、がらんと静まり返っていた。彼は過去を持たないのだろうか。その謎めいた透明さが、私の心をますます強く惹きつけてやまなかった。
第二章 琥珀色の夢
零との日々は、穏やかに過ぎていった。彼は多くを語らないが、その沈黙は心地よかった。ただ、私の内側では奇妙な変化が起きていた。夜ごと、自分のものではない誰かの記憶の夢を見るようになったのだ。
ある夜は、生まれたばかりの赤ん坊の小さな手を握っていた。ミルクの甘い匂いと、頼りないほど柔らかな肌の感触。胸いっぱいに広がる、温かい幸福感。
またある夜は、満開の桜並木の下にいた。ひらひらと舞う花びらの中で、誰かに愛を告げられている。心臓が高鳴り、甘酸っぱい花の香りが鼻腔をくすぐる。
夢はいつも、温かい琥珀色の光に包まれていた。目覚めた後も、その幸福な余韻が胸に残り、一日中私を優しい気持ちにさせた。これは一体、誰の記憶なのだろう。私の能力が、零との関係によって何か別の形に変わってしまったのだろうか。
「零は、昔どんな子供だったの?」
ある日、私は思い切って尋ねてみた。ソファで本を読んでいた彼の肩が、微かにこわばる。彼はゆっくりと顔を上げ、少し寂しそうに微笑んだ。
「……よく、覚えていないんだ」
その答えは、あまりにも脆く、儚い響きを持っていた。彼の過去に触れようとすると、彼はいつもこうして、するりと私の手からこぼれ落ちてしまう。琥珀色の夢の温かさと、目の前の彼の透明な孤独。そのコントラストが、私の胸をちりちりと焦がした。
第三章 記憶の香炉
彼の過去を知りたい。その思いは、日に日に抑えがたい渇望へと変わっていった。零という人間を、その根源から理解したい。彼の孤独に寄り添いたい。その一心で、私は街外れの骨董屋の埃っぽい棚の奥から、曰く付きの品を見つけ出した。
『記憶の香炉』。
掌に乗るほどの小さな青磁の香炉。店主の老人は皺だらけの顔で言った。「そいつは、持ち主が心から願う者の、最も幸福な記憶を香りに変える。だが、代償にその記憶を少しずつ削り取っていくという話だ」。不吉な言い伝えに一瞬ためらったが、私の決意は揺るがなかった。
その夜、零が深い眠りに落ちているのを確認し、私は彼の髪をそっと一筋だけ拝借した。震える手でそれを香炉に入れ、静かに火を灯す。どうか、あなたの幸せを、ほんの少しだけ私に教えて。
立ち上る煙は、すぐに甘やかな香りを放ち始めた。
目を閉じ、深く吸い込む。
けれど、その香りは零のものではなかった。私が知っている香り。幾度となく夢で感じた、あの赤ん坊のミルクの匂いだった。
第四章 空っぽの器
「……っ、う……」
香りが部屋に満ちた瞬間、眠っていた零が苦しげな呻き声を上げた。彼の身体が小さく痙攣し、額には脂汗が滲んでいる。まるで悪夢に苛まれているかのようだ。
私はパニックになり、慌てて香炉の火を吹き消した。煙が途絶えると、彼の呼吸は次第に穏やかになっていったが、その顔は青ざめていた。やがて、零がゆっくりと目を開ける。その瞳には、今まで見たことのない深い怯えの色が浮かんでいた。
「……見て、しまったんだね」
か細い声が、静寂を裂いた。彼はゆっくりと身体を起こすと、すべてを諦めたように話し始めた。
「僕は、人とは違う。誰かを深く愛すると、その人の過去の記憶と時間を、根こそぎ吸い取ってしまうんだ」
彼の言葉が、私の頭の中で理解を拒む。
「吸い取った記憶は、僕の中で眠りにつく。そして、僕自身は空っぽになる。だから、僕の周りには過去の映像が現れない。僕自身の過去なんて、もうどこにもないから」
呆然とする私に、彼は続けた。
「君が見ていた夢は……僕が昔、愛した人たちから吸収した記憶なんだ。母の記憶、昔の恋人の記憶……。僕を愛してくれる君に、その幸福な断片が流れ込んでいたんだ」
記憶の香炉は、零の中に眠っていた「他人の記憶」に反応してしまったのだ。
「僕は空っぽの器なんだよ、響。君にあげられる思い出も、過去も、何一つ持っていない」
彼の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。それは、何の味もしない、透明な雫だった。
第五章 あなたという名の現在(いま)
零の告白は、衝撃的だった。けれど、私の心にあったのは恐怖や失望ではなかった。彼の途方もない孤独と、誰にも言えずに抱えてきた痛みを思い、胸が張り裂けそうになったのだ。
私は震える彼を、力の限り抱きしめた。
「過去なんて、いらない」
私の声も、震えていた。
「私が愛しているのは、誰かの記憶を抱えたあなたじゃない。空っぽでも、何でもない。目の前にいる、今のあなただけ。零、あなた自身よ」
過去がないなら、これから二人で、時間を作っていけばいい。一つずつ、私たちの思い出を積み重ねていけばいい。
「私は、空っぽのあなたを愛してる」
その言葉が、最後の鍵だったのかもしれない。
私の腕の中で、零の身体がふわりと光を放った。驚いて見つめると、彼の身体から無数の光の粒子が溢れ出し、部屋の中を舞い始めた。それは、彼が吸収してきた人々の記憶だった。赤ん坊を抱く母親の映像、桜並木の下で微笑む少女の姿。光たちは、それぞれの持ち主の元へと還っていくかのように、窓から夜空へと溶けて消えていった。
すべてが消え去った後、零は静かに泣いていた。そして、私は感じた。初めて、彼自身の「記憶の断片」が流れ込んでくるのを。
しょっぱい涙の味。
それは、空っぽだった自分を嘆く、彼の最も深い悲しみ。
そして、温かい布の肌触り。
それは、今、私に抱きしめられ、すべてを受け入れられた、彼の最も幸福な瞬間だった。
第六章 二人の時間
奇跡は、まだ終わらなかった。私たちの周りに、ゆらりと陽炎のように、透明な光の映像が浮かび上がった。それは、過去の映像ではなかった。
古書店で初めて会った日の、少し緊張した彼の横顔。
公園のベンチで、他愛ない話をして笑い合った午後。
初めて手を繋いだ夜の、街灯の優しい光。
それは、空っぽだった零が、私と出会ってから紡いできた、生まれたての二人の「時間」だった。映像はまだ数えるほどしかない。けれど、その一つひとつが、どんな宝石よりも輝いて見えた。
零が、涙に濡れた顔で私を見て、はにかむように微笑んだ。
「僕の時間を……これから、君と一緒に作っていきたい」
その言葉と共に、私たちの周りに浮かぶ映像の先に、まだ輪郭のぼんやりとした、未来へと続く光の道が伸びていくのが見えた。
私は力強く頷き、彼の手に自分の手を重ねる。指が絡み合うたび、私たちの周りを舞う時間の光は、また一つ、また一つと数を増やしていく。空っぽだった彼の世界に、今、確かな時が満ちていく。その始まりの瞬間に立ち会えることが、私の何よりの幸福だった。