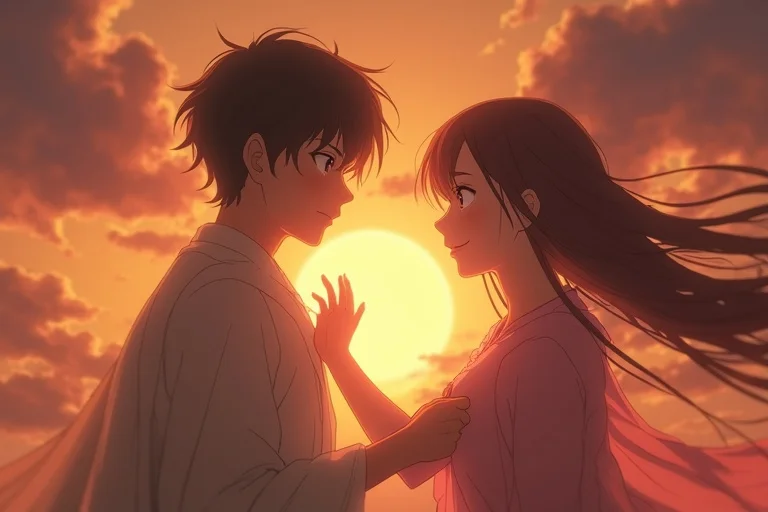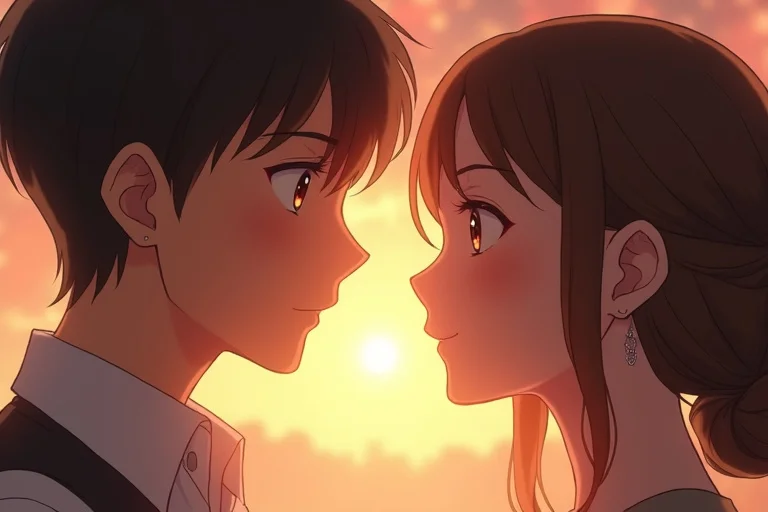第一章: 残光のアトリエ
俺を愛した人間は、世界から忘れられる。いや、正確には違う。愛した相手である俺の存在が、その人間の記憶から、そして周囲の認識から、綺麗に消え去るのだ。まるで最初から、俺という人間など存在しなかったかのように。だから俺は、誰の心にも踏み込まず、誰の心も受け入れず、ただ独り、この呪いを抱いて荒野を歩く。
乾いた風が埃を巻き上げる街の片隅。俺は、数日前まで「おかえり」と皺くちゃの笑顔で迎えてくれた宿の老婆の部屋に、静かに足を踏み入れた。彼女もまた、俺に深い情愛を抱いてしまった犠牲者だ。部屋の主を失った空間は、夕陽の赤に染まり、ひどく寒々しい。壁に立てかけられた一枚のキャンバスが、俺の目を引いた。そこに描かれていたのは、震える線で描かれた、半分に欠けた太陽の絵。そしてその下には、掠れた文字でこう記されていた。
『いつか、光は満ちる』
まただ。俺を愛し、そして忘れていった全ての人間が、必ず最後にこの絵とフレーズを残す。まるで申し合わせたかのように。これが何を意味するのか。それを知ることだけが、俺の旅の唯一の目的だった。
「カイ、いたんだ。やっぱりここだったんだね」
背後から掛けられた声に、俺は振り返らない。リナ。この呪われた世界で、唯一俺を忘れずに隣を歩く、不思議な女だ。彼女の足音が近づき、俺の隣で止まる。彼女の纏う、雨上がりの草のような匂いが、俺のささくれ立った心をわずかに撫でた。
「また、同じ絵…」
「ああ」
「…大丈夫。カイのことは、私が絶対に忘れないから」リナは俺の腕をそっと掴み、力強く言った。「だって、忘れるほど大切な未来なんて、私にはもう無いもの」
その言葉が、予言のように俺の胸に突き刺さった。彼女の瞳の奥に、一瞬だけ、全てを諦めたような深い凪が揺らめいたのを、俺は見逃さなかった。
第二章: 約束はインクに溶けて
俺たちは「記憶の筆」の伝承を求めて、古代図書館の書庫の奥深くへと分け入った。黴と古い紙の匂いが満ちる静寂の中、リナが埃を被った一冊の革張り本を見つけ出す。
そこには、こう記されていた。『持ち主が愛した者の最も輝かしい記憶を、永遠に色褪せぬ絵として写し取る奇跡の筆。されど、その軌跡は持ち主自身の最も大切な記憶をインクとして吸い上げ、やがて持ち主を空っぽにするだろう』
俺は懐から、いつから持っていたのかも思い出せない、一本の古びた木製の筆を取り出した。これが「記憶の筆」に違いない。俺が追うあの絵は、この筆が自動的に描き出したものだったのだ。
その夜、焚き火のそばで眠るリナの無防備な寝顔を、俺は衝動的にスケッチブックに写し取ろうとした。だが、筆を握った瞬間、俺の意思とは関係なく、筆先が紙の上を滑り始める。描かれていくのは、またしても、あの半分に欠けた太陽。
――やめてくれ。
脳裏に、陽光に満ちた丘の上で、泣きじゃくる小さな女の子に何かを約束する、幼い自分の姿が閃光のように過った。だが、その少女の顔も、交わしたはずの言葉も、靄がかかったように思い出せない。筆が、俺の中からまた一つ、大切な記憶を吸い上げてしまったのだ。俺はたまらず筆を投げ捨て、頭を抱えた。俺は、何を忘れてしまったんだ?
「…カイ?」
リナが寝ぼけ眼で身を起こす。俺の苦悶に気づいたのか、彼女は何も言わずに隣に座り、冷えた俺の手に自分の手を重ねた。その温もりが、罪悪感のように俺の心を焼いた。リナ、君は時々言うよな。「昔、画家になりたかった気がするんだ」と。でも、どんな絵を描きたかったのか、どうしても思い出せないのだと。そのたびに君は、寂しそうに笑う。まるで、未来の希望を少しずつ、どこかに落としてきたかのように。
第三章: 欠けた太陽の祭壇
絵とフレーズが指し示す場所は、俺たちが辿り着いた旅の終着点、海を見下ろす丘の上の廃教会だった。崩れかけた祭壇の奥、ステンドグラスが夕陽を受けて輝いている。その模様は、まさしく半分に欠けた太陽だった。
その光を浴びた瞬間、堰を切ったように、失われた記憶の全てが俺の魂に流れ込んできた。
――あの日、この場所で、幼いリナは事故に遭った。画家になる夢も、その脚で大地を駆ける未来も、全てを失いかけていた。俺は泣き叫ぶリナを前に、祈ったのだ。いや、願ってしまった。
『神様なんていないなら、悪魔にでも願う!僕の全てをあげるから!僕の未来も、僕の記憶も、僕がこれから得るはずの愛も、全部あげるから!だから、彼女に…リナに、世界で一番の希望をください!』
それが、呪いの正体だった。俺の願いは歪んだ形で叶えられた。俺を愛した者の「未来の希望」は奪われ、巡り巡ってリナの希望を補う力に変換されていたのだ。希望を全て失った者は、愛の記憶すら維持できなくなり、俺を忘れる。そしてリナだけが俺を忘れなかったのは、彼女こそが呪いの源泉であり、俺の存在と分かちがたく結びついた、最初の受益者だったからだ。
「そうか…俺は…君を救うために、君以外の全ての人を踏み台にしてきたのか…!」
絶望が俺を打ちのめす。俺は祭壇に膝をつき、嗚咽した。リナが震える手で俺の肩に触れる。彼女の瞳にも、全ての真実が映し出されていた。
「違う…違うよ、カイ…」彼女は涙を流しながら、首を横に振った。「私を救うために、あなたは…ずっと、ずっと一人で、全部背負ってくれてたんだね…」
そうだ、俺が「記憶の筆」で何かを描くたびに失っていたのは、他の誰でもない、リナとの記憶だった。彼女を繋ぎ止めるために、俺は彼女を忘れ続けてきた。なんという愚かな愛の形だろう。俺たちは、互いを喰らい合うことでしか、共にいられなかった。
第四章: 君が希望と呼ぶのなら
呪いを解く方法は、たった一つ。俺という「願い」の器が、世界から完全に消滅すること。そうすれば、俺が奪い続けた全ての希望は、元の持ち主たちの元へ還る。もちろん、リナの失われた希望も、完全に。
だがそれは、リナが俺の存在を、記憶の欠片すら残さずに、永遠に忘れることを意味した。
「嫌だよ…そんなの絶対に嫌だ!あなたを忘れるくらいなら、私、希望なんていらない!」
リナは叫び、俺の胸に縋りつく。その温もりも、香りも、もうすぐ失われる。俺は彼女の髪を優しく撫で、空を見上げた。半分だった太陽のステンドグラスが、今は夕陽を浴びて、まるで一つの完璧な円を描いているように見えた。
「リナ。俺が君を愛した記憶は、消えない」俺は彼女の肩を掴み、真っ直ぐにその瞳を見つめた。「俺が世界から忘れられても、この愛だけは、本物だ」
俺は最後の力を振り絞り、「記憶の筆」を取った。描くのは、リナの笑顔。俺が守りたかった、世界で一番の希望の形。そしてその隣に、欠けていない、満ち足りた一つの太陽を描き添えた。
筆を置くと、俺の足元から身体が光の粒子に変わり始めた。
「カイ…!行かないで…!」
俺は薄れゆく腕で、リナを強く、強く抱きしめた。これが最後だ。
「君の未来に、幸あれ」
耳元で囁くと、リナの腕から力が抜けた。彼女の瞳から、俺という存在が急速に色褪せていくのが分かった。
「…ありがとう」
誰に言うでもなく、俺は呟いた。君を愛せて、よかった。
意識が途切れる。
◇
リナは、なぜか丘の上の廃教会に一人で立っていた。夕陽が海を黄金色に染めている。どうしてここに来たのか、全く思い出せない。
ただ、胸の奥がぽっかりと空いているような、ひどい喪失感があった。なのに、それとは裏腹に、身体の底からは、明日が待ち遠しくてたまらないような、力強いエネルギーが満ち溢れてくるのを感じた。これから何でもできる。どんな夢だって、きっと叶えられる。そんな不思議な確信があった。
風が吹き、足元に落ちていた一枚のスケッチが舞い上がった。彼女は慌ててそれを拾い上げる。
そこに描かれていたのは、満面の笑みを浮かべる自分と、隣で優しく輝く、一つの大きな太陽の絵だった。
誰が描いたのだろう。
思い出せない。
思い出せないのに、その絵を見ていると、どうしようもなく涙が溢れてきた。
胸に広がるこの温かい感覚を、人はきっと、「希望」と呼ぶのだろう。