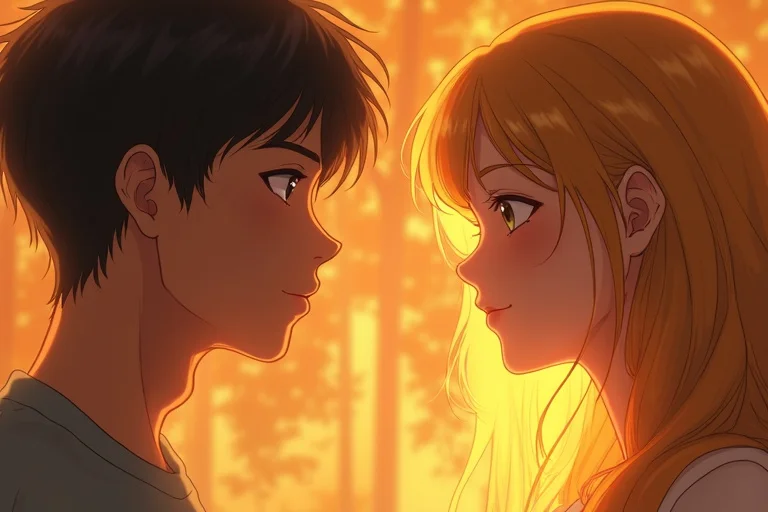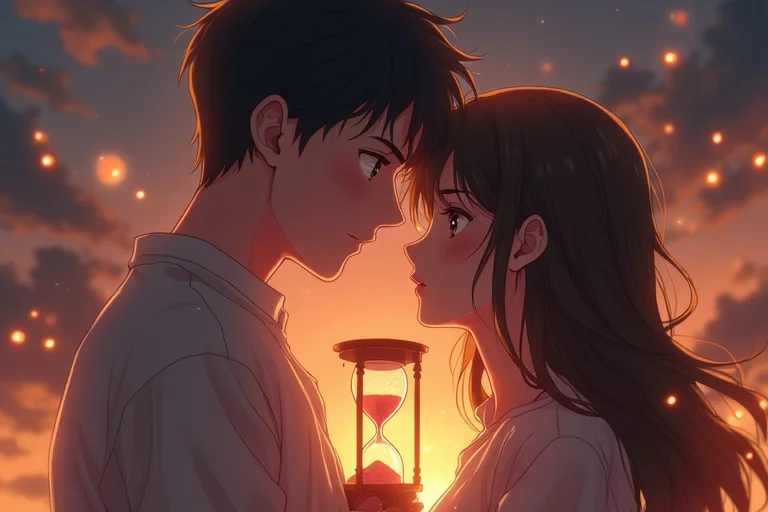第一章 鳴り響く静寂
柏木湊の世界は、常に静寂に縁どられていた。彼が店主を務める古書店『栞文庫』は、埃とインクと古い紙の匂いが満ちる、時間の澱んだ入り江のような場所だった。客のまばらな午後の光の中、ページをめくる乾いた音だけが、彼の孤独に優しい伴奏を添える。湊は、この静寂を愛していた。いや、愛さざるを得なかった。人と深く関わることを、彼は極端に恐れていたからだ。
その均衡が崩れたのは、ある雨の日のことだった。
ドアベルがちりん、と控えめな音を立て、一人の女性が入ってきた。月島詩織。彼女はこの数ヶ月、週に一度ほどのペースで店を訪れる、口数の少ない常連客だった。濡れた傘から滴る雫が、使い古された床板に小さな染みを作っていく。彼女はいつも通り会釈だけすると、植物図鑑が並ぶ棚へと吸い寄せられていった。
湊はカウンターの内側から、彼女の姿をそっと目で追った。細い指が背表紙をなぞり、一冊の本を抜き取る。それは、忘れられた植物学者による、手彩色の挿絵が美しい稀覯本だった。彼女がそのページを開いた、まさにその瞬間だった。
――ああ、見つけた。ずっと探していた、忘れられた植物の息吹がここに……。
湊の鼓膜を、脳を、澄み切ったソプラノの声が直接揺さぶった。彼は思わず息を呑み、カウンターの縁を強く握りしめる。冷や汗が背筋を伝った。声の主は、間違いなく目の前の月島詩織だった。しかし、彼女の唇は固く結ばれたままで、微動だにしていない。
まただ。また、始まってしまった。
これは湊がひた隠しにしてきた、呪いにも似た特性だった。彼が誰かに本気で恋をした瞬間、その相手の「心の声」が、四六時中、頭の中に直接流れ込んでくるようになるのだ。それは相手の意思とは無関係に、思考の断片、感情のうねり、潜在意識の呟きが、フィルターなく垂れ流される現象だった。
かつて、この能力のせいで一つの恋をめちゃくちゃにした。相手の些細な不満や、口に出さない嘘がすべて聞こえてしまい、疑心暗鬼に陥った末に関係は破綻した。もう二度と誰にも心を開くまいと、静寂の中に立てこもっていたというのに。
「……あの、これ、いただきます」
詩織が本をカウンターに置いた。彼女の実際の声は、心の声よりも少しだけ低く、落ち着いていた。
――この店主さん、少し顔色が悪いみたい。疲れているのかしら。
頭の中の声が、湊の心配をしている。湊は平静を装うのに必死だった。
「……はい。三千八百円になります」
震える指で本を包み、代金を受け取る。彼女の指先が偶然触れただけで、心臓が跳ね上がり、頭の中の声がさらにボリュームを上げた。
――この本のインクの匂い、すごく落ち着くなあ。雨の匂いと混ざって、なんだか懐かしい気持ちになる。
詩織は静かに会釈して店を出ていく。ドアベルの音が遠ざかっても、湊の頭の中では、彼女の詩的な独白がいつまでも鳴り響いていた。これから毎日、毎分、毎秒、この声と共に生きていかなくてはならない。湊は、訪れた恋の予感と、それに伴う呪いの再来に、ただ深く絶望するしかなかった。
第二章 心の声と唇の言葉
詩織の心の声との奇妙な共存生活が始まって一ヶ月が過ぎた。当初の絶望とは裏腹に、湊の日常は苦痛に満ちたものではなかった。むしろ、驚くほど豊かになっていた。
口数が少なく、表情もあまり変わらない詩織。彼女が発する言葉は、常に簡潔で、どこか他人行儀だった。しかし、湊の頭の中に響く彼女の心は、饒舌で、好奇心に満ち、世界のあらゆるものに感動する詩人のようだった。
ある日、彼女が珍しいシダの葉を栞代わりに挟んだ本を持ってきた。
「柏木さん、この本のこの部分、少し傷んでいるみたいで」
彼女が指し示したのは、ページの隅の小さな破れだった。
――このシダ、昨日見つけたウラボシ科の一種。葉脈の形が、この本の挿絵の木の枝ぶりにそっくり。きっとこの本も喜んでくれる。
湊は、彼女の心の声を聞きながら、思わず微笑んでいた。
「ええ、少し古い本ですから。でも、この破れ方も、なんだかシダの葉脈のようですね。ウラボシ科の……」
そこまで言って、はっと口をつぐむ。だが、詩織は驚いたように目を丸くし、そして、ふわりと花が咲くように笑った。
「……よく、ご存知ですね。そうです、ウラボシ科のシダです。なんだか、嬉しいです」
初めて見る彼女の笑顔に、湊の心臓は大きく脈打った。頭の中では「どうして分かったんだろう?この人、もしかして私と同じくらい植物が好きなのかも。もっと話してみたい」という喜びの声が弾けていた。
それから、二人の間の会話は少しずつ増えていった。湊は、心の声を手がかりに、彼女が本当に興味を持っている話題を振った。本の紙質、インクの滲み具合、描かれた植物の生態。実際の会話はまだぎこちなかったが、湊には確信があった。自分たちは、誰よりも深く理解し合えている、と。
詩織もまた、湊との時間に不思議な心地よさを感じているようだった。口下手な自分が、なぜか彼と話していると、すらすらと言葉が出てくる。自分の興味の核心を、いつも的確に突いてくれる。まるで、心を読まれているかのような、不思議な感覚。
――この人といると、本当の自分になれる気がする。この静かな場所が、私の世界で一番安心できる空間になってしまった。
彼女の温かい心の声に包まれるたび、湊はかつて呪いだと思っていたこの能力が、かけがえのない贈り物のように思えてきた。過去の失敗は、相手を理解しようとせず、ただ聞こえてくる声に振り回された自分の未熟さ故だったのかもしれない。今度こそ、この力を使って、彼女を幸せにできる。そんな傲慢な希望さえ、抱き始めていた。
第三章 沈黙の告白
季節は初夏に移ろい、古書店の窓から見える街路樹の緑が目にまぶしい季節になった。湊と詩織の関係は、友人以上恋人未満という穏やかな水路を、ゆっくりと進んでいた。しかし湊の中では、彼女への想いはとうに満潮を迎えていた。彼女の心の声は、もはや湊自身の心音と同じくらい、当たり前で、愛おしい響きになっていた。
今日こそ、伝えよう。
湊は決意を固め、詩織を近くの植物園に誘った。ガラス張りの温室は、湿った土と甘い花の香りで満ちている。巨大なシダの葉が作る影の下で、二人は並んで歩いた。
――柏木さんの横顔、綺麗だな。この熱帯植物の葉脈みたいに、繊細で、力強くて……。
聞こえてくる心の声が、湊の背中を優しく押す。大丈夫、彼女も同じ気持ちだ。
「月島さん」
湊は立ち止まり、彼女に向き合った。心臓が早鐘を打つ。詩織も足を止め、不思議そうに彼を見つめ返した。その潤んだ瞳の中に、自分が映っている。
「俺、君のことが……」
好きだ、と言おうとした。その言葉が唇から滑り出ようとした、まさにその瞬間。
――プツン。
まるで古いラジオの電源が落ちるように、湊の頭の中から、詩織の声が完全に消え去った。
永遠に続くかと思われた彼女の思考のメロディが、 абсолютной(アプスリュートノイ)…完全な沈黙に変わった。
「……え?」
湊は混乱した。何が起きた?
目の前の詩織は、驚いたようにわずかに目を見開き、そして、何かを悟ったように、はにかむように、かすかに微笑んだ。だが、彼女が何を考えているのか、湊には全く、何も、分からなかった。
喜び?戸惑い?それとも拒絶?
――どうして?どうして何も聞こえないんだ?嫌われた?僕の気持ちに気づいて、恋が冷めてしまったのか?
今まで彼女の心を映す鏡として頼り切っていた能力が、突如として失われた。それは、ずっと握りしめていた羅針盤を大海原で手放すような、途方もない喪失感と恐怖だった。目の前にいる詩織が、急に得体の知れない、全くの他人に思えた。
「……ごめん」
湊は、それだけを絞り出すと、恐怖に駆られてその場から逃げ出した。温室の湿った空気を引き裂き、訳も分からず走った。後ろで、詩織が息を呑む気配がしたが、振り返ることはできなかった。頭の中に鳴り響くのは、彼女の声ではなく、自分自身のパニックによる耳鳴りだけだった。
店に戻り、鍵をかけてしゃがみ込む。何日も悩んだ。なぜ声は消えたのか。恋が終わったのか。それとも……。
そこで、湊は一つの残酷な可能性に行き着いた。
自分の能力は「自分が一方的に恋をした相手」の声が聞こえるものだと思っていた。しかし、もし、そうではなかったとしたら?もし、その恋が実り、「相手も自分に恋をした瞬間」に、声が聞こえなくなるのだとしたら?
超常的な繋がりは、二人が本当の意味で向き合うべき段階に至った時、その役目を終える。あとは、不確かで、もどかしい現実の言葉と心を、手探りで重ねていくしかない。
能力に頼り、相手を理解した気になっていた自分への、これは罰なのだろうか。それとも、試練なのだろうか。
第四章 きみと話すために
湊は、自分の愚かさに気づいた。
自分は月島詩織という人間を愛していたのか。それとも、彼女の筒抜けの「心」という、決して裏切らない安全な情報源に恋をしていただけなのか。全てが分かるという全能感に酔い、本当の彼女と向き合う努力を怠っていたのではないか。
声が聞こえなくなった今、目の前の「何もわからない」詩織を、それでも愛しているのだろうか。
答えは、すぐに出た。
会いたい。声が聞こえなくても、彼女に会って話がしたい。彼女の本当の言葉が聞きたい。
湊は店のドアを開け、雨上がりの街へ飛び出した。彼女がいつも立ち寄る研究室、行きつけのカフェ、そして、あの植物園。息を切らして探し回り、ついに、閉園間際の植物園のベンチに、ぽつんと座る彼女の姿を見つけた。
「月島さん……!」
彼女はゆっくりと顔を上げた。その瞳は少し赤く腫れているように見えた。
湊は彼女の前に立ち、言葉を選ばず、全てを打ち明けた。自分の持つ特異な能力のこと。初めて会った日から、彼女の心の声がずっと聞こえていたこと。その声にどれだけ救われ、惹かれていったか。そして、告白しようとした瞬間に声が聞こえなくなり、恐怖に駆られて逃げ出してしまったこと。
「君が何を考えているか、分からなくなるのが怖かったんだ。でも、間違っていた。俺は、聞こえる声じゃなくて、君自身を……君のことが知りたい。分からなくても、分かりたいんだ」
詩織は、驚きに目を見開いたまま、黙って湊の話を聞いていた。長い沈黙が落ちる。湊の頭の中は静かだった。ただ、目の前の彼女の表情だけが、唯一の情報だった。
やがて、彼女は小さく息を吐き、そして、静かに口を開いた。
「……そうだったんですね」
その声は、震えていた。
「だから、分かったのですね」
「え……?」
「私が、あの時……あなたが告白してくれると分かった瞬間に、どれだけ嬉しかったか。そして、私が、あなたと同じくらい、あなたのことを好きになったってことが」
彼女は、涙を一筋こぼしながら、それでもはっきりと微笑んでいた。
「あなたの心の声は聞こえないけれど、なんとなく分かりました。あなたが、私の言葉だけじゃなくて、私の心を、ずっと見ていてくれたこと。だから、私も、あなたの前では素直になれたんだって」
二人は、不確かで、時に誤解し合うかもしれない「普通の」恋人になった。もう湊に彼女の心の声は聞こえない。だが、彼は代わりに、彼女の言葉を、かすかな表情の変化を、ためらいがちな仕草の一つ一つを、全身で受け止めようと決意した。
聞こえないからこそ、懸命に聞こうとする。分からないからこそ、必死に分かろうとする。それこそが、本当の対話であり、愛なのだと、湊は嵐のような沈黙の果てに、ようやく悟ったのだ。
古書店『栞文庫』の静寂は、以前とは少しだけその色合いを変えた。湊の頭の中は心地よい沈黙に満たされ、隣には、静かに本を読む詩織がいる。時折、彼女が顔を上げて何かを話しかける。その言葉の一つ一つを、湊は宝物のように受け止める。
愛とは、全てを知ることではない。知り続けようと、手を伸ばし続ける、その果てしない営みのことなのかもしれない。二人の間には、聞こえない心の声の代わりに、もっと温かく、確かな言葉が、これからゆっくりと紡がれていくのだろう。