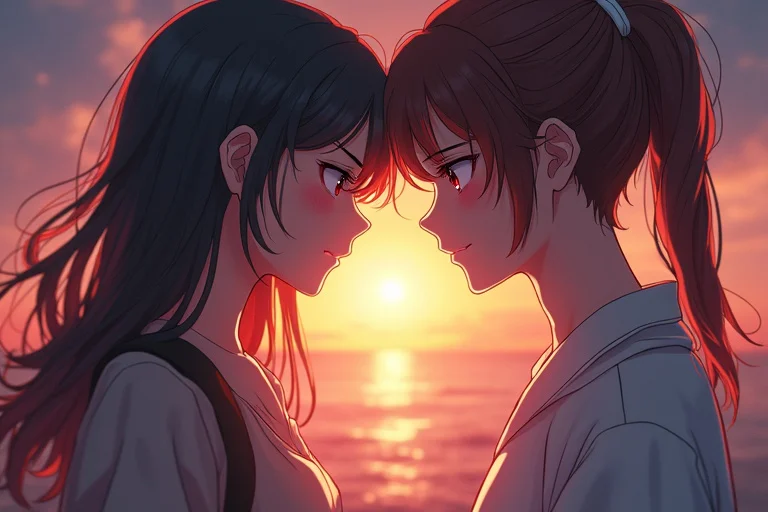第一章 空っぽの石と歌う人
俺の店は、記憶の吹き溜まりのような場所だった。街角の古物商『黄昏堂』。人々が手放した様々な「愛の記憶石」を預かり、次の持ち主へと繋ぐのが俺、レンの仕事だ。店内は色とりどりの光で満ちている。情熱的な愛は真紅に、穏やかな愛は瑠璃色に、若々しい愛は萌黄色に。それぞれの石が、かつて誰かが抱いた想いの温もりを静かに放っていた。
だが、店の奥、ビロードを敷いた黒檀の小箱に収められている一角だけは、まるで光を吸い込むかのように静まり返っていた。そこに並ぶのは、十数個の「無色の愛の記憶石」。水晶のように透明で、氷のように冷たい。訪れる客は皆、その石を見て眉をひそめ、「愛の抜け殻なんて、気味が悪い」と囁いた。俺はいつも曖昧に微笑んで返すだけだった。彼らには、この石が放つ微かな旋律が聞こえない。俺にしか聞こえない、愛した人たちの物語の残響が。
「こんにちは!素敵な石がたくさんあるのね」
鈴を転がすような声に顔を上げると、入り口に一人の旅人が立っていた。日に焼けた肌に、大きなリュートを背負った快活な少女。アリアと名乗った彼女は、吟遊詩人だという。彼女の瞳は、店内の色鮮やかな石には目もくれず、まっすぐに奥の小箱へと注がれていた。
「この、透明な石……すごく静か。でも、なんだか、たくさんの言葉を飲み込んでいるみたい」
アリアは小箱の前に屈み込むと、無色の石をうっとりと眺めた。彼女の言葉に、俺の心臓が小さく跳ねる。この石に興味を示した人間は、彼女が初めてだった。
「それは、愛が失われた石だ。誰も欲しがらない」
俺は努めて無関心な声で言った。彼女を遠ざけなければならない。心のどこかで警鐘が鳴っていた。
「失われた?そうかなあ」
アリアは首を傾げ、悪戯っぽく笑った。
「私には、まだ語り終えていない物語が、この中で眠っているように聞こえるけどな」
そう言って、彼女はリュートを爪弾いた。ポロン、と鳴った優しい音色が、店内の埃をきらきらと舞わせる。その瞬間、無色の石たちが、彼女の音色に共鳴するかのように、ほんの一瞬、淡い光を帯びた気がした。
第二章 満ちる心、消えゆく輪郭
アリアは街に滞在し、毎日のように黄昏堂へ顔を出した。彼女は「無色の石のための歌を作るの」と言って、店の隅でリュートを奏で、旋律を紡いだ。彼女がいるだけで、色のない俺の世界が、少しずつ鮮やかになっていくようだった。彼女が淹れてくれる、ほのかに甘いカモミールの香り。彼女の歌声が、古びた柱を震わせる振動。指先が偶然触れた時の、驚くほどの温かさ。
俺は、自分が彼女に惹かれていくのを、どうすることもできなかった。それは抗いがたい引力であり、同時に、破滅への序曲だった。
「レンは、どうしてそんなに悲しい顔をするの?」
ある雨の日、店先で雨宿りをしながら、アリアが尋ねた。
「俺は……」
言葉に詰まる。真実を告げることはできない。俺が誰かを本気で愛してしまうと、その人は世界から消える。家族も、友人も、誰の記憶からも。ただ俺一人の記憶と、この冷たい無色の石だけを残して。それは呪いだった。俺の愛は、祝福ではなく、忘却という名の死をもたらすのだ。
「悲しくなどない」
俺がそう言って俯くと、アリアは何も言わず、リュートを手に取った。彼女が奏で始めたのは、まだ未完成の、無色の石の歌。それは、忘れられた者たちのための鎮魂歌のようでありながら、どこか希望に満ちた、力強いメロディだった。
「いつか、この石たちが本当に語り出す物語を、私が歌にしてあげる。そしたら、きっと、みんなその物語を好きになるわ」
雨音に混じる彼女の歌声を聞きながら、俺は掌を強く握りしめた。駄目だ。これ以上、彼女のそばにいてはいけない。彼女の優しさが、彼女の笑顔が、俺の心を溶かしていく。そして、愛が完成したその時、彼女は消えてしまう。
だが、俺は彼女から離れることができなかった。彼女のいない世界を想像するだけで、呼吸が苦しくなった。俺は、運命に抗うことを諦め、束の間の幸福に身を委ねるという、最も愚かで、最も人間らしい選択をしてしまった。
第三章 世界のための代償
その日は、空が奇妙なほど赤く燃えていた。街の中心にそびえ立つ、世界の調和を司る「中央の塔」から、重く不吉な鐘の音が響き渡った。世界のエネルギー源である「愛の記憶石」の輝きが、全体的に弱まっているのだという。人々の愛が、世界を支えきれなくなり始めている。街は不安と焦燥に包まれた。
その不穏な空気の中、俺はアリアへの愛が、もう引き返せないところまで来ていることを自覚していた。彼女と過ごした日々は、俺の乾いた心を満たし、無色の石の中に閉じ込めていた過去の痛みさえも、優しく包み込んでくれた。彼女こそが、俺の真実の愛なのだと、魂が叫んでいた。
その想いを自覚した、まさにその瞬間だった。
「あれ……?」
アリアが、自分の手を見つめて呟いた。彼女の指先が、ほんのわずかに透けている。淡い光の粒子が、彼女の身体から立ち上り始めていた。
「アリア!」
俺が駆け寄ろうとすると、店の前を通りかかった老婆が、訝しげに俺を見た。
「坊や、誰と話しているんだい?」
老婆の目には、もうアリアの姿は映っていなかった。世界が、彼女を忘れ始めている。ああ、まただ。また、俺の愛が、大切な存在をこの世界から消し去ろうとしている。
「レン、やっぱり……あなたは、何かを隠していたのね」
消えゆく輪郭の中で、アリアは穏やかに微笑んでいた。恐怖も、絶望も、その表情にはなかった。
「でも、いいの。あなたの瞳の中に、私の姿が見える。それだけで、私は幸せだった」
彼女の身体が、いっそう強く輝き始める。それはまるで、星が燃え尽きる前の、最後の煌めきだった。
「私の歌、覚えていて。私がここにいたっていう、たった一つの証だから……」
「嫌だ!行くな、アリア!」
俺は虚空に手を伸ばす。だが、その指先は温かい肌に触れることなく、光の粒子をすり抜けた。眩い光が店を満たし、そして、静かに消えた。
アリアが立っていた場所には、一つの小さな石が落ちていた。
透明で、冷たい、「無色の愛の記憶石」。
俺がそれを拾い上げた瞬間、遠くで鳴り続けていた中央の塔の不吉な鐘の音が、ぴたりと止んだ。そして、塔の頂が、まるで力強い心臓のように、一度だけ、鮮烈な光を放った。
世界が救われたのだと、直感的に理解した。
俺の愛が、アリアの存在そのものを、世界を維持するための純粋なエネルギーへと変換したのだ。彼女は記憶石にすらなれなかった。彼女は、世界の礎になったのだ。
第四章 君を語るための旅路
絶望が、俺のすべてを塗りつぶした。俺の愛は、呪いではなかった。それは、世界を存続させるための、あまりにも残酷な「生贄」のシステムだったのだ。この世界は、俺のような人間の強すぎる愛を糧にして、かろうじてバランスを保っている。俺が愛を諦めれば、世界は緩やかに崩壊へと向かうだろう。かといって、愛し続ければ、そのたびに誰かが犠牲になる。
膝から崩れ落ち、アリアが残した無色の石を握りしめる。冷たい。いつものように、ただ冷たいだけのはずだった。だが、その時、石の奥底から微かな音が聞こえた。アリアの歌だ。彼女が作っていた、あの未完成の旋律。それは、彼女の存在の残響。彼女が生きた証。彼女の物語そのものだった。
他の石からも聞こえてくる。俺がかつて愛した、優しい花屋の娘の声。博識な歴史学者の青年の声。彼らの存在は世界に吸収されたが、その物語は、俺とこの石の中にだけ、まだ息づいている。
俺はゆっくりと立ち上がった。
涙はもう出なかった。
愛を諦める?世界を見捨てる?どちらも違う。アリアは言った。「私の歌、覚えていて」と。彼女は、忘れられることを何より恐れていた。
ならば、俺のやるべきことは一つだ。
彼らの存在を、愛の記憶石という「形」としてではなく、決して消えない「物語」として、この世界に刻みつける。
俺は黄昏堂の扉に「休業」の札をかけ、アリアが遺したリュートを背負った。そして、無色の石をすべて、革の袋に入れて胸に下げる。それは、俺が語るべき物語の種子だった。
古物商レンは死んだ。今日から俺は、名もなき吟遊詩人だ。
夕暮れの道を、俺は歩き出す。誰も知らない、誰も覚えていない、アリアという少女がいたこと。彼女がどんなに明るく笑い、どんなに優しい歌を歌ったか。その物語を、リュートの音色に乗せて、街から街へと語り継いでいく。
俺の歌が人々の心を打ち、彼らの心の中に新しい愛の光を灯すのなら。それが巡り巡って、この歪んだ世界を少しでも正しい形に戻せるのなら。
胸に下げたアリアの石が、俺の鼓動と歌声に共鳴するかのように、微かな温もりを帯びていた。
「聞こえるかい、アリア。君の物語を始めよう。それは、世界で一番、美しい愛の歌だ」
俺は歌う。君が、そして俺が愛したすべての人々が、物語の中で永遠に生き続けるために。それが、この残酷な世界で俺が見つけた、唯一の愛し方だった。