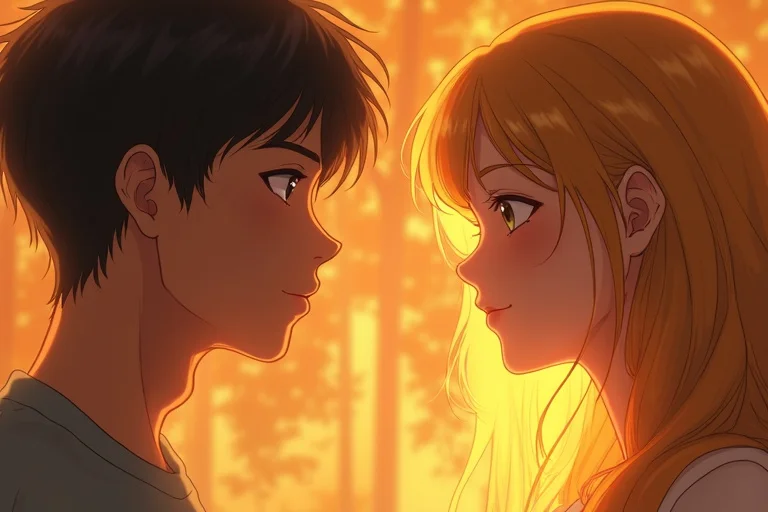第一章 誰かの幸福
水無月律(みなづき りつ)の仕事は、死者の声を聴くことに似ていた。
埃と樟脳の匂いが混じり合う古物店『時のかけら』の店主である彼には、物に触れると、その持ち主の強い記憶を追体験する、という奇妙な能力があった。それは呪いにも似た祝福で、律は他人の人生の断片を覗き見ることに、とうの昔に倦み疲れていた。喜びも、悲しみも、怒りも、すべては借り物の感情。自分の人生を生きているという実感が、日に日に薄れていくようだった。
その日、律が仕入れたガラクタの山の中に、それはあった。手のひらに収まるほどの、銀細工が施された木製のオルゴール。蓋には月長石が埋め込まれ、鈍い乳白色の光を放っている。全体がくすみ、ネジを巻いても音は鳴らない。だが、律がそれに指を触れた瞬間、世界は色を変えた。
――夏の陽光が、勢いよく流れ込んできた。
風鈴の涼やかな音。庭の向日葵が太陽に向かって背伸びをしている。縁側で、若い男が壊れたオルゴールを修理している。その手元を、隣に座る女性が愛おしそうに見つめている。
「ねえ、悠人。本当に直るの?」
優しい、鈴を転がすような声。彼女の黒髪が、風にさらりと揺れる。
「任せとけって。このオルゴールの曲、葵が好きだって言ってたろ」
悠人と呼ばれた男は、自信満々に笑う。その顔立ちは、驚くほど律自身に似ていた。だが、律の知らない、屈託のない明るさがそこにはあった。
記憶は奔流のように律を飲み込んでいく。海辺ではしゃぐ二人。誕生日を祝う小さなケーキ。喧嘩して、仲直りして、未来を語り合う夜。そのすべてが、どうしようもないほどの幸福に満ちていた。律は、まるで自分がその場にいるかのように、風の匂いを、彼女の柔らかな肌の感触を、胸を満たす多幸感を、鮮明に感じていた。
中でも律の心を捉えたのは、葵と呼ばれた女性の笑顔だった。彼女が笑うと、世界の彩度が一段階上がるような気がした。律は、これまで追体験してきた数多の記憶の中で、これほど強く心を揺さぶられたことはなかった。これは誰かの記憶だ。自分のものではない。そう頭では理解しているのに、胸の奥で芽生えた感情は、紛れもなく律自身のものだった。
気づけば、律は店の片隅で、冷たいオルゴールを握りしめたまま、呆然と立ち尽くしていた。窓の外は、すでに茜色に染まっていた。頬を伝う一筋の涙が、自分のものなのか、それとも記憶の中の悠人のものなのか、律には分からなかった。ただ、あの笑顔にもう一度会いたい、と。生まれて初めて、他人の過去に対して、強烈な渇望を覚えていた。
第二章 現実と幻影の境界
その日から、律の世界はオルゴールの記憶に侵食され始めた。店のカウンターで、客の応対をしながらも、意識はしばしば記憶の中の夏に飛んだ。目を閉じれば、葵の笑い声が聞こえる。鼻腔をくすぐるのは、古書の匂いではなく、記憶の中の潮風の香り。現実と幻影の境界線が、ゆっくりと溶けていくようだった。
律は、まるで憑かれたようにオルゴールの記憶を何度も追体験した。あの幸福な日々を、自分のもののように反芻した。記憶の中の葵に恋焦がれる自分は、滑稽で、哀れだった。彼女は実在するかも分からない幻影。それでも、感情の奔流は止められなかった。
そんな日々が続いていたある雨の日、律は気分転換に近所の小さなカフェに立ち寄った。古びた木の扉を開けると、焙煎された豆の香ばしい匂いがふわりと鼻をかすめる。カウンターの奥で、静かにカップを拭いていた女性と目が合った瞬間、律は息を呑んだ。
そこにいたのは、記憶の中の葵、その人だった。
艶やかな黒髪、少し憂いを帯びた大きな瞳、白い肌。記憶の中の快活な笑顔は消え、どこか儚げで物静かな雰囲気を纏ってはいたが、間違いなく彼女だった。
「いらっしゃいませ」
落ち着いた声が、律の鼓膜を震わせる。律は、心臓が喉から飛び出しそうなのを必死で堪え、カウンター席に腰を下ろした。
彼女の名前は、日向葵。このカフェで働いているらしかった。律はぎこちなくコーヒーを注文し、その横顔を盗み見た。彼女は時折、窓の外の雨を眺めては、遠い目をする。その表情には、記憶の中にはなかった深い哀しみの影が落ちていた。
律はそれから毎日、そのカフェに通った。言葉を交わすのは注文の時だけ。それでも、彼女と同じ空間で、同じ時間を過ごせるだけで、胸が満たされた。しかし同時に、罪悪感が律を苛んだ。自分は、彼女の恋人だった男の記憶を盗み見て、彼女に横恋慕しているのだ。卑劣極まりない。
オルゴールの記憶の中の悠人は、葵を心から愛していた。その純粋な愛情を知っているからこそ、律は苦しかった。葵に近づきたい。けれど、どんな顔をして彼女に会えばいい? 自分のこの感情は、本当に自分のものなのか? それとも、悠人の記憶が残した残響に過ぎないのか?
ある日、律は店でオルゴールの修理を試みた。精密な機械いじりは得意だった。もし、これを直して彼女に渡せば、あの笑顔を取り戻せるかもしれない。そんな淡い期待を抱いて。だが、分解していくうち、内部の櫛歯が一本、致命的に折れていることが分かった。修理は不可能だった。絶望が、冷たい霧のように律の心を覆った。自分は、彼女の過去を修復することも、未来に関わることもできない、無力な傍観者なのだ。
第三章 残響の先にあるもの
答えの出ない問いに苛まれ、眠れない夜が続いた。律はついに、すべてを打ち明ける覚悟を決めた。たとえ軽蔑されようとも、この歪んだ状況から一歩踏み出さなければ、自分は壊れてしまう。
次の日、律は店を閉めると、あのオルゴールを手にカフェへ向かった。閉店間際の店内で、葵は一人、静かに片付けをしていた。
「あの、日向さん」
緊張で声が震える。葵は驚いたように顔を上げた。
「これ、見覚えありませんか」
律はカウンターの上に、そっとオルゴールを置いた。
葵の目が、見開かれる。彼女は震える指でオルゴールに触れ、その表面をなぞった。その瞳から、大粒の涙がぽろぽろと零れ落ちる。
「どうして……これを……」
「拾ったんです。そして、僕は……見てしまった。このオルゴールに残された、あなたと、悠人さんという人の記憶を」
律は、自分の能力のこと、記憶の中の幸福な日々のこと、そして彼女に惹かれてしまったことを、途切れ途切れに、正直に話した。軽蔑されるだろう。気味悪がられるだろう。だが、葵の反応は予想外のものだった。彼女は静かに涙を拭うと、真っ直ぐに律を見つめた。
「悠人は、三年前の事故で……亡くなりました。これは、彼が私にくれるはずだった、誕生日プレゼントでした。事故の時に、どこかで失くしてしまって……ずっと探していたんです」
そして、彼女は律の心を根底から揺るがす事実を告げた。
「水無月、律さん……。悠人の苗字も、水無月でした。彼は、幼い頃に両親の離婚で引き離された、あなたの双子の兄です」
時間が、止まった。兄? 自分に、双子の兄がいた? 律は、両親からそんな話を聞いたことなど一度もなかった。記憶の中の悠人の顔が、鏡に映る自分の顔と重なる。だから、あれほど似ていたのか。だから、彼の記憶に、これほど強く同調してしまったのか。
律が葵に感じていた愛情は、彼自身のものなのか。それとも、血を分けた兄の魂が、オルゴールを通して叫んでいた、叶わなかった想いの残響なのか。律のアイデンティティが、ガラガラと音を立てて崩れていく。
「……彼も、あなたと同じでした」と葵が静かに続けた。「悠人も、物に触れると記憶が読めることがあった。だから、古いものが好きで……いつか二人で古物店を開くのが夢だったんです。あなたのお店を見るたび、彼を思い出していました」
衝撃的な事実に打ちのめされ、律はその場に立ち尽くすことしかできなかった。
数日後、律は再びカフェを訪れた。彼は、徹夜で作り上げたものを葵に差し出した。それは、一本だけ材質の違う、新しい櫛歯が組み込まれたオルゴールの機械部分だった。
「完全に同じ音にはなりません。でも、これなら……鳴ります」
律は、兄の記憶を、そして自分の感情を、ただの過去の遺物にしたくなかった。このオルゴールを、過去を閉じ込める箱ではなく、未来へ繋ぐための装置にしたかった。
葵が、ゆっくりとネジを巻く。カチ、カチ、と小さな音が響き、やがて、澄んだ、けれどどこか切ないメロディーが流れ出した。それは、記憶の中で聴いた懐かしい曲でありながら、律が加えた一本の歯が奏でる微かな不協和音が、新しい響きを生み出していた。それは悠人の記憶の音色であり、律の想いの音色でもあった。
葵は、その音色に耳を傾けながら、静かに微笑んだ。それは、記憶の中で見た太陽のような笑顔とは違う、雨上がりの虹のような、儚くも美しい微笑みだった。
「ありがとう。……悠人が、あなたに会わせてくれたのかもしれない」
律の恋は、始まる前に終わった。だが、不思議と心は穏やかだった。兄の存在を知り、彼の愛した人に出会い、自分の感情の正体と向き合ったことで、彼は初めて「自分の人生」の輪郭を掴んだ気がした。借り物ではない、確かな喪失感と、それでも前を向こうとする微かな希望。
二人が恋人になることは、きっとないだろう。しかし、律と葵の間には、死んだ兄を介した、誰にも理解できない特別な繋がりが生まれた。
律は店に戻り、窓から差し込む夕陽を浴びた。店内のガラクタたちが、今はもうただの物に見える。他人の過去はもう必要ない。これからは、自分のための「時のかけら」を集めていこう。そう、心に決めた。
修理されたオルゴールの音色は、過去と現在、そして未来を繋ぐ残響となって、二人の心の中で静かに鳴り響き続けるだろう。