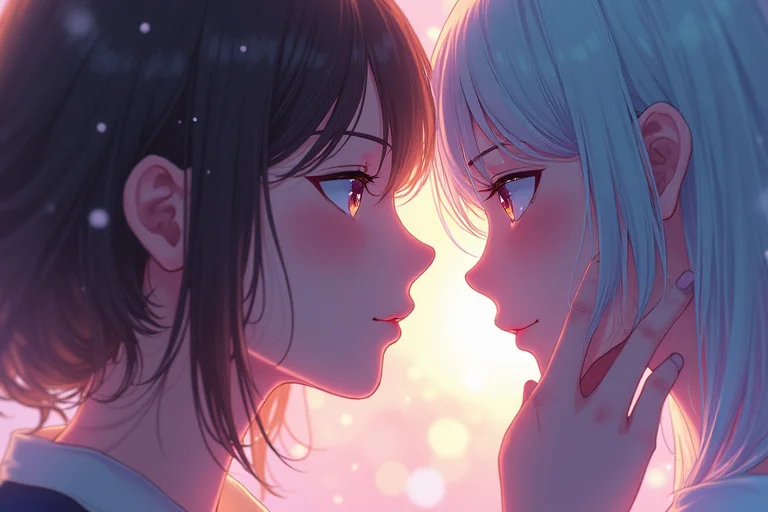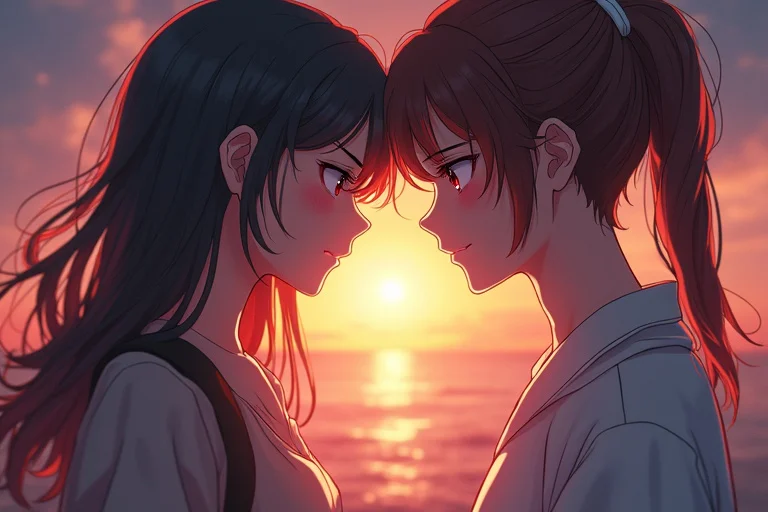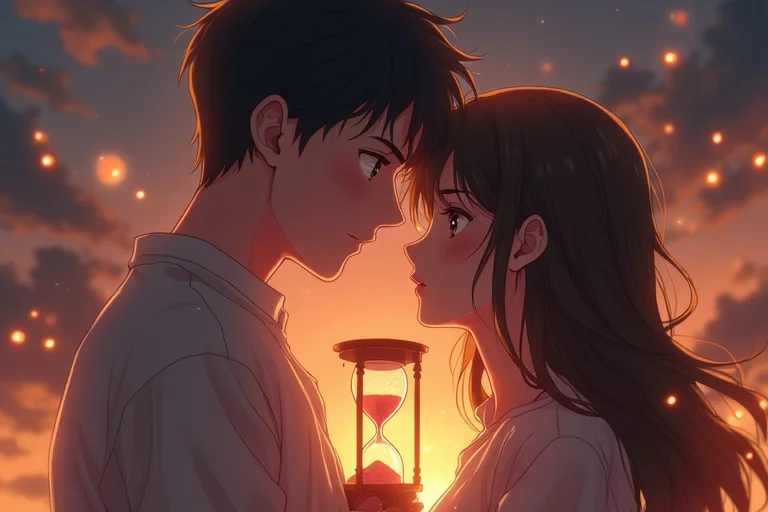第一章 沈黙のプレリュード
私の職業は、ピアノ調律師。音の海を泳ぎ、僅かな周波数のズレも見逃さないことが仕事であり、私の世界の全てだった。父から受け継いだ絶対音感は、時として呪いのように私の耳を苛んだ。街の喧騒、人々の声色に含まれる微細な偽り、調和しない不協和音。それらは全て、私、音葉(おとは)の心を疲弊させるノイズだった。
だから、あの古書店を見つけたのは、一種の奇跡だった。埃とインクの匂いが満ちるその場所は、まるで分厚い頁に吸音されたかのように、心地よい静寂に包まれていた。そして、その静寂の中心に、彼がいた。
店の名は『朔望(さくぼう)書房』。店主の彼は、朔(さく)と名乗った。色素の薄い髪と、古い書物のように落ち着いた瞳を持つ人。彼が発する言葉は、多くはなかった。しかし、その声は、私が今まで聴いたどんな音とも違っていた。チェロの低音のように、空間を柔らかく震わせる穏やかな響き。その声には嘘がなく、虚飾がなく、ただ静かな真実だけがそこにあった。
「この本、面白いですよ。言葉の起源を巡る、少し風変わりな冒険譚です」
彼が薦めてくれた本をきっかけに、私たちは少しずつ話すようになった。調律の仕事の合間に彼の店を訪れ、他愛のない言葉を交わす時間が、私のささくれた心を癒す唯一の処方箋となっていった。彼の声を聞くたび、世界からノイズが消え、美しい和音だけが残るような感覚に陥る。
いつからだろう。彼の声を聞くためだけに、店の扉を開けるようになったのは。彼の瞳に自分が映るだけで、胸の奥で弦が弾かれるようなときめきを感じるようになったのは。
ある雨の日だった。店内で雨宿りをさせてもらっていると、彼が温かいハーブティーを淹れてくれた。カップから立ち上る湯気の向こうで、彼が静かに微笑む。
「雨の音も、いいものですね」
その声が、私の心に最後のひとしずくを落とした。ああ、好きだ。この人が、どうしようもなく。そう自覚した、まさにその瞬間だった。世界が、歪んだ。
彼の唇が動く。「大丈夫ですか?」と、そう言ったように見えた。だが、私の耳には何も届かない。雨が窓を打つ音、壁の古時計が時を刻む音、自分の心臓が早鐘を打つ音。全ての音は聞こえるのに、彼の声だけが、綺麗に切り取られたかのように、私の世界から消え失せていた。まるで、完璧な防音室に彼一人だけを閉じ込めたように。
それが、私の恋の始まりであり、終わりのように思えた、絶望的な沈黙のプレリュードだった。
第二章 筆談と温もり
朔の声が聞こえなくなってから、一週間が過ぎた。私は『朔望書房』に足を運べずにいた。音を扱う仕事の人間が、最も聞きたい音を失う。それは、画家が愛する人の色だけを失うような、あまりにも残酷な矛盾だった。
この現象には、心当たりがあった。幼い頃、祖母が古いお伽話のように語ってくれた言葉が、亡霊のように脳裏に蘇る。「音葉、うちの家系の女はね、本当に誰かを愛してしまうと、その人に関する一番大切な感覚をひとつ、失ってしまうんだよ」。馬鹿げた迷信だと思っていた。だが今、その呪いが現実となって私に降りかかっている。私にとっての一番大切な感覚、それは紛れもなく「聴覚」であり、朔の「声」だった。
もう彼には会えない。そう覚悟を決めていた矢先、店のポストに一通の手紙が届いた。『朔望書房』の便箋に、彼の整った文字が並んでいた。
『最近、お見えになりませんが、お変わりありませんか。もしよろしければ、またお話がしたいです』
その手紙を握りしめ、私は気づけば店の前に立っていた。カラン、とドアベルが鳴る。カウンターの向こうで本を読んでいた朔が顔を上げ、私を見ると、少し驚いたように、そして嬉しそうに目を細めた。
彼の口が動く。何かを言っている。けれど、やはり音はない。私は震える手で、鞄からスケッチブックとペンを取り出した。
『ごめんなさい。あなたの声が、聞こえなくなってしまったんです』
彼の瞳が、僅かに見開かれた。だが、そこに浮かんだのは戸惑いや憐憫ではなく、何かを深く理解したような、穏やかな光だった。彼は黙って頷くと、カウンターの内側から小さな黒板とチョークを取り出した。そして、迷いのない文字を綴る。
『そうでしたか。でも、あなたが来てくれて嬉しい』
その日から、私たちの対話は、筆談になった。スケッチブックと黒板。紙の上を滑るペンの音と、板を擦るチョークの音だけが、私たちの間に流れた。もどかしく、時間がかかる。けれど、言葉を失ったことで、私たちは新しい言語を発見していった。
彼の眉の動き、口角の上がり方、瞬きの速さ。彼の全身が、声の代わりに雄弁に語りかけてくる。私もまた、自分の想いを文字に込めるだけでなく、表情や仕草で伝えようと必死になった。声が聞こえない。その事実が、かえって私たちを、もっと深く互いを理解しようとさせていた。
ある日、私が仕事で落ち込んでいると、彼は黙って隣に座り、私の手のひらに、ゆっくりと指で文字を書いた。「だ」「い」「じょ」「う」「ぶ」。彼の指先から伝わる不器用な温もりが、どんな慰めの言葉よりも、私の心を溶かした。声が聞こえなくても、彼の優しさは確かにここにある。私は、この温もりがある限り、彼と共にいたいと、心の底からそう思った。
第三章 心に響く声
季節は秋に移ろい、私たちの沈黙の対話は、すっかり日常の一部となっていた。朔は、私が聞き取れないことを承知の上で、時々、何かを口ずさむように唇を動かした。その表情から、きっと優しい言葉を紡いでくれているのだろうと想像するのが、私の密かな楽しみになっていた。呪いを嘆く気持ちは、いつしか消えていた。この静かな関係こそが、私たちにとっての愛の形なのだと、受け入れ始めていた。
その日は、冷たい雨が降っていた。高い棚の上にある専門書を取ろうとした朔が、古びた脚立の上でぐらりと体勢を崩した。スローモーションのように、彼の身体が傾いでいく。
「危ない!」
私が叫ぶより早く、彼の落下を予感した、その刹那だった。
――― 大丈夫だ、音葉さん。
頭の中に、直接、声が響いた。それは鼓膜を震わせる物理的な音ではなかった。思考そのものが、何の媒介もなく、私の意識に流れ込んできたような、鮮明で温かい声。間違いなく、朔の声だった。
私は呆然と立ち尽くした。朔は体勢を立て直し、無事に床に降り立つと、私と同じくらい驚いた顔でこちらを見ていた。彼の唇は、一ミリも動いていなかったのに。
「今……あなたの声が……」
スケッチブックに走り書きすると、彼はこくりと深く頷いた。そして、店の奥にある小さな金庫から、鍵のかかった木箱を取り出してきた。中に入っていたのは、古びた一冊の日記だった。彼が指し示した頁には、インクが滲んだ、美しい筆跡が並んでいた。それは、彼の祖父が記したものだという。
『本日、最愛の妻、小夜子の声が、ついに聞こえなくなった。我々の一族に伝わる「対話」の時が来たのだ。人は言葉で嘘をつき、言葉で傷つけ合う。声という不確かな楽器は、時に魂の旋律を歪めてしまう。だが、真に魂が結ばれた相手とは、その楽器を捨て、直接心で語り合うことができる。声が聞こえなくなるのは、喪失ではない。より深く、純粋な対話の始まり。魂が、相手の魂の声を聴く準備ができたという、祝福の証なのだ』
日記を読み終えた私の頬を、涙が伝った。呪いだと思っていた。罰だと思っていた。でも、違ったのだ。これは、祝福だった。
朔が、私の目を見て、ゆっくりと黒板に書いた。
『僕も、あなたを好きだと自覚した日から、あなたの声が聞こえなくなりました。ずっと待っていました。僕の心が、あなたに届く日を』
彼の本当の声が、再び頭の中に響き渡る。
――― やっと、伝えられる。音葉さん。愛しています。
それは、私が生まれて初めて聴いた、真実の愛の音色だった。
第四章 沈黙のエチュード
私たちの世界から、物理的な声は消えた。だが、そこには以前とは比べ物にならないほど豊かな対話が満ちていた。夕暮れの古書店で、私たちは向かい合って座る。窓から差し込む橙色の光が、空気中を舞う細かな埃を金色に照らし出し、まるで時間が止まったかのようだった。
私たちは、もう筆談を必要としなかった。
――― 今日は、難しい調律だったんだね。ベートーヴェンの月光。少し、心が疲れている。
彼の心からの労りが、温かい毛布のように私を包む。
――― うん。でも、こうして朔さんの顔を見たら、全部調律されていくみたい。あなたの心は、どんな音をしているんだろうって、いつも考えてた。とても静かで、澄んだ湖みたいな音。
私の想いが、彼の中にさざ波のように広がっていくのが分かる。彼は穏やかに微笑むと、私の手をとり、その甲にそっと口づけを落とした。言葉にならない、しかし何よりも雄弁な愛情が、肌を通して流れ込んでくる。
かつて私は、言葉に怯えていた。声色に含まれる棘、裏腹な響き、すれ違う意味。言葉は人を繋ぎもすれば、残酷に引き裂きもする。だから、音に嘘のないピアノの調律に逃げ込んでいたのかもしれない。
でも、今は違う。私たちは、嘘や誤解の入り込む余地のない言語を手に入れた。それは、世界でたった二人だけに通じる、魂の言葉。沈黙はもはや断絶ではなく、最も深い交歓の証となった。
失ったのではない。手に入れたのだ。本当に大切なのは、鼓膜で聞くことではなく、心で聴くことだった。愛とは、相手の声を聞くことではない。相手の魂の響きに、静かに耳を澄ませることなのだ。
私たちは見つめ合う。言葉はない。音もない。ただ、世界で最も美しい愛の旋律が、私たちの沈黙の中で、永遠に奏でられ続けている。