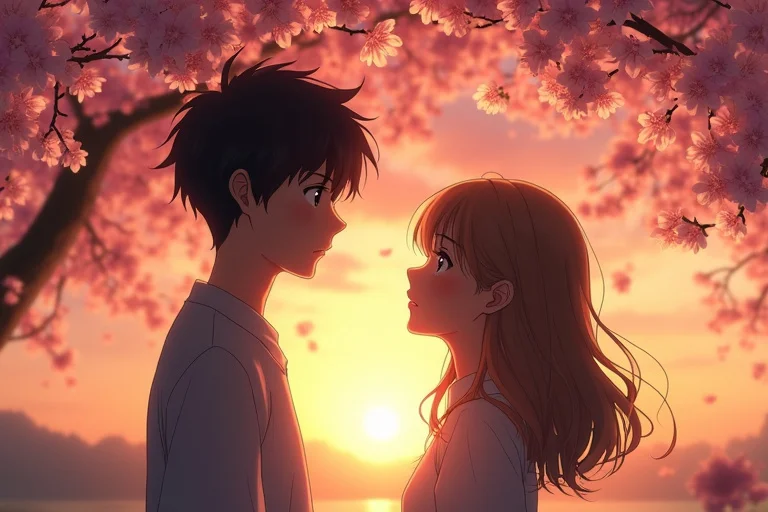第一章 不協和音の住人
僕の日常は、音に支配されている。サウンドデザイナーという職業柄、人より聴覚が鋭いのは自負しているが、僕が聞いているのは、単なる「音」ではない。それは他人の生活が漏れ出す、剥き出しの感情の旋律だ。
キーボードを叩くカチャカチャという音。下の階に住む女子大生のものだろう。締め切りに追われているのか、そのリズムは焦燥感に満ちたスタッカートを刻んでいる。隣の部屋から聞こえる赤ん坊の甲高い泣き声。それは純粋な欲求のクレッシェンドであり、それをあやす若い母親のため息は、疲労と愛情が入り混じった不協和音だ。
僕は、これらの音から逃れるために、都心から少し離れたこの古い鉄筋コンクリートのアパートを選んだ。分厚い壁が、せめてもの救いになると思ったからだ。しかし、僕の耳は壁さえも透過して、他人の日常のメロディーを拾ってしまう。在宅で仕事をする僕にとって、このアパートは巨大な楽器であり、住人たちは僕の意思とは無関係に、それぞれのパートを奏でるオーケストラの団員だった。
中でも、僕の精神を最も深く侵食しているのが、真上の部屋から聞こえてくる音だ。住人は、田中さんという老人だと聞いている。彼が奏でるのは、音楽と呼ぶにはあまりに単調で、不規則なノイズだった。
「コツ……コツ、コツ……」
金属的で、乾いた響き。何か硬いものを、硬い場所に置いているような音。それは毎日、午後三時になると決まって始まり、夕暮れ時まで続く。そのリズムは、まるで壊れたメトロノームのようだ。一定のテンポを保つことなく、唐突に間が空いたり、急に速度を上げたりする。その音からは、何の感情も、何の意図も読み取れない。ただひたすらに無機質で、無感情で、無神経な音の羅列。
僕の耳には、その音が「無為な時間」そのものの旋律として聞こえた。老人が、ただぼんやりと、意味もなく何かをいじくり回している退屈な午後のサウンドトラック。その無意味さが、神経を逆なでする。創造的な仕事をしようとヘッドフォンを装着しても、その低く執拗な響きは、防音の壁を突き破り、僕の鼓膜を、そして思考を直接揺さぶるのだ。
「また始まった……」
今日も午後三時きっかりに、天井からその音が降り注ぎ始めた。僕はキーボードを打つ手を止め、深くため息をついた。このアパートに越してきて半年。僕は、この「不協和音の住人」が奏でる退屈な独奏曲に、そろそろ限界を感じていた。
第二章 消音のレクイエム
田中さんの「コツ、コツ」という音に対する僕の憎悪は、日増しに強まっていった。それはもはや単なる騒音ではなかった。僕の創造性を蝕む悪性腫瘍であり、静謐な日常を脅かす侵略者だった。
ある日、重要なプロジェクトの納品日間近で、僕は極度の集中を強いられていた。クライアントが求めるのは、「夜明けの森の静寂の中に、生命の息吹を感じさせる微細な環境音」。僕は目を閉じ、記憶の中の森を歩く。露に濡れた下草を踏む音、夜明け前の冷たい風が木の葉を揺らす囁き、遠くで響く鳥の最初の歌声……。繊細な音の粒子を一つ一つ紡ぎ合わせ、デジタル空間に新たな森を創造しようとしていた、まさにその時だった。
「コツ……コツ、コツ……」
天井から、例の音が降ってきた。その瞬間、僕の頭の中にあった神秘的な森は、無慈悲な金属音によって跡形もなく伐採された。鳥は飛び去り、風は止み、代わりに無機質なノイズが響き渡る。僕は思わずヘッドフォンをデスクに叩きつけた。
「もう、我慢できない……!」
怒りに任せて椅子から立ち上がり、部屋を飛び出した。階段を駆け上がり、302号室、田中さんの部屋のドアの前に立つ。インターホンに手を伸ばし、しかし、その寸前で指が止まった。何を言うべきか?「あなたの立てる音が不快です。やめてください」。そう言ったとして、老人は理解してくれるだろうか。逆上されたらどうする?そもそも、僕のこの異常な聴覚の方が問題なのではないか?
様々な思考が頭を巡り、僕の怒りは急速に萎んでいった。結局、僕は一度もインターホンを押すことなく、すごすごと自分の部屋に戻った。
だが、このまま引き下がるわけにはいかなかった。直接対決が無理なら、別の方法で戦うしかない。僕は自分の専門知識を武器にすることにした。デスクに戻り、マイクを天井に向け、田中さんの奏でる不快な音をサンプリングし始めた。その音の周波数、波形を徹底的に分析する。そして、その音と寸分違わぬ逆位相の音波を生成するプログラムを組み始めた。ノイズキャンセリングヘッドフォンの原理を、この部屋全体に応用するのだ。
彼の「音」を、僕の「音」で打ち消す。それは僕なりの防衛策であり、彼の無神経さに対する、静かで知的な復讐だった。モニターに表示された不規則な波形を見つめながら、僕は呟いた。
「あなたの退屈な独奏曲に、僕が永遠の休止符を打ってやる」
それは、僕自身のために奏でる「消音のレクイエム」になるはずだった。
第三章 沈黙が語る真実
プログラムが完成に近づいたある日の夜だった。いつものように天井から降り注いでいた「コツ、コツ」という音が、ふと、途切れた。時計を見ると、まだ夕方の五時。いつもなら、まだ続いている時間だ。僕は訝しんだが、訪れた静寂に安堵し、作業を再開した。
しかし、その静寂は長くは続かなかった。遠くから聞こえてきた甲高いサイレンの音が、徐々に大きくなり、僕のアパートの前で止まった。窓からそっと外を窺うと、赤色灯が落ち着きなく明滅し、建物のエントランスを照らしていた。担架が運び込まれ、やがて、一人の人間を乗せて出てくるのが見えた。僕の心臓が、嫌な音を立てて脈打った。
翌日、アパートの掲示板に一枚の紙が張り出されていた。『訃報 302号室 田中様』。僕はその文字を、ただ呆然と見つめることしかできなかった。
数日後、302号室のドアが開いているのが見えた。遺品の整理に、遺族が来ているらしかった。僕が部屋の前を通りかかると、中から初老の女性が出てきて、ばったりと顔を合わせた。僕が下の階の住人だと名乗ると、彼女は田中さんの娘だと自己紹介し、深々と頭を下げた。
「父が、生前は大変ご迷惑をおかけいたしました。特に、あの……音、うるさくありませんでしたか?」
彼女の言葉に、僕はどきりとした。どう答えればいいのか分からず、曖昧に首を振る。すると彼女は、どこか寂しそうに、そして懐かしむように微笑んで、語り始めた。
「父は、時計職人だったんです。何十年も、小さな歯車やネジと向き合う仕事をしてきました。五年前に母が亡くなってからは、めっきり元気がなくなってしまって……。そんな父が、唯一続けていた日課があったんです」
彼女は、部屋の中から小さな木箱を持ってきた。蓋を開けると、中には真鍮色の歯車や、細かなネジ、美しい細工の施された文字盤など、古い柱時計の部品が丁寧に並べられていた。
「母が嫁入り道具に持ってきた、古い柱時計です。父は毎日、決まった時間になると、この時計を分解しては、一つ一つの部品を布で磨き、また組み立てる、ということを繰り返していました。もう動かなくなってしまった時計なんですけどね。父にとっては、母との思い出を確かめる、大切な儀式のようなものだったみたいです。『この音を聞いていると、あいつが隣で編み物をしているような気がするんだ』って、よく言っていました」
「コツ……コツ、コツ……」
その瞬間、僕の頭の中で、あの音が鳴り響いた。それは、老人がピンセットで小さな部品をつまみ、作業台に置く音だったのだ。布で金属を磨く、微かな摩擦音。そして、再び組み立てる時の、精密な作業音。
僕が「無神経な不協和音」と呼び、憎んでいたあの音は、無為な時間の垂れ流しなどではなかった。それは、亡き妻を偲び、共に過ごした時間に想いを馳せる、一人の男の祈りそのものだった。深い愛情と、埋めようのない喪失感から生まれた、静かで、途方もなく長い鎮魂歌(レクイエム)だったのだ。
僕が聴き取っていた「無感情のメロディー」は、僕自身の心の貧しさが作り出した幻聴に過ぎなかった。彼の音に込められた深い悲しみの旋律を、僕の傲慢な耳は、正しく聴き取ることすらできていなかったのだ。
第四章 耳鳴りの交響曲
田中さんの娘が帰った後、僕は自分の部屋に戻り、デスクの前に座り込んだ。モニターには、完成間近の「消音プログラム」が表示されている。田中さんの音を解析した、無機質な波形が並んでいる。僕はその波形を、ただじっと見つめていた。この一つ一つの起伏が、彼の妻への想いの表れだったのだと思うと、胸が締め付けられるようだった。
僕は、そのファイルを、迷うことなくゴミ箱にドラッグした。
それ以来、僕の世界の音は、まるで違う響きを持って聞こえるようになった。隣の部屋から聞こえる赤ん坊の夜泣きは、ただうるさいだけの音ではなく、新しい生命の力強いファンファーレに。下の階の女子大生が叩くキーボードの音は、焦燥のスタッカートではなく、未来の夢に向かう情熱的な練習曲に聞こえた。
僕は、これまで自分がいかに狭い世界に閉じこもっていたかを知った。他人の日常から漏れ聞こえる音を、ノイズとしてしか認識せず、その奥にある物語を聴こうともしなかった。生活音の一つ一つに、その人の人生があり、喜びや悲しみ、希望や絶望が織り込まれている。僕が住むこのアパートは、不協和音を奏でるオーケストラなどではなかった。様々な人生のメロディーが寄り集まった、一つの大きな交響曲だったのだ。
ある晴れた午後、僕は窓を大きく開け放った。車のクラクション、商店街のざわめき、公園で遊ぶ子供たちの笑い声、遠くの踏切が鳴る音。かつては僕を苛んだ街の喧騒が、今は不思議と心地よかった。
それは、完璧に調律された音楽ではない。時折、耳障りな音が混ざり、リズムが乱れることもある。でも、それでいいのだ。不完全で、不揃いで、それでいて確かに生きている。それが、「日常」という名の音楽なのだ。
僕はそっと目を閉じた。田中さんの部屋は、今はもう静かだ。けれど、僕の耳には、あの「コツ、コツ」という音が、確かに聞こえている気がした。それはもう、僕を苛む不快なノイズではない。愛する人を想う、優しく、そして切ない旋律となって、僕の心の中で静かに響き続けている。
僕はもう、音を消そうとは思わない。この世界に満ちる、ありとあらゆる音と共に生きていこう。耳を澄ませば、そこにはいつも、誰かの人生の物語が流れているのだから。