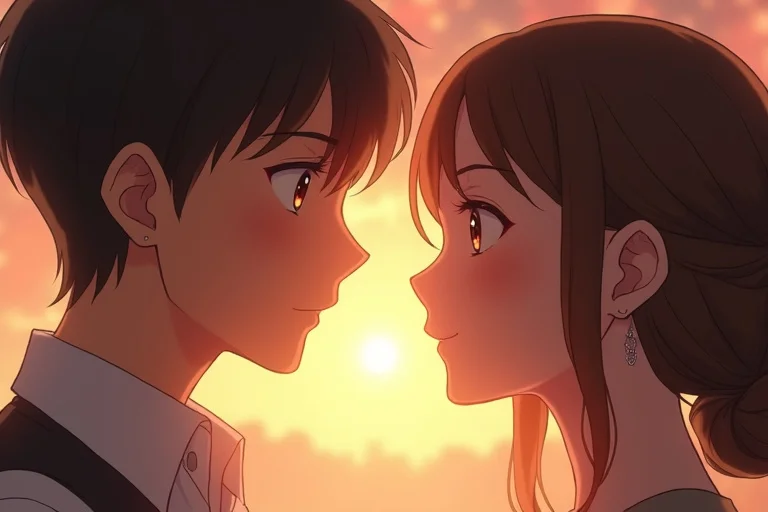第一章 硝子細工の指先
「お願いします」
少女がカウンターに投げ出した両手は、冬の枯れ枝のように震えていた。
爪の先まで白く血の気が引き、焦げ付いたカラメルのような、甘く重苦しい匂いが鼻腔を刺す。
叶わぬ恋に身を焦がす人間特有の、胸焼けするような体臭だ。
私は何も聞かず、彼女の右手首を掴む。
陶器のように冷たく、硬い。
薄い皮膚の下で脈打つ動脈に、私の指先を滑り込ませた。
ドクン。
心臓の拍動が、指の腹を通して直接脳髄に響く。
視界が歪んだ。
店内の薄暗い照明が、彼女の胸元から溢れ出した光に飲み込まれる。
鮮烈な朱色。
熟れすぎた柘榴のような赤が、彼女の胸から奔流となって迸る。
その光は一本の細い糸へと収束し、店の窓を抜け、雨に濡れた石畳の向こう、北西の路地裏へと突き刺さっていた。
私は、自分の左手首に巻かれたリボンに視線を落とす。
無色透明だったその布地が、今は彼女の激情を吸い上げ、まばゆい朱に染まっている。
「……北西の古書店ね」
私はリボンが示す方角を顎でしゃくった。
「そこでページを捲る指先と、あなたの糸は結ばれている」
少女の喉がひくりと動く。
強張っていた肩の力が抜け、頬に瞬時に赤みが差した。
彼女は言葉にならない呼吸を漏らし、弾かれたように店を飛び出していく。
錆びついたドアベルが、カランと乾いた音を残して揺れた。
静寂が戻る。
私は深く息を吐き出し、カウンターに突っ伏した。
左手首を見る。
先ほどまで朱色に燃えていたリボンは、すでに氷のような透明に戻っていた。
「……空っぽ」
胸元を強く握る。
肋骨の奥を探っても、そこには色も熱もない。
他人の運命を覗き見る代償のように、私自身の色素は抜け落ちている。
鏡に映る自分は、背景の棚が透けて見えそうなほど希薄だ。
世界から切り離された、ただの観測装置。
その時。
ドアが開く音もなく、一陣の湿った風が頬を撫でた。
顔を上げる。
入り口に、一人の男が立っていた。
雨傘も差さずに濡れそぼり、黒い髪から滴る水が、床に染みを作っている。
彼は何も言わない。
ただ、濡れた野良犬のような瞳で、私を――いや、私の手首の透明なリボンを、射抜くように見つめていた。
第二章 揺らぐ色彩
男からは、古い雨戸のような匂いがした。
あるいは、乾きかけた油絵具の、ツンとする揮発性の香り。
彼は迷うことなくカウンターへ歩み寄ると、無造作に右手を差し出した。
掌は絵筆のタコで硬く、爪の間にはプルシアンブルーの染みがこびりついている。
「……視てくれ」
声は低く、喉の奥で砂利が擦れるような響きがあった。
私は躊躇った。
彼の手からは、得体の知れない熱気が立ち上っている。
それでも、仕事だからと自分に言い聞かせ、そのゴツゴツとした指に触れる。
瞬間。
指先が爆ぜたかと思った。
「っ……!」
私は思わず手を引っ込めそうになるのを、必死に堪える。
色が、ない。
いや、違う。
極彩色の洪水だ。
燃え盛る森のような緑、深海に沈む鉄のような青、太陽を直視した瞬間の白。
無数の色が混ざり合い、渦を巻き、泥のような黒濁色になったかと思えば、次の瞬間には虹色のプリズムとなって炸裂する。
糸が見えない。
彼の胸から伸びる光は、まるで陽炎のように揺らめき、千切れ、どこへも繋がろうとしない。
天井へ、床へ、あるいは虚空へと霧散していく。
「あんたの顔、真っ青だ」
男が私の顔を覗き込む。
その瞳の奥で、色が万華鏡のように明滅している。
「……あなたの色は、読めない」
私は喘ぐように告げた。
額に冷や汗が滲む。
「糸が、定まらないの。あなたは誰をも愛し、誰にも執着していない。まるで形を持たない雲みたいに」
「雲か」
彼は面白がる風でもなく、ただ自分の掌を見つめた。
「俺はレンだ。絵を描いている」
唐突な自己紹介。
彼はポケットからクシャクシャになった紙幣を取り出し、カウンターに置いた。
「運命が決まっていないなら、何色で塗ってもいいってことだな」
「……そんな単純な話じゃないわ。糸がない人間は、孤独なのよ」
「孤独?」
レンは、私の手首を指差した。
激しく明滅を繰り返していたリボンは、彼の手が離れた途端、また死んだような透明に戻っている。
「あんたのリボンも、誰とも繋がっていない。あんたも孤独なのか?」
心臓を鷲掴みにされたような痛みが走った。
私はリボンを隠すように、袖口を引く。
「私は視る側だから。特別なの」
「ふうん」
レンは口の端をわずかに歪め、笑ったようにも、呆れたようにも見える表情を作った。
「その透明は、何色にでもなれる『白』に見えるけどな」
彼は背を向け、手を振ることもなく出て行った。
残されたのは、床の上の濡れた足跡と、鼻の奥に残る油絵具の匂いだけ。
私の視界が、ぐらりと揺らいだ。
彼の足跡の場所だけ、床の木目が妙に鮮やかに見えた。
第三章 モノクロームの雨
それから、レンは雨の日ごとに現れるようになった。
彼は運命を尋ねない。
ただカウンターの端に座り、小さなスケッチブックを広げ、黙々と鉛筆を走らせるだけだ。
ある時は、私の淹れた珈琲の湯気を。
ある時は、窓枠に止まった蜘蛛を。
またある時は、カウンターで頬杖をつく私を。
「動かないで」
鉛筆が紙を擦る、サァ、サァ、という音だけが店内に満ちる。
その音は不思議と心地よく、私の空っぽな空洞を埋めていくようだった。
彼が描いた私の横顔は、本物よりもずっと生き生きとしていた。
瞳には光が宿り、唇には血が通っている。
「俺には、あんたがこう見えている」
レンは黒い指先で、絵の中の私の頬を撫でた。
「綺麗だ」
その一言が、私の内側に熱い雫となって落ちた。
透明だった心に、ポツリと色が滲む。
それが「恋」だと自覚した瞬間、恐怖が鎌首をもたげた。
『運命の心糸』を持たぬ者が、特定の誰かを愛そうとすれば、世界から色彩を奪われる。
古い言い伝えが脳裏をよぎる。
その夜、私は自室の鏡の前で凍りついた。
赤い口紅を塗ろうとして、手が止まる。
紅の色が見えない。
唇に塗られたそれは、コールタールのような黒い粘液に見えた。
慌てて振り返る。
窓の外の街灯、本棚の背表紙、クローゼットの服。
すべての彩度が落ち、薄汚れた灰色のフィルターがかかっている。
「……嘘」
目を擦る。
まばたきをするたびに、色が剥がれ落ちていく。
鮮やかだった世界が、古い白黒映画のように色褪せていく。
レンを愛してはいけない。
私の運命は彼じゃない。
運命に背けば、私は光を失う。
「来ないで……」
翌日、ドアベルが鳴った瞬間、私はカウンターの下に隠れた。
レンの足音が近づき、やがて遠ざかる。
それを三日繰り返した。
四日目の夕暮れ。
世界は完全なモノクロームになっていた。
灰色の空、黒い海、白い街並み。
色のない世界は、音さえも吸い込んでしまったように静かだ。
私は耐えきれず、店を飛び出した。
色がなくてもいい。
光を失ってもいい。
あの、油絵具の匂いだけは失いたくない。
港の見える丘。
彼がいつも座っているベンチへ、私は灰色の石段を駆け上がった。
第四章 自分で紡ぐ色
彼はそこにいた。
灰色の空の下、灰色の海に向かって、キャンバスを立てている。
「レン!」
喉が張り裂けそうなほど叫んだ。
彼が振り返る。
その顔だけが、この無彩色の世界で唯一、輪郭を持って迫ってくる。
私は彼の胸に飛び込んだ。
勢いでキャンバスが倒れる。
でも、構わなかった。
「アヤメ? どうした、そんなに息を切らして」
彼の腕が私を受け止める。
その体温。
確かな重み。
「色が……見えないの」
私は彼のシャツを握りしめ、震えながら訴えた。
「あなたの運命は私じゃない。だから、あなたを好きになったら、罰として色が奪われた。世界が全部、灰色になっちゃったの」
涙が溢れて止まらない。
その涙さえも、きっと透明な水ではなく、黒いインクのように見えるのだろう。
レンは何も言わず、私の背中に腕を回した。
そして、強く、骨がきしむほど強く抱きしめた。
「目を開けてみろ」
耳元で囁かれる声。
「世界の色を決めるのは、運命なんかじゃない」
彼は私の手首を取り、目の高さまで持ち上げた。
そこにあるはずのリボンは、私の目には鼠色の布切れにしか見えない。
「俺を見ろ、アヤメ」
レンの手が、私の頬を包む。
親指が涙を拭う。
その指先には、いつものように絵具がついていた。
「俺があんたを塗ってやる。何度でも、何色にでも」
その言葉は、呪いのように甘く、祈りのように切実だった。
「……私も、塗りたい」
心の奥底から、言葉が絞り出された。
「運命が決めた色じゃなくて、私が選んだ色で、あなたを愛したい」
運命なんていらない。
私は、私の意志で、この人を愛する。
その覚悟が決まった瞬間。
私の心臓が、鐘のように大きく鳴った。
ドクン!
体内の血液が沸騰し、指先へ、眼球へ、魂の隅々へと駆け巡る。
閉ざされていた水門が開くように、視界が弾けた。
最終章 虹色の運命
世界が発光した。
灰色の空が割れ、そこから夕陽の茜色が雪崩れ込んでくる。
海はサファイアのような群青を取り戻し、街路樹の緑が目に痛いほど鮮やかに蘇る。
そして、私の手首。
カッ、と目も眩む輝きが迸っていた。
赤ではない。青でもない。
無限の色が絡み合い、融合し、螺旋を描いて伸びていく。
それは、一本の太い光の束となって、レンの心臓へと突き刺さっていた。
「……なんだ、これは」
レンが目を見開く。
光は彼の胸からも溢れ出し、私の光と絡み合って、見たこともない複雑な色彩を織りなしている。
オーロラのような、あるいは砕け散ったステンドグラスのような。
既存の運命の枠には収まりきらない、乱暴で、それでいて繊細な色。
「虹だ……」
彼が呟き、その光の束にそっと触れる。
指先が触れた場所から、さらに新しい色が生まれ、火花のように散った。
「俺たちが、作った色か」
「ええ。誰のものでもない、私たちだけの色」
私はレンの瞳を見つめ返した。
そこには、虹色の光に照らされた、泣き笑いの私が映っている。
もう、透明人間じゃない。
私はここにいて、鮮烈な色彩を放ちながら、彼を愛している。
レンが顔を近づけてくる。
唇が触れる寸前、世界中の絵具をぶちまけたような色彩が、私たちの視界を埋め尽くした。
この先、色が褪せる日が来るかもしれない。
黒く塗りつぶされる夜もあるかもしれない。
けれど、もう怖くはない。
白紙のキャンバスがある限り、私たちは何度でも、自分たちの手で色を重ねていけるのだから。