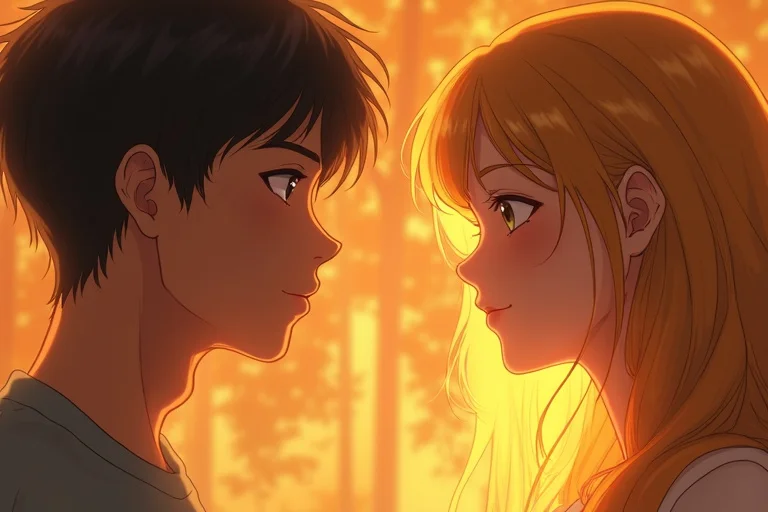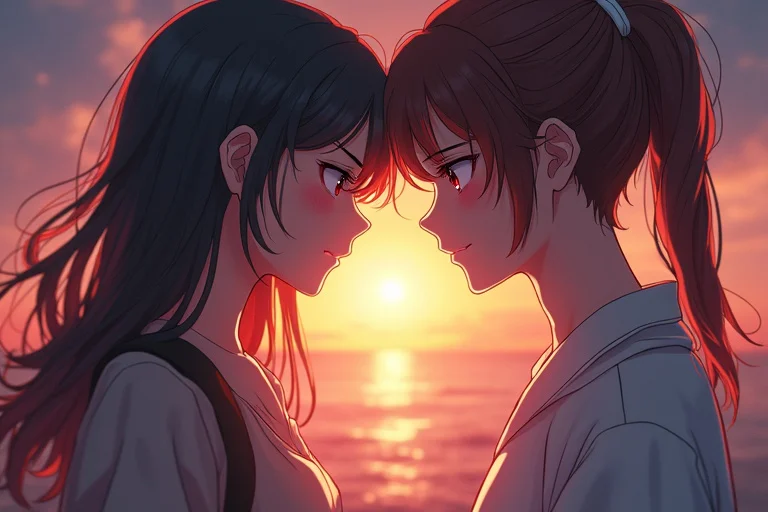目を閉じても、僕の世界には闇しか広がらない。
母の顔も、昨日食べた林檎の赤も、まぶたの裏には浮かばない。
けれど、鼻腔をくすぐる「雨の匂い」だけが、鮮烈に彼女の輪郭を描き出していた。
第一章 欠落したパズル
アスファルトが濡れた匂いがする。
天気予報は晴れだったが、僕の鼻は三十分後の通り雨を予知していた。ペトリコール。土と埃と湿気が混ざり合う、あの独特の匂い。僕は人よりも少しだけ、鼻が利く。
「湊(みなと)くん、また眉間に皺が寄ってる」
ふいに声をかけられ、ビクリと肩が跳ねた。隣のデスクから、調香師の紬(つむぎ)が身を乗り出している。白衣から漂うのは、ベルガモットと微かなサンダルウッド。彼女の「仕事の匂い」だ。
「……雨が降るんです。傘、持ってないなと思って」
「えー、こんなに青空なのに?」
彼女は窓の外を指さして笑う。その笑顔を、僕は「情報」として認識する。口角が上がり、目が細められる。それは笑顔という記号だ。僕の脳内には、映像としての記憶が残らない。「アファンタジア」と呼ばれるこの特性は、僕から視覚的な思い出を奪い続けていた。
だから僕は、匂いで世界を記憶する。
「それより、この試作品。嗅いでみてよ」
紬が小瓶を差し出す。彼女は天才的な調香師だ。だが、最近どこか焦っているように見える。
ムエット(試香紙)を鼻に近づける。トップノートは爽やかなレモン。だが、ミドルに違和感がある。
「……少し、バランスが崩れてます。ジャスミンが強すぎて、ラストのムスクと喧嘩してる」
「やっぱり……?」
紬の声が沈む。彼女はムエットを握りしめ、唇を噛んだ。
「最近ね、鼻が詰まり気味でさ。湊くんの鼻が頼りなんだ」
嘘だ。
彼女の指先が震えているのを、僕は見逃さなかった。鼻詰まりなんて軽いものじゃない。もっと深刻な何かが、彼女の才能を蝕んでいる。
「僕で良ければ、いつでも」
そう答えるのが精一杯だった。僕は彼女の才能に惹かれていたし、何より、彼女が纏う「陽だまりのような匂い」に、どうしようもなく安らぎを感じていたからだ。
その夜、予報通りに雨が降った。
一つの傘に入った僕たちの距離は近く、雨の匂いよりも、彼女の髪の甘い香りが、僕の記憶野を激しく叩いた。
「ねえ、湊くん。もし私が匂いを失くしたら、どうなると思う?」
雨音に紛れそうなほど小さな声。
僕は足をとめた。
「僕が、君の鼻になります」
迷わずに言った。論理的ではない。けれど、それ以外の答えはなかった。
紬は驚いたように僕を見上げ、それから泣きそうな顔で笑った。
「……プロポーズみたい」
その言葉に、心臓が早鐘を打つ。赤くなった僕の顔を見て、彼女は楽しそうに笑い声をあげた。
その瞬間、僕の無機質な暗闇の世界に、一滴の鮮やかな色彩が落ちた気がした。
第二章 透明な肖像画
病魔は、残酷なほど静かに進行した。
嗅覚障害。調香師にとっての死刑宣告。
紬は病院の無機質なベッドの上で、窓の外を眺めていた。部屋には消毒液と、萎れかけた百合の匂いが充満している。
「ねえ、湊くん。今の私、どんな顔してる?」
瘦せ細った彼女が問う。
僕は言葉に詰まる。視覚的イメージが浮かばない僕にとって、彼女の顔を「思い出す」ことはできない。目の前にいる彼女を「観察」することしかできないのだ。
「……綺麗です。窓から入る光が、髪に透けて」
「ふふ、嘘つき。やつれてるでしょ」
彼女は力なく笑う。嗅覚を失った彼女は、それでも調香を諦めなかった。音や色から香りをイメージする「共感覚」に近い才能を持つ彼女は、僕の鼻を頼りに、最後の香水を作り上げようとしていた。
タイトルは『イマージュ』。
「湊くんには映像が見えない。私にはもう、匂いが分からない。だから二人で一つ」
彼女の指示に従って、僕は香料を調合する。
「もう少し青く。深い海の底みたいな静寂」
「では、マリンノートにベチバーを足します」
「次は、夕暮れの切なさ。オレンジ色じゃなくて、茜色」
「……キンモクセイを微量、どうですか」
作業は深夜に及ぶこともあった。彼女は記憶の中の色彩を語り、僕はそれを匂いという数式に変換する。それは、魂の交換のような作業だった。
ある日、調合の最中に彼女が呟いた。
「完成したら、湊くんに一番にあげる」
「僕に? 女性用でしょう?」
「ううん。これはね、記憶の鍵なの」
彼女は僕の手を握った。その手は冷たく、骨ばっている。
「湊くんの暗闇の中に、私を残したいの。写真を見ても思い出せない湊くんが、この香りを嗅いだ瞬間に、私の笑顔も、泣き顔も、全部鮮明に見えるような……そんな魔法」
胸が締め付けられた。
彼女は知っていたのだ。僕が、彼女の顔を思い出せなくて苦しんでいることを。
「約束する。必ず、完成させる」
「うん。……ねえ、湊くん」
「はい」
「大好きだよ」
その言葉は、どんな高級な香料よりも甘く、そして揮発性が高かった。
僕は彼女を抱きしめたかったが、点滴の管がそれを阻んだ。代わりに、彼女の手のひらに額を押し付けた。
石鹸と、消毒液と、その奥にある彼女自身の匂い。それを脳の皺に刻み込むように、深く息を吸い込んだ。
第三章 色彩のなき世界で
葬儀の日は、皮肉なほどの快晴だった。
線香の煙たい匂いが、僕の鼻を麻痺させる。
祭壇の写真は笑っているらしい。参列者が「いい笑顔だ」と囁くのが聞こえる。けれど、僕にはそれが分からない。ただのインクの染み。輪郭線と陰影の集合体。
目を閉じると、完全な闇。
彼女の声は聞こえる。温もりも覚えている。けれど、姿だけがない。
焦燥感が僕を襲う。このまま時間が経てば、彼女の存在は僕の中で概念になってしまう。「かつて愛した人」という、ラベルの貼られた空っぽの箱になってしまう。
家に帰り、机の上に置かれた小瓶を見つめた。
『イマージュ』。
彼女が遺した処方箋を元に、僕が最後の一滴を加えて完成させた香水。
震える手で蓋を開ける。
室内に解き放たれたのは、暴力的なまでの「記憶」だった。
トップノートは、雨上がりのアスファルト。出会った日の匂いだ。
ミドルノートは、古い図書館と紅茶。二人でよく行ったカフェの匂い。
そして、ラストノート。
それは、日向の匂いだった。
彼女の首筋からいつも漂っていた、あの温かく、柔らかい匂い。
「っ……あ……」
鼻腔から脳へ、電気信号が奔流となって駆け巡る。
その瞬間、僕の閉じた瞼の裏で、世界が弾けた。
暗闇に、色が走る。
光が溢れる。
見えた。
振り返り、悪戯っぽく笑う紬。
雨の中で、「プロポーズみたい」と照れる紬。
病室で、僕の手を握りしめる紬。
写真のような静止画ではない。動画のように、鮮やかに、彼女が僕の脳内で息をしている。髪が揺れ、瞬きをし、唇が動く。
『大好きだよ、湊くん』
声と映像がリンクする。
涙が溢れて止まらなかった。アファンタジアの僕には決して見えなかった「心象風景」が、彼女の香りを媒体にして、鮮烈に映し出されている。
これは魔法だ。
彼女が命を削って遺した、僕のためだけの魔法。
「……見えるよ、紬」
誰もいない部屋で、僕は虚空に向かって呟く。
「君は、こんなに綺麗な顔をして笑っていたんだね」
香りはやがて薄れていくかもしれない。けれど、一度灯った色彩は、もう二度と消えない。
僕は小瓶を胸に抱き、瞼の裏の彼女に、何度でも「ありがとう」と繰り返した。
窓の外では、また新しい雨が降り始めていた。
その匂いは、もう寂しくはなかった。