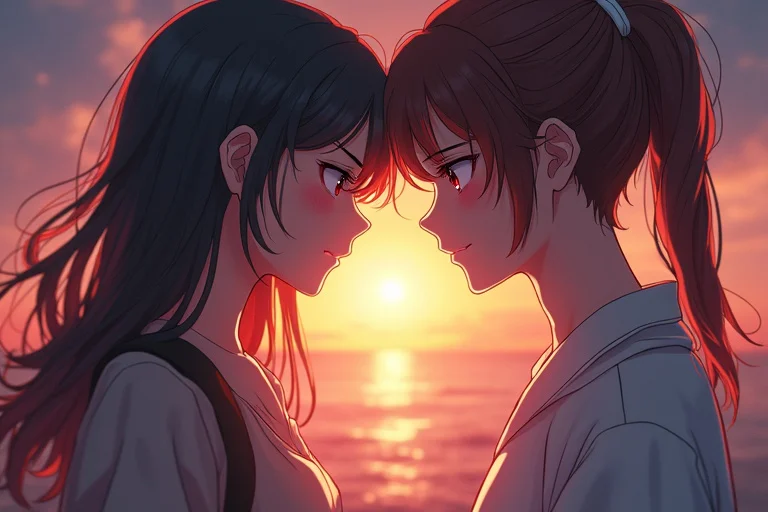第一章 小さな星屑
僕たちの世界では、愛の言葉は形を持つ。
夜空からこぼれた星屑のように、あるいは磨き上げられた宝石のように、それは人の想いの深さに応じて輝きと重さを変え、手のひらの上に結晶として現れるのだ。「おはよう」という朝の挨拶に添えられた小さな好意は露の雫のような透明な粒に、「ありがとう」という感謝は淡い光を放つ小さな角砂糖ほどの結晶になる。そして、「愛してる」という言葉は――それは、他のどんな感情とも比較にならない、特別な重さと輝きを持つはずだった。
僕、相葉海斗の部屋の窓辺には、月島美咲からもらった言葉の結晶を収めたガラスの小瓶が置いてある。付き合い始めた頃、彼女がくれた「好きです」の結晶は、淡い桜色に輝き、指先に心地よい重みを感じさせた。初めて「愛してる」と言ってくれた夜に生まれた結晶は、今でも小瓶の底でひときわ強く、月光を吸い込んで青白い光を放っている。それはまるで、小さな銀河そのものだった。
だが、最近の彼女の言葉は、どうだろう。
一週間前、僕の誕生日。彼女は微笑んで「海斗、愛してるわ」と言った。その言葉から生まれた結晶を、僕は今、指先でつまんでいる。それはあまりに小さく、そして驚くほど軽かった。かつての銀河はどこへやら、今はただの頼りない星屑だ。光も弱々しく、まるで風に吹かれれば消えてしまいそうな儚さだった。
「どうしたんだろう……」
僕は無意識に、自分が彼女に贈った結晶を収めた箱に目をやった。マホガニー製のその箱はずっしりと重い。中には僕が美咲に捧げた、ありったけの言葉たちが詰まっている。「君は僕の太陽だ」「君なしの世界なんて考えられない」。そういった言葉から生まれた結晶は、どれもが大粒で、熱を帯びたように輝いていた。僕は、愛とはその重さと輝きで証明されるものだと信じて疑わなかった。重ければ重いほど、輝きが強ければ強いほど、想いは真実なのだと。
それなのに、彼女から返ってくる結晶は日増しに小さく、軽くなっていく。僕の愛は、ちゃんと届いているのだろうか。それとも、彼女の中で僕という存在が、少しずつ軽くなっているのだろうか。
窓の外では、夜の帳が下り始めていた。街の灯りが、まるで誰かが誰かに贈った言葉の結晶のように点滅している。僕は手のひらの上の小さな星屑をじっと見つめた。そのあまりの軽さが、僕の心を鉛のように重く沈ませていくのを感じていた。もっと、もっと重い言葉を。もっと輝く愛を彼女に捧げなければ。僕たちの関係が、この小さな結晶のように脆く砕けてしまう前に。
第二章 重さという名の証明
焦燥感に駆られた僕は、それからというもの、まるで言葉の鉱脈を掘り当てる探鉱者のように、美咲への愛を表現する言葉を探し続けた。書店の恋愛小説コーナーに立ち尽くし、詩集のページを繰り、果ては古典文学にまで手を伸ばした。すべては、これまで誰も生み出したことのないような、最高に重く、眩い輝きを放つ結晶を彼女に贈るためだった。
「美咲、君の瞳は夜明けの海の色をしている。僕の心を静かに満たしていくんだ」
そう言って渡した結晶は、深い藍色を帯びたサファイアのように美しかった。美咲は「綺麗ね」と微笑んで受け取ったが、その瞳はどこか遠くを見ているようだった。
「君の笑顔ひとつで、僕の世界は色を取り戻す。君は、僕というモノクロのフィルムに差し込んだ、唯一の光なんだ」
次のデートで僕が捧げた言葉は、プリズムのように光を乱反射させる、大粒のダイヤモンドのような結晶になった。僕は得意げにそれを彼女の手に乗せた。だが、彼女は一瞬、その重さに「あっ」と声を漏らし、慌てて両手で支えるようにして受け取った。
「ありがとう、海斗。いつも、すごいね」
彼女はそう言ってくれた。しかし、その声には、僕が期待していたような歓喜の色はなかった。むしろ、何かを堪えるような、微かな震えが混じっていることに、僕は気づかなかった。いや、気づかないふりをしていたのかもしれない。僕の愛がこれほど重く、輝いているのだから、彼女が喜ばないはずがない。きっと、感動で言葉を失っているだけなのだと。
彼女のアパートを訪れるたび、僕は奇妙な光景を目にするようになった。リビングの飾り棚には、僕が贈った結晶がずらりと並べられている。それは壮観なコレクションだったが、よく見ると、棚板が結晶の重みで僅かに、しかし確実に歪んでいた。ミシリ、と時折軋む音が聞こえるたび、美咲はびくりと肩を震わせるのだった。
僕たちは、いつからかすれ違っていた。僕は結晶を生み出すことに夢中になり、彼女はその重さに静かに耐えていた。会話はいつしか、次にどんな言葉を贈るか、という僕の一方的な独白になりがちだった。僕は彼女の顔色を窺う余裕もなく、ただひたすらに「愛の証明」を積み上げていく。その一つ一つが、彼女の心を静かに蝕んでいるとは知らずに。ある週末、僕は生涯で最も重い結晶を作ろうと決意した。僕たちの未来を永遠に約束する、究極の言葉を携えて。
第三章 無重力のさよなら
その日、僕は最高傑作を手に、美咲のアパートのドアを叩いた。「僕の人生のすべてを懸けて、君を永遠に愛し続ける」。そう心の中で唱えながら生み出した結晶は、赤ん坊の頭ほどの大きさがあり、ずっしりとした重みで僕の腕を痺れさせた。内側から燃えるような、深紅の輝きを放っている。これで僕の想いは完全に伝わるはずだ。僕たちの愛は、盤石なものになる。
「美咲、入るよ」
ドアを開けると、彼女は部屋の中央に、荷造りを終えた段ボール箱に囲まれて立っていた。そして、僕の顔を見るなり、静かに言った。
「別れてください、海斗」
時間が止まった。僕の腕の中の結晶が、急にただの重い石塊に感じられた。何を言っているのか、理解が追いつかない。
「……どうして?僕の愛が、まだ足りなかったのか?だから、こんなにすごい結晶を持ってきたんだ。これを見れば――」
僕が結晶を差し出そうとすると、彼女は悲しげに首を横に振った。その瞳には涙が浮かんでいる。
「ううん、違うの。足りなかったんじゃない。あなたの愛は……重すぎたのよ」
彼女はそう言って、リビングの飾り棚を指差した。僕が目を向けると、棚は真ん中から無惨にひび割れ、今にも崩れ落ちそうになっていた。並べられた結晶たちが、まるで墓石のように重々しく鎮座している。
「あなたの言葉を受け取るたび、私はその重さに押しつぶされそうだった。あなたのくれる大きな結晶は、すごく綺麗だったわ。でも、それと同じくらい、私には重かった。こんなにすごい愛をもらっているんだから、私も同じくらい返さなきゃって。でも、私にはできなかった。あなたの期待に応えるのが、どんどん苦しくなっていったの」
衝撃だった。僕が愛の証だと信じて積み上げてきたものが、彼女にとっては苦痛の源だったというのか。僕の価値観が、足元からガラガラと崩れ落ちていく。
「じゃあ……君がくれていた、あの小さな結晶は……」
僕がかすれた声で尋ねると、彼女はポケットから小さな、本当に小さな光の粒を取り出した。それは、僕が最初に感じた不安の源。
「ごめんなさい。これは、あなたに負担をかけたくないっていう、私の精一杯の思いやりだったの。愛がなかったわけじゃない。むしろ逆よ。あなたの重い言葉であなたが疲れてしまわないように、あなたの心を少しでも軽くしたくて……。私にとって、軽いことこそが、愛情表現だったの」
その小さな結晶は、涙に濡れた彼女の瞳のように、儚く、しかし澄み切った光を放っていた。僕は、その光の本当の意味を、今、初めて理解した。愛は、重さじゃない。輝きの強さでもない。相手を思いやる心、そのものなのだと。
腕の中の深紅の結晶が、急に醜悪な塊に見えた。それは愛の証などではなく、僕の独りよがりなエゴの塊だった。指から力が抜け、結晶は床に落ちた。ゴトリ、と鈍い音を立てて転がり、部屋の隅で光を失った。僕たちの関係が終わった音だった。
第四章 言葉が消えた朝
美咲が去った後、僕の世界から言葉が消えた。正確には、僕が言葉を発することをやめたのだ。何かを口にしようとしても、喉の奥で鉛の塊が詰まったようになり、声にならない。愛の言葉が凶器になりうることを知ってしまった僕は、言葉というものそのものを恐れるようになっていた。
僕の周りでは、もう結晶が生まれることはなかった。それは奇妙な解放感をもたらした。これまで、いかに自分が「言葉」という形に、結晶という「重さ」に依存して生きてきたかを痛感させられた。
言葉を失った僕は、ただ世界を眺めるようになった。すると、不思議なことに、今まで見過ごしてきた様々な「愛の形」が見えてきた。公園のベンチで寄り添う老夫婦の、皺の刻まれた手の温もり。子供を叱りながらも、その視線に深い愛情を宿す母親。名前も知らない誰かが、雨の日のバス停にそっと置いていった置き傘の優しさ。
それらはどれも、結晶にはならない。重さも、輝きもない。しかし、そこには確かに、温かく、揺るぎない愛が存在していた。愛とは、声高に叫ぶものでも、重さで証明するものでもなく、日常の何気ない風景の中に、空気のように、光のように、静かに溶け込んでいるものなのだ。僕は、重さのない、ただそこにあるだけの「存在の肯定」に、少しずつ心を癒されていった。
数ヶ月が過ぎた、ある晴れた日の午後だった。僕は馴染みのカフェで、窓の外をぼんやりと眺めていた。その時、通りの向こう側を歩く、見慣れた後ろ姿に心臓が跳ねた。美咲だった。
気づけば、僕は店の外に飛び出していた。彼女の名前を呼びたい衝動に駆られたが、声は出ない。僕はただ、無言で彼女の元へ駆け寄った。驚いて振り返る美咲。彼女の瞳が、僕を捉えて大きく見開かれる。
何を言えばいい?いや、何も言うべきではない。僕はただ、立ち止まった。そして、心の底から湧き上がる、ありのままの感情を乗せて、彼女に微笑みかけた。それは、かつて僕が浮かべていたような、何かを証明するための気負った笑顔ではなかった。何の計算も、下心もない。ただ、君がここにいてくれて嬉しい、とでも言うような、軽やかで、穏やかな微笑みだった。
美咲は一瞬戸惑ったようだったが、僕の表情の中に、かつて彼女が心の底で求めていたであろう何かを見出したのかもしれない。彼女の唇の端が、ゆっくりと持ち上がり、やがて僕と同じように、柔らかく微笑み返した。
僕たちの間に、言葉はなかった。もちろん、結晶が生まれることもない。けれど、その沈黙と交わされた微笑みの中に、僕たちは確かに、重さでは測れない、新しい関係の始まりを予感していた。空はどこまでも青く澄み渡り、吹き抜ける風は、僕の心をどこまでも軽くしていった。