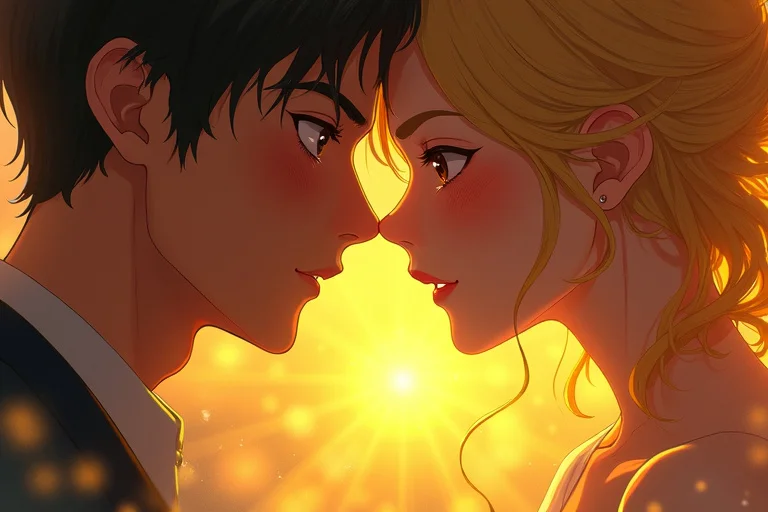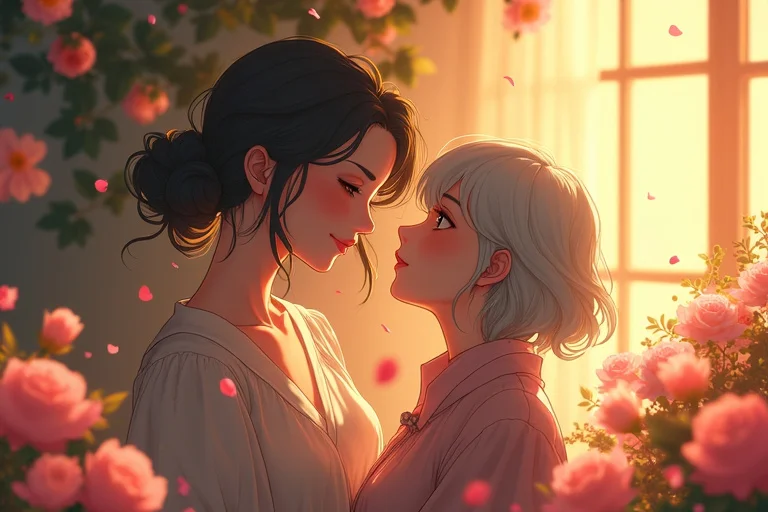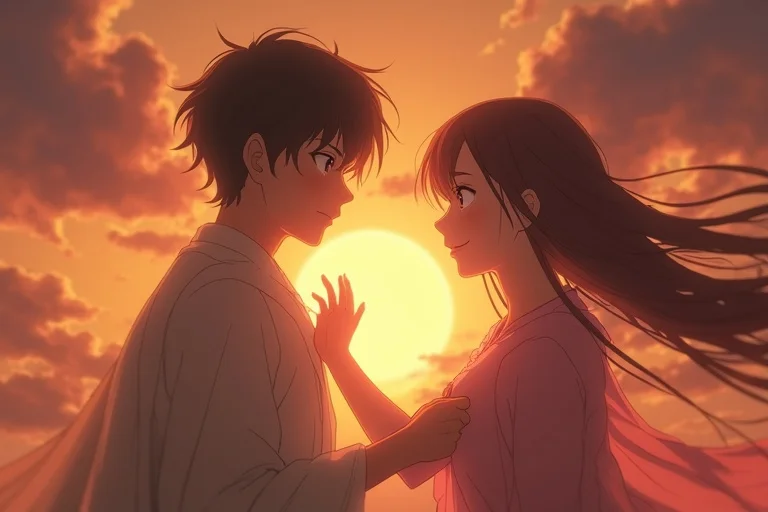第一章 色褪せたページの栞
神保町の裏路地にひっそりと佇む『蒼井書房』の扉についた真鍮のベルが、ちりん、と涼やかな音を立てた。埃と古い紙の匂いが混じり合った独特の空気に慣れきった僕、蒼井湊(あおい みなと)は、カウンターの奥で文庫本の値付けをしていた手を止め、顔を上げた。
そこに立っていたのは、見慣れない女性だった。淡いレモンイエローのワンピースが、薄暗い店内に初夏の日差しを運び込んできたかのように眩しい。
「いらっしゃいませ」
我ながら覇気のない声だと思う。祖父からこの店を継いで三年。僕の世界は、この背の高い書架に囲まれた空間で完結していた。過去の苦い失恋が、僕の心を臆病なカタツムリのように殻の内側へと押し込めて久しい。
彼女は店内をゆっくりと見回すと、僕のほうへ歩み寄ってきた。首から下げた年代物のフィルムカメラが、歩くたびに小さく揺れている。
「素敵な場所ですね。時間が止まっているみたい」
「……どうも」
「あの、店主さん。緊張すると、左の眉が少しだけ上がるんですね」
唐突な言葉に、僕は思わず左の眉に手をやった。確かに、少し痙攣しているのを感じる。初対面の相手に指摘されるような癖ではないはずだ。
「昔、よくお母さんに叱られませんでした?『湊、ポーカーフェイスを覚えなさい』って」
「え……?」
心臓が嫌な音を立てて跳ねた。なぜ、彼女が僕の名前を? 母が僕をそう叱っていたことまで? 僕は彼女の顔を凝視したが、記憶のどの引き出しを探っても、見覚えはなかった。
戸惑う僕を意にも介さず、彼女はふふ、と悪戯っぽく笑うと、「柚木陽菜(ゆずき ひな)です」と名乗った。
「なんだか、懐かしい歌が聞こえてきそう」
陽菜さんはそう言って、書架の隙間から差し込む光の筋を指でなぞった。そして、信じられないことに、僕が幼い頃に祖父にだけこっそり歌って聞かせていた、自作のめちゃくちゃな歌のメロディを、正確に口ずさんだのだ。
「……どうして、それを」
声が震えた。それは僕と、もうこの世にいない祖父だけの秘密のはずだった。
陽菜さんは僕の動揺を楽しんでいるかのように、にっこりと微笑むだけだった。
「あなたを、ずっと探していたんです」
その言葉は、僕の静かで退屈な日常に投げ込まれた、波紋を広げる一石となった。彼女は一体何者なのか。僕の平穏な聖域は、この日を境に、謎と期待の入り混じった、心地よい緊張感に満たされていくことになった。
第二章 フィルムのないカメラ
陽菜さんは、それから毎日のように店に顔を出すようになった。特定のジャンルの本を探すわけでもなく、ただ僕の向かいにある客用の古いソファに腰掛け、紅茶を飲みながら僕と他愛ない話をするのが目的のようだった。
彼女は僕の知らない僕を、たくさん知っていた。高校時代に夢中になったマイナーなバンドのこと。大学の卒業制作で、教授にこっぴどく叱られた絵のテーマ。そのどれもが、僕の記憶の奥底にしまい込んで、自分ですら忘れかけていたことばかりだった。
「どうしてそんなことまで知ってるんですか」と尋ねる僕に、彼女はいつも「さあ、風の噂かな」とはぐらかすばかり。そのミステリアスな部分に苛立ちを覚えながらも、僕は日に日に彼女に惹かれていた。彼女と話していると、分厚い殻の中に閉じこもっていた心が、ゆっくりと解きほぐされていくのを感じた。世界は、この古書店の中だけではないのだと、何年も忘れていた当たり前の事実を思い出させてくれた。
ある雨上がりの午後、僕たちは初めて店の外で会った。近所の公園を並んで歩く。濡れたアスファルトの匂いが、雨に洗われた緑の香りを引き立てていた。陽菜さんはいつものように、首から古いカメラを提げている。
「陽菜さん、いつもそのカメラで何を撮ってるんですか?」
「大切なもの、全部」
そう言って、彼女はファインダーを覗き、僕にレンズを向けた。カシャ、と乾いたシャッター音が響く。
「でも、それ、フィルム入ってないでしょう」
以前、彼女がカメラの裏蓋を開けているのを偶然見てしまったのだ。空っぽのそこには、光を受け止める銀塩フィルムの姿はなかった。
僕の指摘に、陽菜さんは少しだけ寂しそうに笑った。
「うん。フィルムは、ないの」
「じゃあ、写らないじゃないですか」
「写るよ。ここに」
彼女はそう言って、自分の胸を指差した。
「私の心に、直接焼き付けてる。絶対、忘れないように」
その横顔はあまりに切なく、美しかった。僕は、彼女が抱える秘密の重さに触れたような気がして、それ以上何も聞けなかった。この時すでに、僕の心はほとんど決まっていた。彼女の秘密ごと、すべてを受け入れたい。僕の未来に、彼女がいてほしい。そう、強く願っていた。
第三章 約束のなかった住所
陽菜さんと出会って三ヶ月が経った。季節は夏から秋へと移ろい、街路樹の葉が赤や黄色に染まり始めていた。僕は、自分の臆病な心に別れを告げる決心をした。陽菜さんに、僕の気持ちを伝えよう。
その日、僕は朝からそわそわしていた。彼女の好きだと言っていたアールグレイの新しい茶葉を仕入れ、カウンターに小さな花を飾った。しかし、陽菜さんは来なかった。閉店時間を過ぎても、あの真鍮のベルが鳴ることはなかった。
胸騒ぎがした。彼女は引っ越したばかりだと言って、以前、僕に新しい住所を書いたメモを渡してくれていた。「何かあったら、ここに来て」と。僕はそのメモを頼りに、夜の街を走り、記されたアパートへ向かった。
しかし、たどり着いた場所にあったのは、月明かりに照らされた、がらんとした空き地だけだった。雑草が生い茂り、打ち捨てられた看板が虚しく横たわっている。約束の住所など、どこにも存在しなかった。
騙されたのか? 呆然と立ち尽くす僕のポケットで、スマートフォンが震えた。見知らぬアドレスからのメール。添付されていたのは、一枚の画像データと、長いテキストだった。
画像を開くと、そこに写っていたのは、穏やかに微笑む僕と陽菜さん、そして、僕たちの腕に抱かれた小さな赤ん坊だった。背景は、見覚えのない明るいリビング。僕は、僕よりずっと年を重ねていて、目尻には柔らかな皺が刻まれている。
混乱しながらテキストに目を落とした瞬間、僕の世界は音を立てて崩れ落ちた。
『湊さんへ。ごめんなさい。嘘をついていました』
手紙はそう始まっていた。
『私は、柚木陽菜。あなたの、未来の妻です。今から十五年後の未来から来ました。
未来のあなたは、素晴らしい人でした。優しくて、知的で、少し不器用で。私と、私たちの娘を、世界で一番愛してくれました。でも……あなたは、三十九歳で病気で死んでしまうの。治療法のない、残酷な病気で。
歴史を変えることは許されていません。あなたの運命を変えるために、私はここに来たのではありません。
私は、ただ、怖かった。あなたを失った後、あなたと過ごした幸せな記憶が、日々薄れていくことが。あなたの声が、笑い方が、あの不器用な優しさが、時間の中に溶けて消えてしまうのが、耐えられなかった。
だから、来てしまった。私たちの物語が始まった、この時代に。あなたとの記憶を、もう一度、この心に焼き付けるために。フィルムのないあのカメラは、私の記憶を鮮明に保つための、ただのお守りだったんです。
あなたが好きだった紅茶の味も、子供の頃の歌も、全部、未来のあなたが私に教えてくれたこと。私はただ、その答え合わせをしに来ただけ。……ああ、でも、またあなたを好きになってしまった。馬鹿でしょう?
滞在できる時間は、もう終わりです。私は未来に帰ります。あなたがいない、未来へ』
第四章 未来からの返信
絶望が、冷たい水のように全身を浸していく。陽菜さんはもういない。僕たちは結ばれることもなく、そして僕は、若くして死ぬ運命にある。なんて残酷な結末だろう。
僕はその場に崩れ落ち、涙が止まらなかった。しかし、手紙には続きがあった。スクロールした指が震える。
『最後に、未来のあなたが、病室で私に遺してくれた言葉を伝えます。
「陽菜、君と出会えて、僕の人生は完璧だった。少し短かったかもしれないけど、最高の物語だったよ。だから、悲しまないで。僕がいつか、君との記憶を忘れてしまっても、君が覚えていてくれるなら、僕たちの時間は永遠だ。だから、笑って」
私は、この言葉が本当かどうか、確かめに来たのかもしれません。そして、確信しました。二十八歳のあなたに出会って。あなたは、ちゃんと私の愛した湊さんでした。私は、あなたと出会えて、本当に、世界で一番幸せです。
だから、お願い。残りの時間を、どうかあなたらしく、目一杯生きてください。たくさんの本を読んで、たくさんの人と話して、たくさん笑ってください。それが、未来の私への、最高の贈り物です。
愛しています。未来で、また会いましょう。あなたの永遠の妻、陽菜より』
手紙を読み終えた時、僕の涙はいつの間にか止まっていた。空を見上げると、雲の切れ間から、澄んだ月が顔を覗かせていた。
未来の僕は、そんなにも強く、気高い人間になれるのか。死を前にして、愛する人をそんな風に励ますことができるのか。
それは絶望ではない。それは、僕がこれから歩むべき道を示す、道標だった。
陽菜。君は僕に、失われた時間ではなく、与えられた時間の尊さを教えに来てくれたんだ。
数年後。僕は変わらず『蒼井書房』の店主をしている。以前よりもずっと、よく笑い、客と話し、新しいことに挑戦するようになった。店の片隅には、陽菜さんがいつも座っていたソファと、彼女が残していったフィルムのないカメラが、静かに置かれている。
時折、僕はそのカメラを手に取り、窓から差し込む陽光にレンズを向ける。カシャ、という空虚なシャッター音。ファインダーの向こうには、もちろん何も写らない。
けれど、僕の心にはっきりと焼き付いている。
レモンイエローのワンピースで微笑む彼女の姿が。未来で僕を待っている、愛しい人の笑顔が。
「さあ、今日も始めようか」
僕は小さく呟き、カウンターに立つ。限られた時間の中で、最高の物語を紡いでいくために。未来の彼女に、胸を張って「ただいま」と言う、その日のために。僕の人生という、残光のファインダーを覗き込みながら。