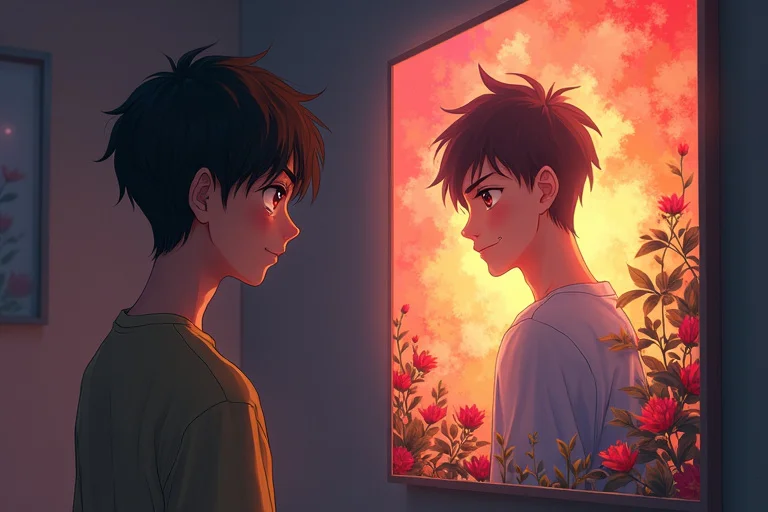第一章 灰色の世界と色彩の儀式
僕、東堂奏多(とうどう かなた)の世界は、常に薄い霧に覆われていた。色褪せたモノクロームの映画のように、喜びも悲しみも、怒りさえも、どこか他人事だった。感情というものが、生まれつき欠落しているのではないかと、物心ついた頃から漠然と感じていた。友人を作ろうと試みたこともあったが、彼らの笑い声は空虚に響き、その輪の中にいる自分は、精巧に作られた人形に過ぎないように思えた。
そんな僕の無彩色の日常に、唯一、鮮やかな色彩をもたらしてくれる存在がいた。月島陽(つきしま はる)だ。
彼との出会いは一年前の春。大学の図書館で、分厚い専門書に埋もれるようにして眠ってしまっていた僕の肩を、彼が優しく叩いたのだ。「大丈夫? すごく疲れた顔してるよ」と屈託なく笑う彼の顔は、まるで太陽そのものだった。それから、なぜか陽は僕に付きまとうようになった。感情の乏しい僕のどこに興味を持ったのかは、今でも謎だ。
そして、僕たちの間には、秘密の儀式が生まれた。
週に一度、土曜の夕暮れ時。僕たちは街外れの岬に立つ、今は使われていない古い灯台で会う。螺旋階段を上った先にある、円形の展望室。潮風が錆びた窓枠を鳴らし、眼下にはどこまでも広がる海。そこで陽は、僕の向かいに座り、静かに僕の両手を取るのだ。
「奏多、準備はいい?」
陽が微笑むと、彼の指先から、まるで電流のような温かい何かが流れ込んでくる。それは、僕の空っぽの器を満たす、鮮烈な「感情」の奔流だった。
先週は、「歓喜」。陽が友人たちとキャンプファイヤーを囲んだ時の、燃え上がる炎のような高揚感。僕の胸がドキドキと高鳴り、意味もなく口角が上がった。その前の週は、「郷愁」。陽が幼い頃に祖母と歩いた田舎道の、土と草いきれの匂いを伴う切ない安らぎ。僕は、体験したはずもないその風景に、涙ぐみそうになった。
この儀式が終わると、僕は数時間、普通の人間のように世界を色鮮やかに感じることができる。陽が「共有」してくれる感情は、僕にとって麻薬であり、救いだった。この瞬間のために、僕は灰色の六日間を耐えているのだ。
だが、最近、奇妙な違和感が僕を苛んでいた。陽からもらう感情が鮮烈であればあるほど、僕自身の過去の記憶が、より一層、霞んでいく気がするのだ。例えば、小学校の卒業式の記憶。写真を見れば、確かに僕はそこにいる。しかし、その時の気持ちを思い出そうとすると、まるで分厚いガラス板に隔てられているかのように、何も感じ取れない。両親の顔さえ、時々ぼんやりとした輪郭しか思い浮かばないことがあった。
まあ、いいか。僕は思考を打ち消す。失われた過去の曖昧な記憶よりも、今、陽がくれる確かな色彩の方が、ずっと価値がある。僕は、陽という太陽なしでは生きていけない、哀れな惑星なのだから。
第二章 借り物の心と蝕まれる輪郭
陽との友情が深まるにつれて、僕の世界は彼の色彩で満たされていった。彼は僕を様々な場所へ連れ出してくれた。満開の桜並木の下、喧騒に満ちた夏祭り、燃えるような紅葉の山道。僕はそれらの風景をただ網膜に映すだけだったが、週末の儀式で陽がその時の「感動」を僕に注ぎ込むと、記憶は後から鮮やかに色づいた。
「すごいだろ、奏多。あの花火、胸にズドンって響いてきたんだ。空いっぱいに広がる光の粒が、まるで生き物みたいでさ」
灯台の展望室で、陽は目を輝かせながら語る。彼の手が僕の手に重なると、あの夜の火薬の匂い、腹に響く轟音、そして夜空を焦がす光の奔流がもたらした圧倒的な興奮が、僕自身の体験として蘇る。僕はその借り物の感動に酔いしれ、何度も頷いた。
「うん……すごかった。本当に」
僕の心は、陽がくれた感情のパッチワークで出来上がっていた。陽が笑えば僕も笑い、陽が美しいと言えば僕も世界を美しいと感じた。僕は陽の感情をフィルターにして、ようやく世界と繋がることができたのだ。陽は僕の唯一の理解者であり、創造主でさえあった。
しかし、その代償は、静かに、だが確実に僕の存在を蝕んでいた。
ある朝、鏡に映った自分の顔を見て、僕は凍りついた。誰だ、こいつは。もちろん、それは紛れもなく僕自身の顔だったが、その表情や目つきが、自分のものとは思えなかったのだ。まるで、誰かの人生を仮面のように被っているような、薄気味悪い感覚。
記憶の欠落も、もはや無視できないレベルになっていた。大学の講義の内容が思い出せないのは日常茶飯事で、ついには、昨日食べた夕食すら思い出せないことがあった。僕という人間の輪郭が、少しずつ溶けて消えていくような恐怖。
陽にそのことを打ち明けると、彼は少し悲しそうな顔をして言った。
「考えすぎだよ、奏多。疲れてるんだ。……大丈夫、僕がいるじゃないか。僕が奏多の心になってあげる。だから、何も心配いらない」
その言葉は、甘い毒のように僕の不安を麻痺させた。そうだ、陽がいればいい。僕が僕でなくなっても、陽が僕のそばにいてくれるなら、それで。僕はますます彼に依存し、自らの足で立つことを放棄していった。
そんなある日、陽が珍しく深刻な顔で僕に尋ねた。
「奏多、もし僕がいなくなったら、どうする?」
「……どうもしないよ。陽がいなくなるなんて、考えられない。僕の世界から太陽がなくなるのと同じだ」
「そっか……」
陽は力なく笑い、窓の外に広がる夕暮れの海を見つめた。その横顔に浮かんだ深い哀しみの色を、この時の僕は、彼から与えられた感情を通してではなく、自らの心のざわめきとして、確かに感じ取っていた。
第三章 灯台守の日記
約束の土曜日。僕はいつものように灯台へ向かった。だが、展望室には陽の姿はなかった。冷たい潮風が、がらんとした空間を吹き抜けるだけだ。彼が遅れるなんて、初めてのことだった。
床の中央に、ポツンと一冊の古びたノートが置かれているのに気づいた。革張りの表紙には、何も書かれていない。そっと開くと、そこには陽の、少し癖のある見慣れた文字が並んでいた。それは彼の日記だった。罪悪感を感じながらも、僕はページをめくらずにはいられなかった。
『五月十日。今日、"彼"を見つけた。東堂奏多。感情の器が、ほとんど空っぽだ。これほどまでに完璧な宿主は、もう二度と現れないかもしれない。僕の命は、あと数えるほどしかない。彼から少しだけ「記憶」と「生命力」を分けてもらえば、僕はもう少しだけ、この世界に留まることができる』
心臓が氷の塊になったようだった。読み進める指が震える。
『僕は"情動喰らい"。人の感情を糧とし、その対価として最も色濃い記憶を奪うことで生き長らえる、寄生生物だ。奏多に近づき、友情を装い、彼の内側を喰らい始めた。鮮やかな「歓喜」を与え、彼の幼い頃の誕生日の記憶を奪った。「安らぎ」を与え、母親に抱きしめられた温もりの記憶を奪った。彼は何も気づかない。僕が与える偽りの感情に酔いしれ、自らが空っぽになっていくことにも気づかずに』
吐き気がした。友情も、笑顔も、優しさも、すべてが僕を捕食するための罠だったというのか。僕が感じていた色彩豊かな世界は、僕自身の過去を犠牲にして成り立っていた、残酷な幻だったのだ。怒りと絶望で、目の前が真っ暗になる。
だが、日記を読み進めるうちに、僕は気づいた。初期の冷徹な観察記録のような文章は、次第に混乱と苦悩の色を帯びていくのだ。
『九月三日。奏多と海に行った。夕日を見て、彼は「綺麗だ」と呟いた。僕が与えた感情ではなく、彼自身の、か細く、だが本物の感情だった。その瞬間、胸を刺すような痛みを感じた。これは何だ? 罪悪感? 僕のような存在が、こんなものを感じるはずがないのに』
『十二月二十四日。奏多が、手編みのマフラーをくれた。「陽は寒がりだから」と言って、はにかむように笑った。嬉しかった。生まれて初めて、他者から何かを与えられることの温かさを知った。僕は彼を喰らう捕食者なのに。彼から奪うばかりの僕が、こんなものを受け取る資格などないのに。涙が出そうになった』
『三月十五日。もう限界だ。奏多の記憶は、ほとんど僕が喰い尽くしてしまった。彼の生命力も、残りわずかだ。このままでは、彼は抜け殻になってしまう。僕は彼を救うために近づいたはずなのに、結局は僕の延命のために彼を破壊しているだけだ。出会った頃から、分かっていたことじゃないか。なのに、なぜこんなに苦しいんだ』
最後の日付は、昨日だった。
『奏多、ごめん。僕は君という存在に、本当の「友情」を教えてもらった。君から奪った感情と記憶で満たされた僕の心は、もう君なしではいられない。でも、これ以上、君を傷つけることはできない。だから僕は消える。君から奪った全ての記憶と感情を、僕という存在ごと、この世界から消し去る。君はまた、灰色の世界に戻るだろう。でも、どうか生きてほしい。空っぽになった君の心に、いつか君自身の色が宿ることを、心から願っている。さようなら、僕のたった一人の、友達』
日記から顔を上げると、窓の外はすっかり闇に包まれていた。涙が頬を伝っていることに、僕は初めて気づいた。それは陽からもらった借り物の悲しみではなかった。裏切られた怒り、失われた過去への喪失感、そして、捕食者でありながら僕のために消えていった彼への、名付けようのない愛惜。それらが渾然一体となった、僕自身の、本物の感情だった。
第四章 僕だけの色
陽がいなくなり、僕の世界から色彩は消え去った。再び戻ってきたのは、あの薄い霧に覆われたモノクロームの世界。だが、何かが決定的に違っていた。以前の灰色の世界は、完全な「無」だった。しかし今の世界には、静かな「痛み」があった。喪失という名の、鈍い痛みが、僕が確かに存在していることを証明していた。
日記を抱きしめ、僕は灯台を後にした。陽が奪った僕の過去は、もう戻らない。両親との温かい思い出も、友人と笑い合った日も、すべては陽の命を繋ぐための燃料となり、彼と共に消え去った。僕は、過去を持たない人間になった。
数日間、僕は部屋に閉じこもった。空っぽの自分と向き合うのは、想像を絶する苦痛だった。鏡に映る自分は、記憶という土台を失い、幽霊のように希薄に見えた。このまま消えてしまいたいとさえ思った。
しかし、ふとした瞬間、陽の最後の言葉が蘇る。
『空っぽになった君の心に、いつか君自身の色が宿ることを、心から願っている』
陽は僕からすべてを奪った。だが、皮肉なことに、彼は僕に最も大切なものを遺していった。「感情」そのものを感じる能力だ。彼との儀式を通して、僕の心は感情の受け取り方を学習したのだ。喜びとは、悲しみとは、愛しさとは、どういうものなのかを。
僕は立ち上がった。失われた過去を嘆くのではなく、これからを生きよう。陽がくれたこの「心」で、僕自身の記憶と感情を、一から紡いでいくのだ。
それから僕は、今まで避けてきたことすべてに挑戦した。一人で映画を観に行き、主人公の境遇に胸を痛めた。道端に咲く名も知らぬ花に足を止め、その可憐さに心を動かされた。大学のクラスメイトに勇気を出して話しかけ、ぎこちない会話の中で、人と関わることの温かさに触れた。
一つ一つの体験は、陽がくれたような鮮烈な色彩ではなかったかもしれない。淡く、繊細で、時には混じり合って濁った色だった。でも、それらは紛れもなく、僕自身の色だった。
一年が過ぎた。僕は再び、あの岬の灯台に立っていた。陽の日記を、僕はあの日以来、開いていない。彼の記憶に頼らず、自分の足で立つと決めたからだ。
眼下には、夕日に染まる穏やかな海が広がっている。かつて陽が「美しい」と教えてくれた光景。だが今、僕の胸に広がるのは、あの借り物の感動とは違う、もっと静かで、深く、そして少しだけ切ない感情だった。失われたものへの哀惜と、今ここに生きていることへの感謝が入り混じった、複雑で豊かな色合い。
僕は、錆びた手すりに手を置き、水平線の彼方に向かってそっと呟いた。
「見てるか、陽。僕の世界は、もう灰色じゃない。君がくれた色じゃない。僕だけの色で、満ちているよ」
風が、僕の頬を優しく撫でた。それはまるで、遠いどこかで微笑んだ、友人の返事のようだった。友情が本物だったのか、それとも巧妙な捕食行為だったのか。その答えは永遠に分からない。だが、その歪んだ関係が僕に「心」を与え、新たな人生へと導いたことだけは、紛れもない真実だった。僕はこれからも、この心で世界を感じ、僕だけの色を重ねて生きていく。さようなら、そして、ありがとう。僕の、最初で最後の灯台守。