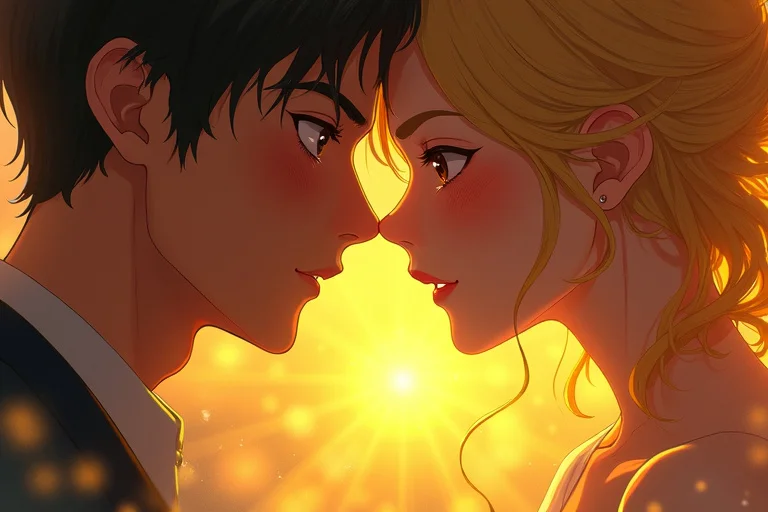第一章 質量の証明
僕にとって、愛とは質量だった。君、ユナを抱きしめるたびに、その腕の中に確かな重みを感じる。しなやかな身体が僕に預けられるその圧力が、僕らの愛の揺るぎない証明だった。この感覚は僕だけのものらしい。他人は愛を「温かい」とか「安らぐ」とか言うけれど、僕には物理的な重さとして、この世界に彼女を繋ぎ止める引力として感じられた。
「ねえ、リョウ。また難しい顔してる」
公園のベンチで、ユナが僕の肩に頭をこてんと乗せる。その心地よい重みに、僕は知らずのうちに強張っていた眉を緩めた。彼女の髪から、陽だまりとシャンプーの混ざった優しい香りがする。
世界は少しずつ、おかしくなっていた。テレビのニュースは連日、原因不明の局所的な無重力現象や、建造物が砂のように崩れる奇怪な事件を報じている。専門家たちは首を捻るばかりで、『集合的愛着心の希薄化が物理法則に影響を与えている』などという、まるで詩のような仮説を唱える学者まで現れる始末だった。人々はそれを一笑に付したが、僕にはその言葉が妙に腑に落ちた。愛が、この世界の繋がりそのものだというのなら。
その時だった。僕の肩にかかっていたユナの指先が、ふっと陽光に透けた。まるで薄いガラスのように、向こう側の緑が揺らめいて見える。僕は息を呑み、瞬きをした。次の瞬間には、彼女の指は元の柔らかな肌色に戻っていた。
見間違いか、と自分に言い聞かせながらも、胸騒ぎが止まらない。僕は無意識に、彼女の胸元で揺れる小さなガラスの砂時計に目をやった。僕がプレゼントした『心愛の砂時計』。その中の煌めく砂が、ほんの少しだけ、減っているように見えた。
第二章 溶け出す境界
ユナが透けて見える頻度は、日を追うごとに増していった。最初は指先だけだったものが、やがて腕になり、肩になり、彼女と視線を交わしているはずなのに、その瞳の奥に部屋の景色がうっすらと映り込むようになった。
「大丈夫? 最近、なんだかぼーっとしてるよ」
心配そうに僕の顔を覗き込むユナを、僕は衝動的に抱きしめた。だが、その腕の中に感じる重みは、明らかに以前より軽くなっていた。まるで密度の低い霧を抱いているような、頼りない感触。彼女の存在の輪郭が、僕の世界から溶け出そうとしている。
「なんでもない。ただ、君がここにいるって、確かめたくなっただけだ」
「もう、変なの」
ユナはくすくすと笑うが、彼女自身に自覚はない。この恐ろしい現象は、僕の感覚の中だけで起きているのだ。その事実が、僕を深い孤独の底へと突き落とした。
僕は必死になった。花を贈り、彼女が好きだと言ったレストランに連れて行き、出会った頃の思い出の場所を巡った。僕の愛が足りないせいだと思ったからだ。僕が君を愛し、その重さを感じている限り、君は消えたりしない。そう信じたかった。僕が愛を強く意識する瞬間、砂時計の砂は微かに増え、彼女の身体も確かな実体を取り戻す。だが、それも束の間。気を抜くと、砂は静かに減り続け、彼女の境界は再び曖昧になっていくのだった。
世界はさらに歪みを増していた。街では「無重力警報」が日常的に鳴り響き、人々は浮き上がりそうになる身体を必死でガードレールに捕まえて耐える。愛が失われ、世界の引力が弱まっているのだ。
第三章 褪色の街
『愛の喪失現象』という言葉が、まことしやかに囁かれ始めた。人々が、ある日突然、家族や恋人といった特定の人への愛を、その記憶と共に完全に失ってしまう現象。忘れられた者は、誰の目にも見えなくなり、その人が使っていた物や住んでいた家は、まるでそこだけ時間が止まったかのように色褪せ、やがて崩壊していく。
僕らの住む街でも、その現象は起きていた。昨日まで賑わっていたはずのパン屋が、一夜にして埃を被った廃墟に変わっていた。店主の老夫婦は、互いのことを忘れてしまったのだという。愛という名の接着剤を失った世界は、かくも容易くバラバラになる。
ある雨の日、アパートの部屋で窓の外を眺めていたユナが、ぽつりと呟いた。
「あの公園、昔から好きなんだ。でも、どうして好きなのか思い出せない。誰かと大切な約束でもしたような気がするんだけど……」
その言葉に、僕の心臓は氷水に浸されたように冷たくなった。あの公園は、僕が初めてユナに告白した場所だ。彼女が、僕との記憶を、僕への愛を失い始めている。僕だけの問題ではなかった。彼女の中から、僕という存在の重みが消えかけているのだ。
第四章 砂時計の告白
その夜、ユナの身体はほとんど光を通すまでになっていた。食卓の向こう側に座る彼女の姿は、揺らめく陽炎のようだ。夕食に手を付けることもできず、僕は震える手で彼女の手を握った。冷たい。そして、信じられないほど軽い。まるで実体がないかのように。
「消えないでくれ、ユナ……!」
僕の悲痛な叫びに、彼女は困惑したように眉を寄せた。その瞬間、彼女の胸元で輝いていた『心愛の砂時計』が、まばゆい光を放った。
視界が白く染まり、僕は時間の流れから切り離された。
脳内に、奔流のようにイメージが流れ込んでくる。―――無。完全な無の中から、一つの巨大な愛が生まれる。その『原初の愛』が宇宙を創造し、星々を紡ぎ、引力を生み出し、生命を育んだ。この世界そのものが、『愛』の具現だったのだ。
だが、永い時の果てに、『原初の愛』は疲弊し、その力は尽きかけていた。だから世界は結合を失い、崩壊へと向かっている。
そして、僕は見た。その『原初の愛』の、最後の、か弱く燃える残滓。それが、ユナだった。
絶望的な真実が、雷となって僕を撃ち抜いた。僕がユナを愛し、彼女の「重さ」を感じるたび、僕は無意識のうちに彼女の中から『原初の愛』の力を吸収し、消費していたのだ。僕の愛こそが、彼女を透明にし、世界を終わらせる原因だった。僕が彼女を愛せば愛すほど、世界は終焉に近づく。
『心愛の砂時計』の砂は、僕の愛の量ではなかった。ユナの中に残された、世界の寿命そのものだったのだ。
第五章 愛の選択
真実は、あまりに残酷だった。ユナを愛することが、彼女を、そしてこの世界を殺すことだったなんて。僕は愛という名のナイフで、愛する人の魂を削り取っていたに過ぎない。絶望が僕の全身を支配し、呼吸すらままならない。
「リョウ、どうしたの? 怖い顔……」
か細い声で、ほとんど透明になったユナが僕の頬に手を伸ばす。その手は僕の肌をすり抜け、確かな感触を残さない。それでも、僕は彼女の温もりを感じようと必死に目を閉じた。
外では、世界が断末魔の叫びを上げていた。空がガラスのようにひび割れ、近所のビルが重力を失ってゆっくりと宙へ浮き上がっていく。もう、時間がない。
僕は、決意した。
この世界で、ただ一つの正しい選択を。
僕はおぼつかない足取りでユナに近づき、その幻のような唇に、自分の唇を重ねた。これが最後だと、魂のすべてに刻みつけるように。かつて感じた柔らかな感触、甘い香り、確かな重み。失われゆく全てを記憶に焼き付けた。
ごめん、ユナ。そして、ありがとう。
第六章 無重力のさよなら
僕は意識を、僕の存在の核へと集中させる。そこには、ユナへの愛が、灼熱の恒星のように燃え盛っていた。僕は、それを自らの手で引き剥がしにかかった。
想像を絶する激痛が全身を貫く。魂が根こそぎ引き抜かれるような感覚。思い出が一つ消えるたび、僕の身体の一部が粒子となって霧散していく。初めて手を繋いだ日のときめき。共に笑い合った夜の温もり。彼女を守ると誓った決意。その全てを、僕は自ら手放していく。
僕が愛を失うのと反比例して、ユナの身体は眩い光を取り戻し始めた。その輪郭はくっきりと鮮明になり、足元から世界へと温かな光の波紋が広がっていく。ひび割れた空は癒え、浮遊していたビルは静かに元の場所へと着地する。世界が、愛を取り戻していく。
僕の身体は、もうほとんど残っていなかった。指先が、腕が、足が、光の粒子となって風に溶けていく。
「リョウ……?」
ユナが、僕がいた空間を見て、不思議そうに首を傾げた。彼女の瞳から、僕という存在の記憶が消えていくのが分かった。
僕は声にならない声で、最後の言葉を紡いだ。
「愛してる」
その言葉を最後に、僕の意識は完全に消滅した。僕という質量は、この世界から完全に失われた。
第七章 君のいない世界で
世界は、あの悪夢が嘘だったかのように、完璧な平穏を取り戻していた。空はどこまでも青く、大地は人々をしっかりと支えている。
ユナは、見覚えのない公園のベンチに一人で座っていた。なぜここに来たのか、誰かを待っているのか、自分でも分からない。ただ、胸にぽっかりと穴が空いたような、漠然とした喪失感が消えなかった。
ふと、胸元で何かがきらりと光るのを感じて、彼女は視線を落とした。そこには、煌めく砂が目一杯に満たされた、美しいガラスの砂時計が下がっていた。いつから持っていたのだろう。誰かからの贈り物だろうか。何も思い出せない。
その時、柔らかな風が吹き抜け、彼女の髪を優しく揺らした。
ほんの一瞬。ほんの一瞬だけ、誰かにそっと後ろから抱きしめられたような、温かくて、確かな「重み」を感じた。
ユナは驚いて振り返るが、そこには誰もいない。
それなのに、どうしてだろう。涙が、一筋、頬を伝った。
理由のわからない切なさに胸を締め付けられながら、彼女はただ、どこまでも青い空を見上げていた。