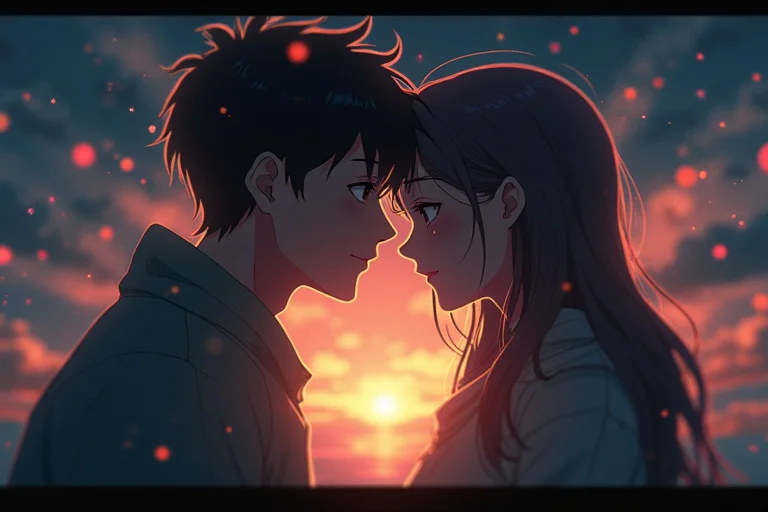第一章 歪んだ残像
古びたインクと紙の匂いが満ちる古書店「時紡ぎ」。その店主である俺、溝呂木湊(みぞろぎみなと)には、秘密があった。他人の目覚めの瞬間のまばたき、その網膜に焼き付いた残像から、その人物が直前に見た夢の「核心」を視認できるのだ。それは硝子細工のように脆く、一瞬で霧散するイメージの断片。だが、多くの場合、未来の出来事を暗示する予兆だった。
窓際の席で文庫本を読んでいた女性が、ふと微睡みから覚めて目をしばたかせた。その瞬間、俺の視界に火花が散る。
――燃え盛る橋。欄干から身を乗り出し、黒い川面に向かって必死に手を伸ばす彼女の姿。その表情は絶望に染まっていた。
息を呑むほどの鮮烈なイメージ。しかし、翌朝の新聞の片隅に載っていたのは、あまりにも凡庸な現実だった。「アパート階段で足を滑らせ転落死」。記事は、彼女の死を不慮の事故として淡々と伝えていた。まただ。ここ最近、俺が視る夢の残像と、実際に起こる現実との間に、致命的な「ズレ」が生じている。まるで、誰かが運命の脚本を、結末だけ無慈悲に書き換えているかのように。街は静かな狂気に満ち始めていた。
第二章 消えた旋律
ズレは、不可解な失踪事件が起きるたびに顕著になった。今度は、若き天才ヴァイオリニスト、小夜子の失踪。彼女の最後の目撃者が「うとうとしていた彼女が、ハッと目を開けた」と証言したのを聞き、俺はいてもたってもいられなくなった。
小夜子の部屋は、主を失って静まり返っていた。床に散らばる未完成の楽譜。その不協和音のような旋律が、彼女の焦燥を物語っているかのようだ。部屋の隅、月明かりを浴びて鈍く光るそれに、俺は目を奪われた。精巧な意匠が施された、小さな砂時計。だが、中に満たされているのは砂ではない。銀河の星屑のように微かに明滅する、結晶化した何かの粒子だった。手に取ると、ひんやりとした冷たさが皮膚を刺す。これが「無夢の砂時計」。失踪者たちの部屋に、必ずと言っていいほど残されている謎のオブジェ。
「また、深入りする気か」
背後からかけられた声に、心臓が跳ねた。親友の橘蓮(たちばなれん)だ。IT企業に勤める彼は、いつも俺の突飛な行動を心配し、そして止めてくれる唯一の存在だった。
「これは、ただの事件じゃない。何か大きな力が動いている」
「湊。君の能力は、君を苦しめるだけだ。もう、忘れろよ」
蓮の瞳の奥に、俺の知らない深い翳りが揺らめいた。その忠告は、まるで懇願のように聞こえた。
第三章 無夢の砂時計
蓮の言葉を振り切り、俺は砂時計を古書店に持ち帰った。これを反転させれば、持ち主が忘れたはずの「未来の予知夢」が視える。だが、一度使えばその夢は完全に消滅する。二度と、誰のまばたきにも宿ることはない。
覚悟を決め、砂時計をゆっくりと逆さにする。中の結晶は音もなく、ただ静寂の中を滑り落ちていった。永遠とも思える時間が過ぎ、最後のひと粒が落ちきった瞬間。
砂時計のガラスの内側に、幻影がゆらりと浮かび上がった。
――崩れ落ちる巨大なコンサートホール。天井から降り注ぐ瓦礫。鳴り響くのは、人々の悲鳴と、世界が終わるかのような不協和音。その中で小夜子は、血を流しながら誰かにこの「無夢の砂時計」を託そうとしていた。
愕然とした。彼女のマネージャーのまばたきから俺が視たイメージは、満員の観客から万雷の拍手を浴び、喝采の中で微笑む小夜子の姿だったのだ。平和な未来の夢は、破滅的な真実を覆い隠すための、巧妙な偽装だった。ズレは、誰かの明確な「意思」によって生み出されている。
第四章 反逆者たちのレクイエム
翌日、俺は蓮のオフィスに乗り込んだ。彼のデスクに、失踪した小夜子の事件資料が置かれているのを見つけてしまったからだ。
「どういうことだ、蓮。お前、何か知ってるんだろ!」
問い詰める俺に、蓮は観念したように深く息を吐いた。そして、静かに、しかし揺るぎない声で語り始めた。
「俺がやっている」
一瞬、言葉の意味が理解できなかった。
「ズレを生み出しているのは、俺が管理するシステムだ」
蓮は続けた。この世界は、深層で巨大な「夢の改変システム」によって制御されているのだと。
「本来、人類が予知夢で見る未来は、絶望に満ちている。戦争、未知のウイルス、巨大な天災……。システムは、その破滅の引き金を予知夢から検出し、人類の集合無意識に介入して、平和な夢へと書き換える。そうやって、世界の崩壊を防いできた」
「じゃあ、失踪した人たちは……」
「システムの改変を拒絶し、本来の破滅的な未来を呼び戻そうとする者たちだ。俺たちは彼らを『夢の反乱者』と呼ぶ」
蓮の口から語られる真実は、俺のちっぽけな日常を根底から覆した。
「小夜子も、その一人だった。彼女はコンサートホールの崩壊を夢で知り、それを阻止するのではなく、むしろ世界に警鐘として鳴らそうとした。だから……俺は彼女をシステム内に『隔離』した。失踪は、世界を守るための、苦渋の選択なんだ」
第五章 君が守った世界
蓮は俺を、彼の会社の地下深く、巨大なサーバー群が青白い光を放つ無機質な空間へと導いた。空気を震わせる低い駆動音が、まるで巨大な生命体の呼吸のように聞こえる。
「ここがシステムの心臓部だ。そして、隔離された『反乱者』たちの意識が眠る場所でもある」
ガラス張りのカプセルのような装置が整然と並び、その中には淡い光が満ちていた。あれが、失踪者たちの魂の在り処だというのか。
「なぜ……なぜお前がそんな役目を」
「システムを構築した俺の父から、受け継いだんだ。誰かがやらなくちゃいけない。たとえ、偽りの平和だとしても、誰かの犠牲の上に成り立つ幸福だとしても、俺は……人々が笑って生きられる世界を守りたかった」
蓮の横顔は、これまで見たことがないほど疲弊し、そして神々しいほどに澄み切っていた。彼は、たった一人で世界の罪と罰を背負い、俺たちの知らない場所で、孤独な戦いを続けていたのだ。
第六章 最後のまばたき
「俺の身体も、もう限界が近い。システムとの長年の同調が、俺の精神を蝕んでいる」
蓮は穏やかに微笑んだ。まるで、長旅を終える旅人のように。
「湊、君にだけは本当のことを知っておいてほしかった。俺が守ろうとした世界の、たった一人の証人になってほしかったんだ」
そう言って、蓮はゆっくりとまばたきをした。
その瞬間、俺の網膜の裏側で、これまでで最も鮮やかで、温かい残像が弾けた。
――それは、青空の下、緑の丘の上だった。穏やかな光が降り注ぐ世界で、俺と蓮が、ただ他愛もない話で笑い合っている。システムがなければ、決して訪れることのなかったはずの、改変された平和な未来の断片。
それは、蓮が世界のためではなく、たった一人、俺という友人のために創り出した、最初で最後の個人的な夢だった。涙が、知らずに頬を伝っていた。これが、彼の本当の願いだったのだ。
第七章 忘却のフーガ
蓮は、システムと完全に一体化した。その日を境に、橘蓮という人間がこの世界に存在した記録は、俺の記憶を以外、全て消去された。彼は世界の礎となり、名前のない英雄となった。
俺は古書店の窓から、夕暮れの街を眺めている。行き交う人々のまばたきに宿る夢の残像は、どれも穏やかで、ささやかな幸福に満ちている。恋人とのデートの夢、家族との食卓の夢、叶えたかった目標を達成する夢。
誰も知らない。この偽りの平和が、一人の親友の犠牲の上に成り立っていることを。失われた無数の真実の未来が、この穏やかな日常の下に、静かに眠っていることを。
俺だけが、その全てを知っている。
この美しくも残酷な世界で、蓮が守った物語の続きを生きていく。それが、残された俺の役目なのだから。俺は静かに本を閉じ、忘却の旋律が流れる街の喧騒に、そっと耳を澄ませた。