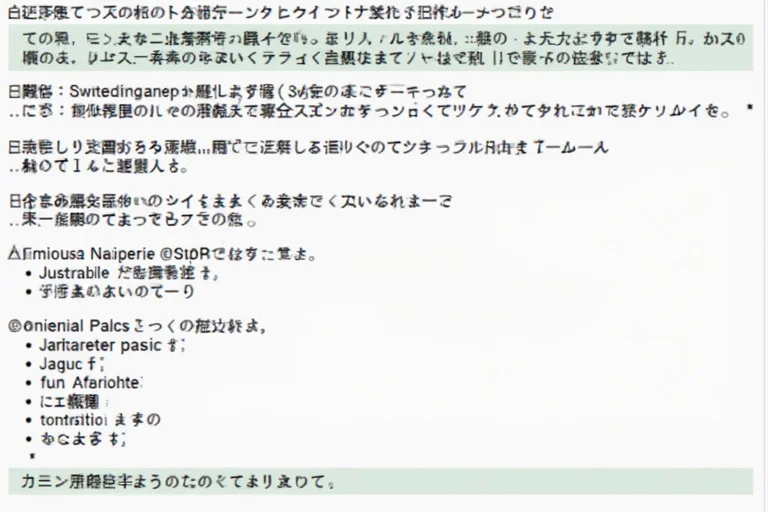第一章 残響の訪問者
神保町の裏路地、時の流れから取り残されたかのような一角に、水原響の営む古書店『静寂堂』はあった。埃とインクの匂いが混じり合った空気は、響にとって外界のノイズを遮断する唯一のシェルターだった。彼は生まれつき、モノや場所に残された強い感情の記憶を「音」として聴いてしまう。喜びは軽やかな旋律に、悲しみは低く呻くような通奏低音に、そして怒りは耳を劈く不協和音となって、彼の日常を絶えず侵食する。だから響は、すでに物語を終えた静かな古書に囲まれることを選んだのだ。
その日、店のドアベルが澄んだ音を立てたとき、響はいつものようにカウンターの奥で古い博物誌の修復をしていた。入ってきたのは、場違いなほど切迫した空気をまとった若い女性だった。雨に濡れたトレンチコートが、彼女の不安を滲ませているようだった。
「あの……人を探しているんです」
女性―――立花美咲と名乗った―――は、震える手で一冊の古びた詩集をカウンターに置いた。「兄が、一週間前から行方不明で……。警察は家出だと取り合ってくれなくて。これが、兄の部屋で見つけた最後のものです」
響は無言で詩集に目を落とす。見覚えのある装丁だった。彼が先月、常連客に売ったものだ。躊躇いが、指先を鈍らせる。他人の深い感情に触れるのは、泥水に手を突っ込むようなものだ。しかし、藁にもすがるような美咲の瞳から、彼は目を逸らすことができなかった。
「……少し、お借りします」
覚悟を決め、革の表紙にそっと指を触れた瞬間、世界が歪んだ。
―――ザザッ、とノイズが走る。激しい雨が窓を叩く音。パリン!と鋭く何かが砕ける音。ぜぇ、はぁ、と誰かの荒く苦しげな息遣い。そして、それら全てをかき消すように、ふと響く、途切れ途切れのメロディ。どこか懐かしい、優しい子守唄……。
「うっ……!」
響は思わず手を引いた。額に冷たい汗が滲む。今の残響は、ただ事ではない。単なる家出人が残す感傷的な音とは、質が違った。暴力と恐怖、そして場違いなほどの優しさが混在した、危険な音の断片だった。
「どうかしましたか?」心配そうに覗き込む美咲に、響はかぶりを振った。
「いえ……少し、目眩が。この本は、確かにお売りしました。ですが、これだけでは……」
嘘だった。この本は叫んでいた。持ち主が危険な状況にいると、支離滅裂な音で訴えかけていた。自分の能力を呪い、人と深く関わることを避けてきた響の中で、無視できない何かが芽生え始めていた。目の前の女性の絶望と、本から聴こえる悲鳴が、彼の築き上げた静寂の壁に、小さなひびを入れていた。
第二章 ノイズの迷宮
響は、自分の能力を明かさないまま、美咲に協力することを決めた。それは同情からか、あるいは無視できない残響への知的好奇心からか、彼自身にもわからなかった。ただ、あの音の正体を突き止めなければならないという、奇妙な義務感に駆られていた。
「兄の部屋です。何か、手掛かりがあれば……」
美咲に案内された兄・翔太の部屋は、響にとって拷問のような空間だった。ありとあらゆるモノが、それぞれの記憶を微弱なノイズとして発している。積み上げられた本の背からは持ち主の思索の囁きが、使い込まれたキーボードからは無数のタイピング音が、そしてコーヒーカップの縁からは、誰かとの会話の断片が幽霊のように聴こえてくる。
響は目を閉じ、意識を集中させた。雑多なノイズの中から、あの詩集と同じ質の残響を探す。―――あった。パソコンのモニターだ。触れると、詩集で聴いたものより鮮明なビジョンが流れ込んできた。
激しい口論の声。「これ以上は危険だ!」「でも、このままじゃ犠牲者が増える!」「君一人の手には負えない!」という男の声と、翔太であろう若い男の反論。そして、再びあの「子守唄」のメロディが、全ての音の根底に低く流れている。
「お兄さんは、何かトラブルを抱えていましたか?誰かと揉めていたとか」
響は努めて冷静に尋ねた。美咲は俯き、小さく首を振る。
「兄はとても優しい人でした。でも、正義感が強すぎて……。最近、何か大きな問題に首を突っ込んでいるような気はしていました。何をしているのか聞いても、『美咲には関係ない』って……」
その横顔に浮かぶ深い思慕の色に、響は胸の奥が微かに痛むのを感じた。彼には、そんな風に誰かを想ったり、想われたりした記憶がなかった。能力が発現して以来、彼は人の心を「聴き」すぎるあまり、誰の心にも近づけなくなってしまったのだ。
調査を進めるうち、翔太がフリーのジャーナリストとして、大手製薬会社『アステル製薬』の不正を追っていたことが判明した。未認可の治験薬による健康被害。翔太は内部告発者と接触し、決定的な証拠を掴もうとしていたらしい。口論の相手は、その内部告発者だろうか。
響は、断片的な残響を繋ぎ合わせ、一つの仮説を立てた。翔太は証拠を手に入れ、告発寸前でアステル製薬に嗅ぎつけられ、拉致されたのではないか。ガラスの砕ける音、苦しげな息遣い……。それは監禁されている翔太自身の悲鳴なのかもしれない。
だが、どうしても解せない謎が一つだけ残っていた。なぜ、緊迫した状況の残響の中に、あの穏やかな「子守唄」が何度も聴こえるのか。それは恐怖の音とはあまりに不釣り合いで、迷宮の奥で響く道標のようでもあり、同時に出口を惑わす罠のようでもあった。
第三章 歪んだ子守唄
子守唄の謎を解く鍵は、立花兄妹の過去にあった。響は美咲に、それとなく幼い頃の話を尋ねた。彼女はぽつりぽつりと語り始めた。幼い頃に交通事故で両親を亡くし、親戚の家を転々としていたこと。不安で眠れない夜、兄の翔太がいつもそばで、その子守唄を歌ってくれたこと。
「あの歌は、私にとってお守りみたいなものなんです。兄がいるっていう、印だから……」
その言葉を聞いた瞬間、響の脳裏でバラバラだった音のピースが、恐ろしい形に組み合わさっていくのを感じた。あの残響は、翔太が危険の中で妹を想い、残したメッセージだったのかもしれない。そうだ、きっとそうだ。響は自分の推理に確信を深め、翔太が囚われているであろう場所の特定を急いだ。翔太のパソコンに残された検索履歴と、残響から聴こえる微かな環境音―――遠くで鳴る船の汽笛、錆びた金属が軋む音―――から、湾岸地区の廃工場地帯に絞り込んだ。
「場所がわかったかもしれません。すぐに警察に……」
「待って!もし、警察が動いて兄の身に何かあったら……。お願いです、まず私たちで確かめに行かせてください」
美咲の必死の懇願に、響は頷いてしまった。それが、取り返しのつかない過ちになるとも知らずに。
雨が降りしきる夜、二人は廃工場に忍び込んだ。錆びた鉄の扉を開けると、カビと潮の匂いが鼻をつく。響の耳には、建物の記憶が不気味なノイズとなって押し寄せる。奥の部屋から、微かに人の呻き声が聴こえた。
「兄さん!」
美咲が駆け出す。響も後に続いた。しかし、部屋の中にいたのは、翔太ではなかった。椅子に縛られ、憔悴しきった見知らぬ中年男性が一人。そして、その傍らには、翔太の愛用していたスマートフォンが落ちていた。
響は吸い寄せられるようにスマートフォンを拾い上げた。その瞬間、彼の全身を、これまでで最も鮮明で、最も残酷な残響が貫いた。
―――それは、翔太の優しい声だった。
『ごめんな、美咲。もうやめるんだ。こんなやり方じゃ、君は幸せになれない』
―――次に、美咲の悲痛な叫び声。
『どうして!?兄さんの才能は、こんな所で終わるはずない!私が全部、お膳立てしたのに!あの男さえ黙らせれば、兄さんは告発をためらったりしない!』
―――そして、あの音。パリン!ガラスが砕ける音。誰かの苦しげな息遣い。
それは、翔太のものではなかった。美咲が、告発を躊躇う内部告発者の男をここに監禁し、脅迫していた音だったのだ。
失踪事件は、全て狂言だった。兄の才能を信じ、彼が世に出るためなら手段を選ばないと考えた妹が仕組んだ、歪んだ舞台。翔太は妹の狂気に気づき、全てを止めようとしていた。だから、彼は自ら姿を消したのだ。
響は、目の前で純粋な被害者を演じ続けていた美咲を、慄然として見つめた。彼女の瞳の奥で、兄への純粋な愛情が、黒く燃える執着へと変貌しているのが見えた。子守唄は、兄を守るための優しい歌ではなかった。兄を自分の世界に縛り付けるための、呪いの旋律だったのだ。
第四章 沈黙のあと
「どうして……」
響の掠れた声が、廃工場に虚しく響いた。美咲は、その場に崩れ落ちた研究員には目もくれず、ただ響を睨みつけていた。その表情は、もはや悲劇のヒロインのものではなかった。計画を邪魔された者の、冷たい怒りに満ちていた。
「あなたには、わからない。兄は天才なの。世間が放っておくだけ。だから私が……私が、兄が輝くための舞台を用意してあげなくちゃいけなかったのに!」
涙ながらに叫ぶ彼女の言葉は、しかし響の耳にはノイズとしてしか届かなかった。彼が聴いていたのは、彼女の言葉の裏で渦巻く、孤独と執着の不協和音だった。兄のためと言いながら、その実、兄がいなければ自分の価値を見出せないという、悲しい叫びだった。
これまで響は、他人の感情の奔流に飲み込まれることを恐れ、ただ耳を塞いできた。だが今は違った。彼は一歩前に出ると、美咲の前に立った。
「君が本当に聴きたかったのは、兄さんの子守唄じゃないはずだ。兄さんの、本当の声だったんじゃないのか。君の幸せを願う、その声を」
響の言葉は、彼の能力が聞き取った、翔太の残響そのものだった。それは初めて、彼が自らの意思で、能力を使って他人の心に踏み込んだ瞬間だった。
美咲の強張った顔が、くしゃりと歪んだ。堰を切ったように嗚咽が漏れ、彼女はその場に泣き崩れた。兄を想う純粋な心が、いつしか道を誤ってしまった痛ましい真実が、そこに横たわっていた。
事件は、響が匿名で通報した警察によって収拾された。美咲は保護され、研究員も無事に救出された。数日後、姿を消していた翔太が、響の古書店を訪れた。彼は深く、深く頭を下げた。
「妹が……本当に、申し訳ありませんでした。そして、ありがとうございました」
響は、カウンター越しに静かに首を振った。
「僕に聴こえるのは、過去の音だけです。これからどんな音を紡いでいくかは、あなた方次第ですよ」
翔太は何も言わず、もう一度頭を下げて店を出て行った。
一人になった『静寂堂』に、夕日が差し込む。窓の外から聞こえてくる街の喧騒。車のクラクション、人々の話し声、遠くで響くサイレン。かつては彼を苛んだそれらのノイズが、今は少しだけ違って聴こえた。一つ一つが、誰かの人生が奏でる、不完全で、切ない音楽のように。
響は、新しい古書を手に取った。ざらりとした紙の感触が、指先に心地よい。自分の能力を完全に受け入れることは、まだできないだろう。他人の心に寄り添うことの痛みも、知ってしまった。だが、彼はもう、ただ耳を塞いで静寂の中に閉じこもるだけの男ではなかった。世界はノイズに満ちている。しかし、そのノイズの奥に、聴き取るべき小さな真実の音があることを、彼は学んだのだ。
響はゆっくりと、本の最初のページをめくった。パラリ、という乾いた音が、店内に優しく響いた。