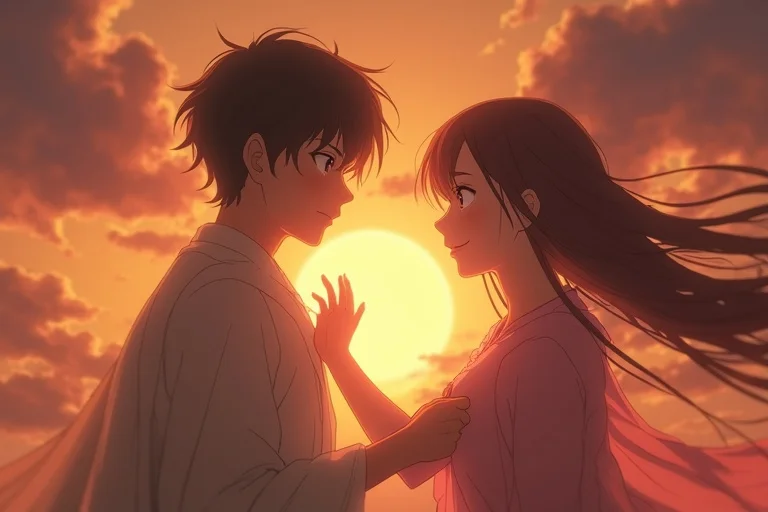第一章 記憶のインクと見知らぬ客
古い紙の匂いと、微かな埃の香りが満ちる「柏木古書店」のカウンターで、俺、柏木湊(かしわぎ みなと)はいつものように本の修繕をしていた。ピンセットで浮き上がったページを慎重に押し、糊を薄く引く。静寂は、この店の唯一の友人だった。人付き合いが苦手な俺にとって、言葉を発しない本たちに囲まれている時間は、何よりの安らぎを与えてくれる。
その静寂を破ったのは、ドアベルの澄んだ音だった。顔を上げると、そこに一人の女性が立っていた。午後の柔らかな光が彼女の輪郭を縁取り、まるで陽炎のように揺らめいて見える。淡いレモン色のワンピースが、初夏の風を連れてきたかのようだった。
「いらっしゃいませ」
かろうじて声を絞り出す。彼女は店の中をゆっくりと見回し、やがて俺のいるカウンターへと近づいてきた。その歩みは猫のようにしなやかで、床の軋む音ひとつ立てなかった。
「あの、お探しのものでも?」
「いいえ」と彼女は首を振り、蜂蜜を溶かしたような甘い声で言った。「あなたに、お願いがあって来ました」
「俺に、ですか?」
訝しむ俺の目を、彼女は真っ直ぐに見つめた。吸い込まれそうなほど深い、黒曜石の瞳だった。
「物語の続きを、書いてほしいんです」
「……は?」
意味が分からなかった。俺は物書きではない。ただの古書店の店主だ。
「人違いでは?」
「いいえ、柏木湊さん。あなたにお願いしています」彼女は微笑んだ。「『空蝉(うつせみ)の庭』の、続きを」
そのタイトルを聞いた瞬間、心臓が凍りついた。それは、俺が十年前に書こうとして、たった数章で投げ出した未完の小説のタイトルだ。誰にも見せたことはない。家族さえ知らない、俺だけの秘密のはずだった。
「なぜ、それを……」
声が震える。目の前の女はいったい何者なんだ。俺の過去を覗き見たのか?
「主人公の夏樹は、恋人の死を受け入れられずに、時が止まった庭を彷徨っています。でも、彼が出会うべき『彼女』はまだ登場していませんよね」
彼女は、まるで昨日のことのように、俺の小説の内容を語り始めた。夏樹の孤独、庭に咲く忘れな草の色、彼が口ずさむ古い歌。全てが、俺の頭の中にしか存在しないはずの描写だった。
「お願いです。彼に、結末を与えてあげてください」
彼女はそう言うと、一枚の栞をカウンターに置いた。押し花だろうか、小さな勿忘草が封じ込められている。
「また、来ます」
そう言い残し、彼女は再びベルの音とともに店を出ていった。残された俺は、埃っぽい静寂の中で、ただ呆然と立ち尽くすしかなかった。胸の奥底で、錆びついていたはずの何かが、軋みを立てて動き始めるのを感じていた。
第二章 未完のプロットと二人の時間
翌日、彼女――柚木陽菜(ゆずき ひな)と名乗った――は、約束通り店に現れた。俺は一晩中悩んだ末、彼女の正体を探るためにも、一度だけ話を聞くことにして、店の奥の物置同然だった部屋に彼女を招き入れた。
「本当に、書く気になったんですか?」
陽菜は嬉しそうに目を細めた。
「……どうしてあの小説を知っているのか、それを聞くまでは協力できません」
俺は埃をかぶった万年筆を手に取り、威嚇するように言った。陽菜は困ったように微笑むだけだ。
「あなたが書き進めてくれたら、いつか、きっと分かります」
その答えはずるいと思った。だが、彼女の期待に満ちた眼差しを見ていると、無下にはできなかった。十年ぶりに開いた原稿用紙は、黄ばんで脆くなっていた。俺は深呼吸をして、インク壺にペン先を浸した。
不思議な共同作業が始まった。俺が数ページ書くと、陽菜はそれを夢中になって読み、感想を語った。
「夏樹のこの台詞、少し硬いかもしれません。彼ならもっと、不器用な優しさを見せるはず」
「この雨の描写、素敵ですね。彼の心の涙みたい」
彼女の言葉は的確で、まるで登場人物たちの心を隅々まで理解しているかのようだった。彼女が指摘するたびに、俺は物語の世界に深く引き込まれていった。かつて、恋人に振られた痛みを紛らわすために書き始めたこの物語。その痛みの源泉である元恋人が夏樹のモデルであることさえ、陽菜にはお見通しのようだった。
陽菜は毎日、手作りの焼き菓子や、香りの良い紅茶をポットに入れて持ってきた。二人でそれを味わいながら、物語について語り合う時間は、次第に俺の日常にかけがえのないものになっていった。閉鎖的だった俺の世界に、陽菜という窓が開き、柔らかな光と風が流れ込んできたのだ。
気づけば、俺は陽菜に惹かれていた。彼女の屈託のない笑顔、時折見せる物憂げな表情、物語を語る時の熱っぽい眼差し。そのすべてが俺の心を掴んで離さなかった。この時間が永遠に続けばいい。そう願うようになっていた。
しかし、陽菜の正体は依然として謎のままだった。彼女は自分の過去を一切語らない。どこに住んでいるのか、何をしているのか、俺は何も知らなかった。彼女は、物語の霧の中から現れ、夕暮れと共に霧の中へ帰っていく、幻のような存在だった。
第三章 空蝉の告白
小説がクライマックスに差し掛かった、ある雨の日の午後だった。俺が書き上げた原稿を読んでいた陽菜の手が、ふと、陽光に透けるように薄くなった。俺は目を疑い、瞬きを繰り返した。気のせいかと思った。だが、一度意識してしまうと、彼女の存在そのものが、どこか現実離れして儚いものであることに気づかざるを得なかった。
「陽菜……?」
俺の声に、彼女は顔を上げた。その笑顔は、いつもよりずっと弱々しく見えた。
「湊さん、もうすぐですね。物語が終わるのが」
「なあ、君は一体、何者なんだ?もう隠すのはやめてくれ」
俺は彼女の肩に手を伸ばした。しかし、その指先は確かな感触を得る前に、するりと空を切った。触れようとした彼女の体は、陽炎のように揺らめき、向こう側の本棚が透けて見えた。
心臓が嫌な音を立てる。目の前で起きていることが信じられなかった。
陽菜は悲しげに微笑み、ついに真実を告げた。
「ごめんなさい。ずっと、言えなくて」
彼女の声は、雨音に溶けてしまいそうなくらい、か細かった。
「私は、あなたが書いているこの物語の登場人物なんです。『空蝉の庭』で、夏樹が最後に出会うはずだった、希望の象徴。それが、私の役でした」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。小説の、登場人物?
「あなたが十年前、書くのをやめてしまったから……私は生まれることも、結末を迎えることもできず、物語と現実の狭間をずっと彷徨っていました。あなたを見つけ出して、物語を完成してもらうことだけが、私の唯一の願いだったんです」
彼女の足元から、体がゆっくりと光の粒子になって霧散していく。存在が、不安定になっているのだ。
「物語が完成すれば、私は……私の役割は終わります。この世界から、消えるんです」
絶望が、全身を叩きのめした。なんだ、それは。そんな残酷な話があるか。
俺が愛した女性は、俺自身が生み出した幻だったというのか。そして、この愛しい時間を続けるために俺がしてきたことは、皮肉にも彼女を消滅させるための行為だったというのか。
「じゃあ、書くのをやめれば……!」
「だめです」陽菜は静かに首を振った。「未完のままでは、私の存在はどんどん希薄になって、いずれ、苦しみながら消えていくだけ。それなら、あなたの手で、ちゃんとした結末を与えてほしい。それが、私の……幸せだから」
俺は膝から崩れ落ちた。どちらを選んでも、待っているのは彼女との永遠の別れ。愛する人を、自分の手で消さなければならない。作家にとって、物語を完結させることは至上の喜びのはずだ。だが、今、俺の目の前にある原稿用紙は、死刑執行人がサインを待つ書類にしか見えなかった。
第四章 君のためのエピローグ
何日も、ペンを持つことができなかった。書けば陽菜が消える。書かなければ陽菜が苦しむ。答えの出ない問いが、鉛のように心を蝕んでいく。陽菜は日に日に透き通り、その笑顔も痛々しいほど儚くなっていった。
ある夜、ほとんど眠れずにいた俺の前に、陽菜がふわりと現れた。彼女は俺の震える手を取り、その冷たい指先でそっと包み込んだ。
「湊さん。怖がらないで」
「怖いさ!君がいなくなるなんて……耐えられない」
涙が、勝手に頬を伝った。
「私は、いなくならないよ」陽菜は優しく微笑んだ。「あなたの物語の中で、永遠に生き続ける。夏樹を救い、彼と共に笑い、幸せになる。それが、私が生まれた意味。あなたが与えてくれる、最高の人生です。だから、お願い。私に、最高の結末をください」
彼女の瞳は、覚悟を決めた者の強さで輝いていた。俺は、ようやく理解した。彼女を本当に愛しているのなら、俺がすべきことはただ一つ。彼女という存在が、たとえ物語の中であっても、最も美しく輝ける結末を、この手で紡ぐことだ。それは、彼女への、そして俺自身の救いになるはずだ。
俺は涙を拭い、万年筆を握りしめた。夜を徹して、最後の一行まで書き続けた。それは、絶望の中にいた夏樹が陽菜と出会い、再び愛を知り、時が止まっていた庭に新しい花を咲かせる物語。二人が永遠の愛を誓う、光に満ちたエンディングだった。
夜が明け、東の空が白み始めた頃、俺は書き上げた原稿を陽菜に手渡した。彼女はそれを受け取ると、一枚一枚、愛おしそうに読み進めていく。やがて最後のページを読み終えると、満ち足りた表情で顔を上げた。その頬には、一筋の光る涙が伝っていた。
「ありがとう、湊さん。これが、私の欲しかった結-末です」
朝日が窓から差し込み、彼女の体を優しく照らす。その瞬間、陽菜の体は眩い光の粒子となり、静かに舞い上がった。ありがとう、さようなら、愛してる。言葉にならない想いが、光の中に溶けていく。
光が消えた後、彼女が座っていた椅子の上には、一冊の真新しい本が残されていた。藍色の表紙に、金色の箔押しで『空蝉の庭』と記されている。俺が書き上げた、完成された物語だった。
あれから、五年が経った。
俺は小説家としてデビューし、今も物語を書き続けている。人付き合いを恐れていたかつての俺はもういない。陽菜との出会いと別れが、俺の心の壁を溶かしてくれたのだ。
新作の執筆に行き詰まると、俺は決まって本棚から『空蝉の庭』を取り出す。ページをめくれば、そこに彼女がいる。陽だまりのような笑顔で、夏樹の隣で幸せそうに微笑んでいる陽菜がいる。
彼女は、俺の物語の中で、そして俺の心の中で、永遠に生きている。
ふと、窓の外に広がる街の喧騒に目をやる。雑踏の中に、レモン色のワンピースを着た女性の姿が見えたような気がして、思わず息をのんだ。もちろん、見間違いだ。それでも、俺は小さく微笑んだ。
この世界は無数の物語でできている。そして、愛した記憶は、決して消えはしない。俺は新しい原稿用紙に向かい、万年筆を走らせる。彼女が教えてくれた愛と希望を、また新しい誰かに届けるために。僕の物語は、まだ始まったばかりだ。