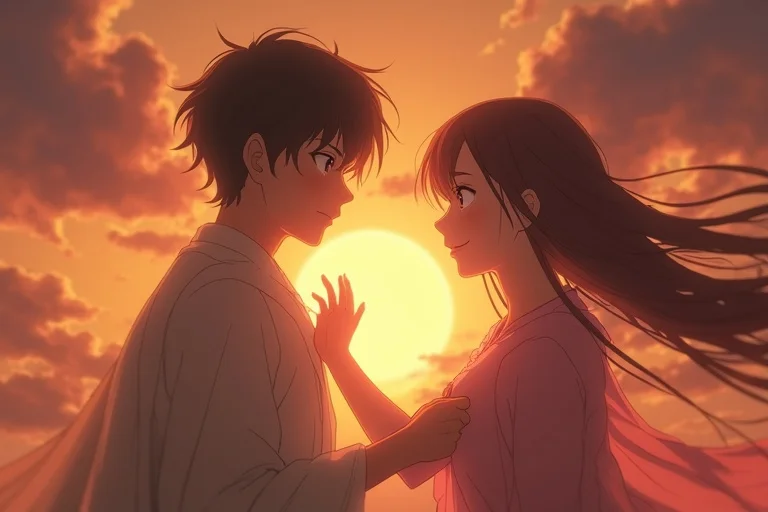第一章 甘美なる不協和音
僕、橘響(たちばな ひびき)の世界は、味で満ちている。それは比喩ではない。降りしきる雨音は舌の上でぱちぱちと弾ける炭酸水になり、ページをめくる乾いた音は香ばしいビスケットの味がする。僕は、音を味として感じる共感覚者だ。この特異な体質は、幼い頃から僕を世界から孤立させてきた。人々の喧騒は、腐った果物と錆びた鉄を無理やり口に詰め込まれるような苦行でしかなく、いつしか僕は静寂を求め、街の片隅にある古書店『言の葉堂』に住み着くように働いていた。インクと古い紙の、落ち着いたナッツのような味がする、そこが僕の唯一の聖域だった。
その日も、外は銀色の針のような雨が降り続いていた。店内に響く雨音は、いつもの優しい炭酸水の味。僕はカウンターの奥で、革表紙の傷んだ本を修繕していた。その時、ちりん、とドアベルが鳴った。雨粒を弾きながら入ってきたのは、黒いチェロケースを背負った女性だった。濡れた髪から滴る雫が、床の木材に染みを作り、ぽつ、ぽつ、というその音は、まるで小さな氷砂糖が舌で溶けるような、微かな甘さを運んできた。
「すみません、少し雨宿りさせていただけませんか」
その声を聞いた瞬間、僕は息を呑んだ。世界が、止まった。
これまで僕が味わってきたどんな音とも違う。それは、透明なアカシアの蜂蜜を煮詰め、そこに一滴だけミントのリキュールを垂らしたような、どこまでも澄み切っていて、それでいて胸の奥をくすぐるような、甘く切ない味だった。混沌としていた僕の世界に、初めて差し込んだ一筋の美しい旋律。僕は、生まれて初めて、他人の声をもっと聞いていたいと、心の底から願った。
彼女は奏(かなで)と名乗った。ストリートミュージシャンで、雨で演奏ができなくなり困っていたのだという。彼女が店内の椅子に腰掛けて話す間、僕はただ相槌を打つことしかできなかった。彼女の笑い声は、キャラメリゼした林檎のタルトのようだった。彼女が時折見せる憂いを帯びた表情は、ビターチョコレートの深みに似ていた。その一つ一つの音が、味覚が、僕の心を捉えて離さない。
雨が小降りになった頃、彼女は「お礼に」と言って、店の隅でチェロケースを開いた。湿った空気を震わせて紡がれた音色は、琥珀色のブランデーに漬け込んだドライフルーツのような、芳醇で温かい味がした。その味に満たされながら、僕は確信していた。これは、恋だ、と。僕の灰色だった世界に、たった一人、極彩色の味をもたらした彼女への、抗いがたい恋なのだと。
第二章 沈黙のデュエット
奏との日々は、まるで夢のようだった。僕は彼女の演奏がある公園のベンチに座り、彼女が紡ぎ出す音のフルコースに舌鼓を打った。陽気な曲は弾ける柑橘のソルベ、物悲しい曲は赤ワインのコンポート。そして何より、演奏の合間に僕に向けてくれる彼女の声。その蜂蜜とミントの味は、僕にとってどんな高級な食事よりも満ち足りたものだった。
奏もまた、僕の静けさの中に何かを見出してくれているようだった。
「響くんといると、心が凪いでいくみたい。騒がしい音が全部消えて、本当に大切な音だけが聴こえてくる感じ」
彼女がそう言って微笑むたび、僕は胸が締め付けられる思いだった。君が僕の世界にもたらしてくれた味のことを、どうして伝えられないのだろう。僕が君に惹かれている理由が、この奇妙な感覚のせいだと知ったら、君は僕を気味悪がるだろうか。その恐怖が、僕の口を貝のように閉ざさせた。
僕たちは多くの時間を共に過ごした。休みの日は二人で古い映画を観た。フィルムが回るカタカタという音は、炒った豆のような素朴な味がして、奏は「いい音」と言って隣で笑った。僕も彼女の隣で、彼女の声がもたらす甘美な味に浸りながら、頷いた。僕たちは違う感覚で世界を捉えている。それでも、同じ瞬間に「心地いい」と感じられることが、奇跡のように思えた。
この幸せが永遠に続けばいい。奏の隣で、彼女の声という名の旋律を味わい続けること。それが僕のささやかな、しかし最大の望みだった。僕は自分の共感覚の秘密を、美しい思い出を仕舞う小箱のように、心の奥底に隠し続けた。この秘密こそが、僕と彼女を繋ぐ細い糸であり、同時に、いつか僕たちを引き裂く刃になるかもしれないことも知らずに。
第三章 割れた音叉
その変化は、嵐の前触れのように突然訪れた。ある晴れた日の午後、奏が「新曲ができたの。最初に響くんに聴いてほしくて」と、少し興奮した面持ちで僕の店へやってきた。僕は胸を高鳴らせながら、彼女がチェロを構えるのを見守った。どんな素晴らしい味がするのだろう。金色の陽光が降り注ぐ午後だ。きっと、完熟した桃のコンフィチュールのような、とろける甘さに違いない。
しかし、弓が弦を捉えた瞬間、僕の舌を襲ったのは、想像を絶する味だった。
焦げた砂糖。それも、真っ黒になるまで煮詰めすぎた、苦くて、ざらついて、喉を焼くような不快な味。奏の指は情熱的に動き、紡がれるメロディは確かに力強く、美しいはずなのに、僕の感覚はそれを拒絶した。息が詰まる。吐き気がする。僕は必死でそれを顔に出さないように耐えたが、冷や汗が背中を伝った。
曲が終わった時、奏は「どうだった?」と期待に満ちた目で僕を見た。
僕は言葉に詰まった。「……すごい、曲だね」と、どうにか絞り出すのが精一杯だった。
その瞬間、僕の耳に届いた彼女の声は、もはや蜂蜜の味ではなかった。熟れすぎて腐りかけた果実のような、甘ったるい異臭を伴う、不快な味へと変貌していた。
その日を境に、全てが変わった。奏が何を話しても、僕の舌にはあの耐え難い味がまとわりついた。彼女の笑い声は、酸っぱくなったミルクのようだった。僕は無意識に彼女を避けるようになった。電話にも出られず、メッセージにも当たり障りのない返信しかできない。理由が分からない奏は戸惑い、傷ついているのが手に取るように分かった。それがまた、僕を苦しめた。
僕の感覚が壊れてしまったのか? それとも、僕の彼女への想いが、偽物だったというのか? 愛が冷めたから、こんな味に感じるのか? 疑念が渦巻き、自己嫌悪に陥った。
そんなある日、僕は公園で奏が見知らぬ男性と親しげに話しているのを見てしまった。楽しそうに笑い合う二人。その光景は、僕の心を真っ二つに引き裂いた。嫉妬という名の激しい炎が、僕の中で燃え盛る。その時、風に乗って聞こえてきた奏の声は、もはや味すらしなかった。ただひたすらに、舌が痺れるような、毒の味だけが残った。僕たちの世界は、完全に調律を失ってしまった。
第四章 心の調律
何日も奏からの連絡を無視し続けた僕に、言の葉堂の店主が静かに言った。
「響くん。言葉っていうのは、心の音叉みたいなもんだよ。ちゃんと鳴らして相手に聴かせなきゃ、どんな音色かなんて伝わりゃしないさ」
その言葉に、僕は顔を上げた。そうだ。僕は怖がってばかりで、一度も自分の音を鳴らそうとしなかった。たとえそれが不協和音だとしても、奏に伝えなければならない。僕は震える足で、店を飛び出した。
奏は、いつもの公園で、俯きながらチェロの弦を調整していた。その姿はひどく小さく、儚げに見えた。
「奏さん」
僕の声に、彼女は驚いて顔を上げる。その瞳が不安に揺れるのを見て、僕はもう逃げないと決めた。僕は、全てを話した。僕が音を味として感じること。初めて会った日、彼女の声がどれほど美しい味がしたか。そして今、それが耐え難い苦い味に変わってしまったこと。支離滅裂だったかもしれない。けれど、僕は必死で心の音叉を鳴らした。
奏は、黙って僕の話を聞いていた。僕が話し終えると、彼女は静かに口を開いた。
「……そうだったんだ。響くんの世界は、そんな風に聴こえていたんだね」
彼女の声は、まだ少し苦かった。でも、その奥に、ほんの少しだけ、昔の蜂蜜の香りがした。
「あの新曲ね、去年亡くなった兄のために書いた曲なの。私のせいで死なせてしまったっていう後悔と、音楽家としての焦り…そういう、私の全部の苦しさを詰め込んだ曲。だから…苦い味がしたのかもね」
そして、公園で話していた男性は、兄の友人で音楽プロデューサーなのだと教えてくれた。奏もまた、僕に言えない苦悩を一人で抱えていたのだ。
その瞬間、僕は雷に打たれたように悟った。
僕が感じていたのは、彼女の「声」の味ではなかった。彼女の「心」の味だったのだ。彼女の悲しみや苦悩を、僕の感覚は正直に「焦げた砂糖」として受け取っていた。そして、僕自身の嫉妬や疑念が、その味をさらに歪め、「毒」に変えてしまっていたのだ。
「ごめん…ごめん、奏さん。僕は君の苦しみに気づけず、自分の感覚ばかりに囚われて…」
「ううん」奏は首を横に振った。「私も、響くんに何も話さなかった。苦しいって言えなかった。…ねえ、響くん。もう一度、聴いてくれる?」
彼女はチェロを構え、僕たちが初めて出会った日に弾いてくれた、あの曲を奏で始めた。
その音色は、澄み切った蜂蜜の味がした。でも、以前とは少し違っていた。そこには、雨上がりの湿った土のような、深くて温かい香りが混じり合っていた。苦しみを乗り越えた、生命の味がした。
演奏を終えた奏が、僕を見て微笑む。
「響くん」
その声は、まだ微かな苦味を残していた。けれど、その奥には、紛れもないあの蜂蜜とミントの甘さが、確かに存在していた。
僕は、もう完璧な味を求めないだろう。彼女の喜びは甘く、悲しみは苦く、不安は酸っぱいのかもしれない。それでいい。それこそが、奏という人間の、かけがえのない味なのだ。僕は、その全てを味わっていきたい。
僕たちは、どちらからともなく手を繋いだ。彼女の手は温かかった。僕の世界は、今、無数の味が複雑に混じり合った、豊かで愛おしいシンフォニーを奏で始めた。それはきっと、僕と彼女がこれから二人で紡いでいく、愛の味だった。