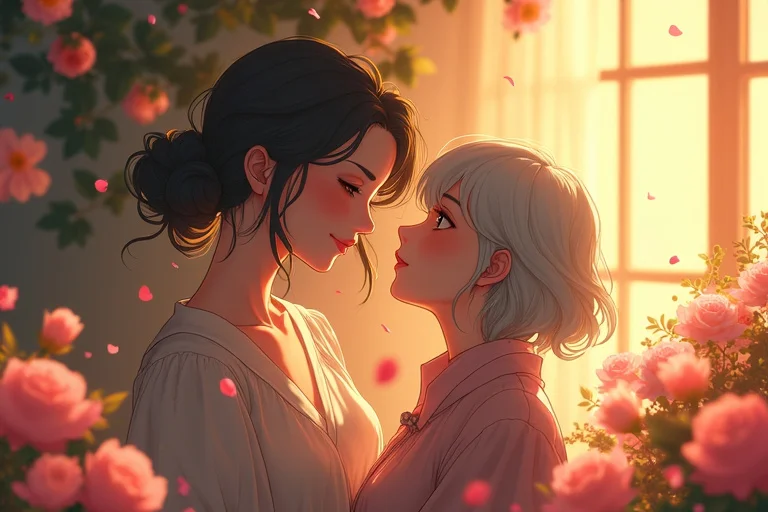第一章 沈黙のアルペジオ
俺の世界は、絶え間ない騒音で満ちている。
それは耳で聞く音ではない。魂に直接流れ込んでくる、感情の不協和音だ。三年前の事故で、俺は声を出す能力と、言葉を組み立てる能力のほとんどを失った。その代償のように手に入れたのが、この忌まわしい共感覚だった。
怒りは耳障りな金切り声。喜びは安っぽいシンセサイザーのメロディ。悲しみは単調なドローンの響き。街を歩けば、人々の無数の感情が濁流のように押し寄せ、俺の意識を削り取っていく。だから、俺はいつもノイズキャンセリングヘッドホンを装着し、分厚い壁の内側で息を潜めるように生きていた。かつて、指先から無限のメロディを生み出していた作曲家の面影は、もうどこにもない。
その日も、俺は図書館の片隅で、静寂という名のシェルターに逃げ込んでいた。分厚い哲学書を開いてはいたが、その内容は一行も頭に入ってこない。ただ、ヘッドホンの性能に感謝しながら、世界の音を遮断していた。
不意に、すぐ近くで小さな悲鳴と本が床に散らばる音がした。視線を上げると、一人の女性が、崩れた本の山を前にして途方に暮れていた。図書館司書だろうか、エプロンをつけた彼女は、慌てて本を拾い集めようとしている。
他の利用者たちの感情が、好奇心という名の不躾なトランペットの音色を奏で始める。俺は舌打ちし、立ち上がった。見て見ぬふりをするのは性に合わない。彼女の前に屈み込み、散らかった本を拾い始めた。
「あ、すみません……」
彼女が小さな声で言った。その声が鼓膜を震わせた瞬間、異変が起きた。
ヘッドホンが遮断しているはずの外界から、一つの音が、クリアに、そして優しく俺の意識に染み込んできたのだ。それは、これまで聴いたどんな感情の音とも違っていた。木漏れ日が降り注ぐ森の奥深くで、誰かが静かに爪弾くピアノのアルペジオ。澄み切っていて、どこまでも穏やかで、温かい。他のあらゆる感情のノイズを浄化していくような、聖域の響き。
俺は顔を上げた。目の前の彼女――千尋(ちひろ)と、その時初めて目が合った。彼女の瞳は、まるで静かな湖面のようだった。彼女の周りだけが、この騒がしい世界から切り取られたかのように、静謐な音楽に満ちていた。
俺は言葉を失ったあの日から、初めて、他人の存在を美しいと感じていた。
第二章 ふたりだけのソナタ
その日を境に、俺の足は吸い寄せられるように図書館へと向かった。響(ひびき)という自分の名前すら、もう音楽とは何の関係もないただの記号だと思っていた。だが、彼女――千尋の奏でる音楽に触れるたび、俺の内の枯れた泉から、再び何かが湧き上がってくるのを感じた。
俺は話せない。だから、コミュニケーションはもっぱらスマートフォンのメモ帳機能を使った筆談だ。最初こそ戸惑っていた千尋だったが、すぐに慣れた様子で、柔らかな笑顔で俺の拙い文章に応えてくれた。
『いつも難しい本を読んでいますね』
彼女がそう打ち込むと、俺の頭の中では軽やかなフルートのメロディが響く。それは純粋な興味の音色だった。
『音楽を失った人間が、言葉の森で迷子になっているだけです』
俺がそう返すと、彼女の音楽は少しだけ調子を落とし、チェロのような深く、そして優しい音色に変わった。同情ではない。ただ静かに寄り添うような、共感の響きだった。
彼女と過ごす時間は、奇跡のようだった。彼女がそばにいるだけで、世界を埋め尽くす不協和音が嘘のように遠のき、彼女の奏でるピアノのアルペジオだけが、心地よいBGMとして俺を包み込む。彼女が微笑めばワルツが始まり、本について熱心に語れば情熱的なソナタが聴こえた。俺は、彼女の感情そのものを聴いているのだと信じて疑わなかった。
いつしか、俺は自分の内側にも変化が起きていることに気づいた。千尋の音楽に応えるように、俺の心の中で新しいメロディが生まれ始めていたのだ。それは、事故以来、完全に凍り付いていたはずの創作意欲の芽生えだった。
彼女に恋をしている。
その自覚は、苦しいものではなく、むしろ救いだった。この感情は、千尋が奏でる音楽への愛着なのだと。彼女という人間そのものが、俺にとって最高の楽曲なのだと。
ならば、俺にできることは一つしかない。俺の感情もまた、音楽で伝えるのだ。言葉を失った俺に残された、唯一の言語で。
俺は、何年も触れていなかったピアノの前に座った。そして、千尋のためだけの曲を書き始めた。彼女のアルペジオに応える、俺の心の旋律を。それは、沈黙の世界で出会った二人が、魂で対話するデュエットになるはずだった。
第三章 不協和音の真実
図書館で開かれる小さな朗読会の後、特別にピアノを弾かせてもらえることになった。千尋に、この曲を届けたかった。俺が作ったメロディに、彼女のアルペジオがどう共鳴するのか。それを確かめたかった。
当日の夜、ホールの照明が落ち、スポットライトがグランドピアノを白く照らし出す。客席の最前列に、千尋が少し緊張した面持ちで座っているのが見えた。彼女からは、期待と優しさが入り混じった、繊細なハープの調べが聴こえてくる。俺は深呼吸し、鍵盤に指を置いた。
弾き始めは、静かな夜明けのように。俺たちの出会い。彼女から聴こえてきた、あの澄み切ったアルペジオを模倣したフレーズから入る。指が鍵盤の上を滑るたびに、俺の想いが音になって溢れ出していく。
曲は次第に熱を帯びていく。彼女と過ごした日々の喜び、安らぎ、そして募る愛情。俺の内側で鳴り響く感情のすべてを、メロディに乗せた。千尋の音楽も、俺の演奏に呼応するように、より一層輝きを増していく。二つの魂が、音楽の中で完璧に溶け合っていく感覚。これ以上ないほどの幸福感に包まれながら、俺は演奏のクライマックスへと突き進んだ。
そして、最後の和音を力強く鳴らした、その瞬間だった。
――ザァァァッ……!
突如、世界からすべての音が消え、耳鳴りのような激しいノイズが頭蓋を揺さぶった。千尋から流れ込んでいた美しい音楽が、まるで壊れたラジオのように、不快な砂嵐に変わる。
何が起きた? 俺は混乱し、鍵盤を押さえたまま凍り付いた。
そして、そのノイズの向こう側から、生まれて初めて、他人の「声」が直接、俺の脳内に響き渡った。
『すごい……なんて、綺麗な曲。でも、ごめんなさい。私には、あなたの悲しみが、わからない』
千尋の……声?
違う。これは彼女の本当の感情だ。俺が今まで聴いていた美しい音楽はなんだ? あれは、彼女の感情ではなかったのか?
血の気が引いていく。全身が冷たくなっていく。俺は悟ってしまった。絶望的な真実を。
千尋から聴こえていた、あの澄み切ったピアノのアルペジオは、彼女の感情ではなかった。それは、俺の脳が、俺自身の願望が生み出した幻聴だったのだ。彼女を「理解したい」「特別な存在であってほしい」と強く願うあまり、俺が勝手に作り上げた、理想の音楽。
彼女の本当の感情は、他の人々と同じ、俺の能力では捉えきれない、断片的なノイズの集合体だった。俺が愛していたのは、千尋本人ではなく、俺が作り出した「千尋という名の音楽」だったのだ。
客席から拍手が沸き起こる。だが、俺の耳には届かない。世界は再び、意味不明な騒音と、そして何より耐え難い、完全な沈黙に引き裂かれていた。
第四章 世界が再び鳴り響く
演奏を終え、亡霊のように舞台袖に戻った俺の元へ、千尋が駆け寄ってきた。彼女の瞳は潤み、その表情は心からの感動を伝えているように見えた。
『素晴らしかった。涙が出たわ』
彼女はそうスマートフォンに打ち込んで見せた。だが、今の俺には、彼女から何の音も聴こえない。ただ、背後でざわめく人々の感情のノイズが、無遠慮に響くだけだ。彼女の周りを満たしていた、あの聖域のような静寂は、もうどこにもなかった。
絶望が胸を抉る。俺が捧げた音楽は、独りよがりの幻想に過ぎなかった。俺は彼女の何も理解していなかった。特殊な能力があるからと、理解した気になっていただけの、傲慢な男だった。
千尋が心配そうに俺の顔を覗き込む。その時、俺はふと気づいた。
幻の音楽は消えた。だが、目の前には、確かに千尋がいる。感動で頬を赤らめ、俺を心から心配してくれる、一人の人間がいる。俺が惹かれたのは、本当に、あの音楽だけだったのだろうか?
違う。
俺が好きになったのは、俺の障害を特別視せず、当たり前のように受け入れてくれた彼女の優しさだ。本について語る時の、知的な横顔だ。時折見せる、不器用で可愛らしい仕草だ。それらすべてが合わさって、俺の中で「千尋」という存在を形作っていた。音楽は、その結果として生まれた、俺自身の願望の反映に過ぎなかった。
俺は、音に恋をしていたんじゃない。千尋という人間に恋をしていたんだ。
能力に頼り、相手を知ったつもりになるのは間違いだった。本当のコミュニケーションとは、そんな安易な道ではない。たとえ言葉がなくても、音が聴こえなくても、相手の心に寄り添おうと、必死に手を伸ばし続けることじゃないのか。
俺は震える指で、スマートフォンを取り出した。そして、これ以上ないほど真剣な想いを込めて、文字を打ち込んだ。
『もう一度、あなたのことを教えてください。今度は、音じゃなく、あなたの言葉で』
千尋は一瞬、きょとんとした顔をした。だが、すぐにその意味を察したのか、ふわりと、これまでで一番優しい微笑みを浮かべた。そして、静かに、しかし力強く、こくりと頷いた。
俺の世界には、相変わらず無数の感情のノイズが溢れている。それは時として苦痛だ。だが、もう絶望はしない。不協和音も、美しいメロディも、すべてがこの世界を構成する音なのだ。
そして何より、その無数のノイズの向こう側に、これから俺が知っていくべき、たった一人の大切な人がいる。
幻のデュエットは終わった。
ここから始まるのは、言葉を探し、互いの心に耳を澄ませる、本当の意味での、俺たち二人の対話なのだ。夕暮れの光が差し込むホールで、俺たちの世界は、再び静かに鳴り響き始めていた。