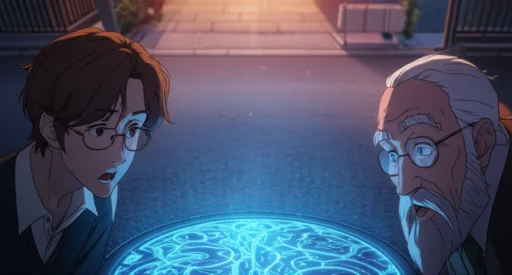第一章 感情のない朝
水野朔(みずの さく)の一日は、いつだって過去の自分からの引き継ぎ業務で始まる。ベッドから抜け出すと、まず机に向かい、昨日の自分が残した「業務日誌」を開く。A5サイズのノートには、几帳不精な彼の性格に似合わぬ、几帳面な文字が並んでいた。
『十月十七日(火)天気:晴れ。
午前:出勤。古書店の店番。常連の佐藤さんが珍しい初版本を持ってきた。鑑定を頼まれる。
午後:大学時代の友人、橘千尋と駅前のカフェで偶然再会。卒業以来か。広告代理店で働いているらしい。近々食事に行く約束をした。
特記事項:再会は予期せぬ出来事だったが、非常に嬉しかった。懐かしさで胸が温かくなる感覚。佐藤さんの本は贋作の可能性が高い。残念。』
朔は、書かれた事実を一つ一つ、頭の中にインストールしていく。日付、天気、出来事。まるで他人の一日を追体験するようだ。いや、体験ですらない。ただのデータ入力だ。
彼には、毎朝目覚めるたびに、前日までの「感情」の記憶だけが綺麗に抜け落ちるという、奇妙な体質があった。嬉しかったことも、悲しかったことも、腹が立ったことも、その肌触りや温度、心の震えだけが、夜の間に漂白されてしまう。だから、この日誌は彼にとって命綱だった。自分が何を感じたのか。それを知る唯一の手段。
「嬉しかった、か」
朔は呟き、コーヒーを一口すする。苦い液体が喉を滑り落ちるだけで、そこに何の感慨も湧かない。「胸が温かくなる感覚」という記述を読んでも、体温は上がらなかった。千尋という女性の顔は思い出せる。彼女の快活な笑顔も。だが、その笑顔を見て自分の心がどう動いたのか、その実感だけがすっぽりと抜け落ちている。まるで、音声の消えた映画を見ているような、もどかしい静寂が常に彼の内面を支配していた。
だから彼は、感情を信用しない。事実だけを積み重ね、客観的に分析し、今日の自分がどう振る舞うべきかを決定する。それが、この欠陥を抱えた彼が、社会で生きていくための処世術だった。
だが、今朝はどこか違った。
日誌を読む前から、彼の胸には奇妙な空洞が広がっていた。それはいつもの空っぽな感覚とは違う。何かを、確かにそこにあったはずの大切な何かを、根こそぎ奪われたような、疼くような喪失感。体の芯が冷たく、重い。
朔は眉をひそめ、もう一度日誌を読み返した。千尋との再会。初版本。日常の断片。どこにも、この激しい喪失感の源になるような記述は見当たらない。昨日の自分は「嬉しい」と「残念」を感じただけのはずだ。この、胸を抉るような痛みは、いったいどこから来たのだろう。
それは、彼の完璧に構築された自己管理システムに生じた、初めてのエラーだった。理由の分からない感情。それは、朔にとって未知のバグであり、静かな日常を侵食する、不穏な兆しのようだった。
第二章 空白のセンチメント
正体不明の喪失感は、幽霊のように朔の日常に憑きまとった。古書店のカウンターに座り、ページを繰る指先に集中しようとしても、ふとした瞬間に、心にぽっかりと空いた穴から冷たい風が吹き込んでくる。古い紙の匂い、インクの香り、静寂を破る客の咳払い。五感で捉える情報はいつもと同じなのに、そのすべてが、彼の内側の空虚さを際立たせる背景音にしかならなかった。
「この喪失感は、どこから来たんだ?」
彼は業務日誌の過去のページを何度もめくった。数年前まで遡っても、これほど強い負の感情を引き起こすような記述はない。彼の記録は完璧なはずだった。彼は自分の感情を、まるで昆虫標本のように正確に記録し、分類してきたのだから。
もしかしたら、記録していない出来事があったのだろうか。無意識の領域で、何かが起きたのか。考えを巡らせていると、店のドアベルがちりん、と鳴った。
「水野くん、いる?」
聞き覚えのある、明るい声。顔を上げると、橘千尋が笑顔で立っていた。ベージュのトレンチコートが、彼女の快活な雰囲気に良く似合っている。
「橘さん」
「やっぱり。この辺だって聞いてたから、近くに来たついでに寄ってみた」
千尋は興味深そうに店内を見回し、それから朔に向き直った。「この前の、食事の約束なんだけど、今週の金曜なんてどうかな?」
朔は一瞬、言葉に詰まった。日誌には「食事の約束をした」とある。だが、その時の高揚感や期待といった感情の裏付けが、彼にはない。ただの約束という事実データがあるだけだ。
「……ああ、金曜日。大丈夫だ」
「よかった!じゃあ、また連絡するね」
手を振って去っていく千尋の背中を見送りながら、朔は再び胸の痛みを感じた。なぜだろう。彼女の笑顔は、日誌に書かれていた「嬉しい」という感情を呼び覚ますはずなのに、むしろ胸の空洞を広げるような気がした。
その夜、朔は自分の部屋を徹底的に調べ始めた。この喪失感は、外部からのトリガーによって引き起こされているのかもしれない。本棚、机の引き出し、クローゼット。彼の持ち物は多くない。どれもこれも、彼にとってはただの「物」であり、特別な思い入れがあるものは一つもなかったはずだ。
彼は手を止め、窓の外に広がる夜景を見つめた。街の灯りが、まるで遠い銀河のように瞬いている。綺麗だ、と頭では理解できる。だが、その光景が彼の心を揺さぶることはない。
感情を失い続けるということは、世界との繋がりを一つずつ断ち切られていくようなものだ。人々が共有する感動や共感の輪から、自分だけが弾き出されている感覚。彼はその孤独に慣れていたはずだった。なのに、今感じているこの喪失感は、彼が失ったものが、単なる日々の喜怒哀楽だけではないと告げているようだった。
もっと根源的な、自分という存在を形作っていたはずの、決定的な何かを失ってしまったのではないか。
その予感が、鉛のように彼の心を沈ませていった。
第三章 木箱の慟哭
喪失感の原因究明は、暗礁に乗り上げていた。朔はまるで、腕のいい探偵が自身の記憶喪失事件を捜査するような、奇妙な自己探求に没頭していた。しかし、どんなに過去の日誌を読み解いても、部屋の隅々を探しても、決定的な物証は見つからなかった。
諦めかけたその時だった。クローゼットの奥、普段は使わない旅行鞄のさらに後ろに、小さな木箱が隠れるように置かれているのを見つけた。埃をかぶったその箱に、朔は全く見覚えがなかった。いつからここにあったのだろう。
彼はそれを手に取り、そっと蓋を開けた。
瞬間、彼の全身を凄まじい衝撃が貫いた。それは感情の津波だった。悲しみ、後悔、愛おしさ、そして絶望。言葉にならない感情の濁流が、彼の内側で乾ききっていた川に一気になだれ込み、防御していた理性の堤をいとも簡単に決壊させた。
「う……っ、ぁ……」
声にならない呻きが漏れ、朔はその場に膝から崩れ落ちた。息ができない。胸が張り裂けそうだ。この痛みは、彼が今まで経験したことのない、魂そのものの慟哭だった。
涙で滲む視界の中、箱の中身がぼんやりと見えた。一枚の、手書きの楽譜。そして、小さな銀色の鈴。
それらを目にした途端、閉ざされていた記憶の扉が、軋みながら開いていく。
フラッシュバックする光景。ピアノに向かう、自分より少し小さな背中。軽やかに鍵盤を踊る指。振り向いた時の、屈託のない笑顔。
『お兄ちゃん、聴いて!新しい曲、できたんだ!』
妹だ。数年前に事故で亡くなった、妹の詩織(しおり)の記憶。
彼は、忘れていたのではない。耐えられなかったのだ。妹を失ったという事実と、それに伴う激烈な感情のすべてを、無意識のうちに記憶の奥底へ封印していたのだ。あまりに強すぎる感情は、彼の日々の記憶処理能力を遥かに超えていた。だから、日誌に書くことすらできなかった。いや、書かないことで、自分を守っていたのだ。
毎朝失っていたのは、前日の感情だけではなかった。彼は、詩織を失ったあの日からずっと、彼女に関するすべての感情を「失い続けて」いたのだ。そして、この木箱に封じ込めた感情の断片が、何かのきっかけで漏れ出し、理由の分からない「喪失感」として彼の心を苛んでいた。この箱は、彼の失われた感情のアーカイブだったのだ。
朔は、震える手で楽譜を拾い上げた。インクが滲んだ五線譜の上には、拙いながらも優しさに満ちたメロディーが記されていた。タイトルは『お兄ちゃんのためのレクイエム』。
彼は嗚咽した。感情を失うはずの自分が、これほどまでに涙を流すなんて。それは、凍てついた大地が初めて春の陽光を浴び、雪解け水として溢れ出すような、痛みを伴う再生の瞬間だった。彼は妹を失った悲しみを、そして、彼女を深く、深く愛していたという温かい感情を、数年越しにようやく取り戻したのだ。
第四章 明日のためのレクイエム
朔は、千尋に連絡を取った。震える声で、妹の楽譜のことを話すと、彼女は驚きながらも、すぐに事情を察してくれた。彼女は音楽系のイベントを手掛ける仕事をしており、ツテを頼って、小さなホールでピアノリサイタルを開く機会を作ってくれたのだ。
リサイタルの日。客席はまばらだったが、その中央に、朔は一人で座っていた。ステージ上のグランドピアノの前に、千尋が紹介してくれた若いピアニストが座り、静かに鍵盤に指を置く。
一音目が響いた瞬間、朔の世界は一変した。
優しいピアノの旋律が、ホールを満たしていく。それは、詩織がすぐ隣で語りかけてくるような、温かく、そしてどこか切ないメロディーだった。
記憶が、感情が、奔流となって彼の中に流れ込んでくる。公園で一緒に遊んだ日の、草の匂い。喧嘩して、彼女を泣かせてしまった時の罪悪感。彼女がコンクールで入賞した時の、胸を張るような誇らしさ。そして、病院の白いベッドで、冷たくなっていく彼女の手を握りしめた時の、無力感と絶望。
全ての感情が、痛みと愛おしさを伴って蘇る。それは、彼の体質が許さなかった、過去との連続性を取り戻す儀式だった。彼はもう、音声の消えた映画を見ている傍観者ではない。自らの人生の主人公として、その喜びも悲しみも、すべて引き受ける覚悟を決めた。涙が、彼の頬をとめどなく伝った。それは、失われたものへの追悼であり、取り戻したものへの感謝の涙だった。
演奏が終わり、静寂がホールを包む。朔は立ち上がり、深く頭を下げた。ピアニストにでも、千尋にでもない。天国にいる妹への、心からの感謝だった。
朔の日常は、あの日を境に変わった。
彼の体質は、治らなかった。翌朝、目覚めた彼の心は、やはりリサイタルの感動を忘れて、いつものように静まり返っていた。しかし、彼はもう絶望しなかった。机の上には、昨日までの日誌とは別に、新しいノートが開かれている。彼はそこに、震える手で、あふれんばかりの言葉を書き記した。
『十月二十五日(金)。詩織の曲を聴いた。言葉にできないほど、心が揺さぶられた。悲しくて、でも、信じられないくらい温かかった。詩織、ありがとう』
彼は立ち上がり、窓を開ける。朝の冷たい空気が、彼の頬を撫でた。
忘れてしまうだろう。明日になれば、この感動の肌触りも、胸の震えも。だが、それでいい。
彼はクローゼットからあの木箱を取り出し、中の鈴をそっと手に取った。ちりん、と澄んだ音が鳴る。その音色を聴けば、楽譜を開けば、彼はいつでも妹を思い出し、この胸を焦がすほどの愛しさを取り戻すことができる。
感情は、消えてなくなるものではない。たとえ忘れてしまっても、大切な場所にしまっておける宝物なのだ。
朔は、机の上のノートに視線を落とした。それはもはや、単なる業務日誌ではなかった。失われた感情を取り戻すための、未来の自分へと宛てた、希望の地図だった。
彼の「日常」は、色褪せた記録の連続ではない。何度でも輝きを取り戻せる、豊かな物語として、今、新たに始まろうとしていた。