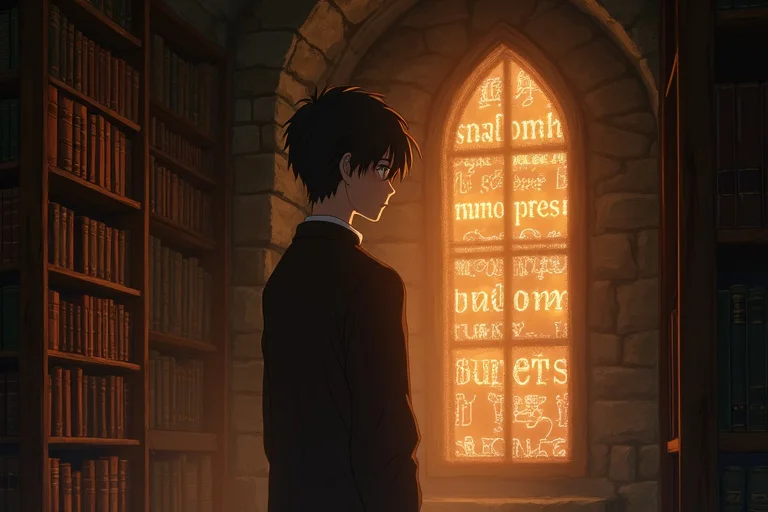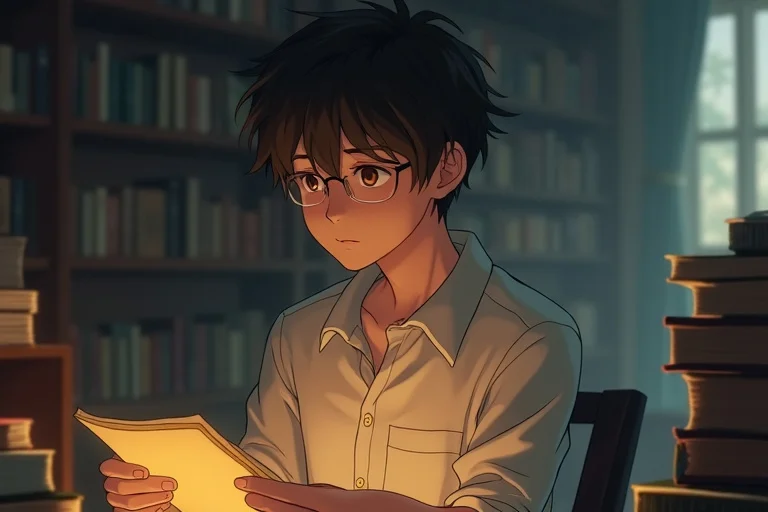第一章 不在の壁、あるいは出現した扉
高槻健司の日常は、寸分の狂いもなく繰り返されるデジタル時計の表示に似ていた。朝六時半にアラームが鳴り、七時十五分に玄関のドアを開け、七時三十七分発の準急電車に乗る。それが、彼の三十四年間の人生がたどり着いた、最適化されたルーティンだった。車窓から流れる風景は、すでに脳の記憶野に焼き付いた壁紙のように、何の感情も揺さぶらない。くすんだビル群、錆びた鉄橋、そして、次の駅の手前で速度が落ちる辺りに広がる、雑草だらけの広大な空き地。
その日も、健司は吊革にぶら下がり、スマートフォンの画面を無心でなぞっていた。ふと顔を上げた瞬間、彼は目を疑った。いつもはただ緑の雑草が風に揺れているだけの空き地の、ちょうど真ん中あたりに、ぽつんと「それ」はあった。
木製の、古びたドアだった。
壁も、柱も、それを支えるものは何一つない。ただ、ドアだけが、まるで異世界への入り口のように、そこに自立していた。健司は瞬きをした。寝不足のせいか。昨夜遅くまで続いたシステムの改修作業で、目が疲れているのかもしれない。しかし、電車がゆっくりと通り過ぎる間、そのドアは幻のように消えることはなく、確かな実体を持ってそこに存在し続けていた。焦げ茶色のペンキは所々剝がれ落ち、真鍮製の丸いドアノブが、朝の低い光を鈍く反射している。
周囲の乗客は誰も気づいた様子はない。誰もがスマホの画面か、虚空か、あるいは自分の靴先を見つめている。健司だけが、世界に開いたバグのようなその光景に釘付けになっていた。
翌日。健司は、昨日の出来事が夢ではなかったことを確認するために、いつもより少しだけ早く家を出た。同じ車両の、同じ位置に立つ。心臓が妙に速く打つのを感じた。電車が例の空き地に差しかかる。そこには、昨日と寸分たがわぬ姿で、ドアが立っていた。
非現実的な光景が、二日連続で彼の日常に侵食してきた。それは、正確無比だったデジタル時計の液晶に、ひとつだけ表示されるはずのないピクセルが点灯したような、小さな、しかし無視できない違和感だった。健司の退屈で灰色だった日常に、初めて鮮やかな問いが投げかけられた。あのドアは、一体何なのだろうか。
第二章 錆びた蝶番の沈黙
ドアの存在は、健司の心をじわじわと蝕んでいった。仕事中も、ディスプレイに並ぶコードの羅列が、いつの間にかドアの木目に見えてくる始末だった。これまで完璧にこなしてきたはずの業務で、些細なミスが目立つようになった。同僚から「高槻さん、最近ぼーっとしてない?」と心配されるほどに、彼の意識は空き地のドアに囚われていた。
あのドアの向こうには何があるのだろう。開けたら、どこか違う世界に繋がっているのだろうか。それとも、ただドアの向こう側に、同じ空き地が続いているだけなのか。考えれば考えるほど、無数の仮説が頭の中を駆け巡り、彼の平穏をかき乱した。
一週間が経った土曜日の朝、健司はついに決意した。普段なら昼過ぎまで惰眠を貪る彼が、平日のように早く目を覚まし、Tシャツとジーンズというラフな格好でアパートを出た。目的地は、もちろんあの空き地だ。
電車を乗り継ぎ、地図アプリを頼りに、彼は初めてその場所に降り立った。線路沿いの道を歩くと、記憶の中の風景が目の前に広がる。テレビゲームの世界に迷い込んだかのような、奇妙な感覚だった。空き地はフェンスで囲われていたが、一部が破れており、簡単に入ることができた。夏の終わりの生暖かい風が、丈の高い雑草を揺らし、ざわざわと音を立てている。
そして、その中心に、ドアはあった。
間近で見ると、それは想像以上に現実感を伴っていた。長年の風雨に晒された木の質感、ところどころにこびりついた土埃、錆びて赤茶色になった蝶番。健司は恐る恐る手を伸ばし、ざらついたドアの表面に触れた。ひんやりとしていて、硬い。間違いなく、本物のドアだ。
彼はごくりと唾を飲み込み、真鍮のドアノブに手をかけた。冷たく、重い感触が手のひらに伝わる。鍵はかかっていないようだ。ノブはゆっくりと回り、カチャリ、と小さな金属音が響いた。あとは、引くだけ。この行為の先に何が待っているのか。彼の日常を根底から覆すような、何かがあるのかもしれない。
しかし、健司の指はそこで凍り付いた。怖い。日常から逸脱することが、これほどまでに恐ろしいことだとは。彼は数分間、ドアノブを握りしめたまま立ち尽くしたが、結局、ドアを開けることはできなかった。錆びた蝶番は、沈黙を守ったままだった。彼は静かに手を離し、逃げるようにその場を後にした。背後で、ドアは相変わらず、何事もなかったかのように佇んでいた。
第三章 老人と妻と希望の残骸
ドアを開けられなかった自分への不甲斐なさと、日に日に増していく好奇心との間で、健司の心は引き裂かれそうだった。彼は翌週の日曜日、再びあの空き地を訪れた。今日こそは。その一心で、彼は固くドアを見据えた。
彼がドアノブに再び手をかけようとした、その時だった。
「そのドア、開けてみるのかい?」
しゃがれた、しかし穏やかな声が背後から聞こえ、健司は心臓が飛び上がるほど驚いた。振り返ると、日に焼けた皺深い顔の老人が、柔和な笑みを浮かべて立っていた。手には小さな園芸用のシャベルを持っている。どうやら、近くの家庭菜園で作業をしていたらしい。
「あ、いえ……これは、一体……」
しどろもどろになる健司に、老人は「まあ、座りなさい」と、そばにあったコンクリートブロックを指さした。健司が腰を下ろすと、老人もその隣にゆっくりと腰を下ろした。
「わしも、最初は驚いたよ。ある朝、突然こんなものが出来ていたんだからな」と老人は笑った。「だが、今ではすっかりこの辺りの名物さ。誰も、なぜここにあるのかは知らんようだがね」
「ご存じないんですか?」
老人は首を横に振ると、遠い目をしてドアを見つめた。「いや、知っているよ。わしが作ったんだから」
健司は息をのんだ。目の前の穏やかな老人が、この不可解なオブジェの製作者だというのか。
「……どうして、こんな場所に?」
老人は少し黙り込んだ後、ぽつりぽつりと語り始めた。「五年前に、女房を亡くしてね。最後の二年ほどは、病気でほとんど家から出られなかった。あの家さ」と老人が指さしたのは、空き地を見下ろす丘の上に建つ、一軒の小さな家だった。「女房はな、毎日あの二階の窓から、この空き地を眺めていた。そして、よくこう言っていたんだ。『ねえ、あなた。あの空き地の真ん中に、ぽつんとドアがあったら素敵じゃない? きっと、どこか綺麗な海辺の町に繋がってるのよ』ってな」
老人の声は、懐かしさと切なさが滲んでいた。
「ただの冗談だと思っていたさ。だが、女房が逝っちまってから、その言葉がどうにも頭から離れなくてな。わしは昔、大工をやってたんもんで、腕はまだ鈍っちゃいない。だから、作ったんだ。女房が見たがっていたドアを。あいつが好きだった、古い洋館にあるようなドアをな」
健司は言葉を失った。彼がSFやファンタジーのような突飛な想像を巡らせていたドアは、一人の男が亡き妻へ捧げた、途方もなく深く、静かな愛の結晶だったのだ。
「開けても、何もないよ」と老人は続けた。「ドアの向こうには、同じ景色が広がっているだけだ。わかっていても、作りたかった。あいつが夢見た『どこかへ行けるかもしれない』という希望を、形にしてやりたかったんだ。まあ、わしにとっては、墓標みたいなもんだな」
健司の胸に、熱い塊がこみ上げてきた。自分の退屈な日常。意味のないルーティン。そんなちっぽけな悩みがいかに矮小なものであったか、思い知らされた。このドアは、ただの奇妙な物体ではない。誰かの人生そのものであり、愛と喪失の物語が、その木目に深く刻み込まれていたのだ。
第四章 始発の風景
「ありがとうございました」
健司は深く頭を下げた。老人は「いやいや」と手を振り、「またいつでも見に来ておやり」と笑って、自分の畑へと戻っていった。健司はもう一度ドアに向き直った。しかし、もうドアノブに手をかけようとは思わなかった。そこは、自分のような部外者が踏み込んではいけない、老夫婦だけの聖域なのだと感じたからだ。彼は静かに一礼し、その場を去った。
翌朝、健司はいつもの準急電車に乗っていた。車窓に流れる風景は同じはずなのに、彼の目には全く違って映っていた。やがて、例の空き地が見えてくる。そこに佇むドアは、もはや不気味なオブジェではなかった。それは、朝の光の中で、温かい光輪をまとっているかのように見えた。誰かの深い想いが込められたものは、こんなにも美しく、強く見えるものなのか。
健司は、自分の日常を思った。変化のない、退屈な毎日。しかし、本当にそうだろうか。この世界には、自分が気づいていないだけで、無数の物語が息づいている。道端の石ころひとつ、すれ違う名も知らぬ他人ひとりにも、それぞれの人生と、それぞれの物語がある。自分が「何もない」と切り捨てていた日常にも、見方を変えれば、意味や価値を見出せるのかもしれない。
会社に着くと、健司はまっすぐ上司のデスクへ向かった。
「課長。先日、募集がかかっていた新規プロジェクトの件ですが、もしよろしければ、私に担当させていただけないでしょうか」
驚く上司の顔を、彼はまっすぐに見つめた。それは、今まで変化を恐れて、安全なルーティンに安住してきた彼にとって、信じられないほど大きな一歩だった。自分自身の人生のドアノブに、初めて手をかけた瞬間だった。
それからも、健司は毎朝、車窓からあのドアを眺める。ドアは変わらず、そこに静かに佇んでいる。それは健司にとって、日常に潜む奇跡の象徴であり、自分の足で一歩を踏み出す勇気をくれる、小さな灯台のような存在になっていた。
世界は、開かれるのを待っている扉で満ちている。あとは、それに気づき、手を伸ばす勇気があるかどうかだけなのだ。健司は窓の外に広がる、見慣れた、しかし全く新しくなった風景を見つめながら、静かにそう思った。