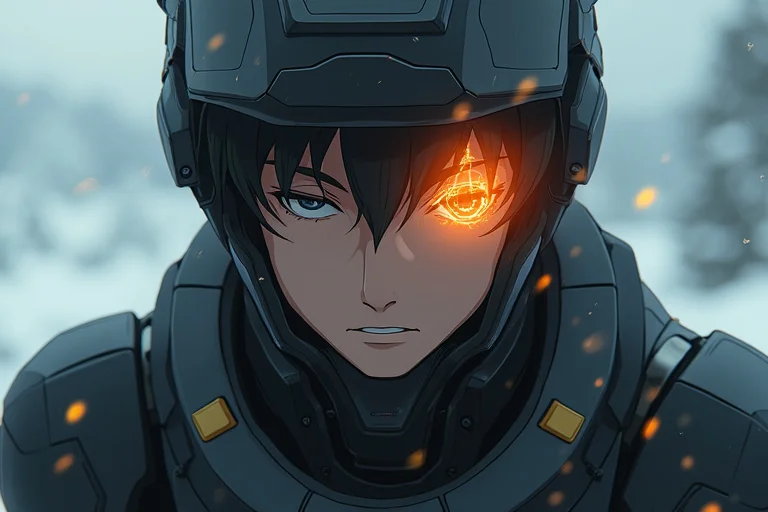第一章 瓦礫の中の秒針
サイレンの絶叫が止むと、耳鳴りのような静寂が街を支配した。リヒトは、煤と埃にまみれた地下室から這い出し、変わり果てた景色に息を呑んだ。数時間前までパン屋の香ばしい匂いが漂っていたはずの石畳の通りは、巨大な獣に抉られたかのように、瓦礫と残骸で埋め尽くされている。空は、硝煙と悲しみが混じり合ったような、鈍い鉛色をしていた。
十五歳のリヒトにとって、戦争は日常の一部だった。遠い前線で父が死んだと知らされたのは、もう五年も前のことだ。有名な時計職人だった父の記憶は朧げで、手元に残されたのは、文字盤に細かな傷の入った銀の懐中時計だけ。それはもう、時を刻むことはなかった。
「生きている者はいるか!」
自警団の怒声が響く。リヒトは無意識に、父の工房があった方角へ足を向けた。そこもまた、無残に崩れ落ちていたが、奇跡的に作業台だけは原型を留めている。その近くに、見慣れない軍服が転がっていた。敵国の兵士だ。ぴくりとも動かないその手から、何かが滑り落ち、瓦礫の隙間で鈍い光を放っている。
好奇心に駆られ、リヒトはそれに手を伸ばした。指先に触れたのは、ひんやりとした金属の感触。引きずり出して、掌の上の埃を払った瞬間、リヒトは凍りついた。
銀の懐中時計。植物の蔓を模した繊細な彫刻が施された、見紛うことなき父の作品。リヒトが持つ形見と、全く同じ意匠だった。
しかし、決定的な違いが一つあった。
リヒトの耳元で、その時計は、チク、タク、チク、タクと、確かな生命の鼓動のように秒針を動かしていたのだ。
なぜ、父の時計が、敵国の兵士の手に? そしてなぜ、それは動いているのか?
瓦礫の山の中で、二つの同じ貌をした時計――一つは沈黙し、一つは時を刻む――その存在が、リヒトの世界に静かだが決定的な亀裂を入れた。
第二章 父の遺した秘密
その日から、リヒトの世界は色褪せた。配給の黒パンも、友人の冗談も、全てが空虚に感じられた。頭の中では、あの懐中時計の秒針の音だけが、繰り返し響いている。父の死は、国が発表した名誉の戦死ではなかったのかもしれない。その疑念が、燻る燠火のように胸の内で熱を持ち始めていた。
リヒトは夜ごと、父の工房跡に通った。瓦礫を一つ一つ手でどかし、父の痕跡を探す。そして三日目の夜、ついに床板の隠し戸棚から、革張りの分厚い手記を見つけ出したのだ。
埃っぽい匂いと共にページをめくると、そこにはインクで描かれた精密な時計の設計図と、父の几帳面な文字がびっしりと並んでいた。それは単なる仕事の記録ではなかった。
『……この新しい脱進機(エスケープメント)は、僅かな衝撃で歯車の動きを止めることができる。だが、特殊な手順で竜頭を回せば、再び正確に時を刻み始める。まるで、仮死状態から蘇る心臓のように。』
リヒトは息を呑んだ。自分の持つ壊れた懐中時計は、ただ壊れているのではなかった。意図的に、時を止められていたのだ。
手記を読み進めるうち、リヒトは何度も同じ名前に出くわした。「クラウス」という、異国の響きを持つ名だ。
『クラウス、君ならこの機構の意図を理解してくれるだろう。国境線など、我々の友情の前では、地図の上に引かれた一本の線に過ぎないのだから。』
『戦争が、全てを分断していく。芸術も、友情も、家族さえも。だが、時だけは平等に流れる。我々の作る時計が、いつか再び同じ時を刻む日を信じている。』
父と、敵国の時計職人クラウス。二人の間には、国境を越えた深い友情があったのだ。父は英雄的な軍人などではなく、ただ平和を愛し、友を想う一人の職人だった。リヒトの胸に、今まで感じたことのない温かい感情が込み上げてくる。父の輪郭が、朧げな記憶の中から、確かな体温を持って立ち上がってくるようだった。
手記の最後の方に、一枚の紙片が挟まっていた。そこには、走り書きのような文字で、こう記されている。
『二つのアリアが重なる時、沈黙の鐘は鳴る。鍵は、月の満ち欠けに。』
謎めいた言葉。だがリヒトは、これが父とクラウスの間の暗号だと直感した。二つの時計、二つのアリア。父は何かを遺そうとしていた。それは、単なる友情の証以上の、もっと大きな何かであるような気がしてならなかった。
第三章 二つの時計の真実
リヒトは手記と二つの懐中時計を自室に持ち帰り、来る日も来る日も、その謎と向き合った。空襲警報が鳴り響く夜も、彼は机にかじりつき、父の設計図と格闘した。
「鍵は、月の満ち欠けに」
その言葉を手がかりに、リヒトは時計の裏蓋に刻まれた、一見ただの装飾にしか見えない月の満ち欠けの図に注目した。そして、ある法則性に気づく。新月から満月、そしてまた新月へ。その順番で竜頭を特定の回数だけ回し、引き、また回す。それはまるで、複雑な金庫の錠を開ける儀式のようだった。
まず、自分の持っていた、止まったままの時計で試した。父の記した通りの手順で竜頭を操作すると、カチリ、と小さな音がして、今まで固く閉ざされていた文字盤の裏の小さな蓋が開いた。そこには、米粒ほどの大きさに折り畳まれた、極薄のフィルムが隠されていた。
心臓が激しく鳴る。同じ手順を、敵兵が持っていた時計にも施す。すると、こちらも同じように隠し蓋が開き、中からマイクロフィルムが現れた。
フィルムを確認する術はない。だが、リヒトは悟ってしまった。これはただの友情の証ではない。父とクラウスは、時計という完璧な隠れ蓑を使って、二つの国の間で何かを伝えようとしていたのだ。
その時、手記の最後のページに、インクの滲みで判読しづらくなっていた一節が、不意に目に飛び込んできた。
『息子よ。もし君がこれを読んでいるのなら、私はもうこの国にいないだろう。私は死んだのではない。境界線を越えるのだ。クラウスと共に、この狂った戦争を内側から止めるために。我々の活動は、両国から見れば許されざる裏切りだろう。だが、人の命を奪うことこそが、最大の裏切りだと信じている。いつか、私が作った時計と、クラウスが作った時計が、君の元で再会する日が来る。それが、我々のささやかな抵抗が、無駄ではなかったという証だ。許してくれとは言わない。ただ、覚えていて欲しい。父は、時を愛し、人を愛した、ただの時計職人だったと。』
全身の血が逆流するような衝撃。父は生きていた。いや、少なくとも、この手記を書いた時点では生きていた。そして、国を捨て、敵国へ渡った。平和のためという大義を掲げながらも、それは紛れもない「裏切り」だった。
名誉の戦死を遂げた英雄の息子。それが、リヒトの唯一の矜持だった。だが、その土台が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちていく。父は英雄ではなかった。もしかしたら、国を売った卑劣なスパイだったのかもしれない。
空襲で死んだ敵兵は、父の協力者だったのだろう。父からのメッセージを運ぶ途中で、命を落としたのだ。
リヒトは、二つのマイクロフィルムと、二つの懐中時計を前に、ただ立ち尽くした。信じるべきものは何か。父は、英雄か、売国奴か。その答えは、戦争の喧騒の中、どこにも見つからなかった。
第四章 時を継ぐ者
長い、長い戦争が終わった。街には少しずつ活気が戻り、人々は未来に目を向け始めた。リヒトは青年になり、父の工房跡を再建して、時計職人として生きていた。父が英雄か売国奴か、その問いの答えは出ないまま、ただ父が遺した技術と、時への愛情だけを胸に刻み、黙々と時計を修理し続けた。父の行方は、知れないままだった。
終戦から五年が過ぎた、ある秋の日の午後。工房のドアベルが、からん、と乾いた音を立てた。入ってきたのは、深く皺の刻まれた顔の、見知らぬ老人だった。旅慣れた様子のその男は、ゆっくりとカウンターに歩み寄ると、震える手で古びた銀の懐中時計を置いた。
リヒトは息を呑んだ。それは、あの日瓦礫の中で見つけたものと寸分違わぬ、蔓の彫刻が施された時計だった。
「君が、リヒト君だね。……私は、クラウスだ」
老人は、穏やかな声でそう名乗った。
時が、止まったようだった。父の手記の中にだけ存在した、伝説の人物。その彼が、今、目の前にいる。
クラウスは、静かに語り始めた。リヒトの父、ハインリヒは、終戦を目前にした冬、敵国領内で潜伏していた先の街で、病のために亡くなったこと。二人が集めた情報は、両国の穏健派の手に渡り、和平交渉のテーブルをほんの少しだけ早く実現させる一助になったかもしれないこと。しかし、彼らの名は歴史に残ることはなく、多くの犠牲の一つとして忘れ去られていくこと。
「君のお父さんは、最期まで君のことを案じていたよ。そして、これを君に渡してくれと」
クラウスが差し出したのは、古びた一通の手紙だった。インクは掠れ、所々涙の染みのようなものが滲んでいる。それは、父が死の床で書いた、息子への最後の手紙だった。
『愛するリヒトへ。
この手紙が君に届く頃、私はもうこの世にいないだろう。結局、私は君に父親らしいことを何一つしてやれなかった。
歴史という大きな歯車の前で、私やクラウスのような人間の力は、あまりに小さい。世界を変えることなど、できなかったのかもしれない。
だが、リヒト。それでも、信じて欲しい。暗闇の中でも、小さな灯火を掲げ続ける人間の尊厳を。国境やイデオロギーよりも、目の前の誰かの涙を拭ってやれる優しさを。
私は、時を刻むことしかできない不器用な職人だった。だが、君という未来に、最高の時を刻んで欲しいと、心から願っている。私の息子としてではなく、リヒトという一人の人間として、君自身の時を生きてくれ。』
涙が、リヒトの頬を伝い、カウンターの上に置かれた二つの懐中時計の上に落ちた。一つは父がリヒトに遺したもの。もう一つは、父がクラウスに託し、長い旅路の果てに、今再びリヒトの元へ還ってきたもの。
二つの時計は、違う場所で、違う主の元で時を過ごしながらも、寸分の狂いもなく、全く同じ時を指し示していた。
リヒトは、嗚咽を堪えながら、深く頭を下げた。父は英雄でも売国奴でもなかった。ただ、息子を愛し、友を信じ、狂った時代の中で人間であろうとし続けた、一人の時計職人だったのだ。
リヒトは顔を上げ、涙に濡れた目でクラウスを見つめた。その目にはもう、迷いはなかった。彼は、父の遺した工房で、父の想いを受け継ぎ、新しい時を刻み始めるのだ。
窓から差し込む西日が、二つの銀の懐中時計を優しく照らし出していた。工房には、リヒトが作り上げた新しい振り子時計の、静かだが、どこまでも力強い秒針の音だけが、永遠に響き渡っていた。