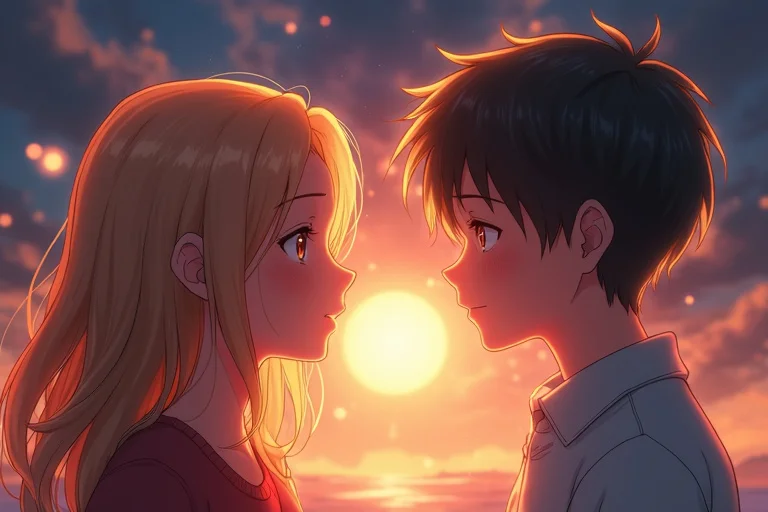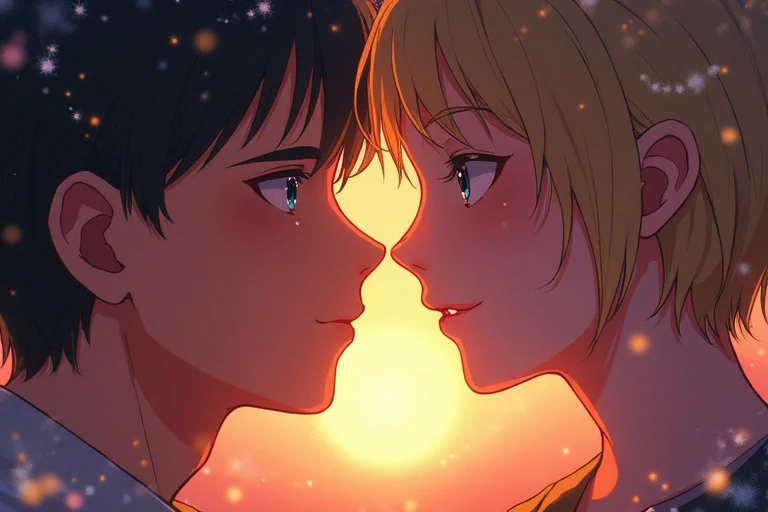第一章 残光のフィルム
じっとりとした熱気が肌にまとわりつく七月の午後、俺、柏木湊は埃っぽい写真部の部室で、過ぎ去った時間の残骸を片付けていた。来たる文化祭の準備という名目だが、実態は不用品の整理だ。汗で額に張り付いた前髪を払いながら、古びたスチールロッカーの扉をぎい、と軋ませて開ける。そこは、一年前に死んだ彼女、七瀬陽菜が使っていた場所だった。
陽菜がいた頃の熱気は、もうこの部室にはない。俺を含めた数人の部員は、ただ惰性でシャッターを切り、暗室に籠ることもなくなった。陽菜は太陽みたいな奴だった。いつも大声で笑い、三つ編みにした髪を揺らしながら、古いフィルムカメラを首から下げていた。そして、ファインダー越しに、いつも俺を見ていた。「湊くん、いい顔!」「あ、今、世界がキラキラした!」そんな言葉と共に向けられるレンズが、当時の俺にはひどく鬱陶しかった。
ロッカーの奥に、見覚えのある革製のカメラケースが転がっている。陽菜の愛機だった、ニコンの古いマニュアルカメラだ。そっと手に取ると、ずしりとした重みが、彼女の不在を改めて突きつけてくる。交通事故だった、と聞いた。夏の盛りの、空が燃えるような夕暮れ時。あまりに突然の、あっけない幕切れ。
何気なく巻き上げレバーに指をかけると、かすかな抵抗があった。カウンターを見ると「24」の数字。まさか。裏蓋を慎重に開けると、案の定、使いかけのフィルムが装填されたままになっていた。
陽菜が死んで一年。彼女が最後に見ていた世界が、この黒い筒の中に封印されている。
心臓が妙な音を立てた。現像すれば、彼女の最後の視線がわかる。あの夏の日、陽菜は何を撮ろうとしていたのか。俺は自分のスマートフォンを取り出し、記憶の底から陽菜の兄の連絡先を探し出した。数回のコールの後、少し気怠そうな声が応える。
「もしもし」
「……柏木です。湊です。陽菜さんの同級生の」
「ああ、柏木くん。どうした?」
部室で見つけたカメラとフィルムのことを伝えると、電話の向こうで兄は少し黙り込んだ。そして、絞り出すような声で言った。「そうか……。それは、陽菜の……。好きにしていいよ。君が見つけてくれたんだから」
その声には、単なる許可とは違う、何か痛切な響きがあった。
電話を切った俺は、カメラからフィルムを抜き取った。ずしりと重いのは、カメラじゃない。この、たった数十グラムのパトローネだ。陽菜の最後の時間が、ここに凝縮されている。鬱陶しいとさえ感じていた彼女の視線が、今になってどうしようもなく知りたくなっていた。俺はフィルムを握りしめ、街の写真屋へと向かって駆け出していた。夏の終わりの宿題に、今さら取り掛かるみたいに。
第二章 色褪せた世界の輪郭
数日後、仕上がった写真を受け取った俺は、近くの公園のベンチに腰掛け、写真の束をめくった。夏の光をめいっぱい吸い込んだ、陽菜らしいキラキラした写真が飛び出してくるだろう。そんな俺の予想は、一枚目から見事に裏切られた。
そこに写っていたのは、通学路の脇にある、錆びて赤茶けたガードレールだった。次の写真は、ひび割れたアスファルトから健気に顔を出す雑草。さらにめくると、雨樋が壊れた古いアパートの壁、閉鎖された商店街のシャッター、公園の隅で忘れられたように横たわる三輪車。
どれもこれも、色褪せて、どこかピントが甘い。陽菜がいつも口にしていた「キラキラした世界」とはかけ離れた、見過ごされ、打ち捨てられたような風景ばかりだった。まるで、世界から色が失われていく過程を記録しているかのように。
そして、束の中ほどで、俺は息を呑んだ。
不意に撮られた俺の横顔があった。授業中に窓の外を眺めている、退屈そうな顔。部室でカメラをいじっている、気難しげな顔。一人で帰路につく、寂しげな背中。すべて、俺が気づかないうちに撮られたものだ。陽菜のレンズは、俺の知らない俺自身を捉えていた。その視線は、かつて感じた鬱陶しさとは違う、何か切実な響きを帯びて俺に突き刺さる。
どうしてだ。どうして陽菜は、こんな写真ばかりを? いつも太陽のように笑っていた彼女が見ていた世界は、こんなにも寂しい色をしていたのか?
混乱した頭のまま、俺はカメラを手に、写真に写された場所を巡り始めた。陽菜の視線を追体験するように。錆びたガードレールに触れ、ひび割れたアスファルトに屈み込む。ファインダーを覗き、彼女と同じ構図でシャッターを切る。だが、何度やっても、俺にはその風景が特別なものには思えなかった。
陽菜、お前は一体、何を見ていたんだ?
答えの出ない問いが、蝉時雨と共に頭の中で鳴り響く。俺は、陽菜という人間のことを、その笑顔の裏側にあるものを、何一つ知らなかったのだ。写真の最後のページには、夕焼けに染まる空を背景に、大きくブレた、誰かの手のひらが写っていた。まるで、何かを掴もうとして、掴みきれなかったかのような、悲痛な残像だった。
第三章 シャッターが捉えた嘘
写真の場所を巡る奇妙な巡礼を始めて一週間が経った頃、俺は最後の写真に写っていた夕焼けの見える丘に来ていた。そこであの日以来となる陽菜の兄と、偶然再会した。彼は、俺が陽菜のカメラを手にしているのを見ると、少し驚いた顔をして、やがて諦めたように微笑んだ。
「陽菜の真似事かい?」
「……彼女が何を見ていたのか、知りたくて」
俺が正直に答えると、彼はしばらく黙って沈む夕日を眺めていたが、やがて重い口を開いた。
「あいつ、嘘つきだったからな」
その言葉から語られた真実は、俺の世界を根底から揺るがすものだった。
「陽菜は、病気だったんだ。少しずつ、視野と光を失っていく……そういう目の病気だった。あいつが死んだのも、ただの事故じゃない。横断歩道の信号の光が、もう、ちゃんと見えなくなっていたんだ」
頭を鈍器で殴られたような衝撃だった。陽菜が? あの太陽みたいな陽菜が、光を失っていた?
「いつも明るく振る舞っていたのは、怖かったからだ。世界から色が、形が、消えていくのが。だから、必死で『キラキラ』を探していた。失っていくものの代わりに、何かを心に焼き付けようとしていたんだ」
俺は手に持っていた写真の束に目を落とした。色褪せ、ピントの甘い風景。あれは、陽菜の目に映っていた世界の、ありのままの姿だったのだ。錆びたガードレールも、ひび割れたアスファントも、彼女にとっては消えゆく世界の輪郭そのものだった。
「じゃあ、なんで俺を……」
声が震えた。
「あいつが言ってたよ。『世界がどんどんぼやけていくのに、湊くんだけは、なぜかハッキリ見えるんだ』って。『私の目に映る最後の光は、湊くんであってほしい』って」
陽菜にとって俺は、失われていく世界の中で、唯一確かで、色鮮やかな存在だった。彼女が向けていたレンズは、救いを求める祈りそのものだったのだ。それなのに俺は。鬱陶しいと顔をしかめ、彼女の必死のサインから目を逸らし続けていた。
「このフィルムに入っていた写真が、あいつが最後に撮ったものだ。多分、最後の写真は、丘から手を振る君を撮ろうとして……でも、もう、ピントを合わせることもできなかったんだろうな」
ブレた手のひらの写真。あれは、陽菜自身の手だったのだ。ファインダーの中の俺に、届かなかった手。
後悔が、黒い奔流となって俺の胸を突き破った。気づけなかった。何もわかっていなかった。彼女の孤独も、痛みも、そして、その奥にあったあまりに切実な想いも。俺はただ、彼女の笑顔という嘘の上で、無邪気に生きていただけだった。膝から崩れ落ちた俺の頬を、熱い何かが伝っていくのがわかった。
第四章 君のいない夏空
陽菜の兄から、一通の封筒を手渡された。彼女が俺宛に遺していた手紙だった。陽菜の墓前で、俺は震える手で封を開けた。丸っこい、見慣れた彼女の文字が並んでいた。
『湊くんへ。この手紙を読んでいるということは、私はもう、湊くんの横顔を撮れなくなっちゃったんだね。ごめんね、ずっと嘘ついてて。本当は、世界がどんどん灰色に見えて、すごく怖かった』
手紙には、病気のことが淡々と、しかし、その行間から恐怖と寂しさが滲み出るように綴られていた。そして、最後にこうあった。
『でもね、湊くんを見ている時だけは、私の世界にはちゃんと色があったんだよ。不機嫌な顔も、笑った顔も、全部キラキラしてた。だから、お願いがあります。私の代わりに、湊くんの目で、世界を撮り続けてください。私がもう見ることのできない、美しいものを、たくさん、たくさん、そのカメラに焼き付けてください。湊くんが見る世界は、きっと、すごく綺麗だから』
手紙を握りしめたまま、俺は声を上げて泣いた。後悔と、申し訳なさと、そして、今さら知った陽菜の愛情の深さに、心が張り裂けそうだった。俺は空っぽだった。彼女がくれたものに気づかず、何も返せなかった。
数日が過ぎた。俺は陽菜の古いカメラを手に、再びあの丘に立っていた。ファインダーを覗くと、ありふれた街の風景が広がっている。だが、それはもう、以前の俺が見ていた退屈な世界ではなかった。家の屋根、電線にとまる鳥、風に揺れる木々、その一つ一つが、陽菜が見たくても見られなかった、かけがえのない光景なのだと思えた。
世界は、こんなにも光に満ちていた。
俺は息を吸い込み、シャッターを切った。カシャッ、と乾いた音が、夏の空に響き渡る。それは、陽菜への鎮魂の音であり、彼女の願いを受け継ぐという誓いの音であり、そして、空っぽだった俺が、もう一度世界と向き合うための、始まりの音だった。
ファインダー越しの空は、どこまでも青い。この青を、いつか君に届けられるだろうか。俺はこれからもシャッターを切り続ける。君が見たかった世界と、君が見ることのできなかった未来を、この一枚一枚に焼き付けながら。君が遺してくれたこの視線で、世界がどれほど美しいかを、伝え続けるために。