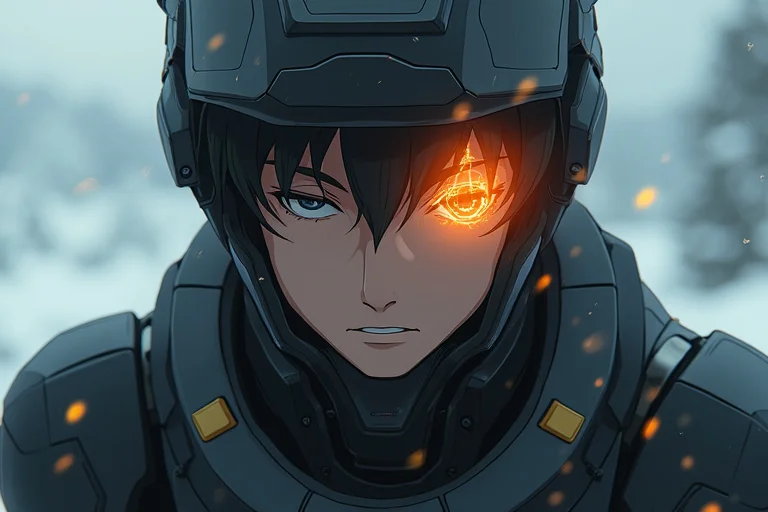第一章 錆びた音叉と囁き
風が瓦礫の隙間を吹き抜けるたび、死者たちの最後の囁きがカイの鼓膜を震わせた。それは音ではない。空間そのものに刻まれた、意識の微細な振動――『響き』だ。カイは膝をつき、錆びた鉄骨の冷たさを掌に感じながら、そっと目を閉じた。
「……寒い……」
「マリア、どこだ……」
「光が、眩し――」
断片的な恐怖、未練、そして愛。ここは三周期前に、『鉄の信念』を掲げる帝国と、『光の教義』を説く教国との『侵食』によって生まれた『失われた領域』の境界線だ。信念の衝突は物理的な現実を歪め、大地を奪い合う。その結果が、この静かな死の骸だった。
カイは懐から古びた音叉を取り出した。黒檀の柄は彼の手によく馴染み、銀色の先端は鈍い光を放っている。それを軽く打ち鳴らすと、キィン、と澄んだ音が虚空に溶け、周囲の『響き』を増幅させた。途端に、無数の声が奔流となって彼の意識に流れ込む。彼はその奔流の中から、一つの特異な響きを探っていた。未来の予兆。世界の悲鳴が凝縮された、ガラスの破片のような鋭い響きを。
不意に、背後で砂利を踏む音がした。
「また、ここにいたのね、カイ」
振り返ると、記録官のエリアが、風に亜麻色の髪をなびかせて立っていた。彼女の瞳には、この荒廃した風景に対する悲しみと、カイという存在への尽きない探究心が同居している。
「何か聞こえた?」
「いつもと同じだ。終わらない後悔の合唱だよ」カイは立ち上がり、音叉を懐に戻した。「だが、時折混じるんだ。まだ起きていない出来事の断片が」
彼は空を見上げた。帝国と教国の信念がせめぎ合う空は、常に奇妙な紫色のグラデーションを描いている。まるで、世界そのものが巨大な痣を作っているかのようだった。
第二章 羊皮紙に沈む声
エリアに促され、カイは彼女が管理する中立都市アルクの古文書館を訪れていた。カビと古い紙の匂いが満ちる静寂の中、エリアは分厚い一冊の書物を開いた。それは、過去の『侵食』に関する最も古い記録だった。
「見て。この記述よ。『失われし領域にて、死者の魂は霧となり、やがて歌を紡ぎ始める』とあるわ」
エリアの指し示す文字は、掠れてほとんど判読が難しい。だが、カイにはその羊皮紙そのものから、微かな『響き』が感じられた。何世代も前の記録官が、恐怖と畏怖を込めてペンを走らせた際の、心の震えが。
彼は再び音叉を取り出し、そっとページの端に触れさせた。澄んだ音色が響くと、彼の視界がぐにゃりと歪む。
――幻視が始まった。
広大な平原。空を埋め尽くす両陣営の旗。鬨の声が地を揺るがし、剣と剣がぶつかる金属音が悲鳴のように木霊する。信念のために命を散らす兵士たち。彼らの肉体が地に倒れる瞬間、淡い光の粒子が立ち上り、渦を巻いて天へと昇っていく。それは無数の蛍の乱舞にも似て、恐ろしくも美しい光景だった。光は集まり、混じり合い、やがて一つの巨大な意識の集合体へと変貌していく。それは嘆きではなく、ただ静かにそこに在る、巨大な存在だった。
「……うっ……!」
カイは額を押さえてよろめいた。幻視の奔流は、彼の精神をひどく消耗させる。
「大丈夫?」エリアが心配そうに彼の腕を支えた。
「あれは……ただの残留思念じゃない」カイは荒い息をつきながら言った。「何か目的がある。あの集合体には、意思のようなものが……」
羊皮紙に沈んでいた声は、カイに新たな謎を突きつけていた。なぜ死者たちは集い、歌うのか。その歌は、一体誰に届けられるものなのか。
第三章 信念の不協和音
その日、世界の痣は、より一層濃い紫色を呈していた。帝国の『鉄の信念』が、教国の『光の教義』を押し返し、その余波が中立都市アルクのすぐそばまで迫っていたのだ。
カイとエリアは、都市の城壁の上からその光景を目の当たりにしていた。帝国の領域と化した大地は、金属的な光沢を帯びた黒い土壌に変わり、草木一本生えていない。対する教国の領域は、眩いばかりの光に満ちているが、その光には触れるもの全てを浄化し、無に帰すような危うさがあった。
二つの領域が接する境界線では、空間が陽炎のように揺らめき、カイの耳には耐え難い不協和音が響いていた。それは、互いに決して交わらない二つの強固な信念が奏でる、世界の軋みだった。
「止めることはできないのか……」
カイは城壁の石に拳を叩きつけた。彼の能力は、死者の声を聴くことしかできない。生きている者たちの狂信的な信念の前では、あまりにも無力だった。
「信念は、人の存在証明そのものだから」エリアが静かに呟いた。「それを否定することは、その人の生を否定することと同じなのよ」
その時だった。帝国の領域が、ぐんとアルク側へ膨張した。城壁がミシミシと音を立て、足元が大きく揺れる。人々の悲鳴が上がり、恐怖の『響き』がカイの心を乱した。彼は強く音叉を握りしめた。死者の声だけではない。今、まさに生まれようとしている死の予兆が、彼の肌を粟立たせていた。
第四章 失われた領域の聖歌
侵食は止まらなかった。アルクの市街地の一部が、帝国の領域に飲み込まれ、そして――『失われた領域』へと変貌した。そこは、全ての色彩と音を失った灰色の世界だった。建物の崩壊は途中で止まり、逃げ惑う人々の姿はまるで彫像のように静止している。時間の流れから切り離された、虚無の空間。
「これが……」エリアは息をのんだ。
カイは躊躇なく、その灰色の世界へ足を踏み入れた。奇妙な浮遊感が身体を包む。ここでは、あらゆる信念が無に帰していた。帝国の兵士も、アルクの住民も、皆等しく時間の牢獄に囚われている。
そして、カイは聴いた。
これまで聴いてきた、個人の死の囁きとは全く異なる音を。それは、この領域全体から響いてくる、荘厳で、どこまでも澄んだハーモニーだった。無数の声が織りなす、一つの『聖歌』。幻視で見た、あの意識の集合体が紡ぐ歌だ。それは悲しみでも怒りでもなく、ただ世界を慈しみ、修復しようとするかのような、祈りの旋律だった。
カイは導かれるように領域の中心へと歩を進めた。そして、音叉を高く掲げ、打ち鳴らした。
キィィィン――。
音叉の音色が『聖歌』と共鳴した瞬間、世界が反転した。
彼の脳裏に、光の洪水となって情報が流れ込む。それは、この世界の創生からの記憶。世界は、強固になりすぎた信念のエネルギーによって、定期的に物理的な崩壊の危機に瀕してきた。その崩壊を防ぐため、世界自身が生み出した自己防衛本能こそが『侵食』だったのだ。
侵食は破壊ではない。疲弊し、硬直した現実を一度『失われた領域』という無に還し、戦争で死んだ者たちの意識――それは次の世界を構成するための膨大な情報――を素材として、世界を『再構築』する。
それは、あまりにも巨大で、あまりにも非情な、世界の再生プロセスだった。
第五章 調律師のフーガ
全てを理解したカイは、静かに目を開けた。
自分が聴いてきた死者たちの『響き』。未来の予兆。それらは全て、この再生を完了させるための設計図の断片だったのだ。そして、自分のような能力を持つ者は、いつの時代にも存在した。散らばった情報を集め、世界に還すための触媒――『調律師』として。
「カイ……?」
彼の異変に気付いたエリアが、不安げに名を呼ぶ。
カイは彼女に向かって、穏やかに微笑んだ。それは、彼が初めて見せた、心からの笑みだった。
「これで、終わらせられる」
彼はもう一度、音叉を構えた。今度は、ただ鳴らすためではない。自らの全てを、この世界の巨大な旋律に捧げるために。
「カイ、だめ!」エリアが叫び、彼に駆け寄ろうとする。だが、見えない壁が彼女を押しとどめた。
カイは最後の音を奏でた。
その音は、彼がこれまで集めてきた全ての死者の『響き』を解き放ち、失われた領域の『聖歌』と溶け合っていく。それは壮大なフーガのように、いくつもの旋律が絡み合い、高まり、やがて一つの完璧な調和へと収束していく。
カイの身体が、足元から光の粒子となって崩れ始めた。指先が、腕が、そして彼という個の意識が、世界の記憶そのものへと昇華していく。痛みはない。ただ、途方もない安らぎと、自分が大きな流れの一部になるという、不思議な充足感があった。
薄れゆく意識の中、彼はエリアの泣き顔を見た。
(泣かないで、エリア。僕は消えるんじゃない。世界になるんだ。君が生きる、この世界の片隅で、風になって君の髪を揺らすから)
それが、カイという個人の、最後の『響き』だった。
第六章 夜明けの残響
カイの姿が完全に光の中に消え去ると、灰色の世界は眩いばかりの純白の光に満たされた。侵食は止まり、歪んだ大地は浄化され、帝国の領域も教国の領域も、その境界を曖昧にして後退していく。
やがて光が収まった時、そこには新しい、生まれたばかりの大地が広がっていた。草木はなく、まだ生命の息吹もない、まっさらなキャンバスのような世界。
エリアはその大地に一人、立ち尽くしていた。戦争は終わったわけではない。いつかまた、人々は新たな信念を掲げ、争い、世界は軋みを上げるだろう。その時、また新たな『調律師』が生まれるのかもしれない。
彼女は頬を伝う涙を拭った。悲しかった。どうしようもなく、悲しかった。だが、同時に不思議な静けさが心を支配していた。
ふと、優しい風が彼女の頬を撫でた。その風は、微かに、あの澄んだ音叉の音色を運んできたような気がした。カイの最後の微笑みが、心に蘇る。
彼の犠牲は、世界を救うための尊い礎だったのか。それとも、永遠に繰り返される残酷なサイクルに組み込まれた、一つの歯車に過ぎなかったのか。
答えは、まだ見つからない。
だが、エリアは前を向いた。彼の物語を、彼が生きた証を、そしてこの世界の真実を記録し続ける。それが、残された自分にできる、唯一のことだから。
夜明けの光が、新しい大地を照らし始めていた。その風の中に、エリアは確かに聴いた。
ありがとう、と囁くような、優しい残響を。