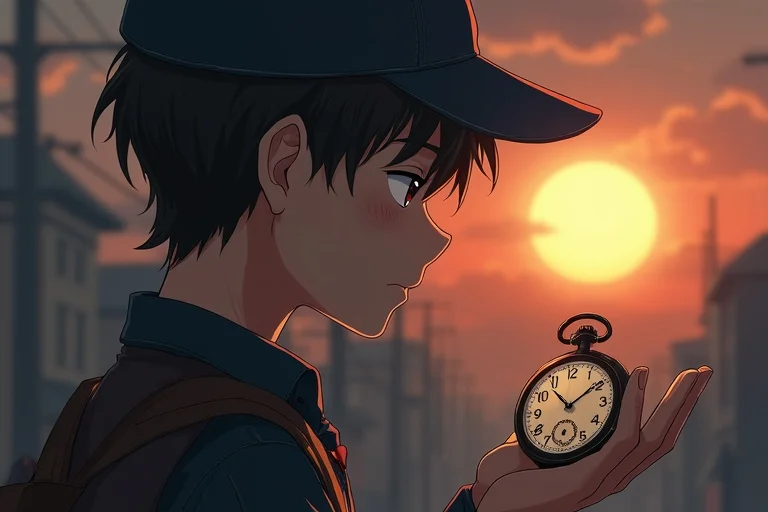第一章 宛名のない封筒
街は灰色だった。爆撃で抉られたアスファルトも、煤けた建物の壁も、空腹を抱えて行き交う人々の瞳も、すべてが同じ色の濃淡で塗りつぶされているようだった。リヒトはこの灰色の世界で郵便配達員をしていた。彼の心もまた、街と同じ色に染まっていた。戦争で両親を失って以来、彼は感情という厄介な荷物を心の奥底にしまい込み、ただ機械のように手紙を運び続けることで日々をやり過ごしていた。
その日も、リヒトはいつものように分厚い革の鞄を肩にかけ、無表情に仕分け作業をしていた。同僚たちの囁き声も、遠くで鳴り響くサイレンの音も、彼にとっては意味を持たない背景音でしかない。そんな彼の指が、一通の奇妙な封筒に触れた。
上質だが少し古びた羊皮紙の封筒。そこには、宛名もなければ、差出人の名も記されていなかった。ただ、封蝋の代わりに、押し花にされた一輪の枯れたエーデルワイスが、丁寧に貼り付けられているだけ。配達先の住所を示す欄には、インクが滲んだような文字で、ただ『街外れの聖マリア教会へ』とだけ書かれていた。
聖マリア教会。そこは数年前の空襲で半壊し、今は打ち捨てられた廃墟のはずだ。司祭は亡くなり、信者たちは散り散りになったと聞いている。誰が、誰に宛ててこんなものを送るというのか。不審に思ったが、リヒトの仕事は配達することだ。彼はため息とともにその封筒を鞄にしまい、灰色の街へと自転車を走らせた。
崩れかけた尖塔が見える。瓦礫と雑草に覆われた参道を進むと、ステンドグラスの砕け散った窓が、まるで巨大な骸骨の眼窩のように黒々と口を開けていた。リヒトは息を殺して教会の中へ足を踏み入れる。静寂が、埃っぽい空気と共に彼の肺を満たした。祭壇は砕け、鳩が瓦礫の山に巣を作っている。彼は指示通り、その祭壇の中央に、エーデルワイスの封筒をそっと置いた。まるで供物のように。
奇妙な任務を終え、彼はすぐにその場を立ち去った。だが、彼の日常を覆す本当の出来事は、翌朝に起こった。
郵便局に出勤したリヒトは、自分の仕分け棚に見覚えのある封筒が置かれているのを見つけ、眉をひそめた。昨日、彼が教会に届けたはずのエーデルワイスの封筒だ。誰かが悪戯で戻したのか。苛立ちながらそれを手に取ると、封筒が昨日よりわずかに膨らんでいることに気づいた。訝しみながら封を開けると、中から小さな真鍮の歯車がひとつ、ことりと音を立ててリヒトの掌にこぼれ落ちた。
第二章 記憶の欠片
その日から、リヒトの灰色の日常に、奇妙な習慣が加わった。毎日、あの宛名のない封筒を聖マリア教会に届け、翌朝、郵便局に戻ってきた封筒から、新たな「何か」を取り出す。それは、彼の心を静かにかき乱す、謎めいた儀式となった。
歯車の翌日は、青い鳥の羽根だった。その次の日は、焼けて黒ずんだ楽譜の断片。またある日は、ビー玉のかけら。どれもこれも、意味の分からないガラクタばかりだ。しかし、それらに触れるたび、リヒトの心の奥底で、固く凍り付いていた何かが、微かに軋むような音を立てた。
青い鳥の羽根を眺めていると、なぜか幼い頃の母親の優しいハミングが聞こえた気がした。焼けた楽譜の切れ端からは、父の書斎に満ちていたインクと古い紙の匂いが蘇るようだった。それはあまりに曖昧で、掴もうとすると霧のように消えてしまう、記憶とも呼べないほどの幻影。だが、感情を殺して生きてきたリヒトにとって、その幻影は無視できない波紋を広げ始めていた。
彼は無意識のうちに、毎朝、封筒が戻っているかを確認することが一日の始まりの合図になっていた。封筒の中身が、彼の心を揺さぶる小さな謎解きになった。
「おい、リヒト。最近少し変わったな」
昼食の固いパンをかじっていると、年配の同僚ハンスが声をかけてきた。
「何がです」
「いや、何というか……お前さんの目の色が、前より少しだけ濃くなったような気がしてな」
リヒトは答えず、視線を落とした。だが、否定はできなかった。灰色の世界に、ほんのわずかな色彩が差し込んでいるような感覚があった。人々の声が、街の音が、以前よりも鮮明に耳に届くようになっていた。
ある雨の日、封筒からは小さな銀の鍵が出てきた。それを見た瞬間、リヒトの脳裏に、錆びたブリキの宝箱のイメージが鮮やかにフラッシュバックした。そうだ、子供の頃、父が作ってくれた宝箱。自分だけの大切なガラクタを、そこに隠していたはずだ。銀の鍵は、その箱を開けるためのものだった。
封筒は一体、何を伝えようとしているのか。送り主は誰で、何を望んでいるのか。謎は深まるばかりだったが、不思議と恐怖はなかった。むしろ、この奇妙なやり取りが続くことを、リヒトは心のどこかで望んでいた。失われた自分の過去と、か細い糸で繋がっているような気がしたからだ。彼は、ただの手紙ではなく、忘れられた記憶の欠片を配達しているのかもしれない。そう思うと、革の鞄の重みが、少しだけ違ったものに感じられた。
第三章 嵐の夜の告白
その夜、街は嵐に見舞われた。風が唸りを上げ、叩きつけるような雨が建物の窓を震わせる。リヒトはずぶ濡れになりながら、それでも自転車を走らせていた。鞄の中には、いつものエーデルワイスの封筒が大切に仕舞われている。こんな嵐の夜でも、彼は教会へ向かうことをやめられなかった。それはもはや義務ではなく、彼自身の意志だった。
教会は、闇の中で巨大な獣のように身を潜めていた。リヒトは懐中電灯の頼りない光で足元を照らしながら、ぎしぎしと音を立てる床を進む。祭壇に封筒を置いた、その時だった。
ガタン、と背後で大きな物音がした。リヒトが驚いて振り返ると、そこには誰もいない。風のせいか。だが、彼の耳は、瓦礫の山の中から微かな息遣いがするのを捉えていた。全身の神経が緊張で張り詰める。敵兵の残党か、それともただの物盗りか。
「……そこにいるのは誰だ」
リヒトが震える声で尋ねると、瓦礫の影から、ゆっくりと一人の老人が姿を現した。痩せこけた体に、ぼろぼろの服。しかし、その瞳だけが、暗闇の中で鋭い光を放っていた。
「驚かせてすまない。わしは、エリオットという」
老人は穏やかな声で言った。その声には聞き覚えがない。だが、不思議なことに、リヒトは目の前の老人に敵意を感じなかった。
「あんたが……封筒を?」
「いかにも。毎日、ご苦労だったな、リヒト君」
リヒトは息を呑んだ。なぜ、この老人は自分の名前を知っているのか。
「わしは時計職人だ。そして……君の父親、アルフレッドの古くからの友人だよ」
エリオットと名乗った老人は、ゆっくりと真実を語り始めた。彼は、この国と敵対する国の生まれだった。戦争が始まるずっと前から、この街で時計店を営み、リヒトの父親とは、国籍を超えて友情を育んでいたという。しかし開戦後、彼はスパイの嫌疑をかけられ、追われる身となった。そんな彼を匿ってくれたのが、リヒトの父親だったのだ。この廃墟の教会は、彼らの秘密の隠れ家だった。
「では、なぜこんな真似を……」
「君の記憶を取り戻したかったからだ」
エリオットは、リヒトの目をまっすぐに見つめた。
「君は、両親が爆撃で死んだと思っている。だが、違う。君の父親は、わしのような『敵』を庇ったことで、自国の兵士に……いや、違うな。それも正確ではない」
エリオットは一度言葉を切り、深く息を吸った。
「あの日、この教会に爆弾が落ちた。君とお父さんは、わしを別の隠れ家へ移すためにここに来ていた。お父さんは、とっさに君を突き飛ばし、自分の体で君を庇ったんだ。そして……彼は瓦礫の下敷きになった。君は、そのあまりの衝撃で、その日の記憶を全て心の奥底に封じ込めてしまったのだ」
リヒトの頭を、巨大な金槌で殴られたような衝撃が襲った。違う。そんなはずはない。父は、母は、爆撃で死んだ。敵の爆撃で。そうでなければ、自分のこの空っぽの心は、どこへ向ければいい?
「封筒の中身は、君が幼い頃に大切にしていたものだ。君の記憶の扉を開けるための、小さな鍵のつもりだった」とエリオットは続けた。「エーデルワイスは、君のお母さんが一番好きだった花だ。歯車は、時計職人だった父さんの仕事場で君がよく拾っていたもの。青い鳥の羽根は、君が怪我をさせて、介抱した鳥の……」
エリオットの言葉が、リヒトの固く閉ざされた記憶の扉を、無理やりこじ開けていく。そうだ。思い出した。父の大きな背中。瓦礫が崩れ落ちる轟音。そして、最後に聞こえた「生きろ、リヒト」という声。
敵は、誰だ。憎むべきは、誰なんだ。敵国の兵士か。父を裏切り者と罵った自国の人間か。それとも、父を死なせてしまった、自分自身か。彼の価値観が、足元からガラガラと崩れ落ちていく。リヒトは、その場に膝から崩れ落ち、嵐の音に紛れて、何年も忘れていた嗚咽を漏らした。それは、灰色の世界が、ようやく終わりを告げた瞬間だった。
第四章 夜明けの配達人
嵐が過ぎ去り、静寂が教会を支配していた。リヒトは、エリオットから古びた銀の懐中時計を受け取っていた。それは父の形見だったが、爆撃の衝撃で針は止まったままだった。
「これを君に渡すのが、アルフレッドとの最後の約束だった」
エリオットは、リヒトの掌にあった小さな真鍮の歯車を指さした。
「その歯車は、この時計から抜け落ちたものだ。さあ、元の場所に戻してあげなさい」
リヒトは震える指で、懐中時計の裏蓋を開けた。複雑に絡み合った機構の中に、ひとつだけ歯車が欠けている場所があった。そこに、封筒から出てきたあの歯車をそっとはめ込む。
カチリ、と小さな音がした。
次の瞬間、チク、タク、チク、タク……と、止まっていた時計が、再び穏やかなリズムで時を刻み始めた。
その音は、まるで父の心臓の鼓動のように、リヒトの体に響き渡った。閉ざされていた記憶のダムが決壊し、忘れていた父の温もり、母の笑顔、三人で過ごした何気ない日々の断片が、鮮やかな色彩を伴って彼の心に溢れ出した。熱い涙が、とめどなく頬を伝う。それは悲しみの涙であると同時に、失われたものを取り戻した、歓喜の涙でもあった。
戦争はまだ終わらない。街はまだ灰色だ。しかし、リヒトの世界はもう同じではなかった。彼の心には、確かな光が灯っていた。憎しみではなく、父が命をかけて守ろうとした「想い」という光が。
翌朝、リヒトはいつもより早く郵便局へ向かった。彼の足取りは軽く、その表情には、以前の無気力な影はどこにもなかった。
「おはよう、ハンスさん」
彼が笑顔で挨拶をすると、同僚は目を丸くして彼を見つめ返した。
リヒトは革の鞄を肩にかけた。その中には、街の人々の想いが詰まった手紙が入っている。それはもう、ただの紙切れではなかった。一通一通が、誰かの記憶であり、希望であり、愛そのものなのだ。彼は、その大切な想いを繋ぐ配達人なのだ。
朝日が、瓦礫の街を黄金色に染め始めていた。リヒトは自転車にまたがり、新しい一日へと漕ぎ出す。彼の胸ポケットで、父の懐中時計が確かなリズムを刻んでいる。チク、タク、チク、タク……。それは、失われた時間を取り戻し、未来へ向かって歩き出す彼の決意の音だった。戦争という巨大な不条理の中で、それでも人が人に何かを伝え、繋ごうとすること。その小さな、しかし何よりも尊い営みを、彼はこれからも続けていく。夜明けの光の中、彼の背中は、昨日までの彼とは比べものにならないほど、大きく、そして誇りに満ちて見えた。