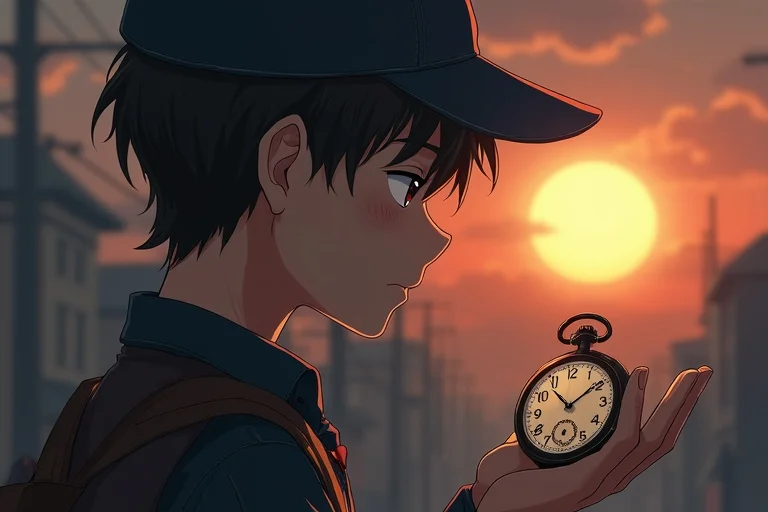第一章 壊れた子守唄
世界から音が消えて久しい。正確に言えば、心地よい音、意味のある音のすべてが、一つの巨大な不協和音に塗り潰されていた。それが、この終わりの見えない戦争の姿だった。
僕、リアムは、共和国軍の音響兵として前線にいた。僕たちの主な任務は、敵国である連合王国に向けて、巨大なスピーカーアレイから「不協和音(ディスコード)」と呼ばれる指向性の音波兵器を照射し続けること。そして、敵から放たれる同様の兵器に耐えることだった。
ディスコードは、物理的な破壊力こそない。だが、その音は人間の精神を内側から蝕む。聞く者の平衡感覚を奪い、論理的思考を麻痺させ、やがては狂気に至らしめる悪魔の囁き。兵士たちは皆、分厚い対音響プロテクターで耳を塞ぎ、特殊な振動吸収スーツに身を包んで、ただひたすらに耐えていた。彼らにとって、ディスコードは意味のない、ただ不快な騒音の塊でしかなかった。
しかし、僕には違って聞こえた。
生まれつきの絶対音感が、この戦場では呪いだった。他の兵士たちがぼんやりとした圧としてしか感じない音の濁流の中から、僕は個々の周波数を、その音程を、正確に聞き分けてしまう。それは、何千本もの錆びついた釘で鼓膜を引っ掻かれ続けるような、耐え難い苦痛だった。
その日も、塹壕の中で身を屈めながら、僕は敵から放たれるディスコードの新たなパターンに歯を食いしばっていた。金属が引き裂かれるような高音と、内臓が揺さぶられる重低音。そのはずだった。だが、その瞬間、僕は全身の血が凍りつくのを感じた。
この拷問のような騒音の奥深く、注意深く耳を澄まさなければ決して気づかない場所に、微かな、しかし確かに存在する「旋律」があったのだ。
それは、壊れたオルゴールが奏でるような、途切れ途切れのメロディ。悲しげで、どこか懐かしい響き。僕はその旋律を知っていた。それは、この戦争が始まるずっと昔、敵国である連合王国から伝わってきたとされる、古い子守唄の一節だった。なぜ、敵の兵器が歌っている? 殺戮と狂気をもたらすはずの音が、なぜ赤子をあやすための歌を奏でているんだ?
プロテクターの内で、僕の心臓が警鐘のように鳴り響く。これは何かの間違いだ。疲労が見せる幻聴か。だが、その旋律は幻聴にしてはあまりに明瞭で、僕の記憶の弦を静かに、しかし強く弾いていた。僕が知る由もないはずの、優しい温もりの記憶を。
世界を覆う不協和音のただ中で、僕はたった一人、禁じられた子守唄を聞いていた。それが、僕の、そしてこの世界の運命を根底から揺るがす始まりの音色だった。
第二章 沈黙の共鳴
子守唄の発見は、僕の日常を静かに侵食し始めた。以前はただの苦痛だったディスコードが、今や解読すべき暗号に変わってしまった。僕は任務の合間を縫って、敵の音波パターンに神経を集中させた。旋律は常にそこにあった。時に明瞭に、時にノイズの奥にかき消されそうになりながら、繰り返し、繰り返し奏でられていた。
この秘密を誰にも打ち明けることはできなかった。「敵の兵器が子守唄を歌っている」などと口にすれば、精神汚染を疑われ、即座に後方の施設送りにされるのが関の山だ。僕は孤独だった。鳴り響く轟音の中で、誰にも届かない旋律を一人で追いかける日々。それは、静寂の中で叫び声を上げるような、奇妙な孤立感だった。
戦況は悪化の一途をたどっていた。両軍は互いに対抗するように、より強力で、より複雑なパターンのディスコードを開発し、投入し続けた。味方の塹壕では、プロテクター越しにさえ精神の平衡を失い、泣き叫んだり、無気力に虚空を見つめたりする兵士が増えていった。指揮官たちの顔からも焦りの色が濃くなる。彼らはただ、出力の数値を上げることしか考えていないようだった。
そんな中、僕は一つの仮説に行き着いた。敵のディスコードに旋律があるのなら、我が軍のディスコードにも、何か隠されているのではないか?
僕は禁忌を犯す決意をした。自軍のスピーカーアレイに最も近い観測ポイントへ向かい、プロテクターの出力を意図的に下げたのだ。鼓膜が張り裂けるような衝撃と吐き気が襲う。だが、僕は耐えた。あらゆる感覚を耳に集中させ、暴力的な音の奔流の中から、意味のある響きを探し出す。
そして、見つけた。
それは、敵国のものとは全く異なる旋律だった。厳かで、力強い、行進曲のようなメロディ。しかし、それもまた断片的で、どこか不完全だった。まるで、壮大な楽曲のほんの一部分だけを、延々と繰り返しているかのようだった。
二つの旋律。敵の子守唄と、味方の行進曲。両者は全く異質で、何の関連性も見いだせない。僕は深い謎の森に迷い込んでしまったようだった。なぜ両軍は、破壊音の中にメロディを隠しているのか? これは、兵器開発者たちが残した、悪趣味なジョークなのだろうか。それとも、僕だけが聞いている、巨大な幻聴なのだろうか。
疑念が心を蝕む。だが、二つの旋律は僕の頭の中で確かに共鳴し、決して消えることはなかった。それは沈黙の共鳴だった。誰にも聞こえず、誰にも理解されない、僕だけの戦いが始まっていた。
第三章 戦場の二重奏
転機は、思いがけない形で訪れた。敵軍の奇襲によって、我々の前線基地が半壊。混乱の中、僕は旧式の記録保管庫に吹き飛ばされた。そこは、電子化される以前の、紙の資料が眠る場所だった。粉塵と古紙の匂いが立ち込める中、僕の目に飛び込んできたのは、埃をかぶった一冊の古い本だった。『両国伝統音楽集』と題されたその本は、戦争前の文化交流時代に出版されたものらしかった。
ほとんど無意識に、僕はそのページをめくった。そこに並んでいたのは、古びた楽譜の数々。そして、僕の目は一つの楽譜に釘付けになった。
『平和を祝す祖霊のフーガ』
それは、かつて共和国と連合王国がまだ一つの国だった時代、豊穣と平和を祈って共に歌われたとされる、伝説的な楽曲だった。楽譜は二段に分かれていた。高音部の、優しく流れるような旋律。そして、それを支える、力強く荘厳な低音部の旋律。
全身に鳥肌が立った。高音部の旋律は、紛れもなく敵のディスコードに隠された「子守唄」だった。そして低音部は、我が軍のディスコードが奏でる「行進曲」と完全に一致していた。
子守唄でも、行進曲でもなかったのだ。
二つの旋律は、本来一つになるべき「二重奏(デュエット)」の、それぞれのパートだったのである。
僕の頭の中で、全てのピースが音を立ててはまった。ディスコードは、単なる破壊兵器ではなかった。その開発者たちは、この狂った戦争を終わらせるための鍵を、兵器そのものに仕込んでいたのだ。おそらく、二つの音が完璧な調和をもって重なり合った時、何かが起こる。それは、両軍の兵器システムを無力化するキャンセル信号かもしれない。あるいは、全く未知の現象を引き起こすのかもしれない。
だが、現実はどうだ。両軍は互いの音を打ち消そうと、ただ出力を上げ、周波数をずらし、不協和音を増幅させている。善意で仕込まれたはずの平和への鍵は、互いの不信と憎悪によって、史上最悪の精神攻撃兵器へと成り果てていた。この戦争そのものが、壮大で、悲劇的な誤解の上に成り立っていたのだ。
愕然として、僕はその場に膝をついた。今まで信じてきたもの、戦う意味、敵への憎しみ、その全てがガラガラと崩れ落ちていく。僕たちは、平和の歌でお互いを傷つけ合っていた。これほど皮肉で、愚かなことがあるだろうか。
涙が頬を伝った。それは絶望の涙ではなかった。暗闇の奥に、一条の光を見出した者の涙だった。
僕には絶対音感がある。二つの旋律を聞き分けることができる。ならば、僕がやるべきことは一つしかない。この狂った二重奏を止めるのではない。完成させるのだ。二つの旋律を正しく調和させ、失われた「平和のフーガ」を、この戦場に響かせる。
呪いだと思っていた僕の耳は、この瞬間のためにあったのだ。僕はゆっくりと立ち上がり、楽譜を強く握りしめた。
第四章 調和のフーガ
僕には計画があった。大胆で、無謀で、一歩間違えれば反逆者として即刻処刑されるであろう計画。だが、迷いはなかった。
基地の通信システムの中枢は、奇襲によってほとんどの機能が停止していたが、一つだけ、旧式の広域放送システムが奇跡的に生き残っていた。それは本来、兵士たちに緊急指令を伝えるためのものだった。僕はそのマイクの前に立った。
まず、基地の音響システムにハッキングし、自軍のディスコードの周波数を微調整する。楽譜と僕の耳だけが頼りだ。敵の「子守唄」の旋律と、味方の「行進曲」の旋律が、最も純粋な和音を奏でるポイントを探り当てる。
次に、広域放送システムを起動する。僕がこれから発するのは、命令でも警告でもない。「歌」だ。楽譜によれば、『平和を祝す祖霊のフーガ』には、二つの旋律を繋ぎ、調和させるための第三のパート、人間の声によるカノンが存在した。
深く息を吸い込む。心臓が張り裂けそうだった。だが、頭の中に鳴り響くのは、完成されようとしている美しいフーガの響きだった。
「…聴いてくれ」
僕の声は、震えていた。だが、音程は完璧だった。僕は歌い始めた。何百年もの間、誰にも歌われることのなかった、祖霊への祈りの歌を。
僕の歌声が、調整されたディスコードの波に乗って、戦場全域へと広がっていく。
その瞬間、世界が変わった。
金属を削るような不協和音と、内臓を揺らす重低音が、ぴたりと止んだ。いや、止んだのではない。変貌したのだ。敵と味方のディスコードが、僕の歌声を触媒として完璧に共鳴し、一つの壮麗なハーモニーを織り成し始めた。
それは、教会のパイプオルガンのようでもあり、幾千の民が声を合わせた合唱のようでもあった。天から降り注ぐ光が音になったかのような、荘厳で、どこまでも優しい調べ。
塹壕に身を潜めていた両軍の兵士たちが、何事かと顔を上げる。恐る恐るプロテクターを外した彼らの耳に届いたのは、何十年も忘れていた、魂を震わせる美しい音楽だった。人々は呆然と立ち尽くし、武器を手に持っていることさえ忘れ、ただ空を見上げていた。涙を流す者もいた。硬直した表情が、ゆっくりと和らいでいく。
音波兵器の巨大なスピーカーは、破壊の象徴から、平和を奏でる楽器へと姿を変えていた。憎悪と狂気を撒き散らしていた鉄の塊が沈黙し、戦場はただ、美しいフーガの残響に満たされていた。
戦争は、終わった。一発の銃弾も、一人の犠牲者を出すこともなく、たった一曲の歌によって。
僕は英雄にはならなかった。ただの「歌い手」として、静かに故郷へと帰った。戦争がなぜ始まったのか、兵器に歌を仕込んだのは誰だったのか、その真相が明かされることはなかった。そんなことは、もはや重要ではなかったのかもしれない。
世界から不協和音は消えた。だが、本当の静寂が訪れたわけではない。人々はこれから、長い時間をかけて、失われた言葉と、忘れていた歌を取り戻していかなければならない。僕の耳に呪いのように響いていた絶対音感は、今、新しい世界の始まりを告げる最初の音色を、静かに聴き取っていた。戦場に響いたあのフーガのように、悲しみと希望が織り混ざった、複雑で、しかし美しい響きを。