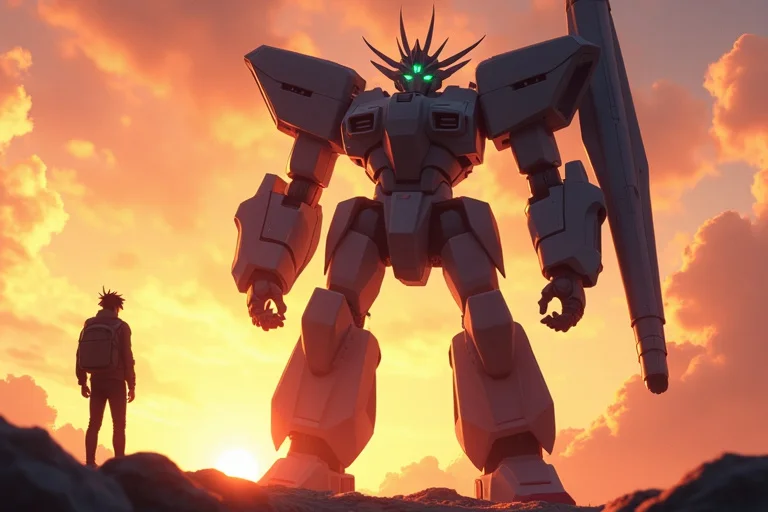第一章 憎しみの種子
灰色の空の下、停戦協定のインクが乾いてから半年が過ぎても、街にはまだ硝煙の記憶が染みついていた。人々は失われたものの大きさを数えることに疲れ、ただ黙々と瓦礫を片付け、乾いたパンを分け合って生き延びていた。私の兄、リオもその数えられた一人だった。彼の最後の報せは、東部戦線の泥濘の中から届いた、インクが滲んだ手紙だった。それきり、冷たい金属の認識票だけが故郷に帰ってきた。
そんなある日、政府はラジオを通じて奇妙な発表を行った。長きにわたる戦争の正式な講和条約の一環として、敗戦国である東方連合から「賠償」が届けられるという。金でも資源でもない。それは「追憶の花」と呼ばれる、植物の種子だった。
アナウンサーは淡々とした声で説明を続けた。その種子は、最新の生体記憶技術と園芸学を融合させたもので、植えて育てると、戦死した東方連合の兵士、一人ひとりの「記憶の断片」を宿した花が咲くのだという。花が放つ香りや光の揺らめきの中に、兵士が生前に見た風景、愛した人の顔、抱いた感情が、夢のように浮かび上がるのだと。
「和解と相互理解の第一歩として、彼らの人生を知る機会を…」
ラジオから流れる言葉に、私は吐き気を覚えた。兄を殺した者たちの記憶だと?冗談じゃない。食卓で硬いパンをかじっていた父は無言でラジオのスイッチを切り、母は静かに涙を流した。リビングの空気は、凍てついた湖面のように張り詰めていた。
数週間後、その「憎しみの種子」は、戸別台帳に基づいて各家庭に配布された。我が家に届けられたのは、くすんだ茶色の小さな紙袋だった。中には、黒曜石のように硬く、冷たい光沢を放つ一粒の種。添えられたカードには、機械的な文字でこう記されていた。『兵士番号819番。東部戦線、白樺の丘にて戦死』。兄が命を落とした、まさにその場所だった。
怒りに任せて、私はその種子を握りしめ、裏庭へと駆け出した。荒れ果てた庭の、雑草が生い茂る隅に力任せに投げ捨てる。土に埋めてやる価値もない。ここで朽ち果ててしまえ。兄の仇の記憶など、この世から消えてなくなればいい。私は種子に土くれを一つ投げつけると、踵を返した。背後で、冷たい風が枯れ葉をさらう音がした。
第二章 根を張る記憶
投げ捨てた種子のことなど、すぐに忘れてしまうと思っていた。だが、私の心とは裏腹に、世界は季節を巡らせようとする。数日後、長く続いた乾いた日々の後に、慈雨が街を濡らした。屋根を打つ雨音を聞きながら、私は窓の外を眺めていた。ふと、視線が裏庭の隅に引き寄せられる。私が種子を投げ捨てた、まさにその場所に、小さな、しかし力強い緑の双葉が顔を出していた。
忌々しい、と思った。引き抜いてしまおうか。だが、なぜか足が動かなかった。その小さな双葉は、まるでこの荒廃した世界で唯一、未来を信じているかのように、健気に天を仰いでいた。その姿に、野戦病院で握った若い兵士の、冷たくなっていく手を思い出してしまい、私はそっと窓から目を逸らした。
日々は過ぎ、その芽は私の無視をものともせずに成長を続けた。細い茎を伸ばし、葉を広げ、やがて硬そうな蕾をつけた。近所の家々でも、同じように花が育ち始めていた。ある夕暮れ時、隣家の庭から、ふわりと甘い香りが漂ってきた。見ると、隣の奥さんが、咲き始めた乳白色の花を、複雑な表情で見つめている。花びらからは淡い光が漏れ、そこには幼い子供の笑い声と、母親を呼ぶ優しい声が、幻のように響いていた。敵兵にも、家族がいた。当たり前の事実が、鋭い棘のように胸に突き刺さった。
その夜から、私は何かに憑かれたように、裏庭の蕾に水をやるようになった。憎い。憎いはずなのに、知らなければならない、という強迫観念にも似た感情が湧き上がっていた。兄を殺した男は、どんな人生を送っていたのか。どんな顔で笑い、誰を愛し、何を夢見ていたのか。それを知った上で、心ゆくまで呪ってやろう。そう自分に言い聞かせながら、私は来る日も来る日も、その蕾が綻ぶのを待ち続けた。まるで、判決を待つ罪人のように。
第三章 彼が見た空
月が満ちた夜だった。銀色の光が庭を照らす中、蕾が静かにほころび始めた。音もなく、一枚、また一枚と、夜闇の色を写したかのような、深い瑠璃色の花びらが開いていく。私は息を殺して、その瞬間を見守った。
花が完全に開くと、中心から燐光のような粒子が香りとともに立ち上り、私の目の前に一つの情景を映し出した。そこには、素朴な木造の家と、そばかすの浮いた笑顔の愛らしい女性がいた。若い兵士が、彼女の髪に野の花を飾り、はにかむように笑っている。彼の瞳は、澄んだ湖のように穏やかだった。次の瞬間、場面は変わり、彼は徴兵列車の中で、窓の外の景色を不安げに見つめていた。その手には、あの女性から贈られたであろう、手編みのマフラーが握られていた。
記憶は次々と流れ込んでくる。泥と汗にまみれた過酷な訓練。故郷を想い、仲間と歌を歌った夜。そして、戦場の恐怖。爆音、閃光、飛び交う怒号。彼の穏やかだった瞳は、恐怖と絶望に染まっていた。私は唇を噛みしめた。そうだ、こいつが、この男が、私の兄を…。憎しみが再び胸の内で燃え盛る。
私は、彼の最期の瞬間を見届けてやろうと、目を凝らした。記憶の風景は、見覚えのある白樺の丘に移る。砲弾が大地を抉り、木々は無残に引き裂かれている。その中で、彼は必死に身を伏せていた。その時、彼の視線の先に、負傷して倒れている兵士の姿が映った。私の軍の軍服。腕章の部隊番号。息が、止まった。リオだ。私の兄だった。
兄は腹部を押さえ、苦痛に顔を歪めている。もう助からないかもしれない、そんな絶望的な表情だった。私は目を覆いたくなる衝動に駆られた。この後、この敵兵が、兄に止めを刺すのだ。そうに違いない。
しかし、展開は私の予想を完全に裏切った。若い敵兵は、銃を置くと、躊躇いがちに、しかし確かに、兄の方へ這い寄っていったのだ。彼は自らの水筒を抜き、兄の乾いた唇を濡らし、覚束ない手つきで鞄から包帯を取り出した。何かを叫んでいるが、言葉は爆音にかき消されて聞こえない。ただ、その表情は、敵意ではなく、同じ人間に対する必死の憐憫に満ちていた。
その時だった。ヒュッ、と空気を切り裂く音が響き、一筋の光が二人を貫いた。どちらの軍から放たれたものか、もはや誰にも分からない流れ弾だった。若い敵兵は、兄の上に覆いかぶさるようにして倒れ、彼の記憶は、故郷の恋人が見せた最後の笑顔を映し出し、ぷつりと途絶えた。
残されたのは、静寂と、瑠璃色の花が放つ、穏やかで少しだけ悲しい香りだけだった。兄は、敵に殺されたのではなかった。敵兵は、兄を殺したのではなく、救おうとして、共に死んだのだった。
第四章 夜明けの花壇
どれほどの時間、庭に立ち尽くしていただろうか。夜は明け始め、東の空が白み始めていた。頬を伝うものが、涙だと気づいたのは、それが地面に落ちて小さな染みを作った時だった。憎しみという、長年私の心を覆っていた分厚い氷が、音を立てて溶けていくのが分かった。私が憎んでいた「敵」という記号の向こうには、ただ、故郷を想い、理不尽な死を恐れた一人の青年がいただけだった。兄と、何ら変わらない、名もなき一人の人間が。
私はそっと瑠璃色の花に触れた。花びらは朝露に濡れ、ひんやりとしていた。「ありがとう」と、私は囁いた。それは、兄を救おうとしてくれた彼への感謝であり、真実を教えてくれたことへの感謝だった。「ごめんなさい」とも囁いた。それは、彼の人間性を見ようともせず、ただ憎しみ続けていた自分への謝罪だった。
その日、私は物置から古びた鋤を持ち出した。そして、裏庭の荒れた土を、一心不乱に耕し始めた。兄が愛した白い野バラを植えよう。そして、彼の隣には、あの瑠璃色の花を。いや、もっと多くの花を植えよう。この戦争で失われた、敵とか味方とか関係なく、全ての「名もなき記憶」たちのために。彼らが確かにこの世界に生きていた証を、憎しみの連鎖を断ち切るための祈りを、ここに作りたかった。
私の小さな花壇作りは、まだ始まったばかりだ。この行為が世界を変えることなどないかもしれない。戦争の傷跡が、人々の心から完全に消えることもないだろう。
それでも、朝日が昇り、瑠璃色の花びらの上で光の粒が踊るのを見ていると、確かな希望を感じることができた。いつか、この庭に咲き誇る無数の花々が、憎しみではなく、鎮魂と、そして未来への静かな対話を人々の間にもたらすかもしれない。
私は土の匂いを深く吸い込み、もう一度、静かに鋤を振り下ろした。空は、どこまでも青く澄み渡っていた。