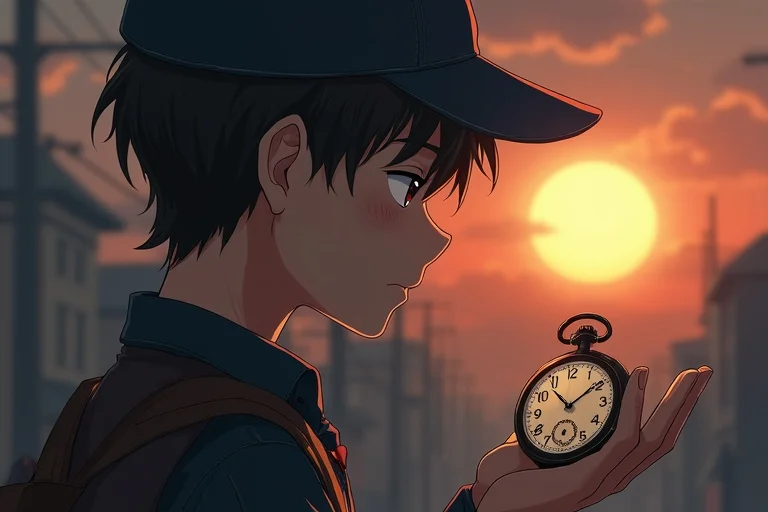第一章 霧の街と加速する鼓動
カイの心臓は、いつも人より少しだけ速く脈打っていた。それは恋慕のせいでもなければ、恐怖に駆られているわけでもない。彼の時間は、世界よりも速く進んでいた。特異体質。そう医師は言ったが、カイにとっては呪いと変わらなかった。
彼が生きるこの街、アウステルは常に灰色の霧に覆われている。大戦の終結から五十年。人々は平和を享受しているはずだったが、その代償のように立ち込める「情報の霧」が、過去のすべてを曖昧にしていた。歴史の教科書は毎年書き換えられ、祖父が語る戦争と父が学んだ戦争は、まるで別の出来事だった。霧は、ただの湿った大気ではなかった。それは物理現象化した、失われた過去の情報の奔流だった。
カイには、その奔流の中に漂う「時間粒子」を感知する力があった。粒子に触れれば、その瞬間の出来事を、まるで自分がそこにいたかのように追体験できる。だが、その力を得るたびに、彼の時間は未来へと「加速」した。一秒の追体験が、彼自身の未来を数時間、時には数日分も奪っていく。だから彼はいつも焦っていた。友人との会話も、食事の味も、彼の中を猛スピードで通り過ぎていく。
「また行くのかい、あの境界線に」
背後からかけられた声に、カイは革袋に最後の乾パンを詰め込みながら頷いた。歴史記録院のアーキビストであるリナが、心配そうな瞳で彼を見つめている。彼女のゆっくりとした瞬きすら、カイの目にはコマ送りのように映った。
「霧が、また濃くなっている。何か大きな記憶が、すぐそこで澱んでいるんだ」
カイは革袋の口を締めると、古びた真鍮のコンパスを手に取った。盤上でざらついた砂鉄が微かに揺れている。過去の真実の瞬間を指し示す、彼の唯一の道標。だが、使うたびに砂のように崩れていく、命にも似た道具だった。
「そのコンパスが砕け散ったら、お前は本当に過去に喰われるぞ」
リナの声には、湿った霧のような憂いが含まれていた。
カイは振り返らず、ドアノブに手をかけた。
「喰われる前に、真実を一口でも味わってみたいだけさ」
彼の言葉は、彼自身の時間と同じように、いつも少しだけ早口だった。
第二章 砂鉄が指し示す囁き
境界線と呼ばれる旧東西陣営の緩衝地帯は、情報の霧が最も濃い場所だった。一歩足を踏み入れると、冷たい湿気が肌にまとわりつき、錆びた鉄と遠い硝煙の匂いが鼻をついた。耳鳴りのように響くのは、無数の声なき声の残響か。カイは息を殺し、砂鉄のコンパスを霧の中へとかざした。
盤上の砂鉄は狂ったように回転し、まるで苦悶しているかのようだった。霧が濃すぎるのだ。無数の嘘と、歪められた真実が混ざり合い、コンパスを混乱させている。カイは目を閉じ、聴覚を研ぎ澄ませた。風の音、自分の鼓動、そして――微かな、金属の擦れる音。
その音の方向へ、カイは足を進めた。ぬかるんだ地面に足を取られながら進むと、崩れかけた塹壕の跡があった。その縁に、コンパスの砂鉄が一斉に吸い寄せられるように、ぴたりと静止した。ここだ。
カイは震える指で、塹壕の壁に触れた。泥にまみれた冷たい感触。その瞬間に意識を集中させると、指先から過去の奔流が流れ込んできた。
――世界が、反転する。
若い兵士の視界だった。泥と汗の匂い。握りしめた小銃は凍るように冷たい。だが、彼の心にあったのは敵への憎しみではなかった。故郷の麦畑の匂い、収穫祭で笑う妹の顔、パンを焼く母の手の温もり。彼はただ、それを守るためにここにいた。敵もまた、同じように守るべきものがあって銃を構えているのかもしれない。そんな考えが脳裏をよぎった、その瞬間。
突如、視界が赤黒い憎悪に塗りつぶされた。
『奴らは悪魔だ』『根絶やしにしろ』『正義は我らにあり』
どこからか流れ込んでくる声、声、声。家族の記憶は焼き尽くされ、目の前の敵兵の顔が悪魔のように歪んで見えた。引き金が引かれる。轟音。そして、静寂。
「……っ!」
カイは壁から手を引き剥がした。激しい動悸が胸を打つ。まただ。彼の時間が、数日分は未来へ跳んだ感覚。追体験した兵士の純粋な願いは、何者かによって暴力的な憎悪に「上書き」されていた。霧は歴史を隠すだけではない。人の記憶すら改竄するのだ。
第三章 二つの歴史
記録院に戻ったカイの顔は、普段の焦燥感に加えて、深い疲労の色が浮かんでいた。リナは黙って温かい茶を差し出す。湯気の揺らめきが、カイの目にはあまりにも緩慢に見えた。
「公式の戦闘記録だ」
リナが古びた電子タブレットを机に滑らせる。そこには、カイが追体験した塹壕戦の詳細が記されていた。『敵国の非人道的な奇襲攻撃に対し、我が国の兵士は正義の怒りをもって勇敢に応戦した』。英雄的な物語。だが、カイが見た兵士の最初の躊躇や、家族への想いは一行も記されていなかった。
「僕が見たものは、記録のどこにもない」カイは呟いた。「まるで、都合の悪い感情だけが綺麗に削ぎ落とされているみたいだ」
「情報の霧は、過去を風化させるだけだと言われてきた。でも……」リナは言葉を濁す。「もし、霧が特定の『解釈』を人々に植え付けるためのものだとしたら?」
彼女の言葉は、カイの心に突き刺さった。そうかもしれない。この終わらない対立の歴史は、誰かが意図的に作り上げた物語なのではないか。人々が互いを憎み続けるように、仕組まれた物語。
「霧の中心には、何がある?」
カイの問いに、リナは息を呑んだ。
「……誰も近づかないわ。『沈黙の塔』。かつて、最終和平交渉が決裂した場所よ。あそこは霧の発生源とも言われている。あまりに情報濃度が高すぎて、普通の人間は精神が崩壊する」
「普通じゃない人間なら、あるいは」
カイは、砂のように細かくなり始めたコンパスを見つめた。盤上の砂鉄は、もう半分近くが失われている。残された時間は、彼自身の時間も、このコンパスの命も、あとわずかだった。
第四章 霧の中心
沈黙の塔は、天を衝く巨大な墓標のように、霧の深淵に聳え立っていた。近づくほどに、コンパスの砂鉄は激しく震え、砕け散らんばかりに盤を打ちつける。カイの耳には、もはや意味をなさない言葉の洪水が絶え間なく響いていた。愛、憎しみ、希望、絶望。あらゆる感情が混ざり合い、彼の精神を削り取っていく。
塔の内部は、がらんどうの空間だった。中央には、かつて交渉のテーブルが置かれていたであろう円形の床があるだけ。コンパスは、その円の中心を指して、最後の役目を終えるかのように静止した。しかし、そこには何もない。ただ、冷たい石の床が広がるだけだった。
「何もない……?いや、違う」
カイは膝をつき、石の床に掌を押し当てた。これが最後になるかもしれない。彼は覚悟を決めた。自身の時間を未来へ大きく投げ打つ覚悟で、ありったけの意識を掌に集中させた。過去の最も深い場所へ。霧の根源へ。
――閃光。
視界が真っ白に染まり、次の瞬間、カイは交渉の場に立っていた。
敵対する二国の代表が、疲弊しきった顔で向かい合っている。だが、彼らの目には憎悪ではなく、安堵の色が浮かんでいた。
「……これで、戦争は終わる」
「故郷に、平和を持ち帰れる」
彼らが固く握手を交わそうとした、その瞬間だった。
どこからともなく、フードを目深に被った数人の影が現れた。彼らは自らを「歴史の編纂者」と名乗った。
『この和平は、あまりに地味だ』
影の一人が言った。
『後世に残すべきは、英雄が悪を討つという、気高き物語。妥協の歴史では、民の心は奮い立たない』
編纂者たちが手をかざすと、和平に合意したはずの代表たちの瞳から理性の光が消え、代わりに狂信的な憎悪の炎が宿った。彼らが交わした握手は、互いの喉を掻き切るためのものへと変貌した。その「解釈の書き換え」という行為が、凄まじいエネルギーの歪みを生み出す。空間が軋み、世界の理が悲鳴を上げた。そして、最初の「情報の霧」が、この沈黙の塔から噴出したのだ。
真の開戦理由は、対立ではなかった。後世に「美しい物語」を残そうとした人間の、傲慢な願いそのものだった。霧は、その歪んだ物語を真実として固定し、人々を永遠に争わせるための、巨大な呪いの装置だった。
第五章 解釈の螺旋
真実の奔流から弾き出されたカイの目の前で、砂鉄のコンパスが最後の輝きを失い、完全にただの砂へと還った。風が吹き込み、カイの手のひらから静かにこぼれ落ちていく。
すべてを理解した。この呪いを解くには、霧の発生源となった、あの「解釈の歪み」を正すしかない。和平が憎悪に書き換えられた、あの瞬間に介入する。そして、歴史を本来あるべき姿に戻すのだ。
カイは立ち上がり、再び塔の中心へと手を伸ばした。残された自分の時間をすべて注ぎ込めば、あるいは――。
彼は目を閉じ、意識を過去へと飛ばそうとした。編纂者たちの邪悪な介入を阻止し、二人の代表が交わすはずだった和平の握手を、守り抜くために。
だが、その指先が過去の時間の境界面に触れようとした、まさにその刹那。カイは凍りついた。
もし、自分が介入したら?
自分が「正しい」と信じる歴史に修正したら?
その行為は、かつての「歴史の編纂者」たちと、一体何が違うというのだろう。
カイが思う「正しさ」もまた、無数にある歴史の解釈の一つに過ぎない。彼の介入は、新たな解釈の歪みを生み、今ある霧とは質の違う、別の霧を発生させるだけではないのか。そして未来の誰かが、カイが創り出した霧を晴らすために、また新たな介入を試みる……。
それは、救いなどではなかった。ただ、無限に続く解釈の螺旋。争いの形を変えるだけの、永久機関。
真の敵は、特定の誰かではない。「歴史に絶対的な正解を求める」人間の、その本質そのものだったのだ。
カイは、そっと手を下ろした。
第六章 未来への加速
塔を出たカイを待っていたのは、変わらず世界を覆う灰色の霧と、彼の帰りを信じて立ち尽くすリナの姿だった。
「カイ……!」
駆け寄ってきたリナは、彼の顔を見て言葉を失った。ほんの数時間しか経っていないはずなのに、カイの瞳には、まるで数十年という歳月を生きたかのような、深い静けさと諦念が宿っていた。最後の追体験の代償は、彼の内側を駆け抜ける時間を、もう誰にも追いつけないほどに加速させていた。
「霧は、晴らせなかった」
カイは、穏やかに微笑んだ。その表情は、ひどく大人びて見えた。
「真実は、どうだったの?」リナが問う。
カイは首を横に振った。彼が語る言葉もまた、新たな解釈の種になるだけだ。真実とは、たぶん、誰にも所有できないものなのだ。
「少し、急ぎすぎたみたいだ。これからは、もう少し……ゆっくり歩くよ」
それは、彼が決して叶えられない嘘だった。
彼の時間は、これからも加速し続ける。リナが歳を重ねる間に、彼はその何倍もの時間を生きるだろう。いずれ、彼女の言葉も、世界の動きも、彼にとっては止まって見えるようになるのかもしれない。
カイは、誰にも語ることのできない真実を、たった一人で抱きしめた。
霧は晴れない。争いの歴史も終わらないだろう。
だが、彼はもう、その螺旋の構造を知っている。そして、その中で戦わないことを選んだ。それが、加速し続ける時間の中で彼が見つけた、唯一の抵抗だった。
カイは、未来へと流れ続ける孤独な時間の中を、一瞬一瞬を噛みしめるように歩き始めた。彼の背後で、忘却の霧は、今日も静かに世界を覆っていた。