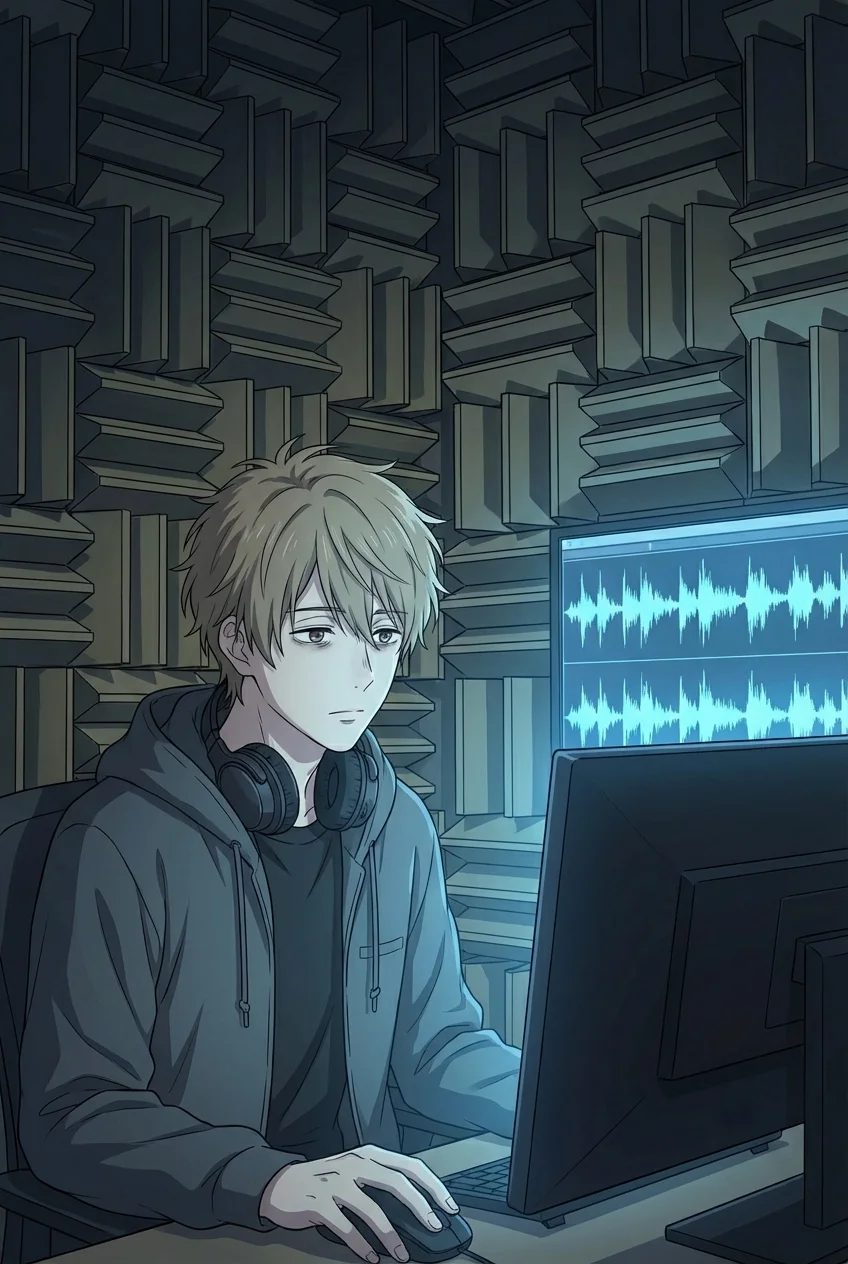第一章 糸のタペストリーと消えた男
僕、東耶(とうや)カイの目には、世界が巨大な織物のように映る。人々が日々繰り返す無意識の習慣――ルーティンは、色とりどりの「見えない糸」となって、その人の身体から伸び、複雑なタペストリーを編み上げていた。規則正しい生活を送る老人の糸は、緻密で頑丈な錦織のように輝き、気まぐれな若者のそれは、ところどころ解れた粗い麻布のようだった。
そして、この世界にはもう一つの法則がある。朝、目覚めると、誰もが手の甲にその日の「感情のテーマ」を授かるのだ。それはまるでタトゥーのように皮膚に浮かび上がり、一日の行動を支配する。『喜びの歌』、『悲しみの雨』、『怒りの炎』。そのテーマに背く感情を抱くと、罰のように世界が一瞬、色を反転させる。
今朝、僕の手の甲に浮かんでいたのは『追憶の霧』。だからだろうか、街の風景がどこか滲んで見える。角を曲がった先にある馴染みのカフェ「一日千秋」の扉を開けると、いつもそこに漂っていたはずの、豆を焙煎する香ばしい匂いがしなかった。代わりに、埃と静寂が僕を迎えた。
店主の佐伯さんの姿がない。彼の身体からは、いつも琥珀色と深緑色の糸が、規則正しくも温かい絨毯のように伸びていたというのに。今、彼のいたカウンターの内側には、力なく崩れ、色褪せた糸の残骸が散らばっているだけだった。
「佐伯さん?」
返事はない。テーブルの上には、飲みかけのコーヒーが冷たく残されている。そして、彼の左手袋が、床に落ちていた。僕はそれを拾い上げ、息を呑んだ。手袋で隠されていたはずの、手の甲の部分がぽっかりと円形に切り抜かれている。
最近、街で囁かれている噂が頭をよぎる。「空白の人間」の話だ。感情のテーマが、ある日突然「空白」になる。そうなった者は、これまで築き上げたルーティンの糸がすべて崩壊し、誰からも認識されなくなり、まるで最初から存在しなかったかのように消えてしまうのだと。
佐伯さんも、そうなってしまったのだろうか。僕はポケットから、いつも持ち歩いている古びた手鏡を取り出した。表面がうっすらと曇った、何の変哲もない鏡。だが、これだけが、失われた人々を追う唯一の手がかりだった。
第二章 曇り鏡の残像
手鏡を、佐伯さんがいつも座っていた椅子にかざす。曇った表面が、微かに揺らめき始めた。それは、他人の感情のテーマの奥底に眠る、真の願望や記憶を映し出す鏡。ただし、僕自身の内面は、決して映そうとはしなかった。
鏡の中に、映像が浮かび上がる。カウンターに立つ、疲れた顔の佐伯さんだ。彼の手の甲には『安らぎの旋律』というテーマが輝いている。しかし、鏡が映し出す彼の心の声は、テーマとは真逆の叫びだった。
『今日も、安らぎを演じなければ。穏やかでいなければ。客のどんな我儘にも、微笑みで応えなければ』
鏡の中の佐E伯さんが、ぐっと奥歯を噛みしめる。その瞬間、彼の周りの世界がネガフィルムのように反転し、すぐに元に戻った。彼は、与えられたテーマという役割に、心身をすり減らしていたのだ。鏡に映る彼のルーティンの糸は、琥珀色の一本だけが異常に太く肥大し、他のすべての糸を締め上げ、ちぎろうとしていた。
映像が消え、鏡は再びただの曇りガラスに戻る。僕はカフェを後にし、街を彷徨った。「空白」になった人々がいた場所を巡り、鏡をかざしていく。
『創造の熱』のテーマに燃え尽きた画家。アトリエには、狂気的な情熱で描かれた未完のキャンバスだけが残り、鏡は「もう描きたくない」という彼の悲痛な願望を映した。
『慈愛の光』を振りまき続けた看護師。彼女の部屋には、誰かのための贈り物ばかりが山積みになっており、鏡は「誰でもいい、私を愛して」という孤独な記憶を拾い上げた。
彼らは皆、自分のテーマに忠実すぎた。そして、その感情に殉じたのだ。彼らが消えた場所には決まって、一本だけが異様に肥大化した、歪な糸の残骸が残されていた。世界は、一つの感情に特化した人間を、まるで異物のように排除しているのではないか。そんな恐ろしい考えが、僕の心を支配し始めていた。
第三章 感情の調律師
答えを求め、僕は街の中央に聳える、大理石でできた古い公文書館へと向かった。埃っぽい書庫の匂いが鼻をつく。何時間も費やし、この世界の成り立ちに関する禁書に近い古文書の束を読み解いていった。
そして、ついに見つけたのだ。羊皮紙に書かれた、かすれた一節を。
『世界は感情の総和によりて成り立つ。一つの色が強すぎれば、織物は裂ける。故に、世界は自らを律するため、時に糸を断ち、調律を行う』
「調律……」
その言葉が、雷のように僕の脳を撃ち抜いた。「空白」は、罰でも消失でもない。世界のバランスを保つための、いわば強制的な調律。強すぎる感情という名のノイズを取り除くための、自己防衛システム。
だとしたら、空白になった人々はどこへ行ったのか。彼らは本当に「消滅」したのか、それとも――。
考えに没頭していた僕の背後で、ふいに冷たい声がした。
「あなた、何を探しているの?」
振り返ると、そこに一人の少女が立っていた。白いワンピースを着て、黒曜石のような瞳で僕をじっと見つめている。彼女の存在に、僕はまったく気づかなかった。まるで、初めからそこに空気が凝って生まれたかのように、彼女はそこにいた。
そして、僕は見てしまった。彼女の白く細い手首から覗く、手の甲を。
そこには、何もなかった。テーマを示すタトゥーも、その痕跡すらない。完全な、「空白」だった。
第四章 空白の使者
「君は……」
言葉が続かない。彼女は消えていない。僕の目の前に、確かに存在している。
「私はシズク。あなたと同じ、答えを探している者」
彼女はそう言うと、僕の持つ古びた鏡に目をやった。「その鏡、真実を映すそうね。でも、映るのはいつも過去だけ。未来は映らない」
彼女に導かれるまま、僕は公文書館の地下深くへと降りていった。ひやりとした空気が肌を撫でる。辿り着いたのは、巨大な空洞だった。壁面には青白い鉱石が埋め込まれ、まるで星空のように明滅している。そして、空間全体が、不協和音のような微かな振動に満たされていた。
「ここが、世界の歪みが集まる場所。人々の強すぎる感情が、時空を軋ませているの」
シズクが指差す先を、僕は凝視した。僕の目には、その振動が視覚化されて見えた。赤黒い『怒り』の奔流、どす黒い『嫉妬』の渦、狂おしいほどのピンク色をした『執着』の棘。様々な感情の過剰なエネルギーがぶつかり合い、世界そのものに亀裂を生もうとしていた。
「すごい……これが、世界の悲鳴……」
「そう。世界はもう限界なの。感情という名の鮮やかすぎる絵の具で、キャンバスが塗りつぶされ、破れかけている。だから、私たちは色を捨てることにした」
シズクは静かに自分の手の甲を見せた。
「空白になることは、消えることじゃない。感情という重荷を下ろし、世界を支える『柱』になるための儀式。私たちは純粋な意識体となって、この世界の過剰な色彩を中和し、調和を取り戻すの。佐伯さんも、画家も、看護師も、今は苦しみから解放されて、穏やかな光としてこの世界を支えているわ」
彼女の言葉は、僕が今まで信じてきた日常のすべてを根底から覆した。失われた人々は、犠牲者ではなかった。むしろ、世界の救済者だったというのか。
第五章 鏡が映した渇望
僕は震える手で、鏡をシズクに向けた。しかし、鏡面はただ静かに曇っているだけで、彼女の過去も願望も、何も映し出さない。彼女はすでに、鏡が映し出すような感情のしがらみから、完全に自由な存在なのだ。
その時だった。鏡の曇りが、ふっと一瞬だけ晴れ渡った。
そこに映っていたのは、シズクではない。驚愕に目を見開く、僕自身の姿だった。
僕の手の甲には、『探求の渇望』というテーマが、まるで烙印のように濃く浮かび上がっている。そして鏡は、そのテーマのさらに奥深く、僕自身も気づいていなかった魂の願望を、容赦なく映し出していた。
――ただ、静かになりたい。
糸が見えるこの目も。感情のテーマに揺さぶられる心も。すべてから解放されて、ただ、ありのままの世界を、音を、光を、風を感じたい。それこそが、僕が心の底から求めていた、唯一の願いだったのだ。
僕が追い求めていた謎の答えは、僕自身を縛り付ける、最も強い感情だった。この『探求の渇望』こそが、世界に負荷をかける、肥大化した一本の糸だったのだ。
涙が、頬を伝った。それは悲しみではない。ようやく本当の自分に出会えた、安堵の涙だった。
第六章 解き放たれる糸
「カイ。あなたは選べる」と、シズクが言った。「真実を人々に告げ、世界を混沌に陥れることも。これまで通り、糸を眺めながら生きていくことも。そして……私たちと同じ道を選ぶことも」
僕は静かに頷いた。失われた日常を取り戻すことは、苦しんでいた人々を再び感情の牢獄へ引き戻すことと同じだ。僕が求めていたのは、そんな結末ではなかったはずだ。
僕が本当に取り戻したかったのは、佐伯さんの笑顔ではなく、彼が本当に得たかった「安らぎ」そのものだったのかもしれない。
僕は、古びた手鏡をそっと床に置いた。鏡は、カタリと乾いた音を立て、役目を終えたように静止した。もう、他人の心を覗き込む必要はない。自分の心と向き合う時が来たのだ。
「ありがとう、シズク。僕は、決めたよ」
シズクは、初めて微かに微笑んだように見えた。それは、どんな感情のテーマにも染まっていない、透明な水面のような微笑みだった。
第七章 静かな朝のソナタ
翌朝、僕は見慣れた自室のベッドで目を覚ました。窓から差し込む光が、いつもより柔らかく感じる。ゆっくりと左手の甲に視線を落とす。
そこは、生まれたての赤子のように、清浄な肌色をしていた。「空白」。
僕は起き上がり、窓を開けた。眼下に広がる街の風景。しかし、そこにはもう、色とりどりの糸が織りなすタペストリーはなかった。人々はただの人々として、そこを歩いている。僕の目には、ただありのままの光景が映っていた。誰かの日常に干渉することも、評価することもない、ただ、そこにあるがままの世界。
街に出る。すれ違う人々は、僕の存在に気づかない。僕はまるで透明人間になったかのようだ。だが、不思議と孤独は感じなかった。むしろ、世界のすべてと繋がっているような、穏やかな一体感があった。
頬を撫でる風の感触。遠くで鳴る教会の鐘の音。パン屋から漂う小麦の焼ける匂い。そのすべてが、感情というフィルターを通さず、直接僕の意識に流れ込んでくる。世界は、こんなにも静かで、美しかったのか。
これは喪失ではない。再生だ。感情という名の激しい交響曲が終わりを告げ、今、世界と僕とが共に奏でる、静かなソナタが始まったのだ。僕は、名前もない一筋の光として、この美しくも新しい日常の中へ、静かに溶けていった。