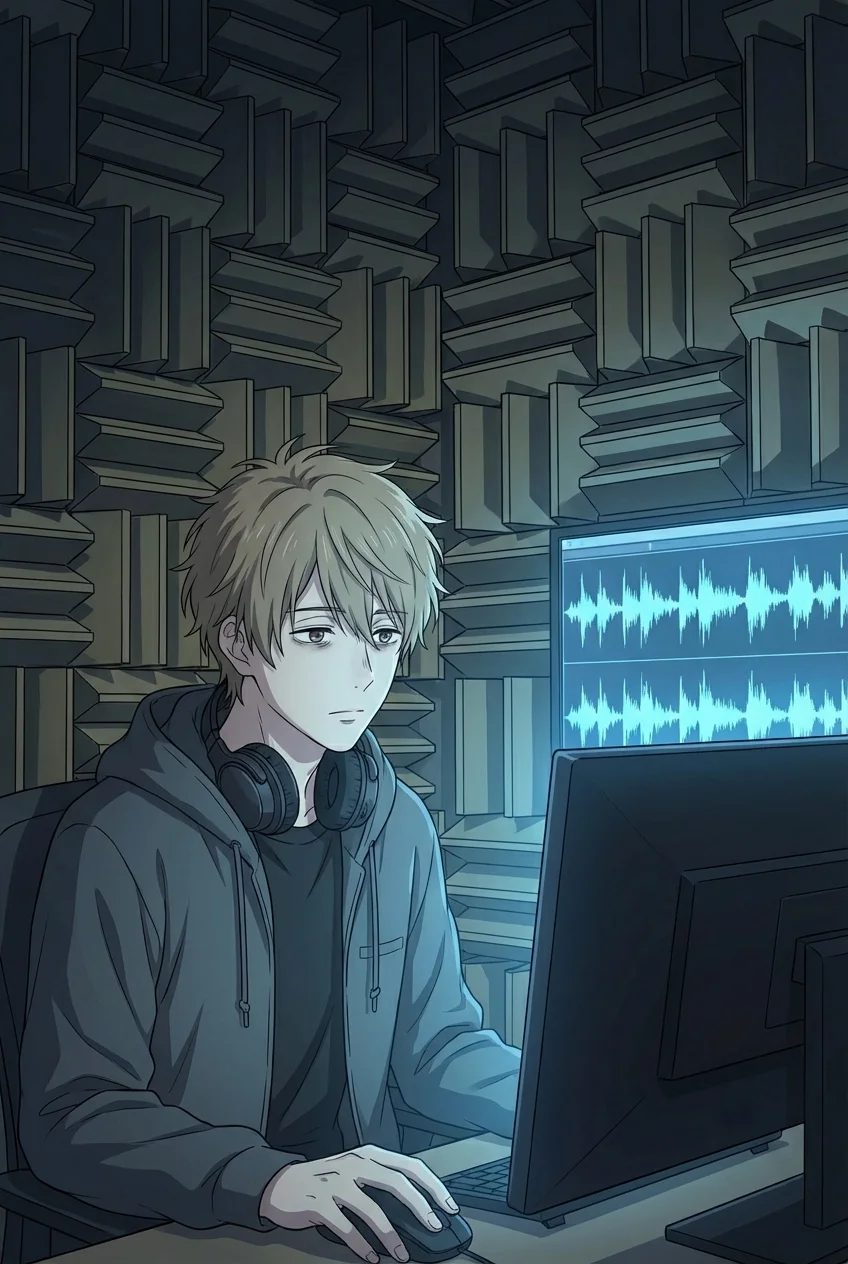第一章 三時三十三分、停止する世界
シュウ、と鋭い音を立ててエスプレッソマシンの蒸気が昇る。
カウンターの砂糖壺が、定位置から二ミリ右にずれていた。たったそれだけの「ズレ」が、私の網膜には腐ったライムのような蛍光緑の飛沫として焼きつく。吐き気を堪え、指先で壺を慎重に滑らせた。ある一点で蛍光色は霧散し、世界は冷徹な透明度を取り戻す。
「アオイちゃん、顔色が悪いよ」
バックヤードから飛び出してきた店長の声が、鼓膜を打つ。
彼は私のために水を汲もうと慌てたのだろう。シャツの第二ボタンが掛け違えられ、布地が奇妙に引きつっていた。
いつもなら、その非対称さを「汚泥のような赤褐色」として嫌悪したはずだ。けれど、私の前に差し出された水入りのグラスと、心配そうに揺れる彼の瞳を見た瞬間、その赤褐色の中に、微かな温かみ――冬の日向のようなオレンジ色が混じっていることに気づいた。
なぜだろう。胸の奥で、鉛色の重りが少しだけ揺らいだ気がした。
早退を促され、逃げるように路地裏へ入る。
角を曲がった先、古びたアンティークショップのショーケースだけが、私の安息の地だった。鎮座する銀色の懐中時計。針は今日も「午後三時三十三分」を指して凍りついている。
一秒の狂いもなく、死んだように静止した時間。そこには一切の「色」がない。私はガラスに額を押し付け、完全なる無音に浸ろうとした。
その時だ。
視界の端で、石畳の継ぎ目が「瞬き」をした。
色が、決壊する。
いつものノイズではない。空間そのものがピクセル状に崩落し、向かいの家の壁が一瞬、裏返ったかのように黒い虚無を晒した。通りがかった野良猫が空中で静止し、フィルムのコマが飛ぶように数メートル先へ瞬間移動する。
周囲の歩行者は誰も気づかない。まるで、その瞬間だけ意識を切り取られたかのように、笑顔のままで硬直している。
世界がバグっている。
痙攣した風景の中心から、一筋の「黄金色の亀裂」が走り、街の図書館へと伸びていた。
第二章 修正される逸脱
黄金の亀裂を跨ぎ、私は図書館の前へ辿り着いた。
ガラス張りの壁の向こうで、司書が本を棚に戻している。その動きはあまりに滑らかで、人間というよりは精密な油圧機械のようだった。呼吸のリズム、まばたきの回数、すべてが完璧な円環を描いている。
違和感の正体は、広場のベンチにいた老婦人だった。
彼女はこの時間、必ずハムサンドを食べる。それがこの街の「設定」であるかのように。
だが今日、彼女の手にあるのは卵サンドだった。彼女がそれを口元へ運ぼうとした、その刹那。
世界が軋んだ。
突如として空が低くなり、物理的な質量を持って広場にのしかかる。大気がゼリー状に凝固し、老婦人の腕を強引に押し戻そうとする圧力が生まれた。
私の目には見えた。空から降り注ぐ無数の透明な触手が、老婦人の手元を、風景を、強制的に書き換えていく様が。
バチッ、と焦げ付くような音と共に、卵サンドがノイズに飲まれる。
次の瞬間、彼女が手にしていたのは、いつものハムサンドだった。
老婦人は何事もなかったかのように微笑み、それを齧る。周囲の景色も、一瞬の歪みを経て、完璧な「日常」へと再構成されていた。
戦慄が背筋を駆け上がる。
誰も気づいていないのではない。気づくことを許されていないのだ。
この街は、誰かの手によって管理された箱庭だ。
そして私のこの目――些細なズレを「色」として感知するこの能力は、バグを排除するためのエラー検知システムそのものだったのだ。
私の頭上で、空が巨大な眼球のようにうねり、私を見下ろしている気配がした。お前も修正対象か、と問うように、圧倒的な重圧が肩に食い込む。
第三章 彩りという名のバグ
息ができない。肺が押し潰されそうな圧迫感の中で、私の脳裏にあの色が蘇る。
店長の、掛け違えられたボタン。
あれはシステムから見れば、修正すべきエラーだったのかもしれない。
だが、あの不格好な「ズレ」の中にこそ、私を案じる彼の心があった。
完璧な整列には存在しない、不純で、あたたかい人間味。
「……ふざけないで」
私は、私を圧死させようとする透明な大気に向かって、歯を食いしばった。
老婦人が卵サンドを食べたかったのなら、それを許すべきだ。店長が慌ててボタンを間違えたなら、その優しさをなかったことにさせてはいけない。
「傷つかないことが幸福じゃない……! 迷って、間違えて、色が濁ることこそが、生きているってことでしょう!」
私は、空から伸びる修正の触手を睨みつけた。
拒絶する。この停滞した平穏を。
その瞬間、私の視界が極彩色に爆発した。
今まで「ノイズ」として嫌悪していた街のあらゆる色が、奔流となって私の中に流れ込んでくる。隣家の少年が転んだ時の痛みの青、恋人たちが喧嘩した時の激情の赤。それらが混ざり合い、私の内側で渦巻いていた鉛色を洗い流していく。
バリ、バリバリ、と音を立てて、世界を覆っていた薄い膜が剥がれ落ちていく。
管理者の圧力が霧散し、代わりに肌を刺したのは、生温かく不規則な突風だった。
私はアンティークショップの前まで走っていた。
ガラスケースの中を見る。
午後三時三十三分。永遠に止まっていたはずの秒針が、わずかに震え――。
カチリ。
乾いた音と共に、針が進んだ。
三時三十四分。
たった一分の前進。だがそれは、この街が「管理された永遠」から決別し、予測不能な未来へと足を踏み出した決定的な証だった。
ショーケースのガラスに、私の顔が映っている。
そこにはもう、神経質な蒼白さはなかった。乱れた髪と、上気した頬。瞳の奥には、恐怖と高揚が入り混じった、名前のつけられない複雑な色が揺らめいている。
街を見渡す。
空の色は均一な青ではない。雲がちぎれ、光がまだらに降り注ぐ。誰かの笑い声と、車のクラクションが不協和音を奏でている。
そのすべてが、愛おしい。
私は深く息を吸い込み、未完成で鮮やかな午後の中へと、最初の一歩を踏み出した。