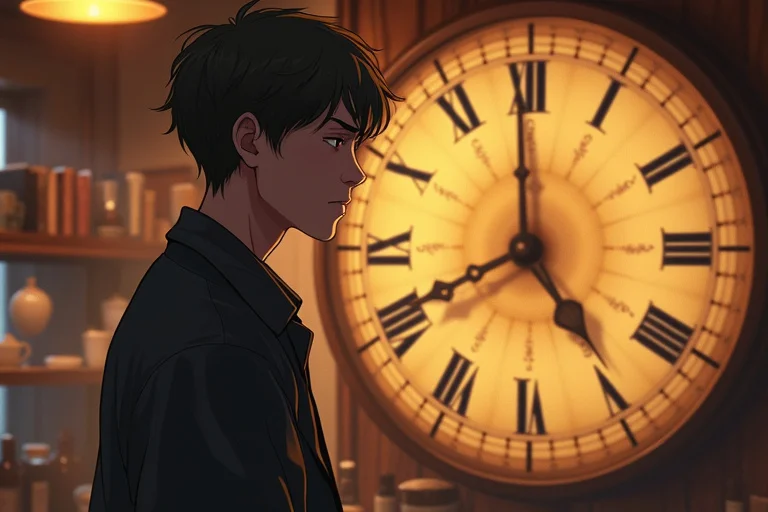第一章 雨音と砕けた記憶
古いニスと、湿った畳の匂い。
俺の店は、いつだってその二つの匂いで満たされている。
路地裏の突き当たりにあるこの「修繕屋」に、客なんて滅多に来ない。
来るとしても、近所の婆さんが壊れた鍋の取っ手を持ってくるか、野良猫が雨宿りに来るくらいだ。
今日もそうだ。
朝から降り続く雨が、トタン屋根を執拗に叩いている。
ラジオからは、気怠げなジャズが流れていた。
俺は作業台に向かい、欠けた茶碗の縁を指でなぞる。
ザラリとした感触。
「……そろそろ、漆が乾く頃か」
独り言が、狭い店内に吸い込まれていく。
俺、坂本健二は、壊れたものを直すことだけで生計を立てている。
人間関係は直せないくせに、茶碗や箪笥なら直せる。
皮肉なもんだ。
カラン、コロン。
ドアベルが鳴った。
風が吹き込み、湿った空気が一気に流れ込んでくる。
「いらっしゃい」
顔を上げずに声をかけた。
どうせ、郵便屋だろうと思った。
だが、返事がない。
代わりに、ヒールがコンクリートの土間を叩く音がした。
コツ、コツ、コツ。
その足音には、どこか迷いがある。
俺は作業用のルーペを外し、ゆっくりと顔を上げた。
そこに立っていたのは、若い女だった。
濡れたベージュのトレンチコート。
長い黒髪には、雨の雫が光っている。
傘も差さずに来たのか、肩が小刻みに震えていた。
「修理、ですか」
俺が尋ねると、彼女はコートの懐から、布に包まれた何かを取り出した。
白いハンカチ。
そこには、赤錆のようなしみが滲んでいる。
彼女は震える手で、それをカウンターの上に置いた。
「……これを、直してほしくて」
声が掠れている。
俺はハンカチを解いた。
中から出てきたのは、無惨に砕け散った木片と、ひしゃげた金属の塊だった。
かつて「オルゴール」だったものだ。
「酷いな」
思わず口に出た。
高い所から落としたのか、あるいは誰かに踏みつけられたのか。
木の箱はバラバラで、心臓部であるシリンダーも歪んでいる。
「直せますか……?」
彼女が縋るような目で俺を見る。
その瞳の奥に、強い焦燥感が見えた。
ただの物じゃない。
俺の職人としての勘が、そう告げている。
「やってみないと分からん。だが、元通りの音が出る保証はないぞ」
「構いません。形だけでも……いえ、どうしても、もう一度聞きたいんです」
「期間は一週間。代金は成功報酬だ」
俺は伝票を書きなぐり、彼女に渡した。
「お名前は」
「……サトウ、です」
嘘をついている時の間だ。
だが、詮索はしない。
俺は壊れたオルゴールを受け取り、作業台のライトの下に置いた。
彼女が出ていくと、再び雨音だけが店内に残された。
第二章 沈黙の修復
木片の断面を見る。
ウォールナットだ。
それも、かなり古い。
断面の毛羽立ち方からして、強い力が加わったのは間違いない。
まずは木工用ボンドではなく、膠(にかわ)を煮溶かすところから始める。
独特の獣臭さが鼻をつく。
この匂いを嫌がる客もいるが、古い家具や楽器を直すには、化学接着剤じゃ駄目なんだ。
木が呼吸できなくなる。
破片をパズルのように組み合わせ、膠で接着し、麻紐で縛って固定する。
欠損している部分は、似た木目の古材を削り出して埋める。
単純作業だ。
だが、俺の指先は、その木の記憶を読み取ろうとしていた。
使い込まれた角の丸み。
底面に残る、微かな擦り傷。
大切にされていた形跡と、突発的な暴力の痕跡。
「……夫婦喧嘩か、それとも」
ピンセットで、歪んだシリンダーのピンを一本ずつ起こしていく。
0.1ミリの狂いが、音を殺す。
息を止める。
心臓の鼓動が指先に伝わらないよう、体の力を抜く。
カチッ。
微かな手応え。
その繰り返し。
夜が更け、雨は小降りになっていた。
俺はふと、引き出しの奥にある一枚の写真を思い出した。
10年前に死んだ妻と、家を出て行った娘の写真。
俺が仕事にかまけて家庭を顧みなかったせいで、娘は妻の葬式の日に俺を罵倒し、そのまま消えた。
『お父さんは、機械しか愛せないのね』
あの時の言葉が、今でも胸の奥に刺さったまま、錆びついている。
俺は自分の心を直せないまま、他人の思い出ばかりを修理している。
シリンダーの修正が終わった。
櫛歯(コーム)の錆を落とし、慎重に噛み合わせる。
試しにハンドルを回してみる。
ジジジ……。
まだ、雑音が混じる。
「違うな」
俺は溜息をつき、眼鏡の位置を直した。
このオルゴールには、特殊な仕掛けがある。
普通の既製品とは違う、ピンの配列。
誰かが、手作業で打ち直しているのだ。
特定のメロディを奏でるために。
俺は楽譜もなしに、ピンの位置から音を想像する。
ド、ミ、ソ……いや、半音下がっている。
短調か?
修正を重ねるうちに、奇妙な既視感を覚え始めた。
この配列。
この不器用なピンの打ち方。
そして、箱の底に隠されていた、小さな彫り込み。
『K to Y』
俺の手が止まった。
背筋に冷たいものが走る。
まさか。
俺は震える手で、もう一度ハンドルを回した。
ポロン、ポロン。
途切れ途切れだが、メロディが繋がった。
それは、よくあるクラシックの名曲なんかじゃない。
俺が、20年前に作曲した曲だ。
売れないバンドマンだった頃、妊娠中の妻のお腹に向かって、毎晩ギターで弾いていた曲。
『星降る夜の眠り歌』。
世界で、俺と妻しか知らないはずの曲。
「……そうか」
俺は作業台に突っ伏した。
涙など枯れたと思っていたのに、視界が滲んで作業ができない。
あの客は、サトウなんかじゃない。
ユイだ。
俺の娘、結衣だ。
第三章 継がれた心
約束の一週間後。
雨は上がり、薄日が差していた。
カラン、コロン。
同じ足音が近づいてくる。
俺はカウンター越しに、完成したオルゴールを差し出した。
ひび割れていた箇所は、金粉を混ぜた漆で修復してある。
「金継ぎ(きんつぎ)」だ。
傷を隠すのではなく、傷を景色として愛でる技法。
「……直ったんですね」
彼女、いや、結衣が息を呑む。
金色の線が走る箱は、持ち込まれた時よりも、どこか凛として見えた。
「音も、出るはずだ」
俺の声は、自分でも驚くほど震えていた。
結衣は恐る恐る、小さなハンドルに指をかけた。
ゆっくりと、回す。
ポロン、ポロン、ポロロン……。
澄んだ音色が、店内に響き渡る。
どこか寂しげで、でも温かい、短調の子守唄。
結衣の手が止まった。
肩が震え、その目から大粒の涙が溢れ出した。
「……お母さんが、言ってたの」
彼女は顔を伏せたまま、絞り出すように言った。
「この曲は、お父さんが私のために作ってくれたんだって」
俺は言葉が出なかった。
ただ、カウンターを握りしめる。
「お母さんが亡くなる前、このオルゴールを私にくれたの。『お父さんは不器用だけど、この曲みたいに優しい人だから』って」
「……ああ」
「でも、私、お父さんを許せなくて……これを壁に投げつけたの。そうしたら、音が鳴らなくなっちゃって……」
結衣は顔を上げ、涙に濡れた瞳で俺を見た。
「直してくれて、ありがとう。……お父さん」
その一言を聞いた瞬間、俺の中で止まっていた時計が、再び動き出した気がした。
俺はカウンターを回り込み、不器用に手を伸ばした。
抱きしめるなんて、何年ぶりだろう。
娘の体は、記憶の中よりもずっと細く、そして温かかった。
「悪かったな……結衣」
「ううん……私も」
店の中に、オルゴールの余韻が優しく漂っていた。
ひび割れた茶碗も、砕けたオルゴールも、そして壊れた親子の絆も。
金色の継ぎ目で繋げば、前よりも強く、美しくなれる。
そう信じてもいいような気がした。
「お茶でも、飲むか?」
俺が聞くと、結衣は涙を拭って、幼い頃と同じ笑顔を見せた。
「うん。……渋いやつね」
雨上がりの空に、虹がかかっているのが見えた。
俺たちの修復は、まだ始まったばかりだ。
けれど、もう大丈夫だ。
俺は、修理屋なのだから。