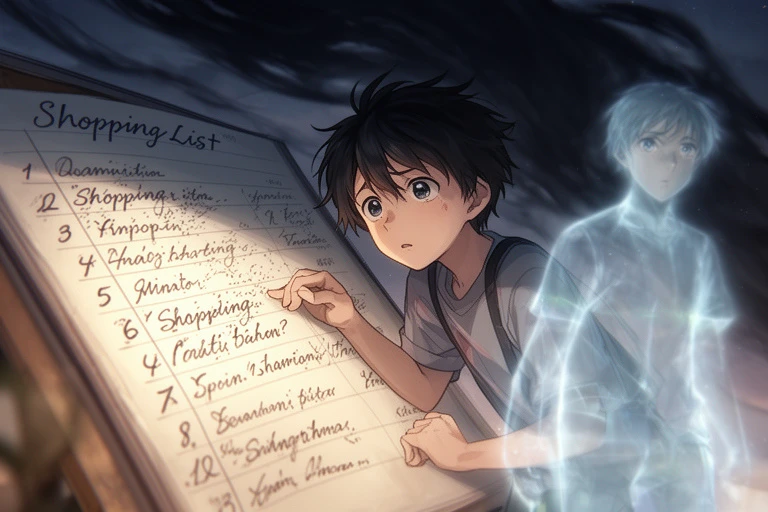第一章 消えたカッコー
御厨響介(みくりや きょうすけ)の耳は、世界からこぼれ落ちる音を拾うためにあるようだった。
それは、他の誰もが意に介さない、日常という名の巨大な交響曲から、ふと一つの楽器が音を止める瞬間。今もそうだ。ひっきりなしに人が行き交うスクランブル交差点。青信号を告げる「カッコー」という電子音が、三度目の鳴動の途中で、ぷつりと糸が切れるように消えた。
響介は立ち止まる。
周囲の人々は、何事もなかったかのように歩き続ける。スマートフォンの画面に目を落とす者、イヤホンで耳を塞ぐ者、隣の友人とのおしゃべりに夢中な者。誰一人として、世界のサウンドトラックに空いた小さな穴に気づかない。
だが、響介には聞こえていた。いや、聞こえなかったのだ。その『無音』が、鼓膜を圧迫するほど雄弁に響いていた。
ポケットの中で、古びた懐中時計が微かに震える。祖父の形見であるその時計には、文字盤に一本の針しかない。時間を告げるのではなく、世界の綻びを告げる針。響介がそっと手のひらに乗せると、銀色の針は震えながら、音を失ったスピーカーの方角を静かに指し示していた。
ここ最近、こんなことが頻繁に起きている。街角のポストに手紙が落ちる音、隣室から漏れるテレビの音、そして時には、自分の左胸で脈打つはずの心臓の鼓動さえも。
世界が、少しずつ静かになっていく。その不気味な静寂の正体を、響介だけが知っていた。
第二章 日常の澱み
音の消えた場所には、奇妙な『澱み』が残る。それは目に見えないが、肌で感じることができた。空気がゼリーのように粘性を帯び、光が僅かに屈折して、世界の輪郭が滲んで見える。人々が決まりきった日常を繰り返すことで生まれる、時間の結露。響介はそれを『日常の澱』と呼んでいた。
懐中時計の微かな震えを頼りに、響介は特に澱みの深い場所へと足を向けた。路地裏にひっそりと佇む、創業五十年の喫茶店『待宵(まつよい)』。重い木製のドアを開けると、カラン、と鳴るべきドアベルの音が、今日はしなかった。
店内の空気は、まるで琥珀の中に閉じ込められたようだった。カウンターで同じ席に座り、同じブレンドを頼む老人。窓際の席で、毎日同じ時間に文庫本を開く女性。彼らの無意識の反復が、この空間の時間を外界から切り離し、濃密な澱みを生み出している。コーヒーの湯気が、まるで時が止まったかのように宙に長く漂っていた。
響介がカウンター席に腰を下ろした、その時。店内に低く流れていたジャズのレコード、そのサックスのソロパートが、最も情熱的なフレーズの頂点で『無音』になった。
心臓が跳ねる。ポケットの時計が、かつてないほど強く震えた。針が、店の隅で静かに回転するレコードプレーヤーを狂おしく指し示す。その瞬間、響介の目に、窓の外を猛スピードで走り抜ける自転車の影が映った。あまりに速く、まるでコマ送りの映像のようだ。この澱みの中では、外の世界の時間が加速している。
『澱み』が崩壊する前兆。音の欠落は、その叫びだった。
第三章 震える針が指す過去
音の欠落は、伝染病のように街中に広がっていった。駅の発車メロディが途切れ、電車は理由もなく遅延し、あるいはあり得ないほど早く到着した。人々は苛立ち、時計を睨みつけ、世界の調律が狂い始めていることに無自覚なまま、ただその不便さに眉をひそめていた。
響介は、もはや震え続ける懐中時計を道標にするしかなかった。時計の針が指し示すのは、ただ音が消えた場所だけではない。それは、失われた『音の残響』が眠る場所でもあった。
針に導かれるまま歩くと、彼は古い公園の跡地に行き着いた。そこはかつて、子供たちの笑い声と、噴水の水音が響いていた場所だ。今はただ、風が乾いた土を撫でる音しかしない。時計の針は、今はもうない噴水の中心を指して静止した。
またある時は、取り壊された映画館の前に。恋人たちが囁き合い、ヒーローがスクリーンの中で叫んでいた場所。時計は、瓦礫の山に残るチケット売り場の跡を指していた。
失われた日常の音。人々が忘れ去った、あるいは、もはや必要としなくなった音の墓標を、響介は巡礼者のように辿り続けた。そしてついに、懐中時計の針は、一つの場所を指して動かなくなった。
響介が幼い頃に住んでいた、再開発でゴーストタウンと化した街。その中心、彼が父の肩車から見上げた、あの時計台があった広場だった。
第四章 無意識のレクイエム
錆びついたフェンスを乗り越え、響介は廃墟の街に足を踏み入れた。アスファルトの裂け目から伸びる雑草が、彼の足に絡みつく。空気が重い。ここには、街一つを丸ごと包み込むほどの、巨大な『日常の澱』が渦巻いていた。人々が去った後も、かつて此処にあった無数の日常の記憶が、時間の澱となって沈殿しているのだ。
広場の中央、時計台の土台だけが残る場所に立った瞬間、ポケットの懐中時計が断末魔のような悲鳴をあげて震えた。響介が取り出すよりも早く、パリン、とガラスの割れる微かな音が響く。
文字盤を覆うガラスが砕け、一本きりの針が根元から折れて、乾いた土の上に落ちた。
その時だった。
『――つまらない』
『何か変わらないか』
『毎日同じことの繰り返しだ』
『このまま、終わるのか』
声が、直接脳内に響き渡った。一人ではない。何百、何千、いや、何万という人々の声。それは悲しみであり、怒りであり、そして切実な祈りだった。日常という名の檻からの解放を願う、無意識の合唱。変化への渇望が織りなす、鎮魂歌(レクイエム)。
響介は悟った。音を奪い、澱みを破壊していたのは、特定の誰かではない。他ならぬ、日常を生きる人々自身の、無意識の集合体だったのだ。彼らが自らの手で、自らが作り上げた安定という名の牢獄を、内側から壊そうとしていた。音の欠落は、その破壊の槌音だったのだ。
あまりの衝撃に、響介は膝から崩れ落ちた。世界が、人々の願いに応えて、自ら壊れようとしていた。
第五章 無音の揺りかご
無数の声に意識を飲み込まれ、響介は底のない場所へ落ちていった。
やがて彼が目を開けた時、そこにいたのは、完全な『無』の中だった。上も下も、右も左もない。色も、匂いも、そして音も、何一つ存在しない真っ白な空間。ここは、全ての日常が生まれる前の原点であり、全ての日常が還る終着点。
時間の概念すら存在しない、永遠の静寂。
不思議と恐怖はなかった。むしろ、胎内にいるような安らぎを感じた。ここでなら、もう世界の軋む音を聞かなくて済む。そう思った瞬間、響介の内に、ある感覚が芽生えた。
それは、一つの『力』だった。
この空間から、世界へ向けて『音』を返すことができる。失われた信号機の音、ドアベルの音、ジャズの音、子供たちの笑い声。人々が日常の愛おしさを思い出す、始まりの音を。そうすれば、澱みは修復され、狂った時間の歯車は再び噛み合うだろう。世界は安定を取り戻す。
だが、それは同時に、人々を再び単調な反復の日々へと閉じ込めることでもあった。変化を求める彼らの願いを、踏み躙ることになる。
混沌とした、しかし変化に満ちた今を肯定するのか。
それとも、安定した、しかし停滞した過去を取り戻すのか。
世界の運命が、響介の選択に委ねられた。彼は、この無音の揺りかごの中で、たった一人、世界の調律師となったのだ。
第六章 選択しないという調律
響介は、選ばなかった。
彼は力を使わなかった。ただ静かに、この無音の空間に満ちる人々の願いを、その全身で受け止めた。そして、ゆっくりと意識を浮上させた。
気がつくと、彼は時計台の跡地で仰向けに倒れていた。夕暮れの空が、紫色に染まっている。手の中には、針を失い、ガラスの砕けた、ただの金属塊となった懐中時計が握られていた。もう、それは震えることはない。
響介はゆっくりと身を起こし、街へ戻った。
世界は、まだ不協和音を奏で続けていた。駅のホームでは、電光掲示板の時刻表示が明滅を繰り返し、人々は戸惑いながらも、次の電車がいつ来るかをお互いに尋ね合っている。いつもなら無言ですれ違う人々が、言葉を交わしている。
交差点では、信号機が故障し、若い警官が必死に笛を吹いて交通整理をしていた。ドライバーたちは窓を開けて、不器用な手信号で道を譲り合っている。クラクションの代わりに、そこには「ありがとう」という小さな声があった。
それは不便で、不安定で、混沌としているかもしれない。
だが、死んではいなかった。停滞もしていなかった。人々は、壊れた日常のルールの中で、もがき、戸惑いながらも、自分たちの手で新しいリズムを、新しい関係性を紡ぎ出そうとしていた。それは、誰かに与えられた譜面ではない、彼ら自身の音楽だった。
響介は、その光景をただ静かに見つめていた。選択しないこと。それが、彼の出した答えだった。世界の未来を、人々の手に委ねるという、最も難しい調律。
第七章 新しい聴き手
響介は砕けた懐中時計を、そっとポケットの奥深くにしまった。もう世界の綻びを追う必要はない。彼の役目は終わったのだ。
これからは、ただの『聴き手』になろう。
人々がこれから奏で始める、新しい日常の音を聴く者になろう。
彼の横を、鼻歌を歌いながら少女が通り過ぎていく。それは響介が聴いたこともない、少し音程の外れた、不格好なメロディだった。だが、そこには澱んだ日常の中には決してなかった、確かな生命力と、明日への予感が満ちていた。
響介は、その不協和音に、思わず口元を緩めた。
完璧な調和だけが、美しいわけじゃない。世界は今、少し不器用で、けれど愛おしい音を、自ら奏で始めたのだから。
風が吹き、街のざわめきが彼の耳に届く。それはもう、欠落を孕んだ悲鳴ではなく、始まりを告げる、希望の産声のように聞こえた。