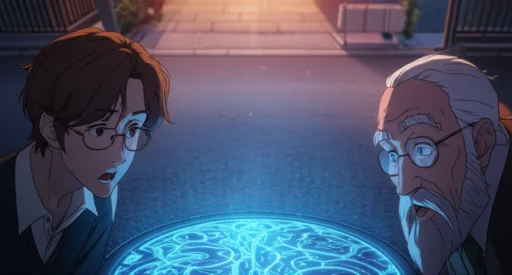第一章 余白の多い買い物リスト
ドアノブに触れた指先に、バチリと静電気が走った。
痛みというより、警告のような刺激。
「……痛っ」
錆びついた鉄の味を連想させる匂い。
冷え切った金属の感触。
見慣れたアパートの玄関なのに、世界が数ミリだけズレているような浮遊感がある。
視線がドアの横に吸い寄せられる。
マグネットで雑に留められた、裏紙の買い物リスト。
『牛乳』
『洗剤』
『 』
三行目。
そこは空白のはずなのに、視界の隅で何かが蠢く。
インクの匂いだけが、不自然に濃い。
「歩、また鍵開けっ放し」
背後から、呆れた声。
心臓が定位置に戻るような安堵感。
振り返ると、幼馴染の相馬湊がコンビニ袋を提げて立っていた。
「あ、湊。おかえり」
「おかえりって。ここ、お前の家だろ」
湊は苦笑しながら、私の散らかり放題の部屋へ足を踏み入れる。
脱ぎ捨てた靴下、読みかけの文庫本。
彼が屈んでそれらを拾い上げる。
その瞬間。
彼の手が文庫本に触れたはずなのに、表紙が一瞬だけ彼の手の甲を透過したように見えた。
「……え?」
瞬きをする。
湊の手には、ちゃんと本が握られている。
「どうした? 顔色が悪いぞ」
「ううん、なんでもない。ちょっと目が疲れてて」
私はソファに座り込む。
湊はキッチンへ立つ。
カチャカチャとカップが触れ合う音。
お湯の沸く音。
日常の風景。
けれど、違和感は拭えない。
湊が差し出したマグカップを受け取る。
温かい。
湯気が立っている。
「ねえ、湊」
「ん?」
「さっき、本を拾ってくれたよね?」
「ああ。棚に戻しておいたよ」
私は本棚を見る。
文庫本は、床に落ちたままだ。
背筋が凍りついた。
血液の温度がスッと下がる。
「……あ、ごめん。戻すの忘れてたわ」
湊は私の視線に気づき、頭をかく。
その笑顔が一瞬、砂嵐の入ったテレビ画面のように激しく歪んだ。
ズレている。
湊の輪郭だけが、世界から浮いている。
ふと、玄関のリストが目に入った。
『牛乳』
『洗剤』
『赤いスニーカー』
さっきまで空欄だった三行目。
そこに、血のような色で文字が浮かび上がっていた。
筆跡が違う。
震えるような、幼い子供の字だ。
ドクン、と脈が跳ねた。
赤いスニーカーなんて持っていない。
なのに、どうしてこんなに懐かしくて、恐ろしいんだろう。
第二章 バグだらけの図書館
翌日の図書館は、耳鳴りがするほどの静寂に満ちていた。
カウンターの中で、私は呼吸を浅く繰り返す。
昨夜の湊は、あの一瞬のノイズの後、普通に戻った。
でも、私の指先にはまだ冷たい感覚が残っている。
「日笠さん」
同僚の佐藤さんに声をかけられる。
「あそこの児童書コーナー、片付けてきてもらえますか?」
「はい」
私はコーナーへ向かう。
今日は水曜日。
いつもなら湊がボランティアで読み聞かせをしている時間だ。
コーナーには誰もいなかった。
子供たちが退屈そうに床で寝転がっている。
「……あれ?」
私は近くにいた男の子に声をかけた。
「ねえ、今日のお兄ちゃんは? 背の高い、優しいお兄ちゃん」
男の子は不思議そうに私を見上げる。
「誰それ?」
「え、ほら。毎週絵本を読んでくれる……」
「そんな人、いないよ。ずっとお姉さんが読んでたじゃん」
心臓を鷲掴みにされたような衝撃。
視界が揺れる。
私はバックヤードへ走り、スマホを取り出した。
発信履歴の一番上。
『湊』の文字をタップする。
『おかけになった電話番号は、現在使われておりません』
無機質なアナウンス。
まるで最初からそんな番号など存在しなかったかのように。
「嘘……」
震える手でポケットを探る。
カサリ、と乾いた音がした。
あの買い物リストの切れ端だ。
いつの間にかポケットに入っていた紙片は、茶色く変色し、ボロボロに古びていた。
『牛乳』
『洗剤』
『赤いスニーカー』
『 』
文字が増えている。
四行目。
そこにある文字を見た瞬間、私の喉から悲鳴にも似た空気が漏れた。
『ブレーキのきかない自転車』
キキキキキッ!
頭の中で、甲高い金属音が鳴り響く。
錆びたブレーキワイヤーが千切れる感触。
制御を失った自転車が坂道を転がり落ちる加速感。
風切り音。
恐怖で引きつった、幼い私の叫び声。
「いやだ、止まって、止まって!」
過去の私の声が、現在の私の鼓膜を叩く。
「日笠さん!?」
佐藤さんが駆け寄ってくる。
その声すら、水底から聞くように遠い。
廊下の向こう。
ガラス戸の向こう側に、人影が見えた。
湊だ。
彼は私を見ていない。
ただ静かに、出口の方へと歩いていく。
「待って!」
私は走り出した。
彼を逃がしてはいけない。
彼を見失ったら、私は私でいられなくなる。
そんな確信があった。
第三章 塗りつぶされた記憶
非常階段の踊り場で、私は彼に追いついた。
湊は手すりに寄りかかり、灰色の空を見上げている。
「湊!」
彼の肩を掴もうと手を伸ばす。
スカッ。
私の手は、彼の方をすり抜け、空気を切った。
「……っ!」
勢い余ってつんのめる。
振り返ると、湊はそこに「いた」。
でも、私の手は触れられない。
「湊、なんで……」
彼はゆっくりとこちらを向く。
その顔には、目も鼻も口もなかった。
のっぺらぼうの顔面に、ノイズだけが走っている。
恐怖よりも先に、理解が追いついた。
昨夜の文庫本。
片付いていなかった部屋。
誰にも見えていない彼。
私のポケットの中で、リストが熱を帯びる。
私は憑かれたように紙切れを取り出した。
紙はさらに劣化し、ボロボロと崩れ落ちそうだ。
そこに、殴り書きのような文字が次々と浮かび上がる。
『盗んだゲームソフト』
『嘘つき』
『身代わり』
脳髄を直接殴られたような衝撃。
封印していた記憶の蓋が、暴力的に吹き飛ぶ。
十九年前の夏。
坂道の途中にある駄菓子屋。
万引きを見つかって逃げ出した私。
ブレーキの壊れた自転車。
制御不能のまま突っ込んだ交差点。
そこへ通りがかったトラック。
そして、私の前に飛び出した、赤いスニーカーの少年。
――ドンッ!
鈍く、重い衝撃音。
トマトが潰れるような、生々しい音。
アスファルトに広がる、粘着質な赤。
鉄と血の混じった強烈な匂い。
「僕じゃない! あいつが飛び出したんだ!」
警官に腕を掴まれた十歳の私は、泣き叫んでいた。
嘘だ。
私がぶつかったんじゃない。
湊が勝手に飛び出したことにしたんだ。
自分の罪を、死にゆく彼になすりつけた。
喉が渇く。
あの時と同じ、張り付くような渇き。
「あ……ああ……」
その場に崩れ落ちる。
湊の顔からノイズが消え、穏やかな表情が現れた。
彼は何も言わない。
ただ、その足元が、アスファルトに同化するように透け始めている。
彼は、私が作り出した幻影。
罪悪感が生み出した、都合の好い「生きている湊」。
私の能力だと思っていた「世界のズレ」を見る力は、この虚構を維持するためのエラーチェックだったのだ。
私が真実を思い出しかけるたび、世界はバグを起こして誤魔化していた。
リストの最後の行。
インクが滲み、黒く塗りつぶされるように文字が刻まれる。
『相馬 湊(享年十歳)』
それを認識した瞬間、目の前の湊が粒子となって崩れ始めた。
「待って、行かないで!」
私は何度も手を伸ばす。
けれど、指先は空虚な空間を掻くだけだ。
「ごめんなさい、ごめんなさいっ! 私が殺したの、私が嘘をついたの!」
湊は、困ったように眉を下げて笑った。
その笑顔は、十九年前、血まみれのアスファルトの上で、最後に私に向けた表情と同じだった。
彼は何かを言いかけて、音もなく消滅した。
残されたのは、冷たい風と、私の嗚咽だけ。
最終章 褪せた色の世界で
目が覚めると、私は自宅のソファで丸まっていた。
部屋は酷く散らかり、埃っぽい匂いがする。
「……湊」
名前を呼んでも、返ってくるのは冷蔵庫の駆動音だけ。
キッチンへ行く。
食器棚には、私のマグカップが一つだけ。
ペアのカップなんて、最初から存在しなかった。
玄関へ向かう。
ドアの横。
マグネットの下には、何の変哲もない広告の裏紙が挟まっている。
『牛乳』
『洗剤』
『ゴミ袋』
私の筆跡だ。
震えも、血の匂いもしない、ただの文字。
靴を履き、外に出る。
世界は鮮明だった。
隣家の洗濯物の揺れも、道路のひび割れも、すべてが圧倒的な解像度でそこにある。
あの「ズレ」を感じる感覚は、もうどこにもない。
バグのない世界。
湊のいない世界。
「……そう」
私は大きく息を吸い込む。
肺に入ってくる空気は冷たく、そして重い。
スマホの連絡先には、もう「相馬」の文字はない。
けれど、右手のひらには、彼を掴もうとして空を切った感触が残っている。
そして胸の奥には、一生消えることのない鉛のような罪の重みがあった。
それは、私が背負って歩かなければならない荷物だ。
忘れることも、書き換えることも許されない、私だけの真実。
「行ってきます」
誰に言うでもなく呟き、鍵を閉める。
カチャリ、と無機質な音が響いた。
私はポケットの中で、古びたリストを強く握りしめた。
そこにはもう、不気味な文字は浮かばない。
でも、私には読める気がした。
私の罪と、これからの贖罪の日々が記された、長い長いリストが。
私は一歩、色の褪せた、けれど確かな現実へと踏み出した。