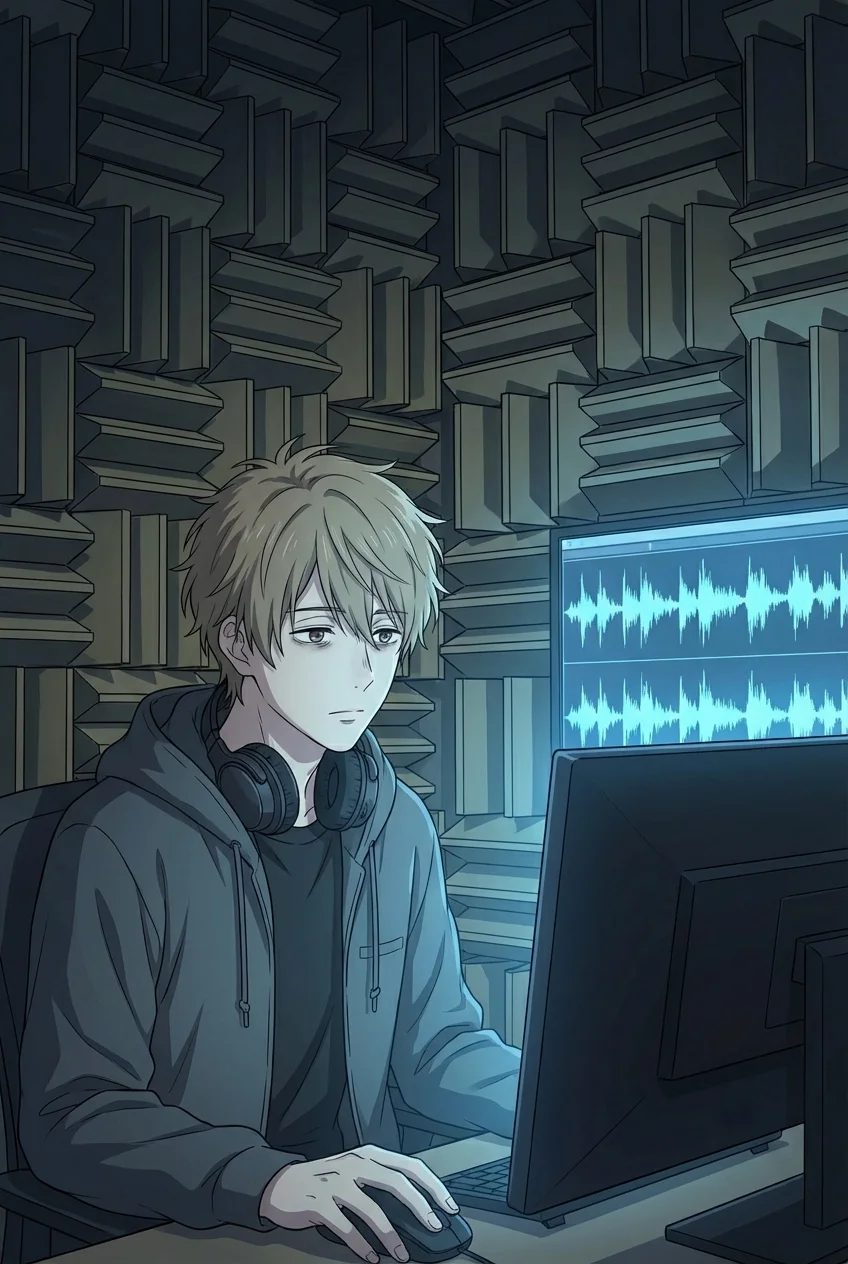第一章 沈黙の店
埃(ほこり)が舞う音さえ、聞こえる気がした。
路地裏の突き当たり。看板のない古びた木造家屋。
店主の壮一(そういち)は、作業机の上のピンセットを手に取った。
目の前にあるのは、百年以上前の懐中時計だ。
だが、彼が修理しているのは歯車ではない。
「音」だ。
壮一には、奇妙な特技がある。
物に染み付いた「過去の音」を聞き取り、不協和音を取り除く。
あるいは、持ち主が望む音色だけを抽出して保存する。
世間からは「音の修繕屋」などと呼ばれているが、壮一自身はただの頑固な世捨て人のつもりだった。
「……錆びた音がするな」
独り言がつい漏れる。
時計の蓋に指を這わせると、かつての持ち主の咳払いと、荒い息遣いが鼓膜を揺らす。
不快だ。
壮一は眉間に深い皺を寄せ、特殊な音叉(おんさ)を叩いた。
キィィン……という清廉な響きが、澱(よど)んだ残留思念を中和していく。
静寂が戻る。
これこそが、壮一の愛する世界だ。
人との会話はノイズでしかない。
感情の起伏は、耳障りな雑音だ。
だから彼は十年前に家を出て、この店に籠城した。
妻の泣き声も、娘の罵倒も、すべて遮断して。
カラン、コロン。
ドアベルが鳴った。
計算された和音。不快ではない。
だが、客が来るのは想定外だった。
「本日は休業の札を出しているはずだが」
壮一は顔も上げずに言った。
「……鍵、開いてましたよ」
若い女の声だ。
緊張しているのか、声帯が微かに震えているのが分かる。
「出て行ってくれ。今は集中している」
「どうしても、直してほしいものがあるんです」
「他をあたれ」
「音が出ないんです。でも、音が聞こえるって祖母が……」
壮一の手が止まった。
音が聞こえる、と言ったのか。
ゆっくりと顔を上げる。
入り口に立っていたのは、大学生くらいの小柄な娘だった。
ショートカットの髪が、西日を受けて透けている。
その顔立ちに、壮一は息を呑んだ。
記憶の底にある、若き日の妻の面影。
そして、反発して出て行った娘の強い瞳。
その両方が、混ざり合っていた。
「……名前は」
「ミナ、です」
壮一は舌打ちを噛み殺した。
知らない名前だ。
だが、血の音がする。
心臓の鼓動が、不規則なリズムを刻み始めた。
第二章 鳴らない風鈴
ミナは、布に包まれた小さな箱をカウンターに置いた。
「これです」
包みを解くと、現れたのはガラス製の江戸風鈴だった。
ただし、奇妙なことに舌(ぜつ)――音を鳴らすためのガラス棒――が無い。
ただのガラスの器だ。
「舌がなければ、鳴るわけがない」
壮一は冷たく言い放った。
「物理的に音が鳴らないのは当たり前だ。私の専門外だ」
「違うんです」
ミナは一歩踏み出した。
「母が、亡くなる前に言っていたんです。この風鈴には、特別な音が閉じ込められているって」
「母……?」
「先月、病気で」
言葉の余韻が、店内の空気を重くした。
壮一の指先がわずかに震える。
娘が、死んだ?
あの喧(やかま)しいほどに元気だった娘が?
「母はずっとこれを大事にしていました。でも、私には何も聞こえない。ただのガラスです。でも……母は最期に、これを耳元に当てて、笑って逝ったんです」
ミナの瞳から、透明な雫がこぼれ落ちそうになる。
「知りたいんです。母が最期に何を聞いていたのか。それがどんな音だったのか」
壮一は目を閉じた。
拒絶すべきだ。
これに関われば、平穏な静寂は崩れ去る。
過去という名の轟音が、彼を飲み込むだろう。
「帰れ」
喉から絞り出した声は、ひどく掠(かす)れていた。
「お代はいくらでも払います!」
「金の問題ではない!」
怒声が店内に響き、壁掛け時計たちが一斉に共鳴した。
ミナが肩をびくりと震わせる。
その怯えた仕草が、幼い頃の娘と重なった。
『お父さんの怒鳴り声なんて、もう聞きたくない!』
十年前の記憶がフラッシュバックする。
壮一は深く息を吐き、乱れた心拍を整えた。
「……一度だけだ」
気がつけば、そう言っていた。
「一度だけ診る。何も聞こえなければ、すぐに持って帰れ」
ミナの顔がぱっと明るくなる。
「ありがとうございます……!」
壮一は手袋をはめ直し、慎重に風鈴を手に取った。
冷たいガラスの感触。
通常、物質に残留する音は、年月と共に劣化する。
だが、この風鈴からは、異常なほどの「圧」を感じた。
何かが、強力に保存されている。
誰かの執念にも似た想いが、音の波形として焼き付いているのだ。
壮一は目を閉じ、聴覚のチャンネルを極限まで開放した。
世界から色が消え、音だけの空間が広がる。
第三章 硝子の向こうのララバイ
最初は、雨の音だった。
激しい夕立。
湿った畳の匂いまで再生される。
(これは……二十年前の我が家か?)
さらに深く潜る。
遠くで祭囃子(まつりばやし)が聞こえる。
そして、誰かの泣き声。
『痛いよぉ、お父さん』
幼い娘の声だ。
転んで膝を擦りむいた日か。
壮一の記憶のデータベースが検索をかける。
違う。
これはもっと、日常的な。
『泣くな。うるさい』
若い頃の自分の声が聞こえた。
冷たく、突き放すような声。
そうだ、自分はいつもそうだった。
仕事に集中したいからと、娘の涙をノイズとして処理していた。
だが、風鈴に残された音は、そこで終わらなかった。
場面が変わる。
深夜。
静寂に包まれた部屋。
幼い娘が熱を出して寝込んでいる。
看病に疲れた妻も、隣で眠っている。
そこに、足音が近づく。
軋(きし)む床の音。
自分だ。
仕事部屋から出てきた自分が、娘の枕元に座る。
壮一は息を呑んだ。
忘れていた。
いや、忘れようとしていた記憶。
風鈴は、その瞬間を鮮明に記録していた。
『……ん、んん……』
うなされる娘。
その額に、不器用な手が触れる。
そして、男が口を開く。
低い、低いハミング。
旋律など呼べないような、拙(つたな)い即興の子守唄。
『大丈夫だ。父さんがいる』
普段の冷徹な彼からは想像もつかない、震えるような優しい声。
『お前が治るまで、ずっと起きているから』
『……ん……おとう、さん……?』
『シィーッ。寝てろ。音を立てるな』
『……うん……』
娘の呼吸が安らかになっていく。
男は照れ隠しのように、窓辺にあったこの風鈴を指で弾いた。
チリリン……。
舌のない今の風鈴ではない。
まだ舌があった頃の、澄んだ音色。
その音色が、子守唄と溶け合って、ガラスの分子構造に刻み込まれていたのだ。
「……あぁ」
壮一の目から、熱いものが溢れ出した。
娘は、覚えていたのだ。
いつも怒鳴ってばかりだった父親が、たった一度だけ見せた愛情を。
それを「宝物」として、舌が外れてもなお、大切に持っていたのだ。
家を出て行ったあの時も、結婚した時も、そして死の淵にある時さえも。
『お父さんの声、聞こえるよ』
亡くなる直前の娘の声が、幻聴のように重なる。
この風鈴は、娘にとっての「父親」そのものだった。
冷たいガラスなどではない。
体温を持った記憶だったのだ。
第四章 新しい音色
壮一が目を開けると、ミナが心配そうに覗き込んでいた。
「あの……大丈夫ですか? 泣いて……」
壮一は慌てて手背で顔を拭った。
「……埃が入っただけだ」
そして、風鈴をミナに押し返した。
「聞こえたぞ」
「えっ! 本当ですか? 何が……どんな音が?」
「……下手くそな歌だ」
「歌?」
「不愛想で、頑固な男が、熱を出した娘のために歌った子守唄だ」
ミナが目を丸くする。
壮一は、店の奥から小さな箱を持ってきた。
中には、色とりどりのガラス棒が入っている。
「舌をつけてやる。サービスだ」
「え、でも」
「このままじゃ、ただのガラスだ。風鈴は、風を受けて鳴るためにある」
壮一は、一番美しい音を奏でる江戸紫のガラス棒を選び、慣れた手つきで風鈴に結びつけた。
「お母さんはな、過去の音を聞いていたんじゃない」
「え?」
「お前という新しい風が吹くのを、待っていたんだ」
それは嘘だ。
けれど、職人としての真実でもあった。
過去に閉じこもるのは、自分だけでいい。
壮一は風鈴をミナの手に持たせた。
「鳴らしてみろ」
ミナがおずおずと風鈴を揺らす。
チリリン。
凛(りん)とした、しかしどこか懐かしい音が店内に響いた。
その音は、記憶の中の子守唄と重なり、美しいハーモニーを奏でた。
「……わぁ」
ミナの顔が綻(ほころ)ぶ。
「綺麗な音……。まるで、母が笑ってるみたい」
「大事にしろよ」
「はい! あの、おじさん……お名前は?」
壮一は少し迷ってから、ぶっきらぼうに答えた。
「……壮一だ。ただの、音の鑑定士だ」
祖父だとは、名乗らなかった。
まだ、その資格はない。
だが、いつかまた、この風鈴のメンテナンスが必要になる日が来るだろう。
その時まで、この「音」を守り続けよう。
ミナが店を出て行く。
ドアベルがカラン、コロンと鳴った。
店内に戻った静寂は、以前よりも少しだけ、温かい色をしていた。
壮一は作業机に戻り、次の時計を手に取った。
その口元には、数十年ぶりに微かな笑みが浮かんでいた。
「……さて、仕事をするか」
埃の舞う音が、今日はオーケストラのように優しく聞こえた。