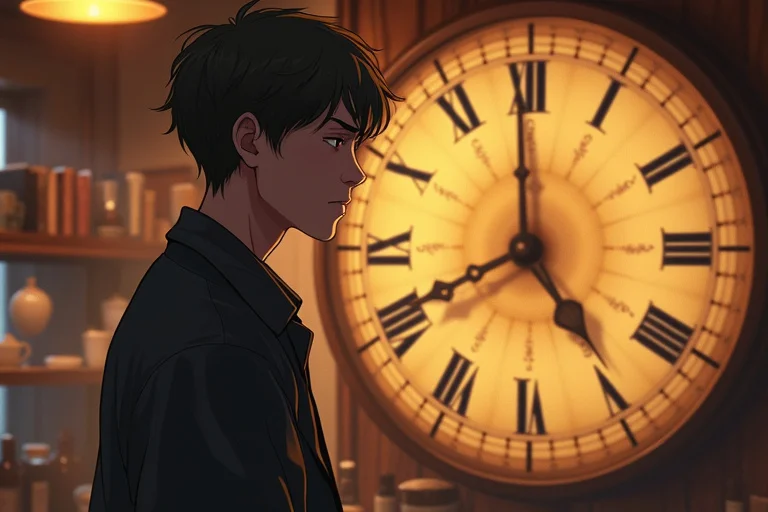第一章 瑠璃色の封印
「佐倉くん、顔色が悪いよ。マスク、二重にした方がいいんじゃないか?」
館長の心配そうな声が、遠くで響く。
俺、佐倉燈(ともし)は、地下倉庫の重い鉄扉の前で、胃の腑がせり上がるような吐き気を堪えていた。
「いえ……埃アレルギーなだけです」
嘘だ。
俺には、この扉の隙間から漏れ出す「気配」が見えている。
錆びた鉄のような赤黒い飛沫。
深海で押し潰されるような、重圧を伴う群青。
俺には他人の感情が「色」として視えてしまう。
だからこそ、この地下室に眠るものが恐ろしかった。
数十年前に失踪した作家、貴島(きじま)蓮。彼が残した遺品からは、年月を経てもなお腐敗することのない、強烈な情念が放射能のように漏れ出している。
ポケットの中でスマホを握りしめる。
恋人の優子からの返信は、まだない。
昨夜のデート。彼女の笑顔の奥に、俺は必死で「退屈」を表す濁ったカーキ色や、「愛想」を示す薄っぺらいピンク色を探していた。
視えるからこそ、信じられない。
彼女の純白の沈黙が、俺への無関心に見えて怯えている。
「開けるぞ」
覚悟を決めて鍵を回す。
錆びついた蝶番が悲鳴を上げ、扉が開いた。
その瞬間、視界が焼き切れるかと思った。
網膜にこびりつく、煮えたぎる泥のような「焦燥」。
そして、喉を詰まらせるほど濃密な、鉛色の「沈黙」。
段ボールの山。その中心にある書きかけの原稿用紙。
そこは、ただの書庫ではなかった。
一人の男が、魂を削って何かを叫び、そして自らその喉を潰した「処刑場」だった。
第二章 沈黙の色彩
「これ、ただの風景写真じゃないの?」
休憩室で、同僚のミサキが数枚の絵葉書をパタパタと仰ぐ。
俺はあわてて彼女の手からそれをもぎ取った。
「素手で触るな。……酔うぞ」
俺は指先から伝わる電気のような痺れに、奥歯を噛みしめる。
絵葉書は、貴島の原稿に挟まれていたものだ。
裏面に文字はない。
だが、そこに塗り込められた透明なニスの層から、鼓膜を突き破るようなノイズが流れ込んでくる。
――キンッ。
耳鳴り。
そして、フラッシュバックのように脳裏に映像が弾ける。
雨のアスファルト。
ショーウィンドウ越しに見る、ウェディングドレス。
それを試着する女性の隣には、貴島ではない別の男。
(書くな。書いてはいけない)
(言葉にすれば、この想いは「事実」になってしまう)
(彼女の平凡な幸福を、俺の物語で汚すな)
「ぐっ……ぅ……」
俺は洗面所に駆け込み、胃液を吐いた。
頭が割れるように痛い。
貴島の苦悩が、あの日彼が感じていた血管が破裂しそうな血圧の高まりが、俺の身体を乗っ取ろうとする。
「佐倉さん!?」
ミサキの声が水槽の外から聞こえるようだ。
蛇口をひねり、冷水を顔に叩きつける。
鏡に映る俺の顔は蒼白だった。
わかった。
貴島蓮が消えた理由が。
彼は書けなかったのではない。
彼女が別の男性と築こうとしている平穏な家庭を守るため、自分の中に渦巻く溶岩のような情熱を、この地下室に封じ込めたのだ。
その苦しみは、「美しい悲恋」なんて生易しい色じゃない。
身を焦がす炎を、氷の海に沈めて殺すような、凄惨な「自己犠牲」の色だった。
第三章 透明な信頼
深夜のデスク。
俺の前には、貴島の未完の原稿がある。
最後のページは、文章の途中で唐突に途切れていた。
『愛しているからこそ、私は――』
その先には、広大な空白が広がっている。
俺はペンを手に取った。
俺の能力なら、貴島の残響を読み取り、彼が書こうとした言葉を代筆し、物語を完結させることができる。
ペン先が紙に触れる。
インクが滲む。
だが、俺の手は震えて止まった。
「……書けるわけ、ないだろ」
貴島はこの空白をもって、物語を完成させたのだ。
言葉にしないこと。
沈黙を守ること。
それこそが、彼が最後に選んだ、何よりも雄弁な愛の形だった。
俺が勝手に言葉を埋めることは、彼の覚悟への冒涜になる。
俺はペンを置いた。
ふと、自分自身の臆病さが重なる。
俺は優子の心が見えないことを嘆き、彼女の沈黙を疑っていた。
だが、それは逆だ。
俺が勝手に彼女の「色」を読もうとして、彼女自身の「言葉」を聞こうとしていなかっただけだ。
貴島は、相手を想うがゆえに筆を折った。
なら、生きている俺は?
俺は、筆を執らなければならない。
能力(いろ)に頼るのではなく、不器用でも、自分の言葉で想いを紡がなければならないんだ。
スマホを取り出す。
指先が震える。
今まで「察する」ことで逃げてきた俺にとって、言葉にするのは怖い。
拒絶されるかもしれない。退屈だと思われるかもしれない。
それでも。
『優子、今度の日曜、海に行かないか。話したいことがたくさんあるんだ』
送信ボタンを押す。
画面の中の文字は、どんな鮮やかな色よりも、確かに俺の胸を熱くした。
既読がつく。
数秒後、吹き出しがポップアップする。
『うん。私も、燈の声が聞きたい』
俺は深く息を吐き出した。
窓の外、白み始めた空は、冬の朝特有の透き通った水色をしている。
原稿用紙は、未完のままでいい。
俺たちの物語は、ここから書き始めるのだから。
俺は貴島のノートを静かに閉じ、鞄を持って立ち上がった。