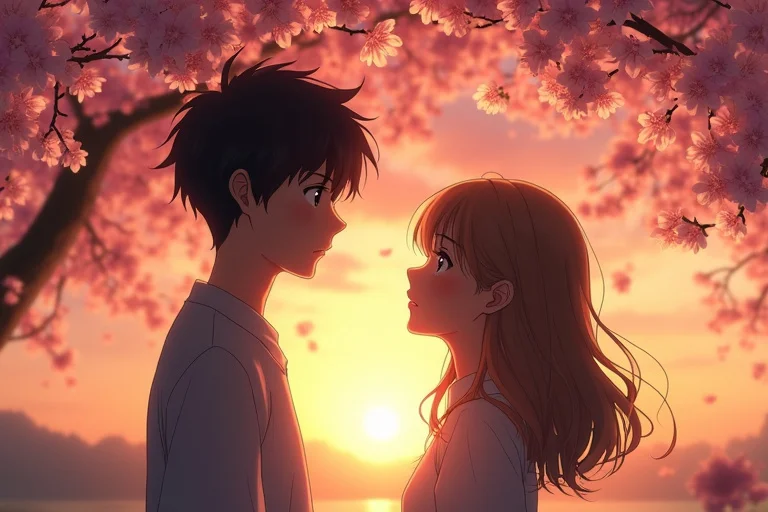第一章 灰色の翅音
水島湊の日常は、無数の灰色の蝶に彩られていた。それは比喩ではない。彼が嘘をつくたび、その口から、まるで吐息が形を成したかのように、儚い翅を持つ灰色の蝶がふわりと生まれ、飛び立っていくのだ。
図書館のカウンターに座る湊の視界の隅で、今も一匹の小さな蝶が舞っている。「この本、もう読んだのですが、とても面白かったですよ」。利用者の老婦人にそう言って微笑んだ瞬間、蝶は生まれた。実際には最初の十数ページで挫折した本だった。当たり障りのない、小さな嘘。蝶もまた、埃のように小さく、すぐに天井の照明に吸い込まれて消えた。
この奇妙な現象がいつから始まったのか、湊はもう覚えていない。物心ついた頃には、自分のつく嘘が可視化されるこの呪いとも祝福ともつかない体質と共存していた。おかげで彼は、極力嘘をつかないように心がけてはいる。だが、社会とは円滑な人間関係という名の潤滑油を絶えず要求する機械のようなものだ。そして、その潤滑油の主成分は、往々にして悪意のない嘘でできている。
「水島さん、お疲れ様」
声に振り向くと、同僚の高梨さくらが柔らかな笑みを浮かべて立っていた。彼女の周りだけ、図書館の静謐な空気が春の陽だまりのように温かく揺らめく気がする。
「高梨さん、お疲れ様です。その資料、運びますよ」
「本当ですか? 助かります」
さくらから分厚いファイルの束を受け取る。ずしりと重いが、彼女の近くにいられるなら苦ではなかった。
「水島さんって、いつも優しいですよね」
「そんなことないですよ。僕なんて……」
――大したことない人間です。そう言いかけて、言葉を飲み込む。謙遜もまた、一種の嘘になることを湊は知っていた。本心では、彼女に良く思われたいのだから。言葉を選びあぐねていると、さくらが不思議そうな顔で湊の口元を見つめた。
「どうかしました?」
「ううん、なんでもない。ただ……水島さん、最近何か隠してませんか? なんて、考えすぎかな」
いたずらっぽく笑う彼女の言葉が、湊の胸に鋭く突き刺さる。隠していること。それは、この灰色の蝶のことか。それとも、彼女に寄せるこの淡い恋心のことか。
「隠し事なんて、ないですよ」
その瞬間、これまで見た中でもひときわ大きく、輪郭の濃い灰色の蝶が、湊の唇からゆるりと飛び立った。それはまるで、彼の罪悪感が具現化したかのように、さくらの肩先をかすめ、書架の奥へと音もなく消えていった。
さくらは何も気づかない。だが湊には、自分の言葉が放った偽りの翅音が、耳の奥でいつまでも響いているように思えた。
第二章 沈黙の観察者
灰色の蝶は、湊の自己嫌悪の象徴だった。蝶が舞うたび、彼は自分の心の弱さや不誠実さを見せつけられている気分になる。蝶のいない世界、思ったことを正直に口にできる世界を、どれほど願ったことだろう。だが、彼の日常は相変わらず、無数の灰色の翅に覆われていた。
さくらとの関係も、蝶のせいで一向に進展しなかった。彼女と話したい。もっと知りたい。けれど、会話を弾ませようとすればするほど、些細な見栄や相槌から小さな蝶が生まれ、二人の間に見えない壁を築いていく。本当の自分を見せることが、怖かった。本当の自分を知られて、幻滅されることが、何よりも恐ろしかった。
そんなある日の午後、湊はカウンター業務の合間に、いつもの光景に気づいた。図書館の窓際にある、一番陽当たりの良い閲覧席。そこにいつも座っている老婦人がいた。腰の曲がった、小柄な女性だ。彼女は毎日同じ時間に来ては、分厚い歴史書を静かに読みふけっている。
その日、湊は年配の男性利用者に、閉館時間の変更について説明していた。本来の手続きが面倒で、つい「ええ、簡単な申請ですぐに延長できますよ」と口にしてしまう。案の定、銀粉をまとったような灰色の蝶が、ひらひらと宙を舞った。
蝶はゆっくりと窓際の方へ飛んでいく。湊が目で追うと、信じられない光景が目に飛び込んできた。例の老婦人が、顔を上げ、その蝶の軌跡を、確かに目で追っているのだ。まるで、そこに存在する飛行物体を認識しているかのように。蝶が窓ガラスにぶつかって霧散すると、彼女は静かに視線を本に戻した。
心臓が大きく跳ねた。
まさか。見えているのか? 自分以外の誰かに、この灰色の蝶が?
それからの数日間、湊は意識的に老婦人を観察した。彼女はいつもと変わらず静かに読書をしている。だが、湊がカウンターで嘘をつき、蝶を飛ばすたびに、彼女の視線がほんの一瞬、僅かに動くのを、湊は見逃さなかった。
恐怖と、そしてほんの少しの好奇心が入り混じった感情が、湊の胸で渦を巻いた。彼女は何者なのだろう。自分と同じ体質なのだろうか。それとも、この現象の何かを知っているのだろうか。
話しかけてみたい。だが、何と言えばいい?「あなたも、嘘から生まれる蝶が見えるんですか?」などと聞けば、ただの不審者だ。湊は、答えの出ない問いを抱えたまま、ただ黙って、書架の陰から沈黙の観察者を眺めることしかできなかった。
第三章 金色の告白
週末、さくらに「駅前に新しくできた植物園、一緒に行きませんか?」と誘われた時、湊の心臓は破裂しそうになった。断る理由などあるはずもない。
ガラス張りの巨大なドームに足を踏み入れると、むわりと湿った甘い空気が二人を包んだ。色とりどりの蘭、天に向かって伸びる巨大なシダ、見たこともないような奇妙な形の花々。そこはまるで、日常から切り離された楽園のようだった。
「すごいですね、ここ!」
目を輝かせるさくらの横顔を見ているだけで、胸が満たされる。
「昔、植物学者になりたかったんです。おばあちゃんが花が好きで」
彼女は楽しそうに自分の子供の頃の夢や、家族の話をしてくれた。その言葉はどれも真っ直ぐで、一片の曇りもない。彼女の口から灰色の蝶が飛び立つのを、湊は一度も見たことがなかった。
それに引き換え、自分はどうだ。
「僕も、植物は好きですよ。特に珍しい食虫植物とか」
知ったかぶりをした瞬間、ハエトリソウの葉陰に隠れるように、小さな灰色の蝶が生まれた。さくらの純粋な言葉の横で、自分の言葉がいかに陳腐で、偽りに満ちているかを思い知らされる。自己嫌悪が、熱帯の湿気のように肌にまとわりついた。
帰り道、夕暮れの公園のベンチで、二人は並んで缶コーヒーを飲んだ。
「今日は楽しかったです。誘ってくれて、ありがとう」
さくらの言葉に、湊は胸が締め付けられるような思いだった。今日の自分は、一体いくつの嘘をついただろうか。
「……高梨さん」
「はい?」
「僕なんて、つまらない男でしょう。大した知識もないのに、知ったかぶりして」
自嘲気味に呟くと、さくらはきょとんとした顔で湊を見つめ、それからふわりと笑った。
「そんなことないですよ。水島さん、一生懸命でした。私、水島さんの、そういう不器用なところ、嫌いじゃないです」
その瞬間、湊の世界から音が消えた。
嫌いじゃない。その言葉が、彼の心の奥深くに、温かい雫のように染み渡っていく。
もう、嘘はつきたくない。偽りの自分ではなく、本当の自分で、彼女と向き合いたい。
高鳴る鼓動を抑えながら、彼は心の中で、ずっと言えなかった言葉を叫んだ。
――あなたのことが、好きです。
声には出せなかった。あまりにも臆病で、情けない告白。だが、それは紛れもなく、湊の生まれて初めての、一点の曇りもない本心だった。
その時、信じられないことが起こった。
彼の唇から、何かが生まれる気配がした。また灰色の蝶だろうか。そう思った湊の目の前に現れたのは、これまで見たこともない、黄金の光を放つ蝶だった。
それは夕陽の光をその身に宿したかのように、眩いばかりにきらめいていた。灰色の蝶のような儚さはない。力強く、そして優雅な翅ばたきで宙を舞い、ふわりと、隣に座るさくらの肩に留まった。
さくらは蝶の存在には気づいていない。だが、何かを感じたかのように「あれ?」と首を傾げ、自分の肩にそっと手を触れた。
「なんだか、急に温かくなった気がする」
そう言って、彼女は湊に微笑んだ。
湊は言葉を失くしたまま、その光景をただ見つめていた。嘘からは灰色の蝶が生まれる。ならば、この金色の蝶は、一体何なのだ? 答えは、彼の胸の奥で、確かな熱を持って脈打っていた。
これは、「心からの真実」が生んだ、奇跡の蝶なのだ、と。
世界が、反転した。彼の呪いは、祝福でもあったのだ。
第四章 言葉が色づくとき
金色の蝶の発見は、湊の日常を根底から変えた。彼はもう、自分の言葉を恐れなかった。嘘をつくことは劇的に減り、カウンターの上を灰色の蝶が舞う光景はほとんど見られなくなった。代わりに、彼は自分の言葉一つ一つに、誠実な色を乗せようと努めた。
数日後、湊は意を決して、図書館の窓際に座る老婦人に声をかけた。手には、彼女がいつも読んでいる歴史書と同じ分野の新刊を携えて。
「いつもご利用ありがとうございます。もしよろしければ、こちらの本はいかがですか?」
老婦人はゆっくりと顔を上げ、湊を見ると、かすかに微笑んだ。
「ありがとう。親切な方じゃな」
湊は深呼吸を一つして、核心に触れた。
「あの……失礼なことをお伺いしますが……あなたにも、見えるのでしょうか。時々、人の口から飛び立つ、蝶のようなものが」
老婦人は驚いた様子も見せず、ただ静かに湊の目を見返した。その深い瞳は、全てを見通しているかのようだった。長い沈黙の後、彼女はそっと口を開いた。
「……あれはな、偽りの言葉から生まれる、灰色の蛾じゃよ」
「蛾……」
「じゃがな、ごく稀に、誠の心から、光を放つ蝶が生まれることもあると聞く。あんた、見たのかね。その金色の蝶を」
湊は息を飲んだ。やはり、彼女は知っていたのだ。彼は静かに頷いた。老婦人は、どこか懐かしむような、優しい目で頷き返した。
「そうかい。それは良かった。言葉は、呪いにもなるが、光にもなるからのう。大事になさい」
それだけ言うと、彼女は再び本に視線を落とした。だが、その横顔は、以前よりも少しだけ穏やかに見えた。
その日の帰り道、湊はさくらを待った。彼女が「お疲れ様」と微笑みながら出てくる。
「高梨さん、少し、いいかな」
「はい、もちろんです」
二人で並んで歩く夕暮れの道。以前なら、何を話せばいいか分からず、意味のない嘘で間を埋めようとしていただろう。だが今は、沈黙さえも心地よかった。
公園の入り口で、湊は立ち止まった。
「高梨さん」
彼はまっすぐに彼女の目を見た。もう、心の中で叫ぶだけでは終わらせない。
「この間のことだけど……僕も、高梨さんのことが、嫌いじゃない。ううん、そうじゃないな」
一呼吸置く。
彼の視界の隅で、小さな金色の光が、蛍のように明滅しているのが見えた。それは、これから彼が紡ぐ言葉が、本物であることの証だった。
「あなたのことが、好きです。僕と、付き合ってくれませんか」
彼の言葉は、もう蝶にはならなかった。それはただの言葉として、真っ直ぐに彼女の心へと届いていく。
さくらは驚いたように目を丸くし、やがて、その頬を夕陽の色に染めて、花が綻ぶように微笑んだ。
その答えを聞く前に、湊は、自分の日常がようやく本当の色を取り戻したことを、確信していた。