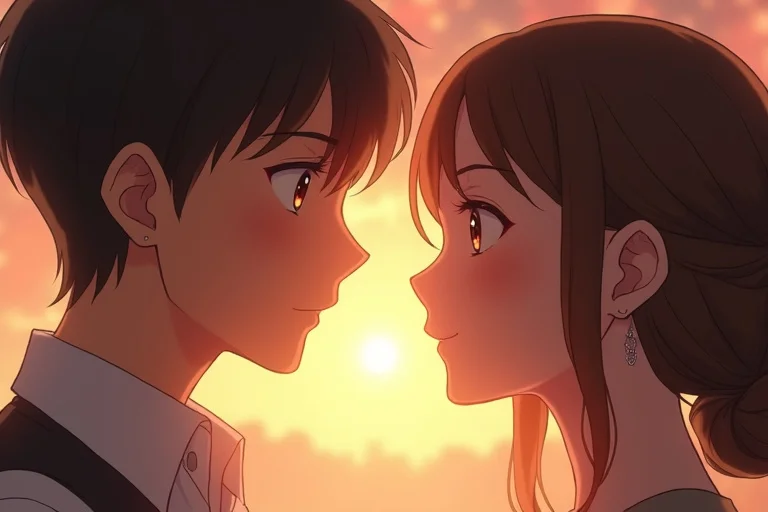第一章 蝕まれる指先
僕の左手の薬指は、光をかすかに透過する。愛するリナが淹れてくれた珈琲の湯気が、指の輪郭を曖昧に揺らした。彼女の温かな視線を感じながらカップを持ち上げると、透けた指先が陶器の藍色をぼんやりと映し出す。これが『愛蝕』。愛の深さに比例して、身体の一部が硝子のように透明になる現象。
「ユキ、大丈夫? また……」
リナが心配そうに僕の手を取る。彼女の柔らかな手のひらの熱が、僕の冷えかけた指に伝わる。その温もりは確かに愛なのに、僕の透明化は止まらない。むしろ、日に日に侵食の速度を増しているようだった。
この世界では、誰もが『一度の愛の呪い』のもとに生まれる。人生でただ一度だけ、『運命の伴侶』を真に愛することができる。その愛が失われれば、二度と魂の芯から誰かを愛することはできないのだと。
僕にも、かつて『運命の伴侶』だと信じた人がいた。ミナト。彼の名を心で呟くだけで、胸の奥が軋む。彼は三年前、理由も告げずに僕の前から姿を消した。その日から、僕の『愛蝕』は始まった。愛する対象との物理的な距離が離れるほど、この現象は加速する。
「大丈夫だよ、リナ。君がいるから」
僕は微笑んでみせるが、その笑顔がどれほど脆いものか、自分がいちばんよく知っていた。机の隅に置かれた、小さな無色の硝子細工が、窓から差し込む午後の光を吸い込んで静かに佇んでいる。ミナトが最後にくれた、ただの硝子の塊。それが今、僕に残された唯一の絆だった。
第二章 欠けた月の記憶
古書店の静寂は、僕の心を落ち着かせてくれる。インクと古い紙の匂いが混じり合った空気を吸い込むと、薄れゆく記憶の断片が少しだけ輪郭を取り戻すような気がした。しかし、それも束の間。ミナトの顔を思い出そうとしても、まるで水面に映った月のように、指で触れた瞬間に揺らいで消えてしまう。彼の声も、笑い方も、すべてが霧の向こう側だ。
「僕への愛が、ミナトという人への愛に及ばないから、ユキは消えていくの?」
ある夜、リナが震える声で尋ねた。彼女の瞳には、僕を失うことへの恐怖と、自身の愛を疑う苦しみが浮かんでいた。
違う。
そう叫びたかった。
君への愛は本物だ。君の温もりも、香りも、声も、僕の世界を彩っている。
だが、言葉は喉の奥でつかえた。ミナトへの愛は、嵐のように激しく、すべてを焼き尽くすような熱を帯びていた。リナへの愛は、陽だまりのように穏やかで、心をそっと包み込む優しさがある。どちらも紛れもない愛なのに、なぜ僕の身体はミナトとの「距離」にだけ反応し続けるのか。この呪いは、愛の質を問うているのだろうか。
僕は彼女を強く抱きしめた。透け始めた腕が、彼女の温かい身体を不確かに感じる。この腕で君を抱きしめることさえ、いつかできなくなるのだろうか。その恐怖が、またひとつ、僕の身体の透明度を増していく。
第三章 硝子越しの残像
透明化は胸元にまで達し、心臓の微かな拍動が、薄皮一枚を隔てて見えるようになった。まるで自分の身体が、自分だけのものではなくなっていくような心許ない感覚。そんなある日、僕はふと、あの硝子細工に光を当ててみたくなった。
書斎の電気を消し、デスクライトの強い光を細く絞って、手のひらの硝子に注ぐ。
すると、信じられないことが起きた。
何の変哲もないはずの硝子の内部に、一瞬だけ、幻が咲いたのだ。向日葵畑で笑うミナトの横顔。二人で訪れた海辺に沈む夕日。僕が彼に贈った本の、少しだけ折れたページの隅。断片的で、儚い残像。光を動かすたびに、記憶はゆらめき、そして消えた。
「……ミナト」
どうして君は消えたんだ。
僕は、ミナトが住んでいた古いアパートへ向かった。もう誰も住んでいないその部屋は、埃と空虚な沈黙に満ちていた。だが、床板のわずかな隙間に、小さな紙片が挟まっているのを見つけた。それは、ミナ-トの日記の破れた一枚だった。震える指で拾い上げる。そこには、乱れた文字でこう記されていた。
『君の愛が深まるほど、僕の炎は強くなる。このままでは、君が消えるか、僕が燃え尽きるか、どちらかだ。だから、君を守るために――』
そこで文章は途切れていた。炎? 燃え尽きる? 言葉の意味が分からず、ただ心臓が冷たく鳴った。
第四章 愛燃の真実
「ユキ、見つけたわ。古い伝承よ」
古書店の店主である老人が、埃をかぶった分厚い本をリナと共に開いていた。僕がミナトの日記の切れ端を見せた翌日のことだった。リナは、僕を救うための手がかりを必死に探してくれていたのだ。
老人が指し示したページには、霞んだインクでこう書かれていた。
『愛蝕は孤独の病にあらず。必ず対となる魂を持つ者が存在する。一方が愛により存在を失う『愛蝕』であるならば、もう一方は愛によりその身を燃やす『愛燃(あいねん)』の宿命を負う。二人の愛が成就する時、一人は硝子となり、一人は灰となる。それは呪いではなく、二つで一つの魂が、再び一つに戻ろうとするための、悲しい儀式なのだ』
全身の血が凍るような感覚に襲われた。
ミナトが言っていた「炎」は、比喩ではなかったのだ。彼もまた、僕と同じ宿命を背負っていた。僕の身体が透明になるのと同じ速度で、彼の身体は内側から燃え上がっていたのだ。
「君を守るために」
日記の言葉が、雷鳴のように頭の中で反響した。彼は僕を生かすために、自ら僕の前から姿を消し、たった独りで燃え尽きることを選んだ。僕の『愛蝕』を止めるために。
だが、現実はどうだ。彼の自己犠牲は、僕を救わなかった。彼の不在は、僕の身体からさらに色を奪い、消滅へと追いやっている。なぜだ、ミナト。なぜ、君の愛は、君がいなくなってなお、僕を蝕み続けるんだ。
その絶望が引き金になった。視界が白く染まり、足元から急速に身体の感覚が失われていく。リナの悲鳴が、遠くに聞こえた。
第五章 心臓に宿る結晶
意識が薄れ、完全に世界から切り離される寸前。僕は、光も闇もない、無垢な空間に立っていた。
目の前に、懐かしい人影が立っている。輪郭は炎のように揺らめいているが、その優しい眼差しは、僕が忘れかけていたミナトのものだった。
『ユキ』
声が聞こえる。それは耳からではなく、魂に直接響くようだった。
『ごめん。君を苦しめるつもりじゃなかった』
「ミナト……君は、どこにいるんだ」
ミナトは悲しげに微笑み、僕の胸を指さした。
『僕は、君の中にいる。あの日、僕は燃え尽きて、実体を持たない『愛の記憶の結晶』になった。君の心臓のすぐそばで、ずっと君と共にあったんだ』
衝撃の事実が、僕の魂を貫いた。透明化の原因は、彼との物理的な距離ではなかった。僕の中にいるのに、実体がない。触れることも、見ることもできない。その「無限の距離」が、僕の身体を内側から蝕んでいたのだ。僕は彼の愛を失ったのではなく、その愛の亡骸を、ずっと抱きしめて生きてきた。
『僕のことは忘れて、リナさんと生きるんだ。この結晶を君が心から手放せば、愛蝕は止まるはずだ』
ミナトが手を伸ばす。しかし、その手は僕に届くことなく、陽炎のように揺れた。
手放す? この温かい記憶を? 僕という人間を形作ってきた、この愛のすべてを? それは、僕の半分を殺すことと同じだった。
第六章 半透明のアリア
僕は、ゆっくりと首を横に振った。
「手放さない。忘れたりしない」
ミナトの瞳が、驚きに見開かれる。
「君の愛も、リナの愛も、どちらも僕だ。君が僕のために燃え尽きたというのなら、僕は君の愛のすべてを抱いて生きる。それが、君の愛に応える唯一の方法だ」
僕は、自分の胸に手を当てた。そこにあるはずの、見えない結晶に向かって語りかける。
「さよならじゃない。これからも、ずっと一緒だ、ミナト」
その瞬間、僕の身体の内側から、まばゆい光が溢れ出した。手のひらに握りしめていた硝子細工が、心臓の結晶と共鳴するように、七色の輝きを放つ。それは、ミナトとの記憶の色だった。
意識が現実へと引き戻される。
目を開けると、涙を流すリナの顔が見えた。僕の身体は、消えていなかった。光をほのかに通す、美しい半透明のまま、そこに在った。急速に進んでいた透明化は、完全に止まっていた。
「おかえりなさい、ユキ」
リナが、僕の半透明の身体を、僕の過去の愛ごと、すべてを包み込むように強く抱きしめてくれた。
僕は、そっと硝子細工に視線を落とす。あれほど鮮やかな残像を映していた硝子は、今やただの無色透明な塊に戻っていた。映し出す必要がなくなったのだ。すべての記憶は、失われることなく、僕自身の中に完全に統合されたのだから。
僕は消えない。燃え尽きることもない。ただ、愛の記憶をその身に溶かし込み、半透明のまま生きていく。それは呪いではない。僕とミナトが選び取り、そしてリナが受け入れてくれた、世界でたった一つの愛の形。陽光が僕の身体を通り抜け、床に淡い虹色の影を落としていた。僕はその影を見つめながら、新しい朝を静かに迎えた。