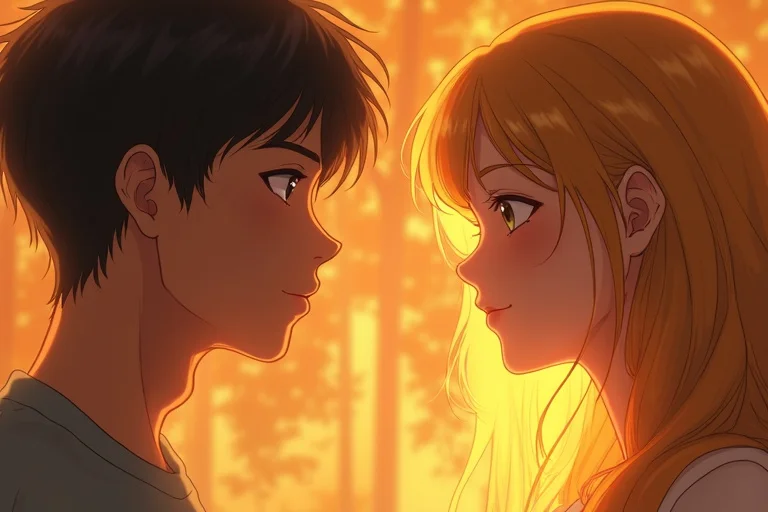第一章 触れてはいけない記憶
神保町の裏路地、時の流れから取り残されたかのような古書店「海馬堂」。その店主代理である水瀬櫂(みなせ かい)にとって、古びた紙の匂いと静寂は、世界で最も安心できるシェルターだった。彼は人と深く関わることを極端に避けていた。それは臆病さからというよりも、ある種の呪いにも似た彼の特異な体質のせいだった。
櫂は、誰かに恋愛感情を抱くと、その相手が「最も失いたくないと願う記憶」を、まるで自分の体験のように鮮明に見てしまうのだ。それは甘美な響きとは裏腹に、他人の最も神聖な領域へ土足で踏み込むような罪悪感を彼に与え、幾度となく心を苛んできた。だから櫂は、本という他人の完成された物語の中にだけ、心を遊ばせていた。
その静寂を破るように、教会の鐘の音にも似たドアベルが鳴った。
「こんにちは、水瀬さん」
柔らかな声の主は、月島詩織(つきしま しおり)。近所でガラス工房を営む彼女は、週に一度ほどのペースで、珍しい植物の画集を探しにこの店を訪れる。陽光を弾くガラスのように澄んだ瞳と、屈託のない笑顔。彼女が店にいる間だけ、埃っぽい空気がきらきらと色づく気がした。櫂の心は、抗いがたい力で彼女に惹きつけられていた。そして、それと同じ強さで、彼は恐怖を感じていた。
その日、詩織は探していた画集を見つけ、嬉しそうにカウンターへ持ってきた。
「やっと見つかりました。ありがとうございます」
「いえ……お役に立ててよかったです」
櫂はぎこちなく応じ、会計を済ませる。彼女が画集を受け取ろうとした時、その指先から小さなガラス細工の栞が滑り落ちた。床に落ちる寸前、櫂は咄嗟に手を伸ばし、それを掴もうとした。彼の指が、栞を追う彼女の指先に、ほんの僅かに触れた。
その瞬間、世界が反転した。
古書店の薄闇は消え去り、目の前に広がるのは、目も眩むような真夏の光景。潮の香りが鼻腔を満たし、肌を焼く陽光と、寄せては返す波の音が全身を包み込む。視界の端には、小さな女の子が立っていた。5、6歳だろうか。麦わら帽子を被り、真っ白なワンピースを着ている。その子が、満面の笑みで誰かに向かって手を振っている。その笑顔はあまりに純粋で、幸福そのものを切り取ったかのようだった。しかし、その記憶には、温かさと同時に、胸を締め付けるような切なさが同居していた。
「……水瀬さん? 大丈夫ですか?」
詩織の心配そうな声で、櫂は現実へと引き戻された。彼は栞を握りしめたまま、呆然と立ち尽くしていた。冷や汗が背中を伝う。始まってしまった。彼女の最も大切な場所に、僕は、また無断で足を踏み入れてしまったのだ。
第二章 ガラス越しの心
あの日以来、櫂は詩織を意識的に避けるようになった。彼女が店に来ても、必要最低限の会話で済ませ、決して目を合わせようとはしなかった。しかし、彼の脳裏には、あの海辺の光景が焼き付いて離れなかった。少女の笑顔を見るたびに、櫂の心は罪悪感と、彼女をもっと知りたいという矛盾した欲求に引き裂かれた。
一方の詩織は、櫂の突然のよそよそしい態度に戸惑っていた。彼の静かな佇まいや、本について語る時の熱のこもった瞳に、いつしか惹かれていたのだ。ある雨の日、ずぶ濡れで店に駆け込んできた詩織に、櫂は黙ってタオルを差し出した。
「ありがとう……。あの、水瀬さん。私、何か失礼なことをしましたか?」
ガラス玉のように透明な瞳が、まっすぐに櫂を射抜く。櫂は言葉に詰まった。本当のことなど、言えるはずがない。
「……いや、そういうわけでは」
「なら、よかったです」
詩織はふわりと微笑んだ。そして、まるで雨宿りを口実にするように、彼女は自分のガラス作品について語り始めた。光を閉じ込め、一瞬の煌めきを永遠にするガラスの魅力。その話をする彼女の横顔は真摯で、美しかった。櫂は、知らず知らずのうちに彼女の話に引き込まれていた。
その日から、二人の距離は少しずつ縮まっていった。詩織は櫂を工房に招き、溶けたガラスが息を吹き込まれて形を変えていく様を見せてくれた。櫂は詩織を連れて、神保町の裏路地にある隠れた名店を案内した。触れ合わないように、細心の注意を払いながら。
それでも、能力は櫂の意思とは無関係に発動した。ふとした瞬間に視線が絡んだ時、隣を歩く彼女の服の袖が偶然腕に触れた時、櫂は何度もあの海辺へと飛ばされた。見るたびに、記憶の中の少女は少しずつ成長していた。小学生になり、中学生になり、それでもいつも同じ海辺で、幸せそうに笑っている。しかし、彼女が誰といるのか、その相手の顔だけは靄がかかったように見えなかった。
櫂は、それがおそらく彼女の初恋の相手か、あるいは大切な家族なのだろうと推測した。その記憶が、彼女の創作の源泉であり、彼女を形作る核なのだと感じた。だからこそ、それを覗き見る行為は、彼女の魂を汚すことに他ならない。詩織への想いが深まれば深まるほど、櫂の苦悩もまた、底なしに深くなっていくのだった。
第三章 海辺の告白
季節は移ろい、風が秋の匂いを運び始めた頃。櫂は、これ以上自分の気持ちに嘘をつき続けることはできないと悟っていた。この呪われた能力ごと、すべてを打ち明けよう。それで彼女が離れていくのなら、それも仕方がない。そう覚悟を決めた矢先、詩織の方から「大事な話があるんです」と切り出された。
「週末、海に行きませんか。私の、一番大切な場所なんです」
その言葉に、櫂の心臓は大きく跳ねた。断る理由など、あるはずもなかった。
週末、二人は電車を乗り継ぎ、小さな海辺の町を訪れた。そこは、櫂が何度も「見てきた」場所だった。白い砂浜、穏やかな波、空に溶けるような青。すべてが見覚えのある光景だった。
詩織は波打ち際まで歩くと、静かに砂浜に腰を下ろした。櫂も、少し離れた場所に座る。
「ここに来ると、姉のことを思い出すんです」
詩織は、遠くの水平線を見つめながら、ぽつりぽつりと語り始めた。彼女には、一卵性の双子の姉がいたこと。幼い頃、この海で不慮の事故に遭い、彼女だけが助かり、姉は帰らぬ人となったこと。
「私がガラス工芸を始めたのも、姉が好きだったから。キラキラしたものが大好きで、ビー玉とか、海岸に打ち上げられたシーグラスとかを、宝物みたいに集めてたんです」
櫂は息を飲んだ。彼が見ていたあの幸福な記憶は、彼女が失った双子の姉との、かけがえのない思い出だったのだ。なんと残酷な真実だろう。櫂は、彼女の最も触れられたくない傷に、何度も塩を塗り込んでいたのだ。
「謝らなければならないことが……」
櫂が口を開いた時、詩織は静かに首を横に振った。
「私ね、時々、不思議なものを見るんです」
彼女の声は、凪いだ海のように穏やかだった。
「愛しいと思う人や、大切にしたいと思うものに触れると、姉が見せてくれるのかもしれない……未来の記憶、みたいなものが、見えることがあるんです」
「……え?」
櫂は、彼女の言っている意味が理解できなかった。
「姉が生きていたら、経験したであろう幸せな未来。それを、私を通して見ているような……そんな感じ。だから、私は姉の分まで、たくさん笑って、幸せにならなきゃって思うんです」
そして、詩織は決定的な一言を告げた。読者の予想を裏切る、衝撃の事実だった。
「水瀬さん、あなたが私の手に触れたあの日。私にも見えたんです。この海辺で、白髪になったあなたと私が、笑いながら手をつないでいる、とても温かい未来の記憶が」
櫂の頭の中が、真っ白になった。
彼が見ていた記憶。あの少女は、幼い詩織本人だった。だが、彼女と一緒にいた「誰か」は、過去の人物ではなかった。それは、亡き姉が妹に見せる「未来の希望」。つまり、櫂が見ていたのは、詩織が最も失いたくないと願った「姉との過去」ではなく、詩織の姉が最も見たかったであろう「妹の幸せな未来」の断片だったのだ。そして、その未来にいるのは、紛れもなく、水瀬櫂、その人だった。
彼は他人の過去を盗み見る呪われた存在だと思っていた。だが、違った。彼は、未来の希望を、愛の記憶を、受け取る側に選ばれたのだ。価値観が根底から覆る、雷に打たれたような衝撃だった。
第四章 二人が紡ぐ未来
潮風が、二人の間の沈黙を優しく撫でていく。櫂は、ようやく自分の喉から言葉を絞り出した。
「僕も……僕も、見ていたんだ。君の記憶を」
彼は、震える声で自分の能力について全てを打ち明けた。人を好きになると、その人の大切な記憶が見えてしまうこと。そのせいで、人と深く関わることを恐れていたこと。そして、彼女の温かい記憶を見て、罪悪感に苛まれていたこと。
すべてを聞き終えた詩織は、驚いた顔をしたが、やがてその瞳に涙の膜が張った。
「そうだったんですね……。私の見ていた未来と、あなたの見ていた記憶は、きっと繋がっていたんですね」
彼女はそっと立ち上がると、櫂の前にひざまずき、ためらうことなく彼の手を取った。
「あなたの能力は、呪いなんかじゃない。だって、あなたは私の姉の願いを受け取ってくれた。私の未来の幸せを、私より先に見ていてくれた。それは、とても……とても、素敵なことだと思います」
詩織の体温が、櫂の冷え切った心へと流れ込んでくる。その瞬間、またしても鮮やかな光景が彼の脳裏に広がった。
それは、古書店「海馬堂」のカウンター。少し年を重ねた詩織が、櫂の淹れたコーヒーを飲みながら、穏やかに微笑んでいる。窓の外では、柔らかな雪が舞っていた。それは過去の記憶でも、誰かが見せた未来でもない。これから二人が築いていくであろう、ごくありふれた、しかし、かけがえのない日常のワンシーンだった。
櫂は、初めて、この能力を持って生まれたことを感謝した。これは呪いではない。誰かの心を深く理解し、その人が大切にしている想いを共有するための、特別な贈り物なのかもしれない。人と関わることを恐れる必要などなかったのだ。
彼は、詩織の手を強く握り返した。
「君の隣に、いさせてほしい」
それから数年後。
櫂と詩織は、あの海辺を再び訪れていた。二人の左手の薬指には、詩織が自ら作ったガラスの指輪が、夕日を受けて控えめに輝いている。
彼らは黙って手をつなぎ、水平線に沈んでいく太陽を眺めていた。櫂はもう、記憶が見えることを恐れてはいなかった。むしろ、それは二人の愛を確かめるための、ささやかな儀式となっていた。
彼が詩織の手のぬくもりに意識を集中させると、温かなビジョンが心に流れ込んできた。
たくさんの本に囲まれた縁側で、白髪になった自分と詩織が、寄り添いながら静かに同じ本を読んでいる。ページをめくる指には、深い皺が刻まれている。それでも、つないだ手は、今と少しも変わらない温かさだった。
それは詩織の姉が見せた未来の続きなのか、それとも、二人の愛が新たに紡ぎ出した未来の記憶なのか。答えはどちらでもよかった。
大切なのは、これから先、どんな記憶も二人で分かち合い、共に未来を築いていくという、揺るぎない確信だけだった。櫂は、隣で微笑む詩織の肩を、そっと抱き寄せた。海は、二人の永遠を祝福するかのように、黄金色にきらめいていた。