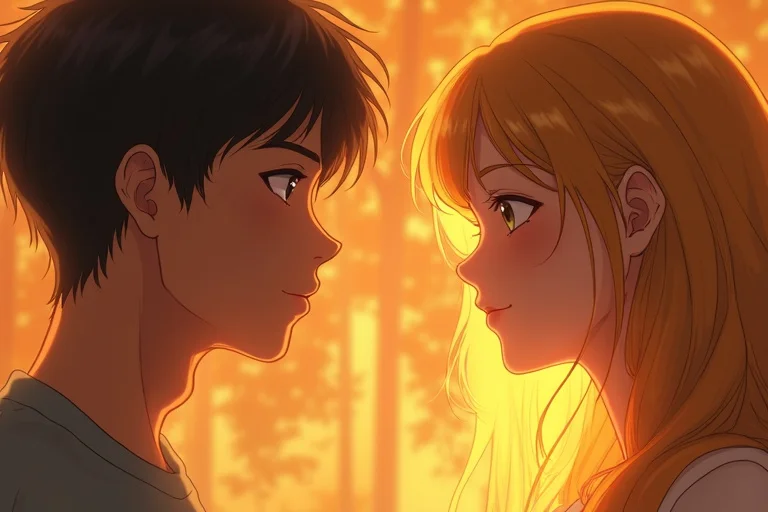第一章 不協和音の波紋
私の左手首には、時折、淡い光の波紋が浮かび上がる。皮膚の下、静脈が走るその場所で、それはまるで水面に落ちた雫のように静かに広がり、そして消える。これは病ではない。呪いであり、そして、おそらくは祝福でもある、私の特異な体質。誰かを強く想うとき、その相手の心臓の鼓動が、私自身の身体にこうして「共鳴」するのだ。
古書の修復師である私の日常は、紙魚(しみ)の匂いと、乾いた糊の感触、そして静寂に満ちていた。古い物語の破れたページを繕い、失われた言葉を甦らせる仕事は、人と深く関わることを無意識に避けてきた私にとって、心地よい隠れ蓑だった。他人の感情の奔流に触れることなく、ただ黙々と、過ぎ去った時間と対話する。それで満足なはずだった。
彼、相葉奏(あいば かなで)と出会うまでは。
雨がアスファルトを叩く音だけが響く午後のことだった。店のドアベルが澄んだ音を立て、長身の男性が入ってきた。濡れた髪を無造作にかき上げる彼の手には、古いチェロケースが握られていた。
「すみません、古い楽譜を探しているんですが」
彼の声は、低く、けれど空間を震わせるような響きを持っていた。それが、私の静かな世界に投じられた最初の石だった。
奏はチェリストだった。失われた祖父の楽曲を探しているのだと、彼は情熱的に語った。彼の言葉の端々から、音楽への深い愛情が滲み出ていた。私は彼の話に耳を傾けながら、書庫の奥から古びた楽譜の束を運び出した。彼がページをめくる真剣な横顔を盗み見た瞬間、私の手首に、ちくりと針で刺されたような微かな疼きが走った。そして、温かい光の波紋が、ゆっくりと広がった。穏やかで、力強いリズム。それは、彼が奏でる音楽のように、私の心を優しく揺さぶった。
それが、私たちの始まりだった。彼が私に微笑みかけるたび、私の名前を呼ぶたび、手首の波紋はより鮮明に、より温かく輝いた。私は初めて、この体質を呪いではなく、愛の証として受け入れることができた。奏の心が、彼の感情が、この光の波紋を通して私に直接語りかけてくるようだった。
しかし、今、私の手首に浮かんでいるのは、彼の穏やかなリズムではない。
深夜、ベッドの中で一人、私は左手首を見つめている。そこに刻まれているのは、速く、どこか切なさを帯びた不規則なリズム。奏は隣町のアパートで、明日の練習のために一人でいるはずだ。この胸を締め付けるような不協和音は、一体誰に向けられた、彼のどんな感情なのだろうか。愛の証だったはずの光は、今や私の心をじわじわと蝕む、冷たい疑念の染みと化していた。
第二章 満ちる旋律、乱れる鼓動
奏との日々は、色褪せた古書に鮮やかな色彩が蘇っていくようだった。彼は私を、埃っぽい書庫から陽光の下へと連れ出してくれた。彼の演奏会では、客席の片隅で、彼のチェロが紡ぎ出す旋律に身を委ねた。弓が弦を滑るたびに生まれる情熱的な音色と、私の手首に刻まれる力強いリズムが完全にシンクロする。その瞬間、私は彼と一つになったような、満ち足りた幸福感に包まれた。
「咲の手、綺麗だね。まるで、古い物語を守ってきたみたいだ」
公園のベンチで、奏が私の指先にそっと触れた。その瞬間、手首に広がる温かい波紋。彼の愛情が、言葉以上に雄弁に私に伝わってくる。私は自分の体質を彼に打ち明けてはいない。この不思議な繋がりは、私だけの秘密だった。彼が私を想う純粋な感情を、私だけが知覚できる。その事実に、密かな優越感と喜びを感じていた。
私たちは、互いの世界を補い合うように惹かれ合った。私は彼の音楽に静かな深みを与え、彼は私のモノクロームの世界に鮮烈な音色をもたらしてくれた。彼が私を想うときに刻まれる、穏やかで優しいアンダンテのリズム。それは私の心の錨となり、どんな不安からも守ってくれる聖域のはずだった。
異変に気づいたのは、秋も深まった頃だった。
奏が新しい楽曲の創作に没頭し始めてからだ。彼はアパートにこもる時間が増え、会えない夜が続いた。そんな夜、決まって私の手首に、あの奇妙なリズムが現れるようになった。
それは、プレスト(急速に)と表現するしかない、焦燥感に満ちた激しい鼓動だった。だが、ただ速いだけではない。時折、ふっと脈が飛ぶような、不規則な揺らぎがある。それは、彼の創作の苦しみなのだろうか。それとも――。
一度芽生えた疑念は、毒草のように心を覆い尽くしていく。
彼は、私ではない誰かのことを考えているのではないか。私には見せない、情熱的な別の顔があるのではないか。この激しいリズムは、私への愛とは全く質の違う、別の感情の奔流なのではないか。
奏に会うと、彼はいつもと変わらず優しかった。私の顔を見れば、手首にはいつもの穏やかなリズムが戻ってくる。その事実に安堵する一方で、彼がいない時にだけ現れる「もう一つの心音」が、私を苛んだ。
愛の証だった共鳴は、今や彼の心を盗み見るための盗聴器のようになっていた。私は奏の笑顔の裏側を、手首に浮かぶ光の波紋から探ろうとする、醜い自分に嫌悪感を覚えた。それでも、知りたいという欲求を抑えることはできなかった。彼の本当の心を。その不協和音の正体を。
ある晩、電話の向こうで「今夜も作業で帰れない」と告げる彼の声を聞きながら、私の手首には、またあの激しいリズムが刻まれ始めていた。もう、限界だった。私はコートを羽織ると、彼の嘘を、そして私の愚かな嫉妬を終わらせるために、夜の街へと駆け出していた。
第三章 告白のアダージョ
奏のアパートの明かりは消えていた。予感はしていた。彼はここにいない。私の手首で不規則に明滅する光だけが、彼がどこかで活動していることを示している。私はまるで探偵のように、彼の行きそうな場所を頭の中で巡らせた。練習スタジオ、馴染みのカフェ、それとも…。ふと、彼が以前話していた言葉が脳裏をよぎった。
「子どもの頃、よく忍び込んだ古い市民ホールがあるんだ。誰もいないステージで、一人で弾くのが好きでね」
タクシーを拾い、取り壊しが決まっているという古い市民ホールへと向かった。寂れた建物の前に立つと、隙間から漏れる微かな光と、チェロのむせび泣くような音色が聞こえてきた。間違いない、彼だ。
通用口の鍵はかかっていなかった。軋む床に足音を殺しながら、私は闇に沈む客席の最後列に身を潜めた。
ステージ上には、スポットライトもない中で、月明かりだけを浴びてチェロを弾く奏の姿があった。
彼が奏でているのは、聴いたことのない曲だった。それは嵐のように激しく、祈りのように静かで、絶叫のように悲痛な旋律だった。そして、その音色と寸分たがわず共鳴するように、私の手首の波紋は、今までで最も激しく、複雑な光のリズムを刻んでいた。恐怖、情熱、焦燥、そして深い、深い愛。あらゆる感情が混ざり合った奔流が、私の身体に流れ込んでくる。
一曲弾き終えた彼が、ふと顔を上げた。闇に慣れた彼の目が、客席の隅にいる私を捉える。
「……咲?」
彼の声は、驚きと諦めが入り混じったように震えていた。
チェロを置いた彼が、ゆっくりとステージを降りてくる。私の前に立った彼の顔は、月光の下で青白く見えた。
「いつから、そこに?」
「……最初から」
沈黙が落ちる。私は、彼が口にするであろう残酷な真実を覚悟し、唇を噛みしめた。しかし、彼の口から紡がれたのは、私の浅はかな想像を遥かに超える告白だった。
「僕の心臓は、もう長くないんだ」
彼は静かに言った。まるで天気の話でもするように。
「先天性の病気でね。医者には、もうチェロを弾くような負担はかけるなと言われてる。……この激しい動悸は、恋のせいじゃない。ただの、壊れかけた心臓の音だよ」
私の頭を、鈍器で殴られたような衝撃が襲った。手首の不協和音。脈が飛ぶような揺らぎ。それは、別の誰かへの情熱などではなかった。彼の、生命そのものの叫びだったのだ。
「君に出会って、僕は初めて、生きたいと、もっと弾きたいと心から思った。君に、僕が生きた証になるような、最高の曲を遺したかった。でも、時間がなかったんだ」
彼の瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちた。
「この不規則な鼓動も、君を想うときの穏やかな鼓動も、どっちも本当の僕なんだ。君を愛しているから生まれる恐怖も、焦りも、全部……。隠していて、ごめん」
私は、言葉を失くしたまま、自分の手首を見つめた。そこに明滅する、激しくも切ない光のリズム。私は、これを疑念の証だと、心変わりの烙印だと思っていた。なんて愚かだったのだろう。私は彼の愛の、ほんの一部分しか見ていなかった。光り輝く美しい部分だけを求め、その裏側にある痛みや苦しみから目を背けていたのだ。
愛とは、心地よいリズムだけではない。不安も、恐怖も、不協和音さえも、全てを抱きしめること。
彼の命の叫びを、私は嫉妬という醜いフィルターを通してしか聞くことができなかった。溢れ出す涙で視界が滲む中、私は彼の冷たい手を、震える両手で強く、強く握りしめた。
第四章 永遠のアンダンテ
それから三ヶ月後、奏の最初で最後のリサイタルが開かれた。医者の反対を押し切って彼が決めた、たった一夜限りの舞台。私は、彼が用意してくれた最前列の席で、その時を待っていた。
ステージに現れた奏は、以前よりも少し痩せたように見えたが、その瞳は驚くほど澄み切った光を宿していた。彼は客席に一礼すると、私のほうを見て、ほんの少しだけ微笑んだ。その瞬間、私の手首に、懐かしいほど穏やかな、温かい波紋が広がった。
一曲、また一曲と、彼のチェロが物語を紡いでいく。喜びの歌、悲しみの歌、そして生命を讃える力強い歌。ホール全体が、彼の魂の音色に満たされていく。私の手首には、彼の音楽と生命が織りなす、複雑で美しいタペストリーが刻まれ続けていた。穏やかな愛のリズム、音楽への情熱的なリズム、そして時折混じる、彼の命の不協和音。その全てが、今の私には愛おしかった。
そして、プログラムの最後の曲。アナウンスされたタイトルに、私は息を呑んだ。
『共鳴』。
あの日、誰もいないホールで彼が弾いていた、私のための曲だった。
奏が弓を構える。静寂の中、最初の音が響いた瞬間、激しくも切ない旋律が、私の全身を貫いた。それは、彼の人生そのものだった。病の苦しみ、音楽への渇望、そして私へのどうしようもないほどの愛。彼の全ての感情が、音の奔流となって押し寄せる。私の手首の光は、まるで生命の最後の輝きを放つ星のように、激しく明滅を繰り返した。痛みさえ感じるほどの、強い共鳴。でも、私はもう目を逸らさなかった。これが、彼の全て。私が愛した、相葉奏という人間の、全ての音なのだから。
壮大なクライマックスの後、最後の音が、長く、長く尾を引いて、静寂の中に溶けていく。
同時に、私の手首で激しく明滅していた光が、ふっ、と力を失った。
万雷の拍手の中、奏はチェロを抱きしめたまま、ゆっくりと前に傾ぎ、ステージの上で静かに倒れた。
彼の心臓は、その最後の音色と共に、永遠の沈黙に入った。
あの日以来、私の手首の光が動くことは二度とない。けれど、消えることもなかった。
皮膚の下には、彼が最後に奏でた『共鳴』のリズムが、淡い光の波紋として、永遠に刻み込まれている。それはまるで、遠い星の光が、何万光年もかけて今ここに届いているかのように、静かに、しかし確かにそこに在り続ける。
私は時折、その動かなくなった光の波紋を、そっと指でなぞる。
それは奏が生きた証。彼が私を愛した証。そして、彼の命の全てを受け取った、私の心そのものだった。
冷たい光に触れると、彼のチェロの音色が、今も胸の奥で静かに響く気がする。
「ここに、あなたは生きている」
私は、この永遠のアンダンテを胸に、明日からも生きていく。